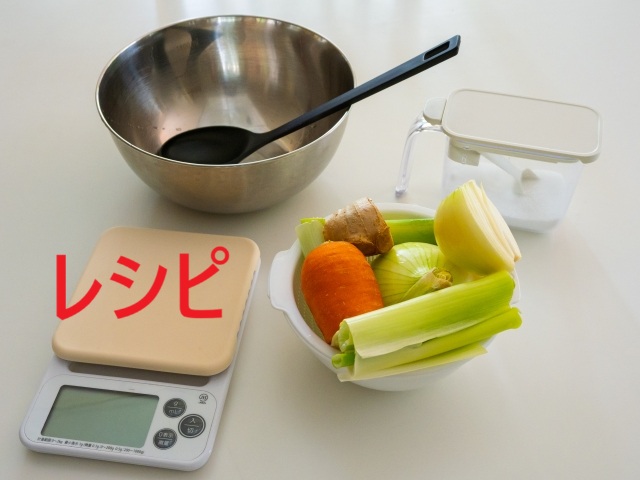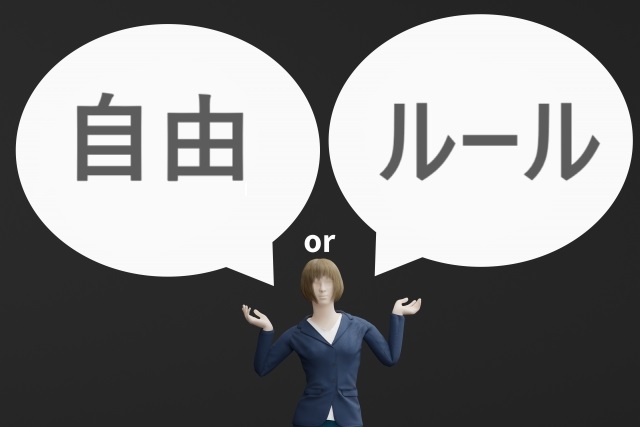マネジメント課題解決のためのメディアプラットホーム「識学総研(https://souken.shikigaku.jp)」が、ビジネスの最前線の用語や問題を解説するシリーズ。今回は、夏休みの宿題を例にして、マネジメントの本質について考察します。
識学から考える、部下を動かすマネジメントの本質
「夏休みの宿題」。誰もが子どものころに経験した、この“恒例行事”は、実はマネジメントの縮図である――。そう聞くと、多くの方が「子どもの課題とビジネスマネジメントを一緒にしていいのか?」と疑問に思うかもしれません。しかし、実はこの夏の課題には、ビジネスにおける目標管理、期限厳守、進捗管理、動機づけといったあらゆるマネジメント要素が詰まっており、部下を持つマネージャーにとって大変示唆に富んだ題材です。
特に識学の観点から見ると、「なぜ人は動かないのか」「どのように動かすべきなのか」という構造的な疑問に対し、夏休みの宿題というわかりやすい題材は明確な答えを与えてくれます。
この記事では、夏休みの宿題を例に、部下に目標達成を促すマネジメントの本質を、識学の理論に基づいて紐解いていきます。
「宿題をやらない子ども」と「動かない部下」の共通点
まず、多くの親が経験していることですが、夏休み序盤、子どもは宿題に対して本気になりません。自由な時間が広がっていると感じ、つい後回しにします。やるべきことがあるのに、実行に移さない――これは、職場における「やる気が見えない部下」や「動かない社員」と同じ構図です。
この構図を識学では「認識のズレ」として捉えます。
すなわち、
・「宿題を8月31日までに終わらせる」という目的と、
・「今この瞬間に宿題をやる必要がある」という行動の優先順位が、
本人の中で結びついていない状態です。
この認識のズレは、マネジメントの失敗と直結します。部下が目標を達成しない、納期を守らない、という現象の裏には、「自分が今なぜそれをすべきなのか」という理解が不足していることが多いのです。
宿題をやらせる「親」の行動から学ぶマネジメント手法
では、親はどうするか? 多くの場合、次のようなステップを踏みます。
1.宿題の全体量を把握する(計画)
2.進捗状況を定期的に確認する(モニタリング)
3.「今やらないと間に合わないよ」と警告する(リスク認識の喚起)
4.ご褒美や叱責などの管理を行う(動機づけ)
これはまさに、マネージャーが部下の目標達成を管理するための基本ステップです。
識学では、「組織の生産性は、ルールと評価によって決まる」と定義します。つまり、親の「8月31日までに終わっていなければゲーム禁止ね」という“ルール”と、それを破ったときに罰があるという“評価”が、行動の動機となるのです。
「やらせる」のではなく、「自分でやる状態」を作る
とはいえ、宿題に対して反発する子どもに、「やりなさい!」と一方的に怒鳴っても、逆効果になることがあります。これもまた職場において、部下に「なんでできてないんだ!」と感情的に詰め寄っても、反発や萎縮を生むだけであるのと同じです。
識学では、「人は感情ではなく構造で動く」と定義します。つまり、感情的な説得ではなく、行動の“前提条件”を整えることが重要だと説いています。
親が行うべきことは、「本人が納得した上で、自ら行動に移せる状態を作る」こと。たとえば、「1日に2ページずつ進めていけば、旅行にも行けるよ」とスケジュールを可視化する、「終わったら好きな本を買おうね」と報酬を設定する、などです。
職場でも同様です。目標達成のためには、次の3点をマネージャーが徹底する必要があります。
・明確な目標設定(宿題の総量の把握)
→ 目標は曖昧ではなく、「〇月〇日までに、〇件の案件を完了させる」と具体的に行う。
・期限の明示と中間チェック(スケジュール管理)
→ 夏休みの宿題を7月末・8月中旬・8月末の3段階に分けて確認するのと同じように、中間レビューを設定する。
・行動と結果に対する評価(識学の評価制度)
→ 宿題を計画通りにこなせたら「評価」し、滞ったらルール通りに「指導」する。
なぜ「手取り足取り」は逆効果になるのか?
ここでありがちな落とし穴があります。それは、「子どもがやらないから」と親が代わりにやってしまうこと。これは一見、問題解決のように見えて、本人の成長機会を奪い、結果的には「自分でやる力」を弱めます。
識学でも、「上司が手を出しすぎると、部下の責任意識は低下する」と明確に警告しています。なぜなら、「最終的には上司がどうにかしてくれる」と思った瞬間に、人は行動責任を放棄するからです。
つまり、
・親が宿題を代筆する = 上司が資料を作る
・子どもが怒られる前提で放置 = 部下が「詰められるのは一時だけ」と甘える
という構造が完全に一致してしまうのです。
マネジメントの本質は、「自走させること」。そのためには、目標を本人に認識させ、進捗を自分で管理させ、評価と結果を紐づける「仕組み」を構築することが不可欠です。
成果が出る組織に共通する「識学型マネジメント」とは?
識学型のマネジメントは、感情によらず、「ルール」「評価」「責任」に基づく明確な構造づくりです。以下の3点がポイントです。
1.ゴールとルールを明示する
夏休みの宿題も、「いつまでに」「どのくらいの量を」「どのように進めるか」が明確だからこそ、管理が成立します。
2.評価基準はブレずに提示する
「最後の日に徹夜でやっても評価しないよ」という方針を示すことで、日々の行動に意味が生まれます。
3.介入しすぎず、ただし監視は緩めない
自走を促しながらも、進捗は確認し、ルール違反には淡々と対応する。
このような「構造で動かす」マネジメントを行えば、部下は納得感を持って目標に向かい、自ら行動するようになります。それはちょうど、子どもが「自分の意思で宿題に取り組む」状態とまったく同じです。
結論:マネジメントは「夏休みの宿題」に学べ
夏休みの宿題は、子どもの成長における“訓練”であると同時に、社会人にとってのマネジメントの原点とも言える存在です。
部下を動かすとは、言い換えれば、「やらされ感」ではなく「自らやる」状態に導くこと。そして、それを可能にするのが、識学の考える「構造に基づくマネジメント」です。
「子どもに宿題をやらせるにはどうすればいいか?」
この問いに真剣に向き合うことが、実は「部下に成果を出させるにはどうすればいいか?」という問いに対する、最良のヒントとなるのです。
識学総研:https://souken.shikigaku.jp
株式会社識学:https://corp.shikigaku.jp/