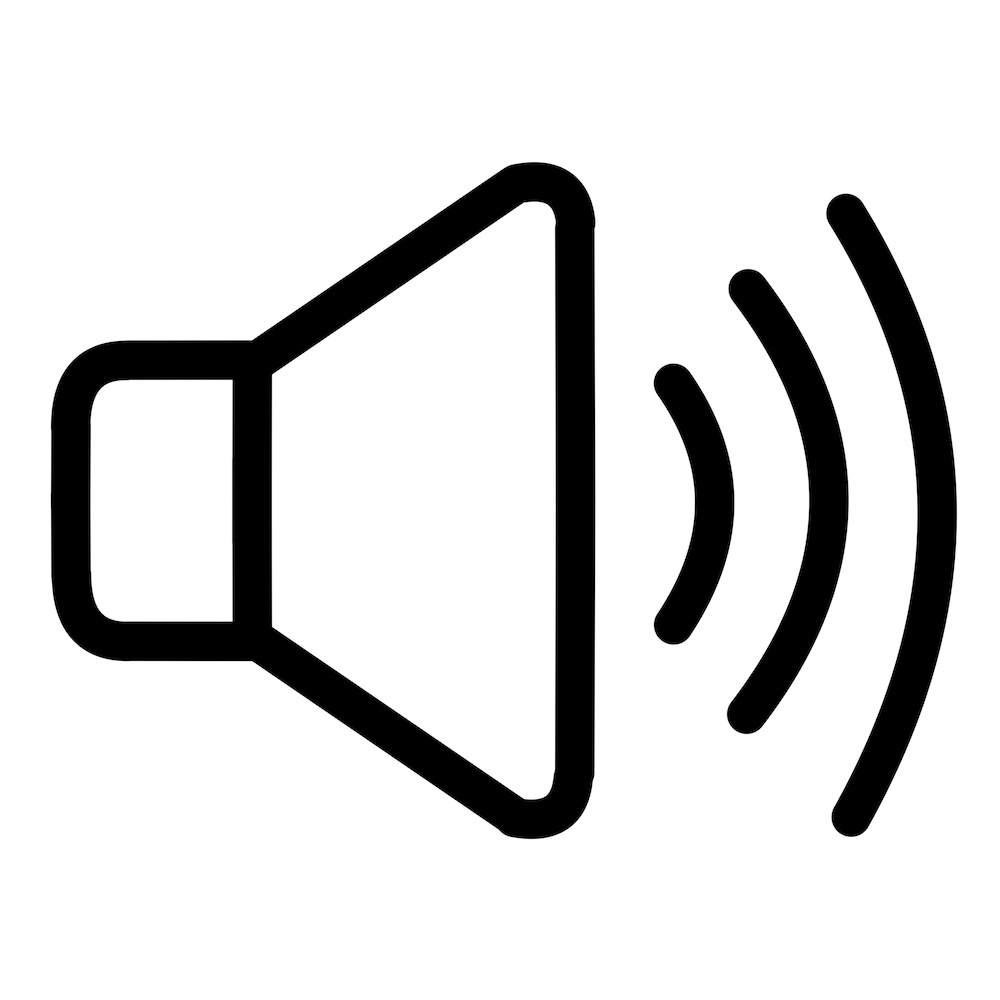取材・文/長嶺超輝
あまり知られていないが、裁判官には、契約や相続などのトラブルを裁く「民事裁判官」と、犯罪を専門に裁く「刑事裁判官」で分かれている。片方がもう片方へ転身することはほとんど起きず、刑事裁判官は弁護士に転身するか65歳の定年を迎えるまで、ひたすら世の中の犯罪を裁き続ける。
では、刑事裁判官は、何の専門家なのだろうか。日本の裁判所は「できるだけ裁判を滞らせず、効率よく判決を出せる」人材を出世ルートに乗せる。判決を片付けた数は評価されるが、判決を出したその相手が、再び犯罪に手を染めないよう働きかけたかどうかは、人事評価で一切考慮されない。
その一方、「人を裁く人」としての重責を胸に秘め、目の前の被告人にとって大切なことを改めて気づかせ、科された刑罰を納得させ、再犯を防ぐためのきっかけを作ることで、法廷から世の中の平和を守ろうとしている裁判官がいる。
刑事訴訟規則221条は「裁判長は、判決の宣告をした後、被告人に対し、その将来について適当な訓戒をすることができる」と定める。この訓戒こそが、新聞やテレビなどでしばしば報じられている、いわゆる「説諭」である。

本連載の第2回でお届けした幼児虐待の事件と、その裁判官の説諭に関する記事に対し、読者の皆さまから大きな反響をいただいた。
育児中は、子どもがなかなか言うことを聞かず、思わずカッとなる親御さんも多いことだろう。もちろん、カッとなるたびに児童・幼児虐待の事件が起きていてはたまったものではない。
ほとんどの親御さんは、しつけで冷静かつ懸命に対処し、未来を担う子どもたちの人格を誠実に育んでいるはずである。その事実に敬意を表しながら、今回は、数年前に西日本の某都市で発覚した、別の虐待事件ならびに裁判についてまとめさせていただいた。
育児と紙一重の悲惨な虐待事件が、少しでも減るよう祈るものである。
■突然に起きた虐待ではなかった
閑静な住宅街にある地方都市の新興団地。
その住人の多くが、女の子が泣き叫ぶ声と、張り上げられる母の叱責を毎晩のように聞いていた。
「やだーー! いやだぁあーーー!」
「ごめんなさいは?」
「ごめんなさい! ごめんなさい! ごめんなさい!」
中には、その母に注意を促し、たしなめた住人もいた。しかし、母は「うちじゃないですよ」と、シラを切ったり、「娘が全然言うことを聞かないから」と開きなおったりしていたという。
ある夜、その叫び声が突然途絶え、数分後に救急車のサイレン音が、アパート群の狭間に響き渡る。
4歳になる女の子は、意識不明の重体となった。タンスの上によじ登って遊ぼうとしたところを、女児が転落し、頭部などを床に強打したのである。
■家庭内の事故のはずが一転、刑事事件として立件へ
診察の結果、女の子の身体には、やけどなどの痕跡がいくつも見つかった。まもなく、病院から警察署へ通報が入った。
取調べに対して、母は当初、娘がひとりで遊んでいて転落したと言い張っていた。
しかし、3日後に涙を流しながら「私が娘を引っ張って落としました」と、認めたのである。
いつも元気な娘が、床の上であおむけになって気を失い、静かになってしまった。口からは吐瀉物が流れ出ている。その異変に激しく動揺したのだという。119番通報にも時間がかかってしまった。
■経済的に困窮しながらも、親子の絆を築き続けてきた
母親は、現在の夫と出会う前、隣県でシングルマザーとして2人の娘を育てていた。しかし、経済的な理由などにより、「もう、育てられない」と、地元の児童相談所に駆け込んだ。
実際、普段の食事もままならなかったようで、児童相談所の職員の見立てでは、姉妹の健康・栄養状態に危険信号が灯っている状況だった。
そこで、法的な処分に基づき、姉を児童養護施設、幼い妹を乳児院に入所させることにした。
3か月ほど経ち、母親が引き取る意思を見せたため、その後、児童相談所は姉妹を一時的に自宅に帰す措置を繰り返し、様子を見ていた。やがて、姉妹の「自宅外泊」も認めるようになった。
現在の県に引っ越した後も、お互いの児童相談所が連携をして、地元の児童相談所の職員がたびたび家庭訪問をしていた。
現在の夫とも入籍し、経済状態も改善され、日常的な言動から、娘達に対する母親の愛情も確かなものだと認められた。その結果、「問題はない」と判断し、家庭復帰が正式に決まった。
ただ、その直後から虐待が始まってしまったのである。
【誰もが「見て見ぬふり」をしてしまった…次ページに続きます】