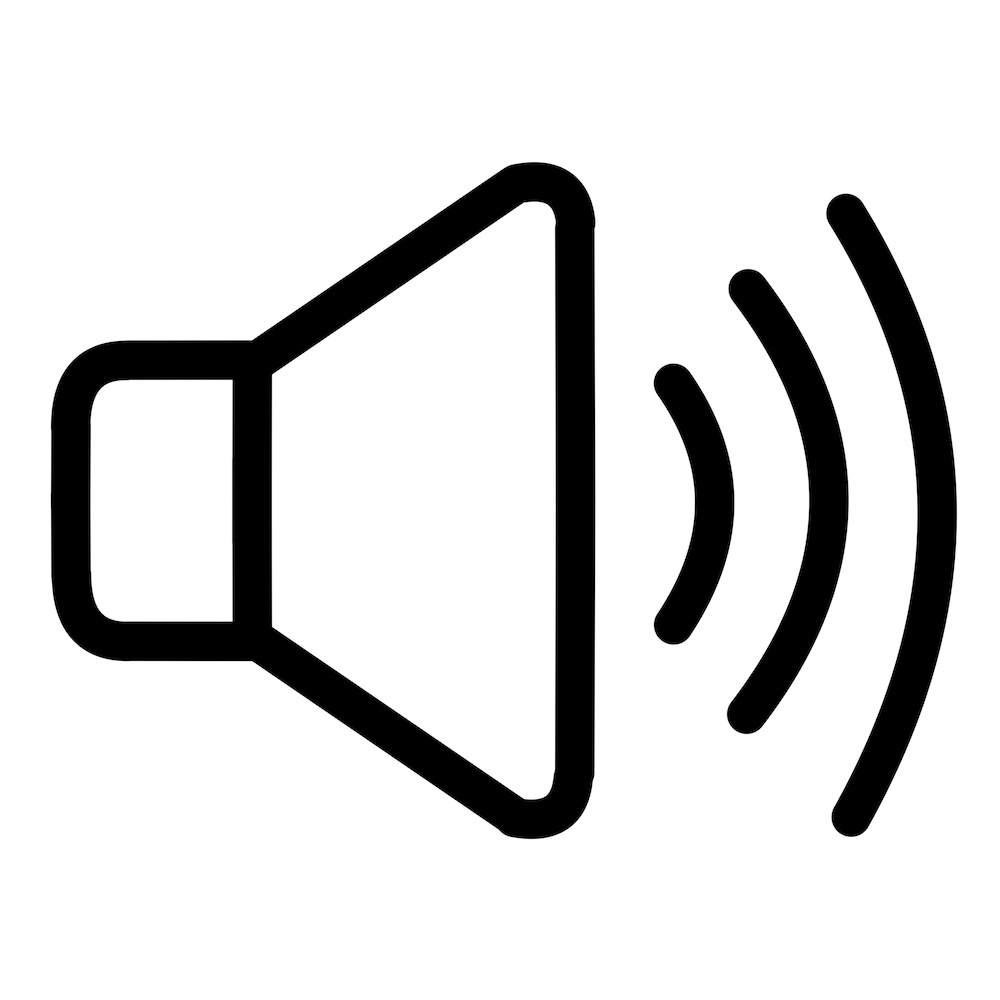■誰もが「見て見ぬふり」をしてしまった
パジャマ姿でアパートの廊下に放り出されて、泣きじゃくっている女児を目撃し、声をかけた住人もいた。
女児は「ママなんか、いなくなればいい……」などと話していたという。しかし、児童相談所への通報にまでは至らなかった。
仕事が忙しく、家庭を顧みなかった夫も、その虐待について見て見ぬふりを決めこんでいた。それどころか、おもらしをした娘を風呂場に閉じ込めていた妻の虐待に、夫も加担していた形跡もあった。
■児童相談所には一部、手続きの違背があったが……
厚生労働省のガイドラインによると、児童の家庭復帰を決めた後、児童相談所はその親に対して、専門家である児童福祉司による6カ月以上の継続的な指導を求めている。しかし、児童相談所はそれを怠っていた。
また、家庭の転居があった場合には、お互いの都道府県で連携し、児童相談所同士で、電話やメールだけでなく、文書による情報交換をすべき内部規定もあったが、それも怠っていたという。
たしかに、統一された適正な手続きを経ることは大切である。
しかし、児童相談所がこれらの手続きをすべて踏んでいたとしても、一連の虐待を止められたかどうかはわからない。
そもそも、本件の第一次的な責任は、児童相談所でなく、被害幼児の両親に問われることは間違いない。
傷害や監禁などの罪に問われた母親の裁判が、いよいよ始まろうとしていた。
【後編に続きます】
取材・文/長嶺超輝(ながみね・まさき)
フリーランスライター、出版コンサルタント。1975年、長崎生まれ。九州大学法学部卒。大学時代の恩師に勧められて弁護士を目指すも、司法試験に7年連続で不合格を喫し、断念して上京。30万部超のベストセラーとなった『裁判官の爆笑お言葉集』(幻冬舎新書)の刊行をきっかけに、記事連載や原稿の法律監修など、ライターとしての活動を本格的に行うようになる。裁判の傍聴取材は過去に3000件以上。一方で、全国で本を出したいと望む方々を、出版社の編集者と繋げる出版支援活動を精力的に続けている。

『裁判長の沁みる説諭』(長嶺超輝著、河出書房新社)