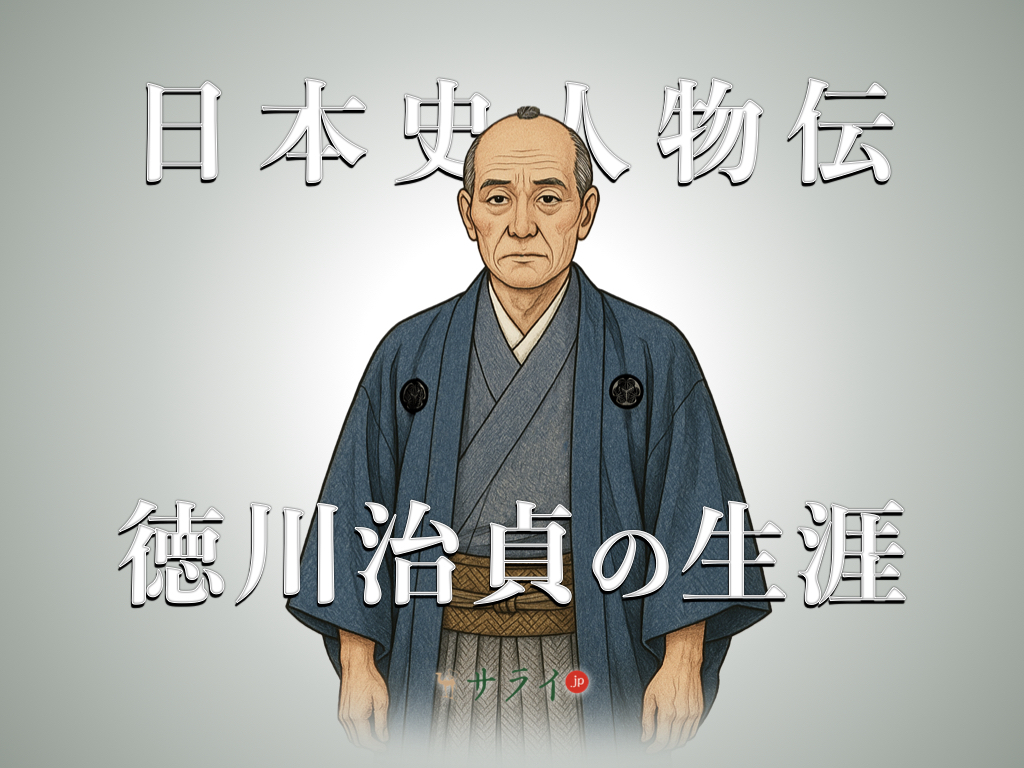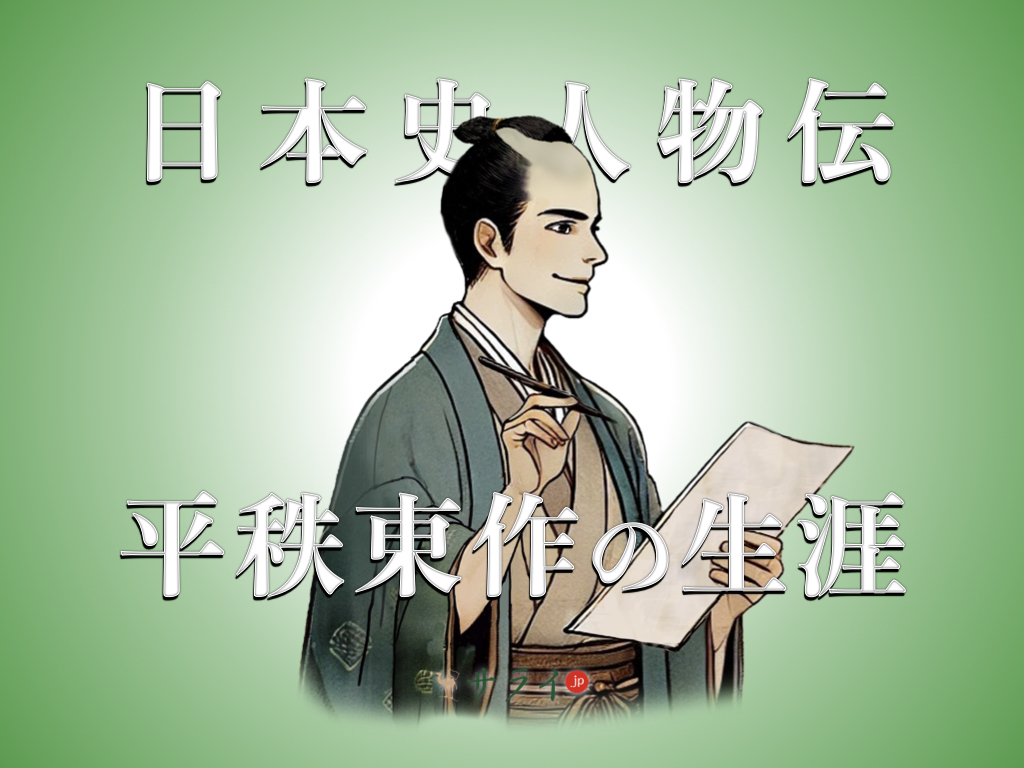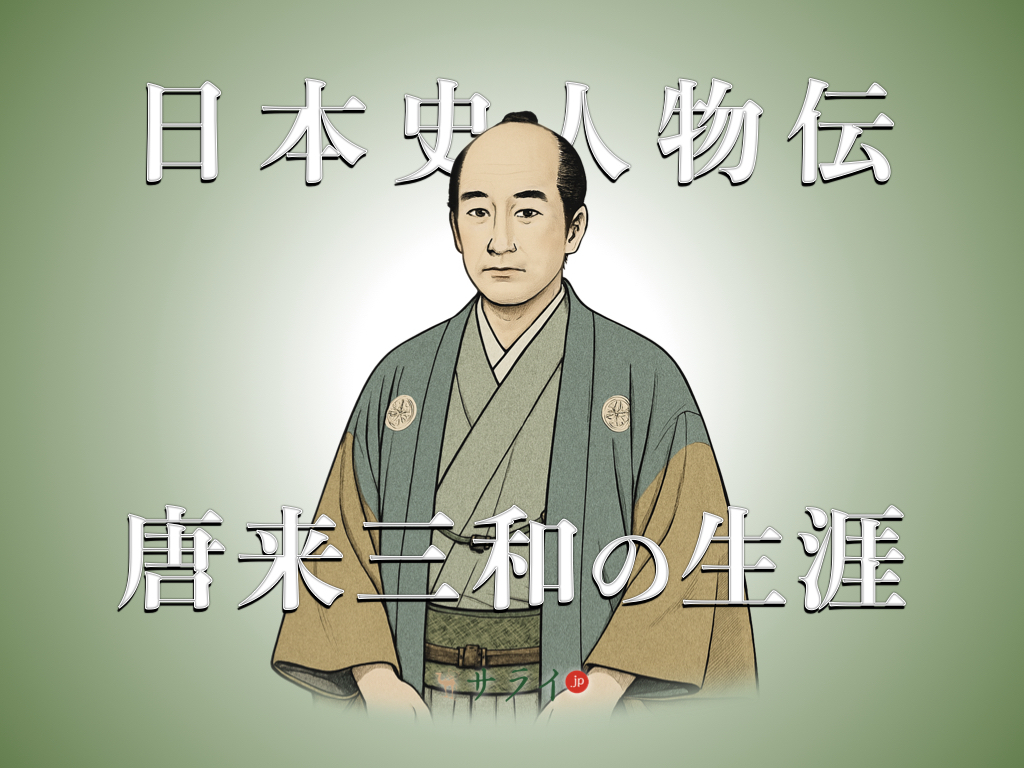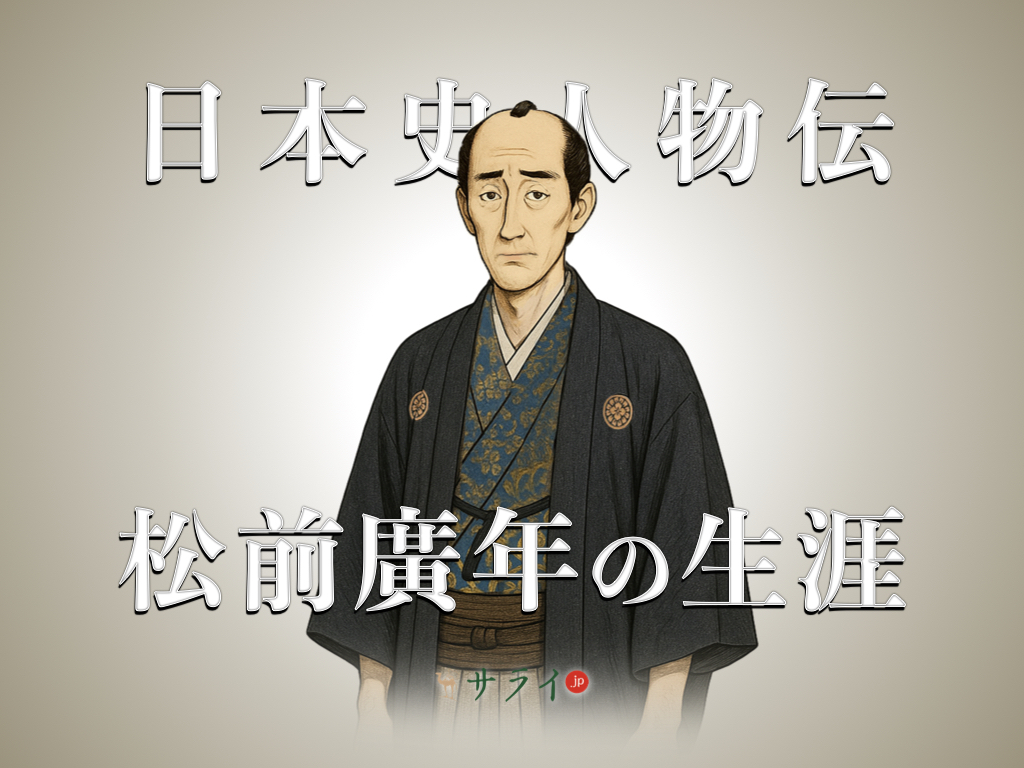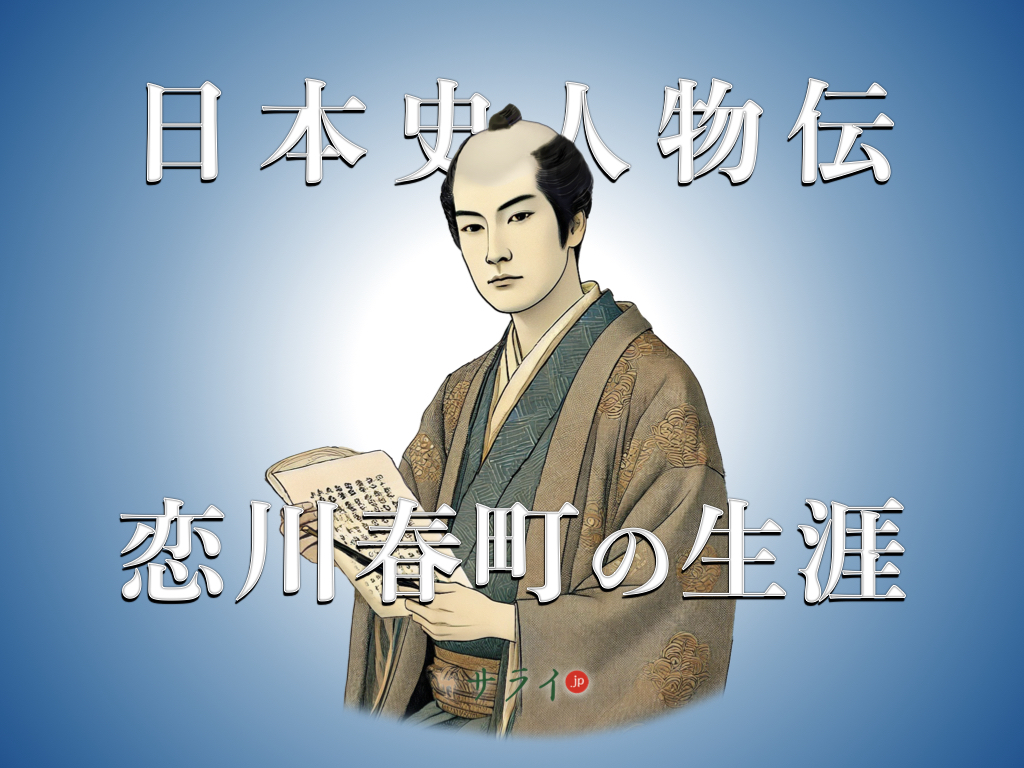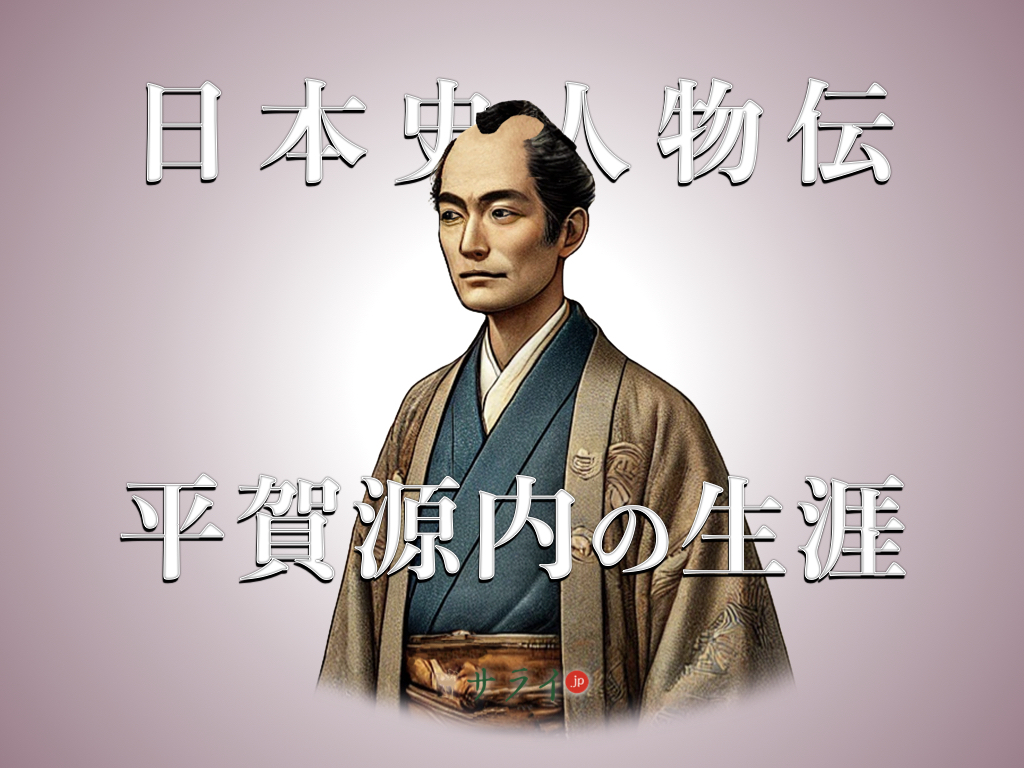はじめに-徳川治貞とはどのような人物だったのか
江戸時代中期、和歌山藩(紀州藩)の藩政改革に力を尽くした人物がいます。その名は徳川治貞(とくがわ・はるさだ)。紀州徳川家の一員として藩主に就任し、倹約や人材登用など地道な施策で藩政の立て直しを図りました。政治に誠実に向き合った一方で、民意をくみ取る仕組みも模索した人物として知られています。
そんな徳川治貞ですが、実際にはどのような人物だったのでしょう。史実をベースに紐解きます。
2025年NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では、財政が上向かない幕府の政策に、苦言を呈す紀州藩主(演:高橋英樹)として描かれます。
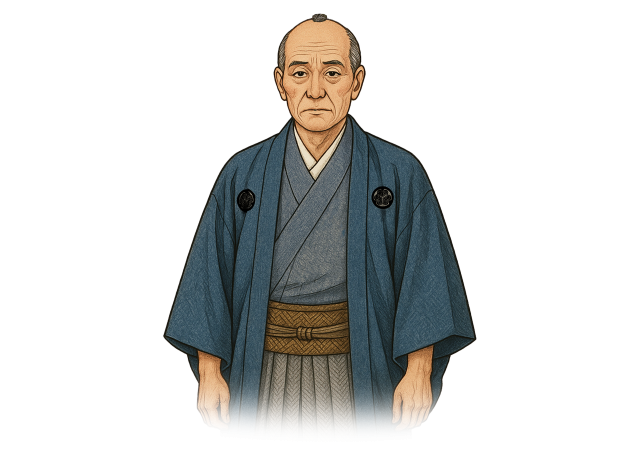
目次
はじめに-徳川治貞とはどのような人物だったのか
徳川治貞が生きた時代
徳川治貞の生涯と主な出来事
まとめ
徳川治貞が生きた時代
徳川治貞が生きたのは、18世紀の中頃から後半にかけて。享保、宝暦、安永、天明、寛政といった時代を通じて、幕藩体制が安定から変動へと向かい始めた時期でした。
各地で財政難が深まり、改革の必要性が叫ばれる中で、藩主としての手腕が問われる時代でもありました。
徳川治貞の生涯と主な出来事
徳川治貞は享保13年(1728)に生まれ、寛政元年(1789)に没しました。その生涯を、出来事とともに紐解いていきましょう。
紀州藩主の血筋に生まれる
徳川治貞は享保13年(1728)2月16日、江戸赤坂の紀州藩邸にて誕生しました。父は紀伊国和歌山藩第6代藩主・徳川宗直(とくがわ・むねなお)、母は外山氏(あるいは尾関氏、藤田氏とも)です。治貞は、次男でした。
幼名は春千代、のちに頼淳(よりあつ)と称しました。
西条藩主から和歌山藩主へ
宝暦3年(1753)、26歳のときに伊予国西条藩主となり、紀州松平家の5代当主を継ぎます。その後、安永4年(1775)2月、兄・宗将の跡を継いで和歌山藩9代藩主に就任。徳川御三家の一つ・紀州藩の当主として重責を担うことになります。

藩政改革に尽力
藩主となった治貞は、藩の財政健全化と政治の再建に着手。執政や参政といった重職に有能な人材を登用し、倹約令を徹底。また、武芸を奨励し、藩士の規律を引き締めました。安永5年(1776)には、権中納言に昇進しました。
さらに安永7年(1778)には、和歌山京橋口に「訴訟箱」を設置。これは、藩政に対する意見や不満を広く募るもので、当時としては珍しい民意を取り入れる仕組みといえます。藩主としての誠実な姿勢がうかがえる施策でした。
晩年と最期
寛政元年(1789)10月26日、江戸で死去。享年62。法号は香厳院殿三品前黄門心斉円通。紀伊国海部郡上村(現・和歌山県海草郡下津町)の長保寺に葬られました。
まとめ
徳川治貞は、ただ名門の出であるというだけでなく、実直に藩政と向き合った藩主でした。倹約や人材登用、訴訟箱の設置など、地に足のついた改革を重ね、和歌山藩の舵取りに尽力。その姿勢は、江戸中期の藩主像として注目に値します。
歴史の表舞台で派手な活躍をしたわけではありませんが、その足跡は今も静かに語り継がれています。
※表記の年代と出来事には、諸説あります。
文/菅原喜子(京都メディアライン)
肖像画/もぱ(京都メディアライン)
HP:http://kyotomedialine.com FB
引用・参考図書/
『日本大百科全書』(小学館)
『日本人名大辞典』(講談社)
『国史大辞典』(吉川弘文館)