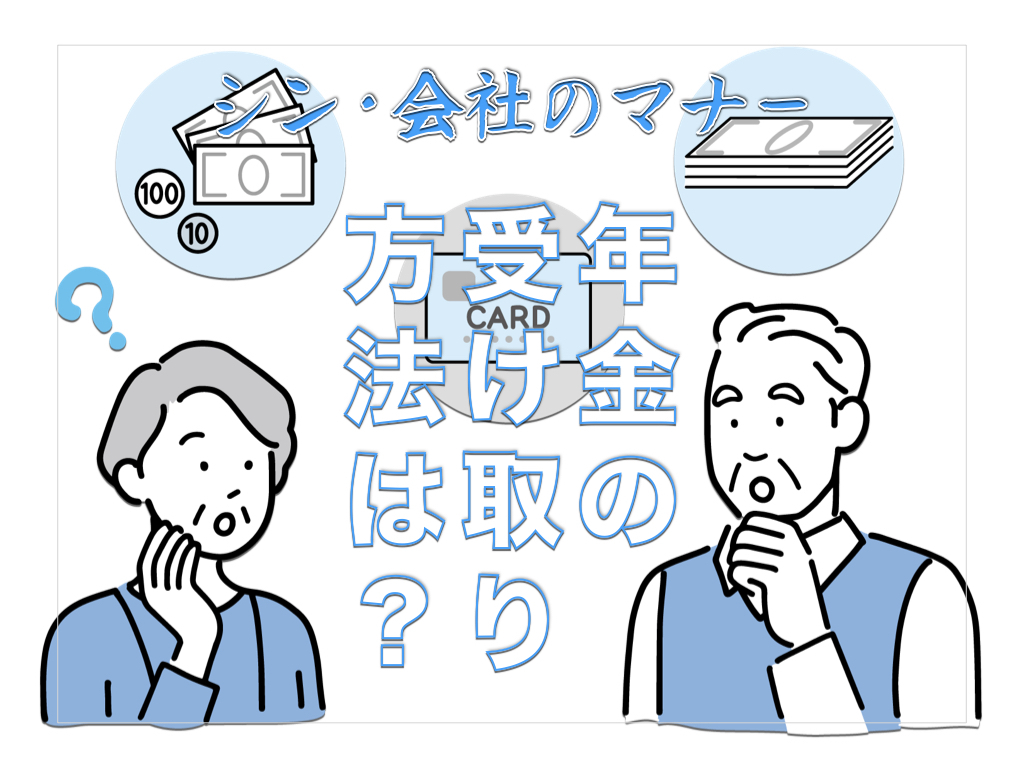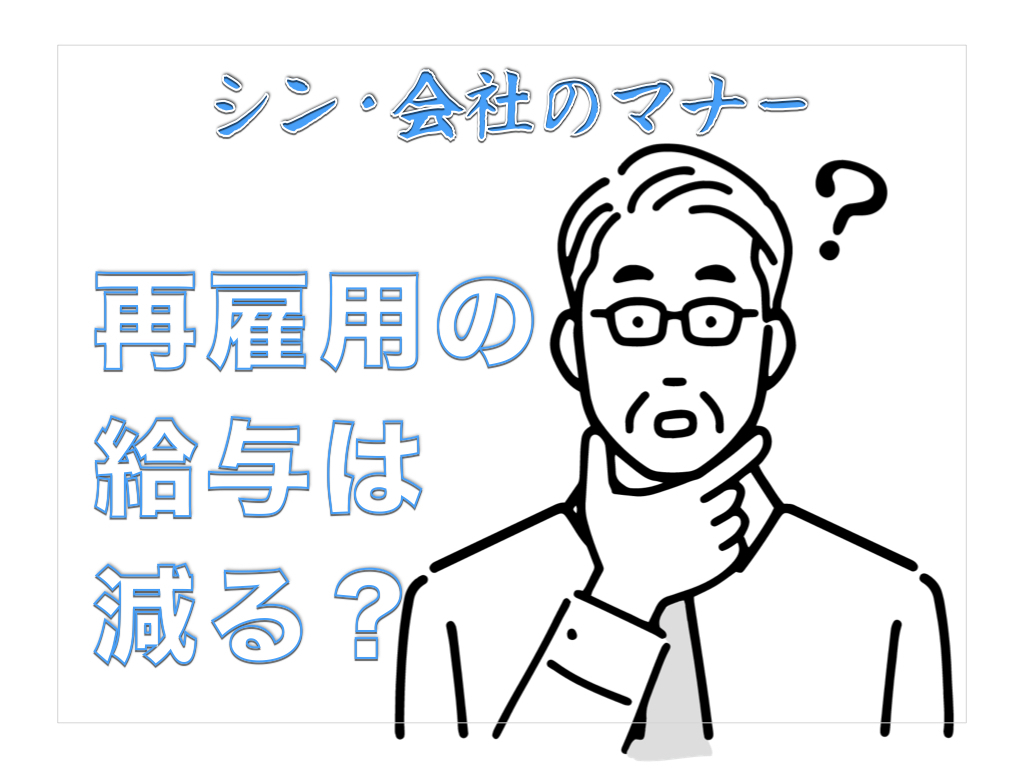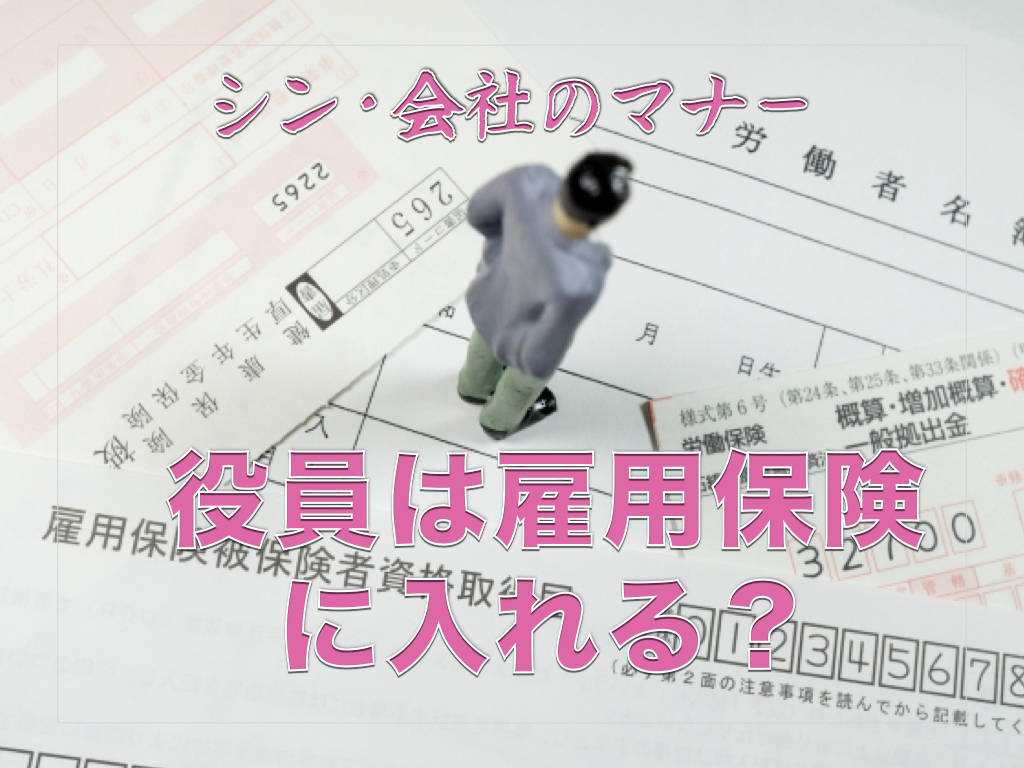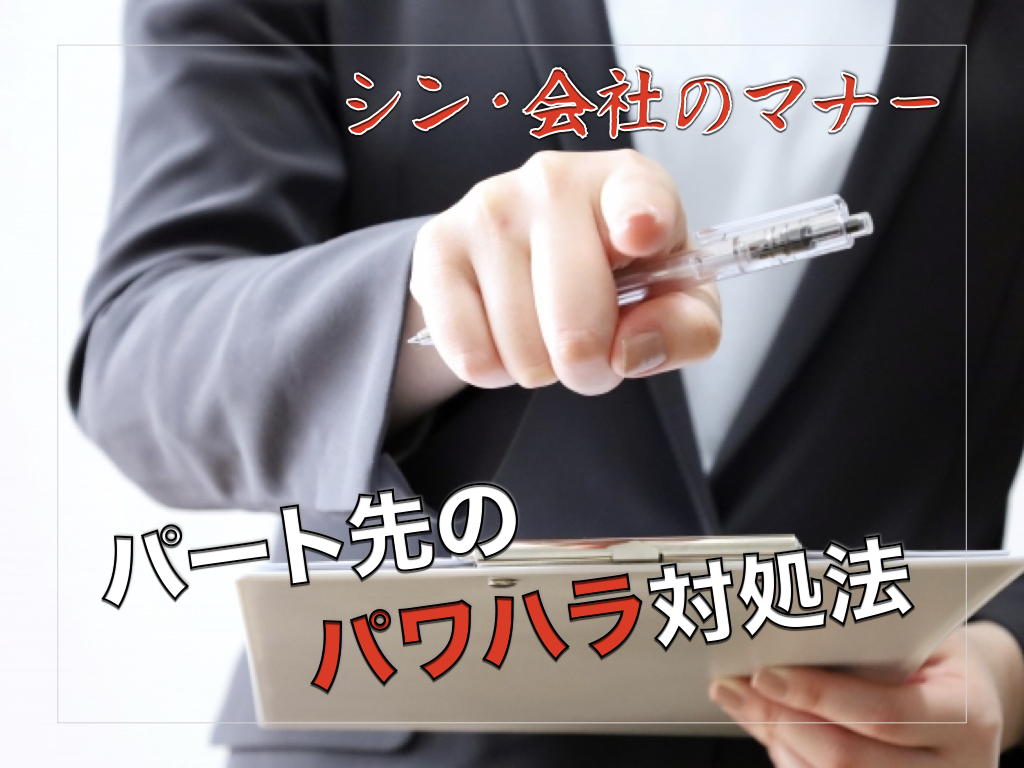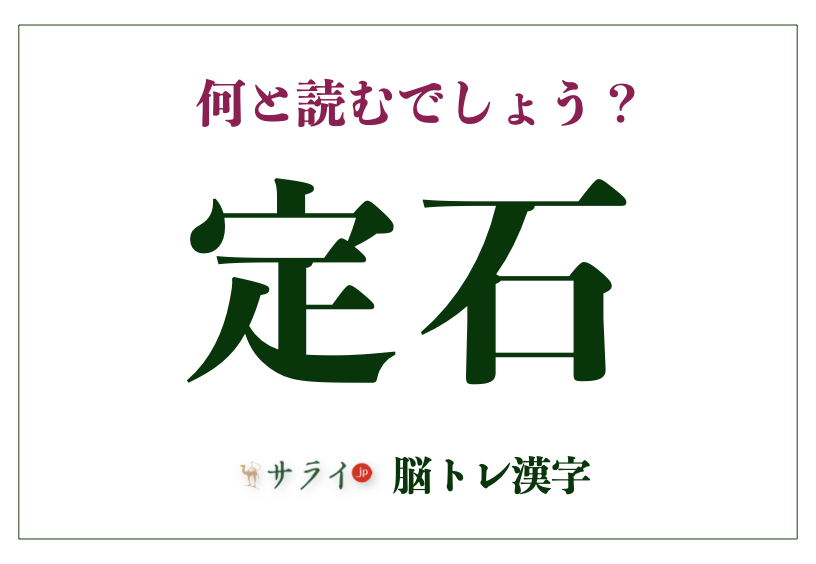熟年離婚という言葉も聞かれる昨今、中高年になってから離婚を考える夫婦は増えました。けれども、離婚したくても、その後の生活を考えるとできないという人もいます。特に妻の側は、経済的な問題で踏み切れないという人も多いのでないでしょうか? 今回は、離婚時の年金分割について、人事・労務コンサルタントとして「働く人を支援する社労士」の小田啓子が解説していきます。
目次
年金の離婚分割とは?基本的な仕組みと概要
年金分割を受けるための条件
年金分割の具体的な計算方法とシミュレーション
年金分割の手続きと必要書類
まとめ
年金の離婚分割とは? 基本的な仕組みと概要
離婚するとき夫婦の共有財産を分けることは、一般的になっています。けれども、年金も分割できることを知らない人は少なくありません。年金分割の仕組みについて見ていきましょう。
年金分割の対象となる年金の種類
年金分割は、結婚生活の中の夫婦それぞれの役割・経済的貢献度を公平に評価することを目的としています。対象となる年金は、婚姻期間中の厚生年金です。国民年金は分割の対象になりません。離婚時の年金分割制度は、次の2種類となります。なお、国民年金の第3号被保険者とは、厚生年金の被保険者に扶養されている配偶者を指します。
(1)合意分割制度
離婚したとき、夫婦の一方、又は双方の請求により、婚姻期間中の厚生年金の記録を当事者間で分割できる制度です。それぞれの報酬に開きがあっても、当事者の合意または裁判で按分割合を決めることがきます。
(2)3号分割制度
離婚したとき、第3号被保険者であった人の請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の配偶者の厚生年金記録を夫婦で2分の1ずつ分割できる制度です。3号分割は相手の合意は必要ありません。
年金分割を受けるための条件
離婚時に年金を分割するためには、婚姻期間中に厚生年金に加入していたことがあることが条件です。制度の内容をもう少し詳しく見ていきましょう。
婚姻年数と年金分割の関係
合意分割制度は、婚姻中の全期間の厚生年金記録が分割の対象になります。厚生年金の支給額は、給与・賞与の標準報酬額の記録に応じて計算されますので、離婚時の分割は基本的に標準報酬の多いほうから少ないほうに分割されることになります。
つまり、婚姻期間が長いほど、報酬の少ないほうは有利になります。一方、3号分割できる期間は平成20年4月1日以後の婚姻期間となっています。3号分割の請求を行なうと、夫婦のどちらかが専業主婦(夫)で無収入の場合であっても、相手の年金の2分の1を受け取ることができます。これもまた、平成20年以降4月1日以後の婚姻期間が長いほど、分割される金額は多くなります。
共働き夫婦の年金分割
共働き夫婦の場合、主に合意分割制度を利用することになります。この制度は夫婦の合意により、婚姻期間中の2人の厚生年金納付記録(標準報酬)を、任意の割合で分割することができる制度です。例えば、婚姻期間中の夫の標準報酬の合計が妻の2倍であったとしても、協議または家庭裁判所の決定でその割合を変えることができます。
報酬が多い方から少ない方に、両者が2分の1ずつの割合になることを限度として、合意した按分割合で分けることができるのです。なお、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間があったときは、同時に3号分割の請求があったものとみなされます。

年金分割の具体的な計算方法とシミュレーション
離婚して、実際に年金分割を行なうとどのようになるのでしょうか。具体的な例を挙げて、分割後の年金を試算してみることにします。
年金分割額のシミュレーション例
次のような、厚生年金記録を持つ夫婦が離婚したと仮定して分割を行ないます。
参考例)
夫:A社勤務…20年
妻:B社勤務…8年(合意分割期間)
専業主婦…12年(3号分割期間)
2人が共働きであった8年間の標準報酬の合計
夫…5,000万円
妻…2,000万円
妻が専業主婦であった時の標準報酬の合計
夫…8,000万円
この場合、共働きの8年間の記録を4対3の割合で合意分割したとすると、夫4,000万円、妻3,000万円となります。妻が専業主婦の期間は3号分割となるので、12年間の標準報酬を2分の1ずつに分割するとそれぞれ4,000万円となり、20年間の年金記録は夫8,000万円、妻7,000万円となります。
年金分割の手続きと必要書類
分割の手続きは、合意分割も3号分割も離婚した後に行なうことになります。手続きが大変なのでは? と心配する人もいるかもしれません。手続きとその流れについて解説します。
必要な書類とその取得方法
まず、合意分割です。「標準報酬改定請求書」を年金事務所で入手し、提出することによって分割は行なわれます。請求時には、以下の書類を添付することが求められます。
(1)請求日前1か月以内に交付された夫婦二人の生存を証明できる書類
戸籍謄本、抄本、住民票など
請求書にマイナンバーを記入することで省略できます。
(2)婚姻期間を証明する書類
(3)話し合いで按分割合を決めたときは公正証書など
裁判で決めた場合は審判書、調停調書の謄本、抄本。3号分割の場合は2人の合意は必要ないので、(3)の書類は不要となります。
年金分割の手続きの流れ
離婚すると決めても、それぞれの年金記録がどうなっているのかわからないと不安ですね。分割のための情報請求は離婚前でも行なうことができます。年金事務所に情報請求すると、離婚前は請求した人に、離婚後はそれぞれに情報通知書が届きます。合意分割の場合は、話し合いまたは裁判所で按分割合を決定します。
3号分割のみ請求する場合は、2人の合意は必要ありません。「標準報酬改定請求書」に必要書類を添付して年金事務所に提出し、分割の手続きを行ないます。手続きが完了すると、「標準報酬改定通知書」を受け取ることになります。それぞれの厚生年金は、改定後の記録に基づいて支給されます。
なお、分割の手続きは、離婚後2年を過ぎるとできませんので注意が必要です。
まとめ
離婚したら、老後の生活が心配という人は少なからずいるでしょう。離婚時の年金分割は、専業主婦やパートなど収入の少ない人にとって心強い制度です。夫が主な働き手だった場合、「年金までとられるのか」と反発するかもしれません。けれども、年金も含めて結婚生活で築いた財産は、夫婦2人の努力によるものであることを忘れてはなりません。
●執筆/小田 啓子(おだ けいこ)

社会保険労務士。
大学卒業後、外食チェーン本部総務部および建設コンサルタント企業の管理部を経て、2022年に「小田社会保険労務士事務所」を開業。現在人事・労務コンサルタントとして企業のサポートをする傍ら、「年金とライフプランの相談」や「ハラスメント研修」などを実施し、「働く人を支援する社労士」として活動中。趣味は、美術鑑賞。
●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com