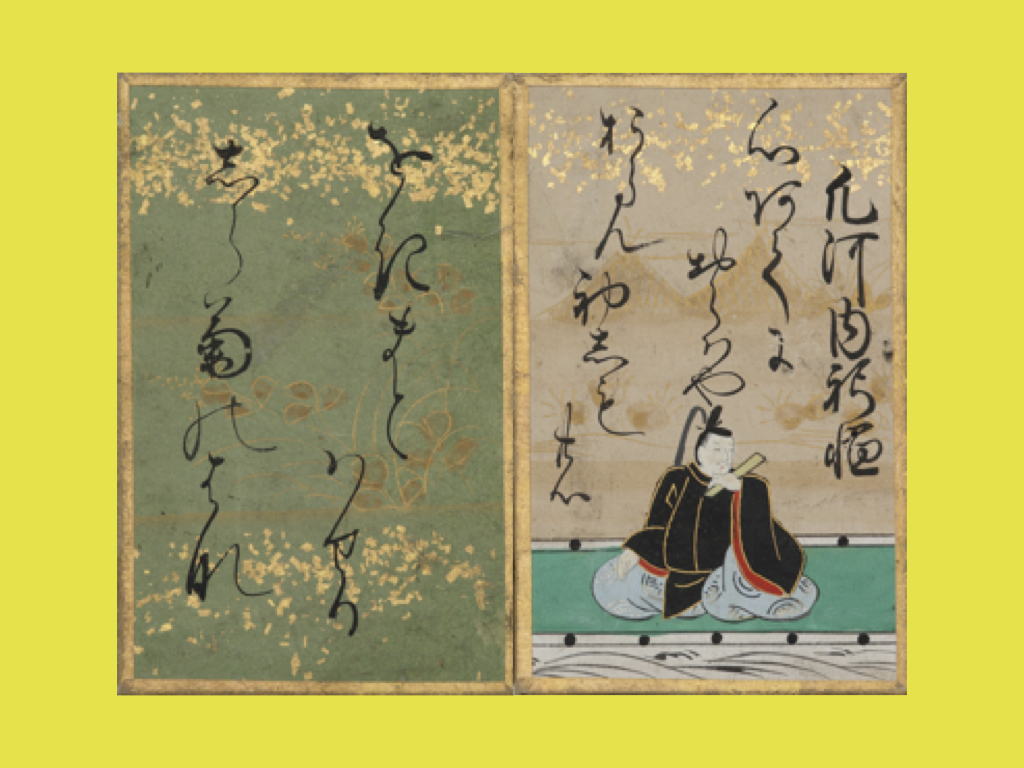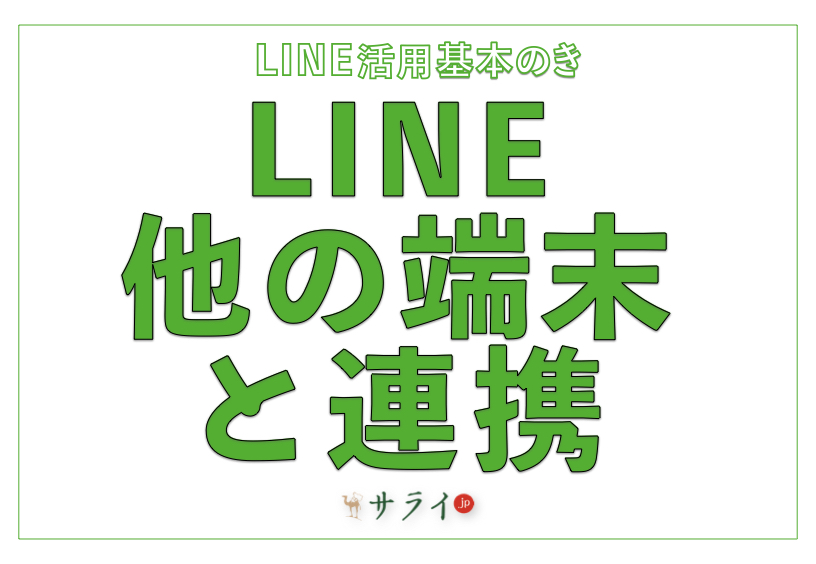連日暑い日が続きます。
東京・日本橋では、毎年夏に「ECO EDO 日本橋」と題し、“江戸の涼”を体験できるイベントを街の至るところで実施しています。そんな中、老舗百貨店の日本橋三越では、7月3日(金)~7日(火)まで店内のご案内係や各階の店頭販売員がゆかたを着用し、接客しました。期間後も、店舗内の一部ではゆかた姿の店員を見かけることができるはずです。
また、4日(土)には、日本橋料理飲食業組合青年部が結成する「日本橋三四四会(みよしかい)」の若旦那による「ゆかた自慢大会」が行なわれました。
この「日本橋三四四会」は、昭和34年(1959)4月に発足したことにちなみ“三四四会”と名づけられました。真摯に料理作りに励むことで日本橋の味を守り、地域のさまざまな活動に積極的に参加することで、日本橋の活性化に取り組んでいます。
現在の会員数は約60名で、老舗あり、創業したての店もありと様々です。
今回は、そのうちの24名がゆかた姿で参加。料理場の白衣姿とは違った装いで、来場者を楽しませてくれました。

↑「日本橋 舟寿し」の二永展嘉さん(日本橋料理飲食業組合の組合長)。このゆかたは、日本橋小舟町・町会役員用として、同町の着物店「竺仙」の協力で作られたとか。現在は、一般会員や町会など多くの方に親しまれているゆかただ。

↑「鰻 高嶋家」の五代目の鴛尾 明さん。同店は、明治8年(1875)に神楽坂で創業し、その後日本橋小舟町に移転して140年続く。写真のゆかたは、この日のためにあつらえたもの。涼しげな青い瓢箪柄で、無病息災を願っているそう。

↑昭和21年に日本橋・茅場町で創業した果実店「イマノフルーツファクトリー」が経営するレストラン「ビストロ サブリエ」のシェフ・今野登茂彦さん。季節の果実を料理に取り入れていて、四季の移り変わりも料理と一緒に楽しめる。

↑昭和23年に創業し、今年で67年を迎える居酒屋「いけ増」の喜多高廣さん。四季折々の旬の食材を毎朝築地より仕入れ、丹念込めて調理しています。今回の浴衣は、幼少期に過ごした新潟県・小千谷の小千谷縮で仕立てました。

↑明治2年創業で、東京で最も歴史あるすき焼き店として知られる「伊勢重」の七代目・宮本尚樹さん。この浴衣は、五代目の祖父の形見の反物で仕立てたもの。高砂部屋のOB会会長を努めていたご縁で、部屋より頂戴したものとか。

↑明治7年創業の鰻料理店「喜代川」の五代目・渡辺昌宏さん。この浴衣は若女将が嫁ぐときに誂えた手ぬぐいの型を使って作ったもの。カタカナの「キ」、火消し文字の「よ」、三本線で「川」と、喜代川をあしらっています。

↑昭和18年に遡る初代の本店長から数えて28代目の日本橋三越本店長・中 陽次さん。延宝元年創業の呉服商・越後屋がその前身で、日本初の百貨店は今年で創業342年目。日本橋の老舗の皆さんとともに、1日楽しめる街づくりに参加していきたい、とのこと。

↑江戸時代の日本橋の魚河岸は「毎朝千両ずつ落ちる」と言われたほど盛況な魚河岸がありました。その日本橋室町の魚河岸の魚屋「高根屋」を前身とする鮨店「繁乃鮨」三代目で三四四会会長の佐久間一郎さん。この浴衣は、日本橋三越で新調したものです。

↑日本橋・八重洲地域の若旦那集の記念撮影会。この後、お客様との記念撮影会も行なわれた。
三四四会の若旦那たちが浴衣を誂えた日本橋・竺仙については、以下をご覧ください。
日本橋 竺仙
http://www.chikusen.co.jp/