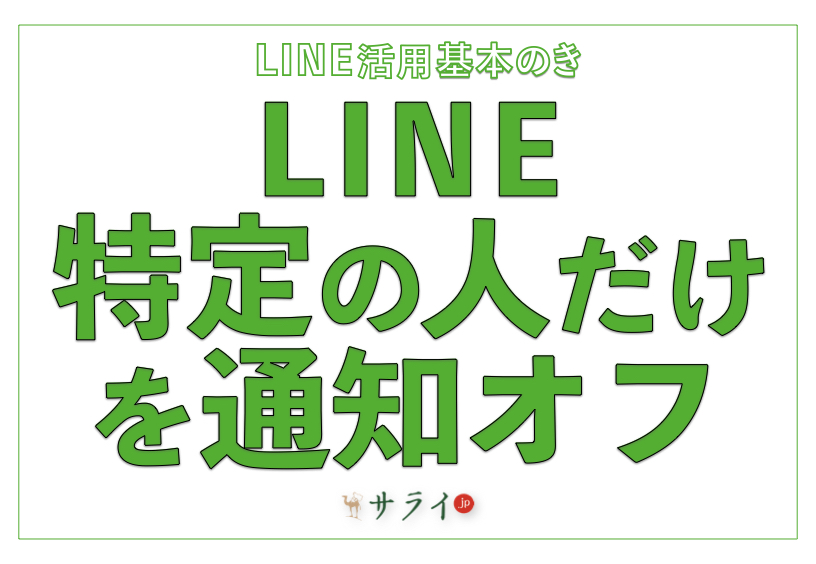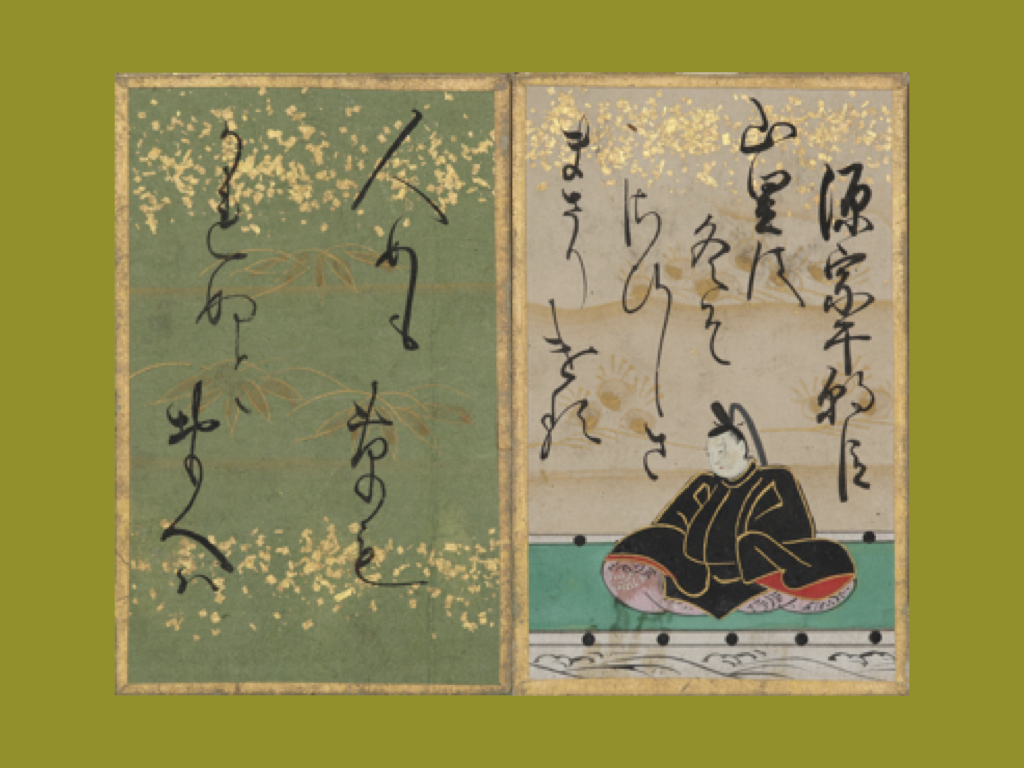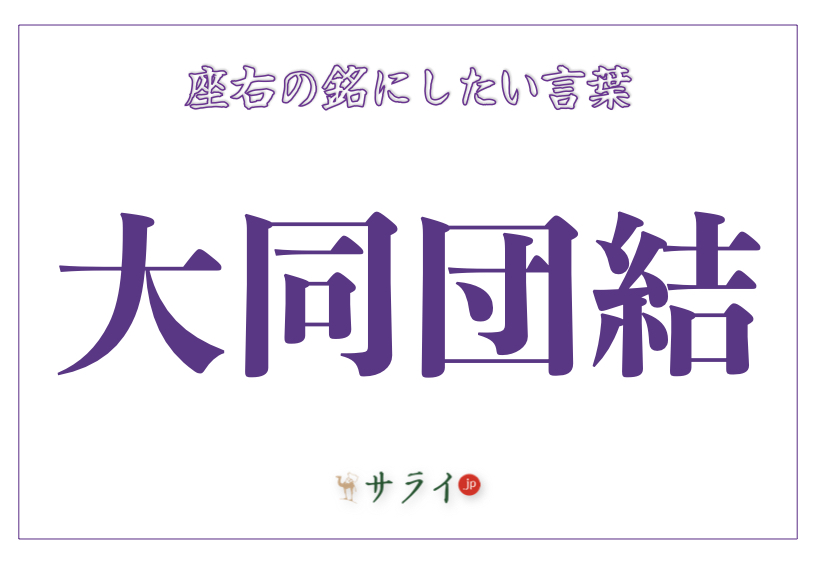妻の遺品をフリマアプリで孫が処分、売り上げ総額は60万円に
コロナ禍もあり、「いつ死ぬかわからない」という思いもあって、卓治さんは家の処分を決意する。
「息子に“本を捨てるのは忍びない”と言うと、“いいようにするから心配ない”と言ってくれました。どうするのかと思ったら、SNSで次の引き取り手を探してくれたんです。僕の蔵書は文学や写真集、妻のは被服史やフランス関連の本が多かった。まず、業者を呼んで、めぼしい本を持っていってもらったら、30万円にもなったんです」
値段がついたのは、妻が持っていた遊郭関連の資料が中心だったという。卓治さんの写真集も高値がついた。購入時無名だった有名写真家の写真集は、一冊5万円で買い取りされたという。
「そこから、息子夫妻がSNSで知り合った人を家に連れてきてくれた。小学生から70代の人まで40人くらいいたんじゃないかな。“ありがとう。探していた本です”と持っていってもらえるのが、本当に嬉しかった。マスクで顔が見えないのが残念だったけどね。みんながお菓子や佃煮や酒などを持って来てくれて、それはありがたくいただきました」
1万冊あった蔵書は、3年かけて減っていき、最後に残ったものは古紙回収に出した。
「息子夫婦は、捨てたくないという僕の気持ちに寄り添ってくれた。あと時間をかけて伴走してくれたのもありがたかった。片付けをしていたら、教員をしていた親父が退職金で手に入れたモンブランの万年筆が出てきたり、質屋の娘だった母が実家から譲られたダイヤモンドの指輪が出てきたり。母の指輪はみんな立て爪のもので、昔風のデザインだったので、妻は仕舞い込んでいたんですよ。このお宝を息子夫妻に渡せたのもよかった。こういうことも親孝行だと思いました」
当時、高校生だった孫は、両親から「おじいちゃんの家からお宝が出てきたよ」と聞いたのだろう、学校帰りに飛んできたという。
「息子の家は、ウチから2時間の神奈川県内にあるので、盆と正月、あとは彼岸のお墓参りのときくらいしか会わなかったんです。孫は男の子なんですが、上手にいろんなものを探してきて、それをフリマアプリで売るという。“売れたらそのお金はあげるよ”と言うと、“それは公平ではないので、山分けしよう”と言うんです。1年くらい売っているうちに、総額が60万円になったと、30万円をくれました」
妻の出自を聞くと、「義父は地方の経営者で、義母はお妾さんでした」という。妻が大学に進学した1970年の女性の進学率は6.5%(文部科学省『文部統計要覧』)であり、裕福でリベラルな家庭でないと、娘を大学に出すことは難しい時代だった。
「育ちがいい妻は、何かを買うときに“ブランドものは間違いがない”と2倍以上の値段がするのをポンと買う。それが時間を経ても高額で売れるのはすごいことですよ。そのお金を使って、息子一家3人と僕で、妻との思い出がある群馬の温泉旅館に泊まりました。一人で行くのは寂しいけれど、死ぬまでに1度は行きたいと思っていたところに、息子夫婦や孫まで同伴してくれるという」
さらに嬉しかったのは、それを聞きつけた福岡に住む娘夫婦が、“私たちも行く”と合流してくれたことだ。
「思いがけない大旅行になって、楽しかったですよ。娘は食事の間“お母さん、ここにいるでしょ?”と、妻のためのワイングラスを置いた席に、ことあるごとに話しかけ、ずっと泣いていました。そこに婿さんが泣きながら“いるよ、いてくれているよ”と泣いている。息子もお嫁さんも、孫もみんな泣いていて、私も心置きなく泣いて、あれがお葬式になったと思います」
娘夫婦には子供はおらず、息子夫婦に授かった孫は一人だ。卓治さんは「孫はやがて一人になる。血が繋がった人がみんな集まるという経験をさせられたのもよかった」と話していた。この旅行の後、卓治さんは近所のサービス付き高齢者住宅に引っ越した。月の家賃は20万円近くするが、年金で賄えているという。
しかしこの住宅は、介護度が重くなったら住むことはできない。介護施設の入居になったときには、きっと息子夫婦や孫がサポートするだろう。その繋がりを作るのも、老いた親にとって嬉しいことなのかもしれない。
取材・文/沢木文
1976年東京都足立区生まれ。大学在学中よりファッション雑誌の編集に携わる。恋愛、結婚、出産などをテーマとした記事を担当。著書に『貧困女子のリアル』 『不倫女子のリアル』(ともに小学館新書)、『沼にはまる人々』(ポプラ社)がある。連載に、 教育雑誌『みんなの教育技術』(小学館)、Webサイト『現代ビジネス』(講談社)、『Domani.jp』(小学館)などがある。『女性セブン』(小学館)などにも寄稿している。