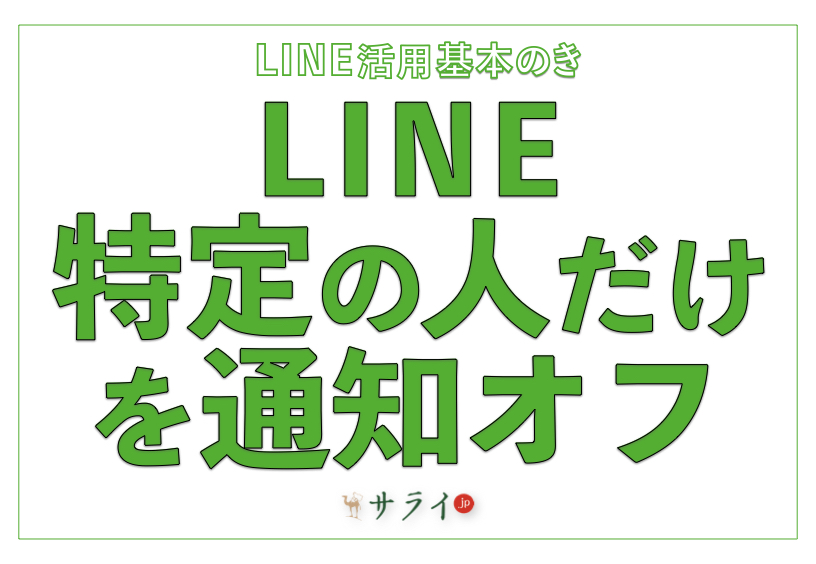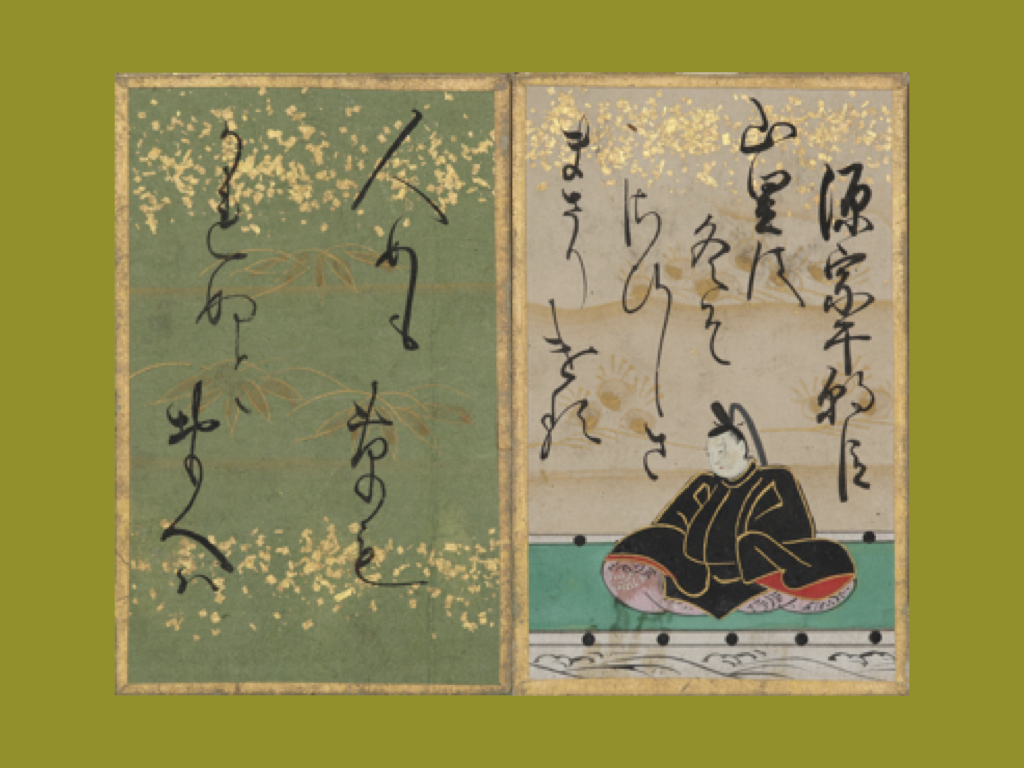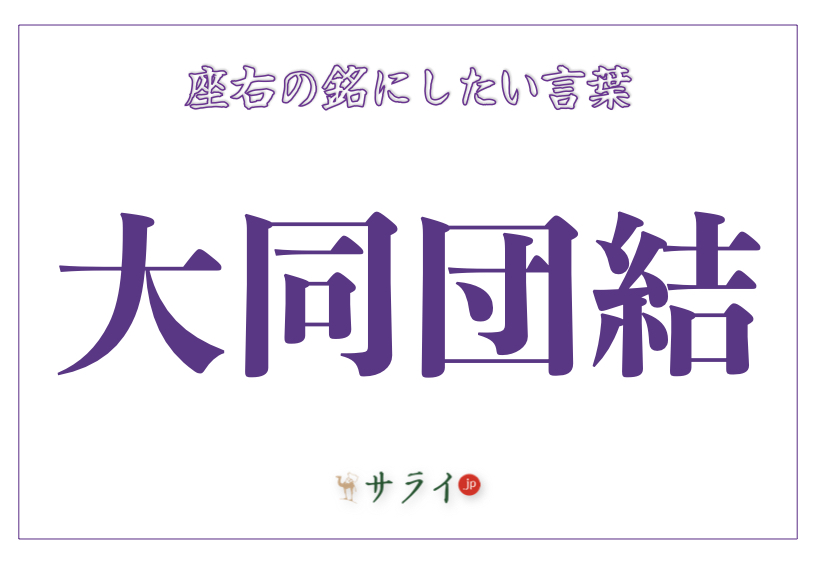高齢者が賃貸住宅の入居を断られるケースが増えている。これは大家側が、孤独死や認知症発症を懸念した結果ともいえる。とはいえ、高齢者は増え続けており、2025年10月には対策につながる「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(住宅セーフティネット法)が成立した。
これにより、高齢者、障害者、低所得者など住宅の確保に配慮を必要とする人が、民間賃貸住宅への入居につながるような市場整備が進められている。
現在、東京都内のサービス付き高齢者住宅(サ高住)で一人暮らしをしている卓治さん(75歳)は「多分、うちには1万冊の本があった。あれを抱えたままでは、ここに引っ越せなかった。体が動くうちに、息子が“然るべき次の世代の人”に届けてくれたことに感謝している」と言う。
元会社員の卓治さんは5年前にコロナで妻を亡くした後、階段がある自宅での生活に不安を覚え、サ高住の入居を検討する。5年間の準備期間を経て、1年前に入居したバリアフリーの30平米のマンションは、それまでの戸建てと比べると、圧倒的に住みやすいという。
【これまでの経緯は前編で】
本を捨てたくなくて、狭い実家に住むことを決める
大学時代に、歌舞伎町の喫茶店でボーイのアルバイトをして、ホステスと交際。学業にも手を抜かず、学生運動と距離を置いていたこともあり、大手企業に入社。
「インフラ関係の会社でとても安定していました。会社が仕事と給料をくれて、家も提供してくれる。会社名を言うだけで、いくらでもお金を貸してくれる時代でした。28歳のときに、大学で知り合った2歳年下の妻と結婚し、下町の狭い家を出ました。結婚すれば社宅を提供してもらえたので、そこに入居。その間に息子と娘が生まれて、彼らの大学の学費を払い終えて、ホッとしたところで両親が相次いで亡くなったのです」
京都に住む兄夫婦と、実家をどうするかという話になったが、実家には卓治さんの大量の本がある。
「僕も兄も自分たちが買った家があったものの、実家をそのままにするわけにもいかない。兄は“ここを更地にして、地主さんに土地を返そうか”と持ちかけて来たんです。実家にある本を捨てたくなくて迷っていると、妻が“私たちがここに住まない?”と言う。妻はデラックスなマンションで生まれ育っているので、階段がある家に憧れがあったみたいです」
水回りのリフォームを済ませて、50代半ばの卓治さん夫妻は両親が住んでいた家に転居する。東京郊外のマンションは売り、そのお金は資産運用に回した。
「そこに結婚してから買った本も運び込んだんです。2階の6畳は本で潰れました。以前に住んでいた家よりも収納が多く、子供もいない。妻も本が好きなので、せっせと買い込んで、レコードをかけながら本を読んでいました」
生まれ育った街に戻ったことは、卓治さんの毎日を楽しいものにした。
「小中学校の同級生は地元で商売をしていますので、とにかく顔見知りが多い。祭りや行事に誘われたり、手伝いを頼まれたりしているうちに、あっという間に歳月が経っていきました。地元の人間関係は面倒でもありますが、年を重ねるといいもの。定年退職後も、“俺の店を手伝え”と蕎麦屋やフグ屋でホールの接客を頼まれる。これは昔とった杵柄で何とでもなります。でもそう考えると、15年前から人手不足は始まっていたんですね」
定年から10年間、コロナ禍になる70歳まではそれなりに楽しかった。コロナ禍で飲食店は休業に追い込まれ、冷静になったときに、卓治さんは体の老いを実感する。そんなとき、妻が68歳の若さで、新型コロナ感染により命を落としてしまったのだ。
「まだ、感染が危険視されていた頃で、陽性だと分かったら病院に運ばれ、骨になって帰って来ました。だから全く気持ちの整理がついていませんし、実は今も生きているような気がするんです。遺体に触って“ありがとう”とか“愛している”と伝えたかった。僕の人生はラッキーの連続だと思っていましたが、最後の最後で、幸せのツケを払わされるとは思わなかった」
自宅には妻の本や服など、気配が濃厚に残っている。
「病院に行く前に、妻は僕にシチューを作ってくれたんです。でもこっちは心配で食欲がない。入院の3日後に死んだと連絡が来たときに、初めて口にしました。妻が帰ってくるんじゃないかと思ったんですが、そうはならなかった」
妻の死去後、家も命を終えようとしているのか、雨漏りやネズミの侵入など多くの問題が起こり始める。
「息子夫婦に連絡すると、“家を撤去して、地主さんに土地を返すしかない”という話になったんです。1年くらい迷いましたが、この家にいては孤独死する未来しか見えなかった」
【息子夫婦がSNSで本の引き取り手を探してくれた…次のページに続きます】