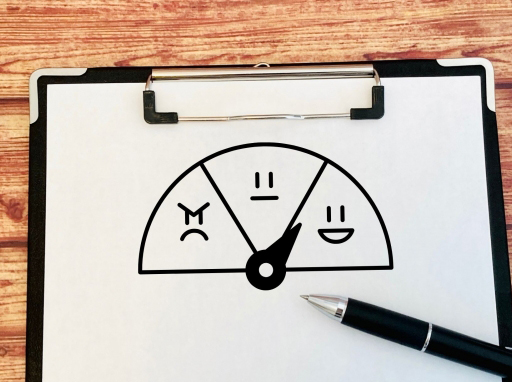取材・文/沢木文
親は「普通に育てたつもりなのに」と考えていても、子どもは「親のせいで不幸になった」ととらえる親子が増えている。本連載では、ロストジェネレーション世代(1970~80年代前半生まれ)のロスジェネの子どもがいる親、もしくは当事者に話を伺い、 “8050問題” へつながる家族の貧困と親子問題の根幹を探っていく。
* * *
2023年10月13日、内閣府は「家計可処分所得・家計貯蓄率四半期別速報(参考系列)」を発表。これは日本の家庭の財布事情を表すデータともいえるのだが、それを見ると、可処分所得に占める家計の貯蓄率が2023年4ー6月期(季節調整値)で1.8%と5期ぶりに増加していることがわかる。
高額な維持費に危機感を覚え、マンションを売却
このことを知り、「そう、貯蓄はした方がいい。なぜなら、高齢無職になると、貯金が生命線になるから」と語るのは、現在都内の高齢者住宅で独り暮らしをしている康夫さん(79歳)だ。康夫さんはかつて、フリーランスの芸能関連プロデューサーとして活躍していた。当時は、芸能人と交際したり、海外ロケに行ったり、三ツ星レストランで食事をしたりと派手な生活をしていたという。
「あのころはデタラメだったから。昔を振り返りたくないけれど、やはり考えてしまう。今は独居の貧困老人だから。収入は国民老齢年金と、女房の遺族年金、あとは給付金(年金生活者支援給付金)を合わせて10万円くらい。これで、家賃、光熱費、スマホ代、介護保険料、食費を払うのだからカツカツ。生活費は1日1000円と決めてやりくりしている」
住まいは、都営住宅だ。50代後半のあるときから、ぱったり仕事がなくなり、それまで住んでいたマンションを売却し、都営住宅に移り住んだ。
「これがとてもよかった。あのマンションは、年間の管理維持費が15万円ほどかかり、固定資産税も15万円くらいあった。持ち家なのにさらに金がかかるって、ばかげた話。女房は“持ち家で終の棲家だから”って反対したけれど、私は維持費をかけないほうをとった。いま、ウチの団地の友達とたまに話しているんだけど、賃貸は楽だってこと。貧乏人の負け惜しみかもしれないけれど、不動産の所有には金がかかる。あの時売っておいてよかった」
しかし、売却したのは、東京のマンションが底値だった2000年代前半。いまならもっと利益があったのに、と康夫さんは笑う。そんな彼が今のような苦しい生活になったのは、5年前に妻が死去してからだという。
「マンションを売ったのは、還暦のころ。あの頃は貯金もあったのよ。ウチの娘2人は海外の大学を出ているのだけれど、それができたのは私の収入も合ったけれど、女房も稼いでいたから。この年にしては珍しく、一般企業に定年まで勤めた女傑なんだよね。今でいうダブルインカムだから、それなりに貯えもできたわけ」
【妻の厚生年金は15万円もあったが……次のページに続きます】