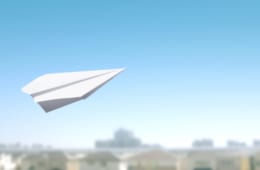文/印南敦史

『老いを愛づる – 生命誌からのメッセージ』(中村桂子 著、中公新書ラクレ)の著者が年齢を感じたのは、50代の初めごろ、白い髪の毛を見つけたときだったそうだ。
以後、美容師に勧められ黒髪に染めた時期もあったものの、86歳になった現在は全体がグレーになった状態。自然に任せた結果、気分が明るくなったという。
先日、電車で立ったまま本をバッグから出して読もうとしましたら、前の席に座っていた青年がスッと立ち上がりました。どうぞと言われ、大丈夫ですよと遠慮したのですが、「座って読まれた方が楽ですよ」とニコニコされたので、思わず座ってしまいました。申し訳なく思いながら、とてもよい気持ちにもなっていました。大学生でしょうか。このような若者がこれからすてきな社会をつくってくれるのだろうなという期待も生まれました。私の方が先に降りましたので彼に席をお返しして、浮き浮きしながら家路についたのでした。実はグレーヘアにしてから、このような体験が増えました。(本書「はじめに」より)
やがて、そんな日常的な経験は、「老いをマイナスとして捉えるのではなく、なかなかおもしろいところもあるという気持ちを語ってみたい」という思いへとつながっていく。同時に、理学博士として長らく続けてきた研究ともリンクしていったようだ。
私の場合、生きているってどういうことだろうという問いに正面から向き合い、しかもそれを小さな生きものたちが生きている姿に学ぶという生命誌の研究を続けてきましたので、そこから生まれる思いを語りたい気持ちもあります。(本書「はじめに」より)
つまりそれは、他の生きものと同等に、人間を生きものとして見るということ。そうすることによって、「生まれる」「育つ」「成熟する」「老いる」「死ぬ」という自分の一生を少し離れたところから見られるようになるのだろう。
生命誌の研究をしてきた自分が、年を重ねるにつれ、生きものとしての自分を外から見る気持ちになれたことを、純粋に「おもしろいな」と感じられているようだ。そこで本書では、著者が「いいな」と感じる生き方をしている人がもらしたことばを取り上げ、さまざまな思いをつづっているのである。
しかもその人選と、そこからつながる発想がユニークだ。たとえば草取りと落ち葉掃きの作業が「バカボンのパパ」に考え方につながっていったりするのだから。
生きものの研究という仕事柄、自然から離れた暮らし方は苦手で、東京という高層ビルが立ち並ぶ街の中でも緑が多い場所で暮らしています。ただ、自然とは面倒なもので、いつも変化していますし、手入れが必要です。ちょっとお洒落に園芸というとカッコよいですが、庭での作業のほとんどは草取りと落ち葉掃きです。(本書31ページより)
嫌いなことではなかったこともあり、60代くらいまでは「やるからには徹底的に」という気持ちがあった。ところが次第に「また生えてくるんだから」「明日になったらまた落ちてくるんだし」などと考えるようになり、それまで100%やっていた作業は97%くらいに減ったという。
重要なポイントは、わずか3%の差がとても大きかったという事実だ。たとえば濡れて地面にくっつき、すぐには取れない葉っぱなどがあっても“これでいいのだ”と思えるようになり、驚くほど気持ちが楽になったというのだ。
これって赤塚不二夫さんの『天才バカボン』のパパのセリフですよね。でも、今や私のものになりきっています。(本書32〜33ページより)
年をとって体力が落ちてきても、“ああ、年をとった……”と落胆するのではなく“これでいいのだ”と思えばいい。自分にはできると必要以上にがんばってしまったり、できないと嘆いたりすればつらく感じるのは当然。逆に、逆らわないようにすれば楽だという発想である。
それは救いの道ができていると考えることもでき、そういう意味で人間はうまくできているのだ。
真宗大谷派難波別院の掲示板には、「これでいいのだ 〜赤塚不二夫〜」とあるとのことです。バカボンのパパのこのセリフは、「ありのままを受け入れる」というお釈迦様の悟りの境地に重なると解説されていました。それは「過去」や「未来」から離れて「現在」を見ることであり、目の前にある幸せを感じることなのだそうです。お釈迦様と比べるのはおこがましいですし、難しいことはわかりませんが、私は「今を大切に」生きていこうとしています。(本書33ページより)
たかが草取りや落ち葉掃きだとはいえ、“これでいいのだ”と考えれば気持ちはおのずと楽にもなるだろう。また、それがお釈迦様の教えに通ずるものがあると知り、「なんともありがたく、元気になりました」と著者は述べている。
だがこれは、すべての人に当てはまることではないだろうか。人は日常生活のなかにおいても、(著者の草取りや落ち葉掃きがそうであったように)ちょっとしたことで自分を追い詰めてしまいがちだ。
そんな傾向は、年齢を重ねれば重ねるほど強くなってもいくだろう。だが、それがうまくいかないとなると、そこからくる怒りや不満が外部に向かってしまう危険性もないとはいえない。
しかしそんなとき、“これでいいのだ”と思えることができたらどうだろう? おそらく、著者のように楽な気持ちになれるはずだ。

中村桂子 著
中公新書ラクレ
文/印南敦史 作家、書評家、編集者。株式会社アンビエンス代表取締役。1962年東京生まれ。音楽雑誌の編集長を経て独立。複数のウェブ媒体で書評欄を担当。著書に『遅読家のための読書術』(ダイヤモンド社)、『プロ書評家が教える 伝わる文章を書く技術』(KADOKAWA)、『世界一やさしい読書習慣定着メソッド』(大和書房)、『人と会っても疲れない コミュ障のための聴き方・話し方』『読んでも読んでも忘れてしまう人のための読書術』(星海社新書)、『書評の仕事』(ワニブックスPLUS新書)などがある。新刊は『「書くのが苦手」な人のための文章術』(PHP研究所)。2020年6月、「日本一ネット」から「書評執筆数日本一」と認定される。