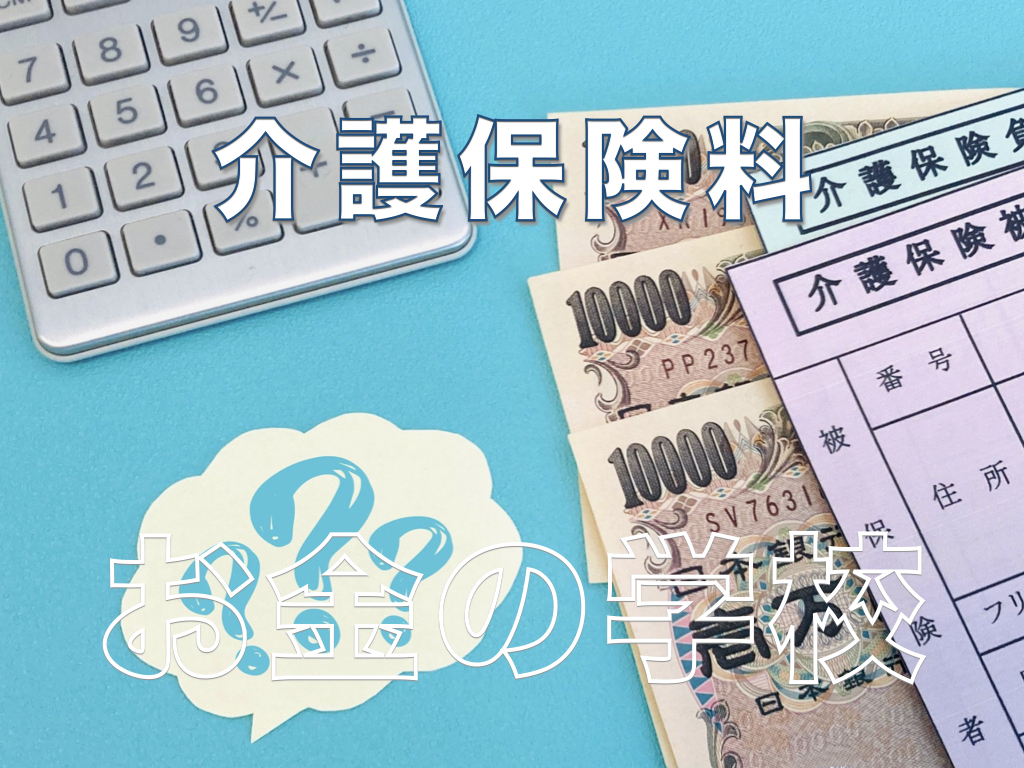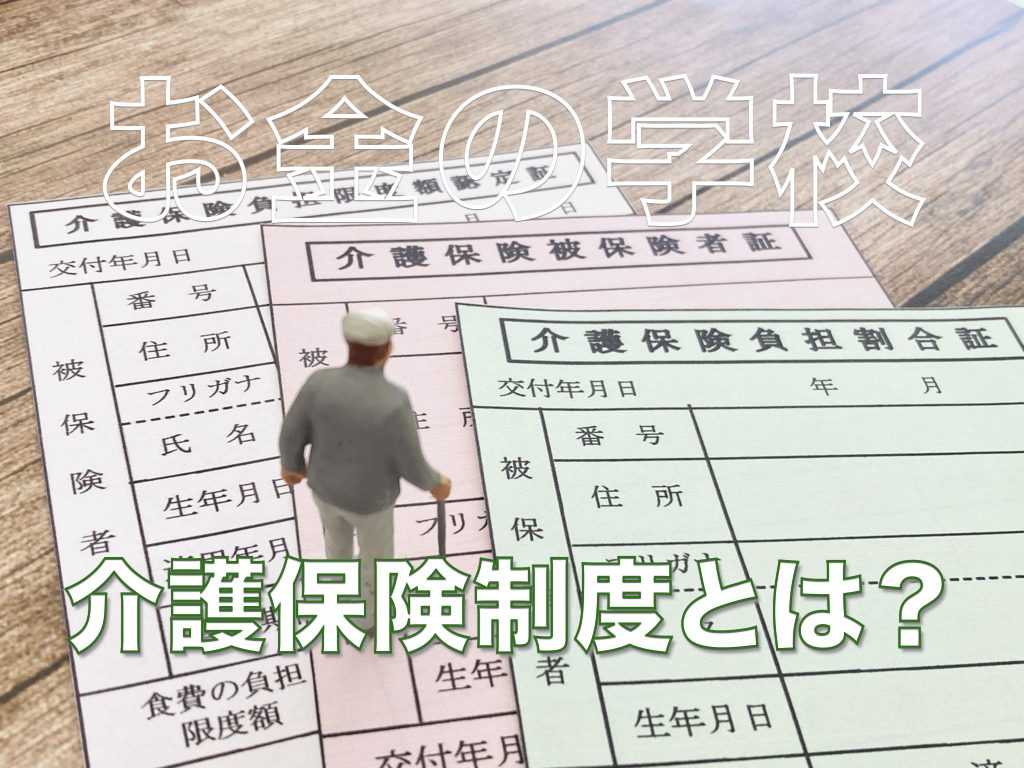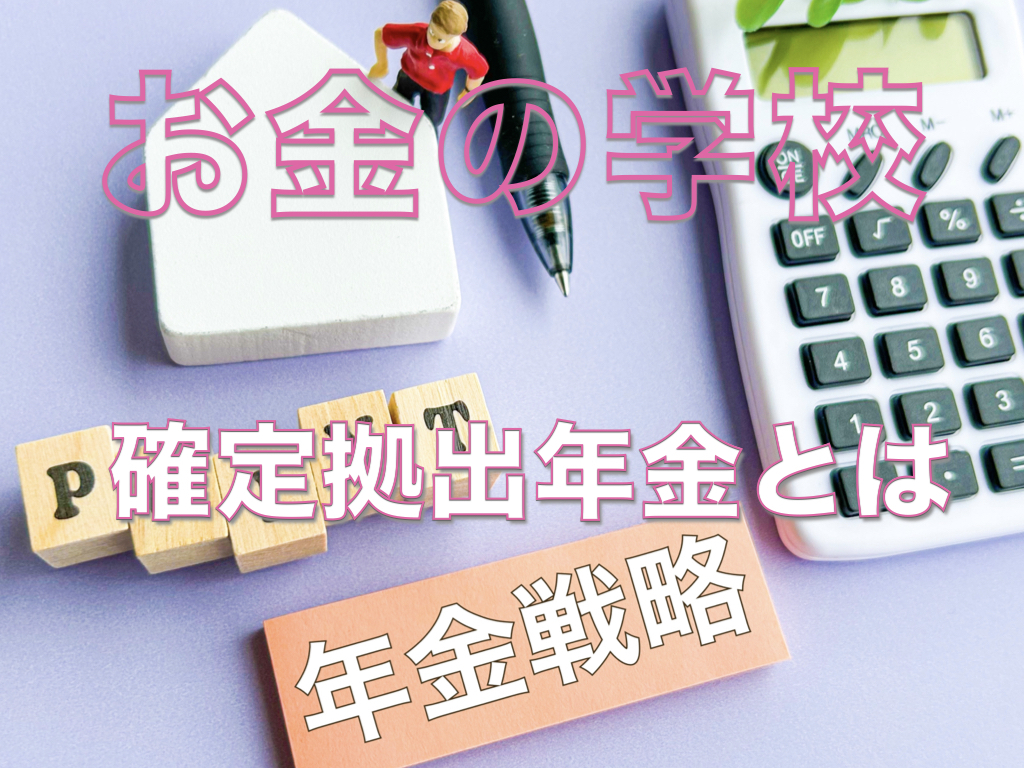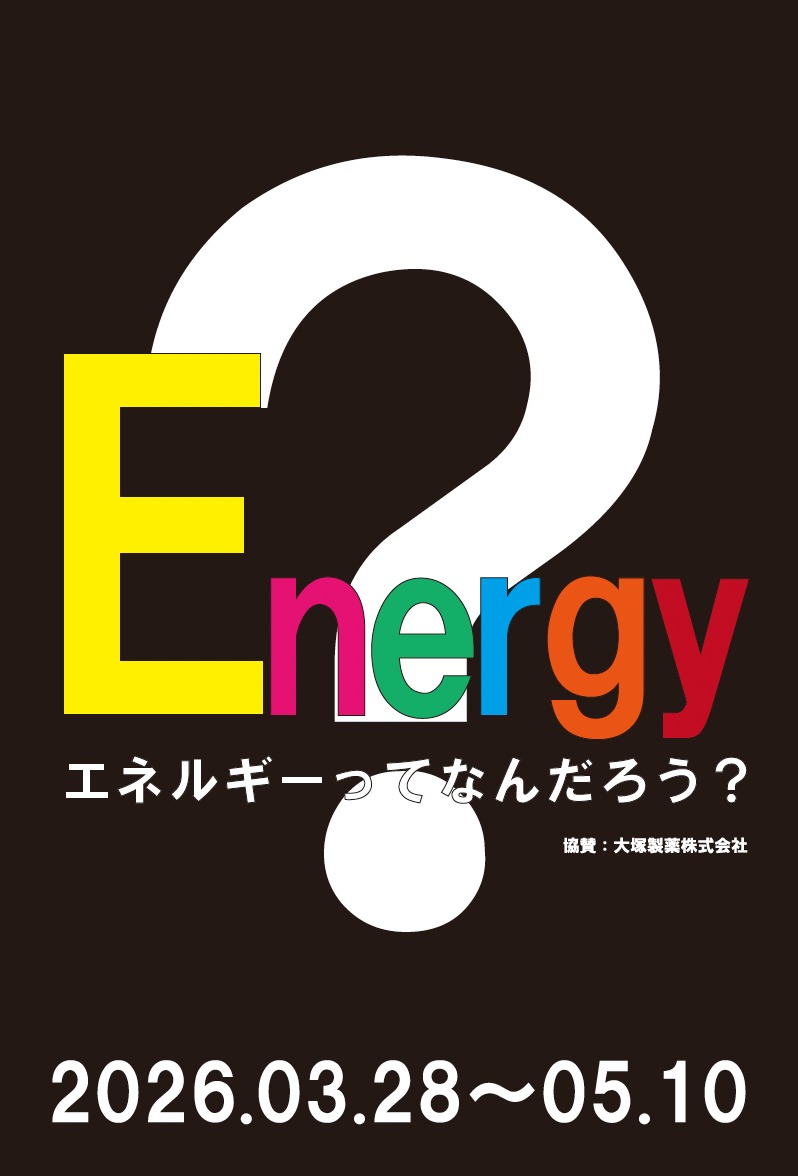介護保険制度は、介護が必要になったときに備える大切な制度ですが「いつの間にか保険料を支払っていた」と感じる人も多いのではないでしょうか? とくに65歳以上になると、年金からの天引きなどで、介護保険料の負担や具体的な仕組みがわかりにくい部分もあります。
今回は、介護保険料の支払い開始のタイミングや仕組み、負担額についてみていきましょう。これから介護保険料を負担する方や、仕組みを理解しておきたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
100歳社会を笑顔で過ごすためのライフプラン、ライフブック(R)を提唱する、独立系ファイナンシャルプランナー藤原未来がわかりやすく解説します。
目次
介護保険料とは? 65歳からの負担と支払い方法を解説
介護保険料はいくらかかる? 年齢別・地域別の違いを解説
介護保険料と他の保険料との違い|国民健康保険や社会保険との関係
介護保険料の段階区分とは? 負担額が決まる仕組みを理解しよう
まとめ
介護保険料とは? 65歳からの負担と支払い方法を解説
介護保険料とは、介護サービスを必要とする高齢者を社会全体で支えるために、すべての40歳以上の方が負担する保険料です。介護保険制度は「公的な社会保険制度」で、介護が必要になったときに介護サービスを受けることができる制度です。
介護保険料の負担は年齢によって異なります。40歳から64歳までの方は「第2号被保険者」として医療保険(健康保険・国民健康保険など)に上乗せして支払い、65歳以上の方は「第1号被保険者」として市区町村に直接納めます。
65歳以上になると、介護保険サービスを利用できる一方で、保険料も引き続き負担し続けることになります。
介護保険料はいつから払う? 年齢とタイミングを確認
介護保険料の支払いは、40歳の誕生日を迎えた月からスタートします。会社で健康保険に加入している人は、とくに通知されることなく保険料が給与から天引きされ始めるため「いつの間にか保険料を支払っていた」と感じる原因になっているのでしょう。
65歳以上になると、支払い方法や金額が変わります。65歳の誕生日を迎えた月の翌月から、「第1号被保険者」としての介護保険料負担が始まります。例えば、4月生まれの方なら5月から「第1号被保険者」として保険料を負担することになります。年齢による区切りが明確なため、65歳を迎える際には、事前に市区町村から介護保険料の通知が届きます。
これにより、どのタイミングで負担が発生するのか確認できます。介護保険料は一生涯にわたる負担となるため、長い目で仕組みを理解しておくことが大切です。
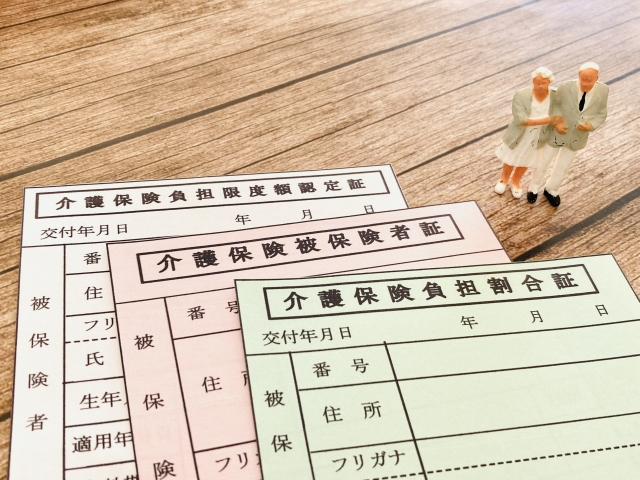
介護保険料は年金から天引き? 支払い方法を整理
65歳以上の介護保険料は、原則として年金からの天引き(特別徴収)で支払います。これは年金の受取額が年間18万円以上の人が対象です。年金が支給される際に、あらかじめ介護保険料が差し引かれるため、手続きの手間はほとんどありません。
一方、年金受給額が年間18万円未満の方や年金を受給していない人は、口座振替や市区町村から届く納付書による支払い(普通徴収)となります。このように、年金の金額や受給状況によって支払い方法が異なるので、届いた通知をよく確認しましょう。
介護保険料はいくらかかる? 年齢別・地域別の違いを解説
介護保険料の金額は、年齢によって決まるわけではなく、所得や居住する市区町村によって異なります。65歳以上の介護保険料は、各市区町村が条例で定める「基準額」と、所得に応じた段階(所得段階区分)によって決まります。
詳しくは、各市区町村の役所の窓口やホームページで確認できますので、自分がどの段階に該当するのか、一度確認しておくと安心です。ここでは、65歳以上・70歳以上の目安や地域による違いを見ていきましょう。
65歳以上・70歳以上で変わる保険料の目安
65歳以上の介護保険料は、原則として市区町村の基準額をもとに決められます。全国平均では月額約6,000円前後とされていますが、これはあくまで目安であり、実際には市区町村ごとに数百円〜数千円の差があります。
また、70歳以上になると収入や所得控除の状況によって、介護保険料が変わる場合もあります。ただし、65歳から70歳以上への移行自体で一律に保険料が変わる仕組みではなく、あくまで個人の所得段階によって決まります。
つまり、「70歳以上だから保険料が高くなる」というわけではありません。年齢だけでなく、収入の状況が大きな影響を与える点を理解しておくと安心です。
地域差に注意! 市区町村別の保険料例
介護保険料は市区町村ごとに決められるため、地域差が大きいことが特徴です。たとえば、都市部では月額7,000円を超えることもあれば、地方では5,000円台に収まることもあります。
こうした地域差の理由は、地域による高齢化率や介護サービスの利用状況などです。高齢化率が高い地域や介護サービス利用が多い地域では、保険料が高くなる傾向にあります。

介護保険料と他の保険料との違い|国民健康保険や社会保険との関係
介護保険料は、健康保険料や国民健康保険料と一緒に納付しますが、仕組みや負担の考え方が異なります。ここでは、介護保険料が他の保険料とどう関係しているかを整理しましょう。
介護保険料は健康保険料に含まれている? 仕組みを理解
40歳から64歳までの人は「介護保険第2号被保険者」として、健康保険料や国民健康保険料に介護保険料分が上乗せされる形で徴収されます。
65歳以上になると、介護保険料は医療保険とは別に市区町村に直接支払う「第1号被保険者」としての保険料になります。医療保険料と合算ではなく別々に徴収されるため、通知書や納付の仕組みが変わります。
国民健康保険の場合の介護保険料負担はどうなる?
65歳以上で国民健康保険に加入している人も、介護保険料は別途市区町村から請求されるため、国民健康保険料と介護保険料は別々に納める必要があります。40歳から64歳の間は、国民健康保険料の中に介護保険料が含まれており、65歳からは別々になるので、年齢による変化に注意しましょう。
介護保険料の段階区分とは? 負担額が決まる仕組みを理解しよう
介護保険料の大きな特徴は、所得に応じた「段階区分」で負担額が決まる点です。この仕組みをしっかり理解しておきましょう。
介護保険料の段階とは? 所得別に決まる負担額
市区町村では、住民税の課税状況や所得金額に応じて、介護保険料を15段階前後に区分しています。たとえば、住民税非課税世帯や生活保護を受けている方は、最も低い段階に設定されます。逆に、高所得者層は基準額の1.5~2倍程度の保険料を負担するケースもあります。
段階区分を左右する要素とは? 控除や扶養も影響
段階区分を決める際には、単純な所得額だけでなく、各種控除や扶養親族の有無なども考慮されます。医療費控除や社会保険料控除などがある場合、課税所得が減り、結果的に段階区分が下がることがあります。
また、配偶者や扶養家族がいる場合も、税法上の控除によって負担額が変わるケースがあります。こうした仕組みを理解し、必要な控除が漏れなく適用されるように申告しておくことも大切です。

まとめ
介護保険は、将来の介護サービスを支えるための大切な仕組みです。介護保険料は、年齢による一律の金額ではなく、所得や地域によって負担額が決まるため、段階区分の仕組みや徴収方法、他の保険料との関係をしっかり理解しておきましょう。
ご自身のライフプランを考えるときには、生命保険や金融商品の販売をせずに中立的な立場からコンサルティングに徹する独立系のファイナンシャルプランナーへの相談をお勧めします。
●構成・編集/京都メディアライン(HP:https://kyotomedialine.com FB:https://www.facebook.com/kyotomedialine/)
●取材協力/藤原未来(ふじわらみき)

株式会社SMILELIFE project 代表取締役、1級ファイナンシャルプランニング技能士。2017年9月株式会社SMILELIFE projectを設立。100歳社会の到来を前提とした個人向けトータルライフプランニングサービス「LIFEBOOK®サービス」をスタート。米国モデルをベースとした最先端のFPノウハウとアドバイザートレーニングプログラムを用い、金融・保険商品を販売しないコンサルティングフィーに特化した独立フランチャイズアドバイザー制度を確立することにより、「日本人の新しい働き方、新しい生き方」をプロデュースすることを事業の目的とする。
株式会社SMILELIFE project(https://www.smilelife-project.com)