
小泉セツ&小泉八雲の夫婦がモデルとなった朝の連続テレビ小説『ばけばけ』が注目されています。実はその小泉夫妻と、明治の文豪・夏目漱石と妻・鏡子は、不思議と重なり合う縁で結ばれていた、というのをご存じでしょうか。
夏目漱石の研究家として知られ、『心を癒す漱石の手紙』などの著書を持つ、作家で雑誌編集記者の矢島裕紀彦さんによると、二人の文豪とその妻たちには奇縁と呼ぶしかないような不思議なつながりがあると言います。
多数の文献や手記を紐解きながら、二組の夫婦の知られざる素顔を全26回の連載にて紹介します。
第12回では、小泉八雲が新聞記者として叩き上げ、作家として認められるまでの苦難をたどります。一方の夏目漱石は教師をしながら小説家デビューし、新聞社の社員となって数々の名作長篇を連載しその地位を確立しました。
文・矢島裕紀彦
イギリスからアメリカへ、貧困から抜け出すための旅
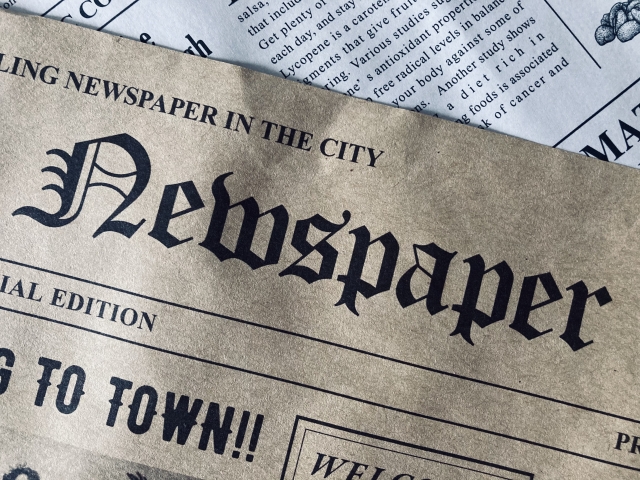
19歳の小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が、イギリスのリバプール港から移民船に乗ってアメリカ・ニューヨークへ向かったのは、1869年の夏だった。八雲の後見人だった大叔母がこの2年前に破産。八雲は学校を退学し、ロンドンで貧窮暮らしに陥っていた。そんな日々に見切りをつけ、新しい出直しを企図してのアメリカ行きだった。このとき日本は明治2年、セツは1歳、漱石は2歳の幼児である。
八雲はまもなく、シンシナティへ身を移し、召使や給仕、電報配達などして糊口を凌ぐうち、印刷屋の主人ヘンリー・ワトキンと出会う。このワトキンに仕事と住まいを与えられ、生活が安定した。働きながら図書館通いをし、読書と文章を書くことに精力を注いだ。苦労して書き上げた原稿『王の牧歌』を『インクワイヤラー』紙に持ち込んだのは1872年(明治5年)秋。これが認められて、ほどなく新聞記者として歩み出していく。八雲の文筆生活の出発点は、新聞記者だったのである。1875年(明治8年)には『シンシナティ・コマーシャル』紙に移籍した。
この頃、八雲が書いていたのは、主として、読者の耳目を引くセンセーショナルな記事と、下層民の日常生活に目を向けた記事だった。たとえば、1874年(明治7年)11月中旬の『インクワイヤラー』紙には、皮革製作所殺人事件を取材し、こんな死体の描写もしている。
頭蓋骨は砲弾のごとく爆裂し、焼却炉の高熱の中で飛び散っていた。その上半分はぶくぶく煮沸する脳髄の蒸気でもって吹き飛ばされたかのごとく思われた。後頭部の後半部分と頭頂骨、上下の顎骨、ならびに多少の顔面骨のみが残っていた。(略)脳漿はほとんど沸騰してなくなってしまったが、それでも頭蓋の底部にレモン程度の大きさの小さな塊が残っていた。
後年、この時期のことを回顧して、八雲は、「1日16時間、ガス灯の明りで夜ふけまでペンを持ち、雨が降ろうが風が吹こうが取材に飛び出して行った」と語っている。
その後、八雲はニューオリンズに移る。混血女性との結婚の破綻がきっかけとも言われる。またもやの貧窮生活を経て、小新聞『デイリー・アイテム』紙の記者として働きはじめ、1881年(明治14年)の年末に『タイムズ』と『デモクラット』が合併して南部一の大新聞『タイムズ・デモクラット』紙が生まれると、その文芸部長に迎えられた。編集長はページ・M・ベーカーだった。
八雲がエリザベス・ビスランドと出会ったのも、この頃らしい。八雲は31歳。ビスランドは八雲より11歳年下で、八雲の書いた記事に感動して、同じ新聞社の女性記者となり主に「婦人欄」を担当したという。その後、ビスランドはさらなるキャリアを求めてニューヨークへ居を移し、一流雑誌『コスモポリタン』の編集記者となる。ふたりは互いの才能を認め合っていた。「汚染されていない野蛮人か野生動物」「優雅な猛獣」というのが、互いの印象だったというから、両人とも内に抱える並々ならぬ熱情があふれ出ていたのだろう。八雲は美貌のビスランドに対し秘かに憧れの気持ちを抱いていたが、ビスランドは微妙な距離を保ち、ふたりは恋に落ちることなく生涯の友となった。
『タイムズ・デモクラット』の八雲は、シンシナティ時代とは異なる文学的な香り高い文章を発表し、『異邦文学残葉』『中国霊位談』といった単行本も上梓。新聞社を辞めて、作家として独立する決意を固めていくが、ことはなかなか思うようには運ばなかった。この間、ニューオリンズで開催された万国博覧会で日本館を訪れて日本の魅力に強く惹きつけられた。ニューヨークの出版社ハーパー社の通信記者として日本を目指す航海に出るのは、1890年(明治23年)3月、八雲はまもなく40歳になろうとしていた。
実はビスランドは八雲の来日に先立つこと数か月、日本を訪れていた。雑誌『コスモポリタン』の企画で前年の11月、世界一周の旅に出て、76日間かけて旅を完遂した。その際、横浜でグランド・ホテルに宿泊し、ホテルの大株主でもある米国海軍主計大佐ミッチェル・マクドナルドと面識ができていた。日本へ向かう八雲のため、ビスランドはマクドナルドへの紹介状を書いてくれたという。
来日後の八雲は、松江を振り出しに、学校教師という職業を軸として暮らしていくが、新聞社との新たな縁も生まれていた。その新聞は横浜の『ジャパン・メール』。主に横浜の居留地とその周辺に住む欧米人を読者とする週刊の英語新聞で、日本に関連する情報や論考などを掲載していた。八雲は来日後まもなく、この『ジャパン・メール』に寄稿をはじめ、折にふれ原稿を発表し続けた。このことは、明治24年(1891)5月26日の『松江日報』の、次のような記事からも確認できる。
我が尋常中学校御雇教師ヘルン氏は西洋人として稀なる日本好にして(略)横浜メール新聞記者たる頭本元定農学士は之に就て過般上京中なりし当地の某氏に語りて曰く「ヘルンは我がメール新聞の通信員にして、時々日本の事情に就て通信すれども、氏の如く日本の真情を穿(うが)ちて一読掬(きく)すべき名文を草するものは数多の通信員中一人として之れあるなく、(略)氏の如き文章は中々得(え)易(やす)からざるものなれば、務めて之を優待し永く日本に滞留せられたきものなり云々」
松江から熊本に移っても、八雲の『ジャパン・メール』への寄稿は続く。到着まもない明治24年(1891)11月30日に熊本の第一印象を書き送ったのをはじめ、明治26年(1893)8月2日付の同紙には『夏の日の夢』が掲載された。これは長崎旅行の紀行文を「浦島太郎」の説話を織り込みながら紡いだ名篇で、のちに単行本『東の国から』に収められることになる。八雲の『ジャパン・メール』への寄稿は、その後、間隔を空けながらも、明治29年(1896)7月の神戸からの通信まで続いたという。
この間、明治27年(1894)9月にアメリカで刊行した単行本『日本瞥見記』(『見知らぬ日本の面影』)で、八雲は多くの読者を獲得し作家としての地位を確立。『東の国から』『心』『霊の日本』『日本雑記』『骨董』といった作品を経て、『怪談』で独特の再話文学の世界を極めていった。
八雲寄稿の英字新聞の入社試験に落ちた漱石

新聞記者を出発点とした八雲と対照的に、夏目漱石の場合、文筆家として到達した場所が新聞社だった。どういうことかというと――。
漱石は教師として東京帝国大学と第一高等学校の教壇に立ちながら、雑誌『ホトトギス』に掲載した『吾輩は猫である』で一躍文壇の寵児となった。その後、『坊っちやん』『草枕』などの雑誌発表を経て、明治40年(1907)5月、40歳で教職を辞し、東京朝日新聞に入社した。いわゆる「小説記者」で、以降、出社義務のない専属作家のような立場で筆を執り、『三四郎』『それから』『門』『彼岸過迄』『行人』『こころ』『道草』『明暗』などの名作長篇を新聞紙上に連載していった。その身分は朝日新聞社員であり、長篇小説執筆の合間には、同紙に多くの評論や随筆を書き、自身の長篇小説の間をつなぐ執筆者のプロデュースもした。「朝日文芸欄」を立ち上げ、その運営にも心を砕いた。
朝日入社に先立ち、漱石は、膨張する経済を支える生活者として、条件面の交渉を詰めている。年1度100回ほどの連載小説を書くのを主な仕事とし、月給は200円、賞与を含めた年俸は2800円。主筆・池辺三山の交際費を含めた月俸が270円、経済部長・松山哲堂の月俸が140円だったというから、かなりの厚遇であった。
それでも、その頃の漱石の総収入とさほど大きな差はなく、一方で、新聞社は官立の学校ほどの安定は見込めない。まもなく東京帝国大学教授となる話も内定していたらしい。なぜにそれを棒に振るのか、というのが当時の世間一般の見方だった。だからこそ、漱石は『入社の辞』で、《新聞屋も商売ならば、大学屋も商売である》と些か意気込んで「野に下る」ことになった。後年の「博士号辞退」(文部省から送られてきた文学博士の「博士号」を辞退し証書を送り返した)にも通じる、漱石の気概が感じられる。このあたり、偏屈ともとれる頑固一徹ぶりは、小泉八雲と重なるものがある。40歳で大きな転機を迎えたのも、両人に共通する。
ついでに言えば、朝日入り決断の最後の決め手は、面談した池辺三山の、西郷隆盛を思わせるような人品骨柄に打たれたためだったという。これも、八雲が外山正一の真情に打たれ帝大講師を引き受けたという逸話と似通ったところがある。
実をいうと、漱石は20代の頃にも一度、新聞記者を目指したことがあった。その頃の漱石は大学院で学問を続ける傍ら、東京高等師範学校で英語教師をつとめていた。そこから先の進路をどうするか模索する中で、明治28年(1895)の初め、新聞社の採用試験を受けた。それがなんと、横浜の『ジャパン・メール』だった。漱石は、友人の菅虎雄を介して、禅についての英語の論文を10枚ほど書いて送ったという。
顧みれば、漱石は大学在学中の明治24年(1891)12月、外国人教師のディクソンに頼まれ『方丈記』を解説つきで英訳したことがあった。それはのちにディクソンが『日本アジア協会会報』(明治26年、第20巻)に発表する論考の基礎となり、そこには漱石への謝辞も付記されていた。そんな過去の手応えも、漱石が『ジャパン・メール』の記者を志望するとっかかりとなっていたのかもしれない。ところが、結果は不採用だった。黙って突き返されてきた論文を、漱石は菅虎雄の目の前で破り捨てたとも伝えられる。そして3か月後、漱石は愛媛・松山へ教員として赴いていく。松山での教師体験が、のちに名作『坊っちやん』に結びつくのは周知の通りである。
漱石が『ジャパン・メール』の採用試験を受けた明治28年(1895)は、ちょうど小泉八雲が同紙に寄稿を続けていた時期。入社を希望して論文を提出したほどだから、几帳面な漱石は、事前の紙面研究の中で、八雲の書いた通信文も読んでいたのではないか。一方で、日本の古典に強い興味を持っていた八雲は、持ち前の勤勉さから、『日本アジア協会会報』に掲載された『方丈記』の論考に目を通していた可能性が高い。八雲自身、この会報には、寄稿もしているのである。
* * *

矢島裕紀彦(やじま・ゆきひこ)
1957年、東京都生まれ。早稲田大学政経学部卒。作家・雑誌編集記者。文学、スポーツ、歴史など幅広いジャンルをフィールドに“人間”を描く。著書に『心を癒す漱石の手紙』『文士の逸品』『文士が愛した町を歩く』『鉄棒する漱石、ハイジャンプの安吾』『ウイスキー粋人列伝』『著名人名づけ事典』『こぼれ落ちた一球』『石橋を叩いて豹変せよ』『あの人はどこで死んだか』など多数。グランドセイコー広告の掌編小説シリーズ『時のモノ語り』で2018年度朝日広告賞朝日新聞特別賞受賞。https://atelier1328.com
(この連載を通しての主な参考文献)
『漱石全集』全28巻、別巻1(岩波書店、1993~1999年)/夏目鏡子述・松岡譲筆録『漱石の思い出』(文春文庫、1994年)/夏目伸六『父・夏目漱石』(文春文庫、1991年)/夏目伸六『父・漱石とその周辺』(芳賀書店、1967年)/高浜虚子『回想子規・漱石』(岩波文庫、2002年)/松岡陽子マックレイン『漱石夫妻 愛のかたち』(朝日新書、2007年)/荒正人『増補改訂漱石研究年表』(集英社、1984年)/江藤淳『漱石とその時代』第1部~5部(新潮新書、1970~1999年)/『新潮日本文学アルバム夏目漱石』(新潮社、1983年)/『別冊國文学 夏目漱石事典』(学燈社、1990年)/『夏目漱石の美術世界』(東京新聞、NHKプロモーション、2013年)/出久根達郎『漱石先生とスポーツ』(朝日新聞社、2000年)/江戸東京博物館・東北大学編『文豪・夏目漱石』(朝日新聞社、2007年)/平岡敏夫『「坊つちやん」の世界』(塙新書、1992年)/恒松郁生『漱石 個人主義へ』(雄山閣、2015年)/小泉節子、小泉一雄『小泉八雲 思い出の記 父「八雲」を憶う』(恒文社、1976年)/小泉八雲、平井呈一訳『日本瞥見記』上・下(恒文社、1975年)/小泉八雲、平井呈一訳『東の国から・心』(恒文社、1975年)/小泉八雲、平川祐弘編『怪談・奇談』(講談社学術文庫、1990年)/小泉八雲、池田雅之編訳『虫の音楽家』(ちくま文庫、2005年)/『明治文学全集48 小泉八雲集』(筑摩書房、1970年)/小泉時共編『文学アルバム小泉八雲』(恒文社、2000年)/小泉凡監修『小泉八雲、開かれた精神の航跡。』(小泉八雲記念館、2016年)/池田雅之監修『別冊太陽 小泉八雲』(平凡社、2022年)/池田雅之『小泉八雲』(角川ソフィア文庫、2021年)/田部隆次『小泉八雲』(北星社、1980年)/長谷川洋二『八雲の妻』(今井書店、2014年)/関田かをる『小泉八雲と早稲田大学』(恒文社、1999年)/梶谷泰之『へるん先生生活記』(恒文社、1998年)/池野誠『松江の小泉八雲』(山陰中央新報社、1980年)/工藤美代子『神々の国』(集英社、2003年)/工藤美代子『夢の途上』(集英社、1997年)/工藤美代子『聖霊の島』(集英社、1999年)/平川祐弘編『小泉八雲回想と研究』(講談社、1992年)/平川祐弘『世界の中のラフカディオ・ハーン』(河出書房新社、1994年)/熊本大学小泉八雲研究会『ラフカディオ・ハーン再考』(恒文社、1993年)/西川盛雄『ラフカディオ・ハーン』(九州大学出版会、2005年)/西成彦『ラフカディオ・ハーンの耳、語る女たち』(洛北出版、2024年)/池田雅之『日本の面影』(NHK出版、2016年)/ラフカディオ・ハーン『小泉八雲東大講義録』(KADOKAWA、2019年)/芦原伸『へるん先生の汽車旅行』(集英社インターナショナル、2014年)/嵐山光三郎『文人暴食』(新潮文庫、2006年)/河東碧梧桐『子規を語る』(岩波文庫、2002年)/『正岡子規の世界』(松山市立子規記念博物館、1994年)/『子規全集』18巻、19巻(講談社、1979年)/『志賀直哉全集』第8巻(岩波書店、1999年)/『芥川龍之介全集』第4巻(岩波書店、1996年)/瀬沼茂樹『評伝島崎藤村』(筑摩書房、1981年)/矢島裕紀彦『心を癒す漱石の手紙』(小学館文庫、2009年)/矢島裕紀彦『鉄棒する漱石、ハイジャンプの安吾』(NHK生活人新書、2003年)/矢島裕紀彦『文士が愛した町を歩く』(NHK生活人新書、2005年)/矢島裕紀彦『文士の逸品』(文春ネスコ、2001年)





























