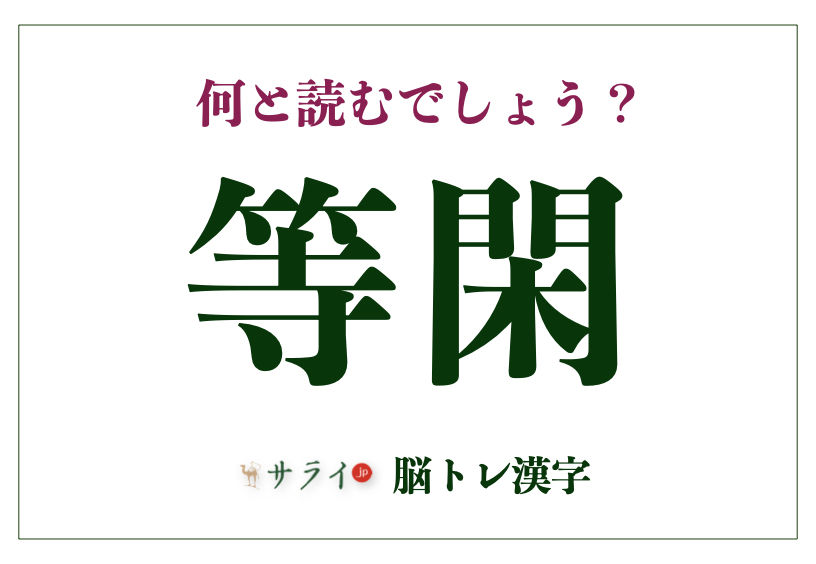小泉セツ&小泉八雲の夫婦がモデルとなった朝の連続テレビ小説『ばけばけ』が注目されています。実はその小泉夫妻と、明治の文豪・夏目漱石と妻・鏡子は、不思議と重なり合う縁で結ばれていた、というのをご存じでしょうか。
夏目漱石の研究家として知られ、『心を癒す漱石の手紙』などの著書を持つ、作家で雑誌編集記者の矢島裕紀彦さんによると、二人の文豪とその妻たちには奇縁と呼ぶしかないような不思議なつながりがあると言います。
多数の文献や手記を紐解きながら、二組の夫婦の知られざる素顔を全26回の連載にて紹介します。
第11回では、小泉家と夏目家のお正月の様子をご紹介。紋付き羽織袴姿で周囲を驚かせたという八雲と、年賀状も出さなかったという漱石との違いが興味深いです。
文・矢島裕紀彦
八雲と漱石、お正月に対するそれぞれの思い入れ

小泉八雲が日本で初めての正月を迎えたのは明治24年(1891)、場所は松江であった。松江に暮らして4か月余り、日本式の生活に浸りはじめていた八雲は、紋付き羽織袴姿で年始回りをして周囲を驚かせたという。ただ、草履だけは馴染めず靴を履いていたあたりに、本人の純で健気な一生懸命さを越えて、切なさとおかしみがこぼれる。
八雲はこの翌年、熊本で教官や役人を集めた新年会が開かれたときも、ほとんどの日本人が黒のフロックコートにシルクハットという出で立ちでいる中に、完璧な和服の正装で登場して度肝を抜いたと伝えられる。このときは草履も履きこなしていたのだろう。
ちなみに、八雲の用いた紋は「下ゲ羽の鷺」。これは、従来の古代紋帳大全等に載っている「下ゲ羽の鶴」にヒントを得た八雲が、松江中学の美術教師・後藤魚洲に依頼して、自分の祖先であるノールタンバランド・フォードの城主サー・ヒュー・ド・ヘロンの旗標である鷺を図案化したものだったという。凝り性に楽しんでもいる八雲なのである。
齢33。家族と別れて向かった海路はるかなロンドン留学。初めて体験したクリスマスのあと、故国で待つ妻への手紙に
昨日は当地の「クリスマス」にて日本の元日の如く頗る大事の日に候青き柊にて室内を装飾し家族のもの皆其本家に聚(あつま)り晩餐を喫する例に御座候昨日は下宿にて「アヒル」の御馳走に相成候
と書いたのは夏目漱石だった。七面鳥でなくアヒルが供されたのは、おそらく、下宿の主婦がフランス人でその風習にならったものだったと思われる。漱石は一方で、友人・正岡子規宛てに送った絵葉書の隅へは「屠蘇なくて酔はざる春や覚束な」と、つい愚痴めく一句を書き込んだ。不惑過ぎて単身パリに渡った島崎藤村もそうだったが、言葉も習慣もまったく異なる外国で迎える初めての年越しに、ごく当たり前の「日本の正月」を改めてしみじみ懐かしく想起せざるを得なかったのである。
私は以前、宮城県仙台市の東北大学附属図書館漱石文庫を訪れ、漱石留学時の「渡航日記」を取材させてもらったことがある。そのとき、茶色の革表紙の日記の冒頭、出発前の身支度について記したメモがとりわけ印象に残った。衣類や手拭い、傘、薬、名刺、剃刀(髪ソリ)などの必需品が列挙されたメモの中ほどに、《一梅ボシ、福神漬》の一行が読めたのである。馴れない海外生活に際して、誰もが気にかける「味覚」の問題を、漱石もはっきり意識していた。
そんな漱石は帰国後数年を経て、『私のお正月』と題する談話を残している。曰く。
私の家には老人もなく、別にやかましく云ふものもなく、私が主人で、私が祖先のやうになつて居ますから、無理に古きを追はねばならぬと云ふ事もありませんから、平素の生活が簡素である如く、正月も矢張り簡単で、頗る気楽であります。
この先、話はもう少し具体的内容に及び、家では門松と注連縄を飾ること、屠蘇を飲み雑煮を食うこと、年賀の客は多く若い人で特別な饗応もしないこと、そして、漱石自身は回礼もせず遠方に出かけもせず、ごく安閑とした数日を送ることなどが述べられていく。語る言葉の端々から、うららかな陽の匂いさえ漂ってきそう。手紙好きで知られる漱石にして、《賀状も出しません》と語り、虚礼としての年賀状を廃してしまっていることも、好もしく映る。余分な衒いや構えを脱し、やがて「則天去私」へと至る人生観さえ見え隠れする。
松江の八雲は正月の注連飾りが気に入って、1月末まで飾り続けたという。とくに門松に思い入れを持ったようで、のちにまとめた『日本瞥見記』(『知られぬ日本の面影』)の中にこう綴っている。
門松といっても、これは松だけではない。松の若木、もしくは松の小枝に、梅と竹の枝がくくりつけてある。この松と梅と竹は、象徴的な意味の発達したもので、(略)竹の謎は、これはちょっとヨーロッパ人にはわかるまい。それは一種の洒落を象徴しているのである。「節」という漢字には、元来二つの意味があって、一つは竹の「ふし」を意味し、も一つは、「操」「信義」「誠実」を意味する。その意味から、竹はめでたいしるしに使われているのである。日本の女の子は、よく「節」という名がつけられているのを注意するといい。これは、ちょうどイギリスの少女に、“Faith”(誠実)“Fidelia”(信義)“Constance”(操)などという名がつけられるのと同じである。
門松の竹について語りながら、そこに妻セツの名をだぶらせているのは明白だろう。
漱石が人生最後に食べた松茸入りのお雑煮

大正5年(1916)の「漱石山房」の元日も、例年と同じく簡素だった。玄関には門松と注連縄が飾られ、家族で屠蘇を飲み、雑煮を食べて新春を寿ぐ。いつもと少し違うのは、雑煮の中身。鶏肉、小松菜に加え、ちょっと贅沢に塩漬けの松茸が入っていた。
水戸徳川家で食されていたと伝えられる「けんちん雑煮」にも、車海老、大根、牛蒡、人参、里芋、ねぎ、こんにゃくに加え、塩漬けの松茸が入っていたという。時代が江戸から明治、大正へと移り変わっても、電気冷蔵庫などないから、秋が旬の松茸を長持ちさせるためには、塩漬けにするのが普通のやり方だった。晩年の漱石のもとには、主人の嗜好を汲んで松茸を送ってくれる人が少なからずいた。とくに大正4年(1915)秋にはそれが顕著だったことが、次の礼状から読み取れる。
又松茸を沢山にありがたう
此間から名古屋大阪京都の三市から松茸を幾度も貰ひ幾度も茸飯を食ひました(略)あなたのは北国の産だから(ことに謙信の城址の産だから)自ら味も特別だらうと思つて是から風味に取りかかります
何時もながら御好意を感謝致します。(大正4年11月7日付、新潟在住の医師・森成麟造宛て)
かくして、秋の内に松茸御飯や吸物等で賞味し切れないものが塩漬けにされ、年明けの雑煮を豪華にしたのだろう。この松茸入り雑煮が、漱石の食した最後の雑煮となった。
年始の訪客の一番乗りは、古くからの門下生である寺田寅彦だったらしい。午前中に自宅を出て《夏目先生方にて雑煮を呼ばれ》たと、日記に記す。夕方には多くの門下生がやってきて、晩餐として神楽坂の鶏料理屋「川鉄」の合鴨鍋がふるまわれた。夜9時頃に一同が引き上げたあと、漱石は、子どもたちの勉強部屋の離れで、家族や、居残った小宮豊隆とともに遅くまで百人一首の歌留多とりを繰り広げた。
漱石が歌留多とりの名手だったわけではない。むしろ、その逆だった。
子供たちと遊ぶイロハ歌留多でも、「屁をひって尻つぼめ」「頭かくして尻かくさず」「臭いものにはふた」という三枚のおかしな札を自分の前に並べ、これだけはと意気込むのだが、それさえも誰かに先をこされたりしていたという。
鏡子と見合いをした直後の明治29年(1896)1月3日も、漱石は中根家(鏡子の実家)の新年会に招かれ、鏡子やその妹たちと歌留多とりをやり、さんざんな負けっぷりを披露した。それを見ていた鏡子の父の中根重一は、大いに喜び上機嫌となった。「今どきの若い者は遊ぶことばかりが上手でなんにも役に立たないが、ああいうふうに不器用なほうが学者としては望ましい」というのだった。
そのあと皆で福引をやると、漱石は絹の帯締め、鏡子は男持ちのハンカチ1ダースを当てた。ハンカチは何かの広告なのか、藍で大きく「国の光」と染め出してあった。母親からの「取り替えてあげたら」という進言があって、あとで鏡子は別室でひとりくつろいでいた漱石に交換を申し出た。漱石は「そうですか」とだけ言ってこれに応じた。以下は、鏡子が語る後日譚。
後で申すのには、あの時は紐のほうがよっぽどよかった。あのハンケチじゃしかたがない。おおかた兄貴の子供のおしめにでもしただろうって悪口をいっていましたが、あの人の文運がひらけて、今では一つの国の光になったことの運命を、僣越ながらなんだかその時に私の手で暗示したように感じられもするのであります。(『漱石の思い出』)
どこまでも縁起担ぎが好きで、少々自惚れ屋の鏡子なのである。
日本食を洋食のフルコースのように食べた八雲
松江地方の雑煮は独特で、たっぷり砂糖をきかせた小豆汁の中に煮た丸餅を入れた「小豆雑煮」とでも呼ぶべきもの。八雲はこれは苦手だったらしい。八雲の孫の小泉時は、祖母であるセツから「ひと箸つけたきり、あとは残した」と聞かされた記憶があると、雑誌の取材に応えて語っている(『サライ』1990年1月1日号)。
セツが八雲のもとに住み込みの手伝いに入った時期が諸説ある中で、もしセツが明治24年(1891)の正月にはまだ八雲の身近にいなかったとすれば、世話をしていた富田旅館の方から供された雑煮の話を、あとでセツが耳にしたということだろう。
もともと八雲は、土地土地の食文化というものに強い興味を有していた。
米国ニューオリンズにいた頃には、『クレオール料理』という料理の本までまとめている。ニューオリンズという国際色豊かな土地柄を反映した、独特の料理の数々を紹介した本だった。共同出資者の裏切りでわずか21日間で閉店したが、「不景気(ハード・タイムズ)」という大衆向けの料理店を開いたこともあった。
そんな八雲だから、雑煮は別としても、松江では進んで和食を食べた。チェンバレン宛ての手紙にも、
わたしは、すっかり日本の食事や習慣に慣れ、いまさらあらためるのが苦痛なくらいです。(略)わたしが日本人よりも余分に摂るものといえば大量の目玉焼きと生玉子くらいのものでしょう。
と、記した。毎日の食事を、米、魚、豆、野菜、海藻で済ませ、大根のピクルス(たくあん)という珍味の美味しさまでわかるようになってきたと、胸をそらしている。旅先で口にしてから、奈良漬けも好きになったという。
最初の下宿先だった富田旅館の女将ツネも、こう証言している。
先生は朝は牛乳と数個の生卵ですまされました。昼と晩との二食はお刺身、煮つけ、酢の物、焼き魚等なんでもおあがりでした。例の握り箸で召し上がりますので、魚の骨は取っておきました。その食べ方は妙なもので、まず膳のうえにある副食物即ちお菜の方から、それを一皿一皿次々とことごとく平らげて、それから巻鮨とかご飯だけを食うというやりかたでした。(『松江に於ける八雲の私生活』)
八雲は、洋食のコース料理を食べるようなやり方で和食を平らげていたのである。
だが、1年が経過する頃には、長年の食習慣を置き去りに日本食一辺倒に傾斜し過ぎたためか、八雲は胃腸の調子を悪くした。体力も減退し、夜は西洋料理店からビフテキを取り寄せたりするようになる。明治24年(1891)11月に熊本に移ってからは、さらに洋食回帰を進めバランスをとったという。
小泉家の雑煮に話を戻す。先述の小泉時によれば、のちのちまで小泉家で食べられていたのは、
代々、女房たちが受け継いできた雑煮で、銀杏切りにした大根、人参、それに青菜などの入ったおすまし、四角い餅を入れた精進風のもの。
だったという。
熊本転居以降の八雲は、セツの手作りするそんな雑煮を食していたのだろう。
* * *

矢島裕紀彦(やじま・ゆきひこ)
1957年、東京都生まれ。早稲田大学政経学部卒。作家・雑誌編集記者。文学、スポーツ、歴史など幅広いジャンルをフィールドに“人間”を描く。著書に『心を癒す漱石の手紙』『文士の逸品』『文士が愛した町を歩く』『鉄棒する漱石、ハイジャンプの安吾』『ウイスキー粋人列伝』『著名人名づけ事典』『こぼれ落ちた一球』『石橋を叩いて豹変せよ』『あの人はどこで死んだか』など多数。グランドセイコー広告の掌編小説シリーズ『時のモノ語り』で2018年度朝日広告賞朝日新聞特別賞受賞。https://atelier1328.com
(この連載を通しての主な参考文献)
『漱石全集』全28巻、別巻1(岩波書店、1993~1999年)/夏目鏡子述・松岡譲筆録『漱石の思い出』(文春文庫、1994年)/夏目伸六『父・夏目漱石』(文春文庫、1991年)/夏目伸六『父・漱石とその周辺』(芳賀書店、1967年)/高浜虚子『回想子規・漱石』(岩波文庫、2002年)/松岡陽子マックレイン『漱石夫妻 愛のかたち』(朝日新書、2007年)/荒正人『増補改訂漱石研究年表』(集英社、1984年)/江藤淳『漱石とその時代』第1部~5部(新潮新書、1970~1999年)/『新潮日本文学アルバム夏目漱石』(新潮社、1983年)/『別冊國文学 夏目漱石事典』(学燈社、1990年)/『夏目漱石の美術世界』(東京新聞、NHKプロモーション、2013年)/出久根達郎『漱石先生とスポーツ』(朝日新聞社、2000年)/江戸東京博物館・東北大学編『文豪・夏目漱石』(朝日新聞社、2007年)/平岡敏夫『「坊つちやん」の世界』(塙新書、1992年)/恒松郁生『漱石 個人主義へ』(雄山閣、2015年)/小泉節子、小泉一雄『小泉八雲 思い出の記 父「八雲」を憶う』(恒文社、1976年)/小泉八雲、平井呈一訳『日本瞥見記』上・下(恒文社、1975年)/小泉八雲、平井呈一訳『東の国から・心』(恒文社、1975年)/小泉八雲、平川祐弘編『怪談・奇談』(講談社学術文庫、1990年)/小泉八雲、池田雅之編訳『虫の音楽家』(ちくま文庫、2005年)/『明治文学全集48 小泉八雲集』(筑摩書房、1970年)/小泉時共編『文学アルバム小泉八雲』(恒文社、2000年)/小泉凡監修『小泉八雲、開かれた精神の航跡。』(小泉八雲記念館、2016年)/池田雅之監修『別冊太陽 小泉八雲』(平凡社、2022年)/池田雅之『小泉八雲』(角川ソフィア文庫、2021年)/田部隆次『小泉八雲』(北星社、1980年)/長谷川洋二『八雲の妻』(今井書店、2014年)/関田かをる『小泉八雲と早稲田大学』(恒文社、1999年)/梶谷泰之『へるん先生生活記』(恒文社、1998年)/池野誠『松江の小泉八雲』(山陰中央新報社、1980年)/工藤美代子『神々の国』(集英社、2003年)/工藤美代子『夢の途上』(集英社、1997年)/工藤美代子『聖霊の島』(集英社、1999年)/平川祐弘編『小泉八雲回想と研究』(講談社、1992年)/平川祐弘『世界の中のラフカディオ・ハーン』(河出書房新社、1994年)/熊本大学小泉八雲研究会『ラフカディオ・ハーン再考』(恒文社、1993年)/西川盛雄『ラフカディオ・ハーン』(九州大学出版会、2005年)/西成彦『ラフカディオ・ハーンの耳、語る女たち』(洛北出版、2024年)/池田雅之『日本の面影』(NHK出版、2016年)/ラフカディオ・ハーン『小泉八雲東大講義録』(KADOKAWA、2019年)/芦原伸『へるん先生の汽車旅行』(集英社インターナショナル、2014年)/嵐山光三郎『文人暴食』(新潮文庫、2006年)/河東碧梧桐『子規を語る』(岩波文庫、2002年)/『正岡子規の世界』(松山市立子規記念博物館、1994年)/『子規全集』18巻、19巻(講談社、1979年)/『志賀直哉全集』第8巻(岩波書店、1999年)/『芥川龍之介全集』第4巻(岩波書店、1996年)/瀬沼茂樹『評伝島崎藤村』(筑摩書房、1981年)/矢島裕紀彦『心を癒す漱石の手紙』(小学館文庫、2009年)/矢島裕紀彦『鉄棒する漱石、ハイジャンプの安吾』(NHK生活人新書、2003年)/矢島裕紀彦『文士が愛した町を歩く』(NHK生活人新書、2005年)/矢島裕紀彦『文士の逸品』(文春ネスコ、2001年)