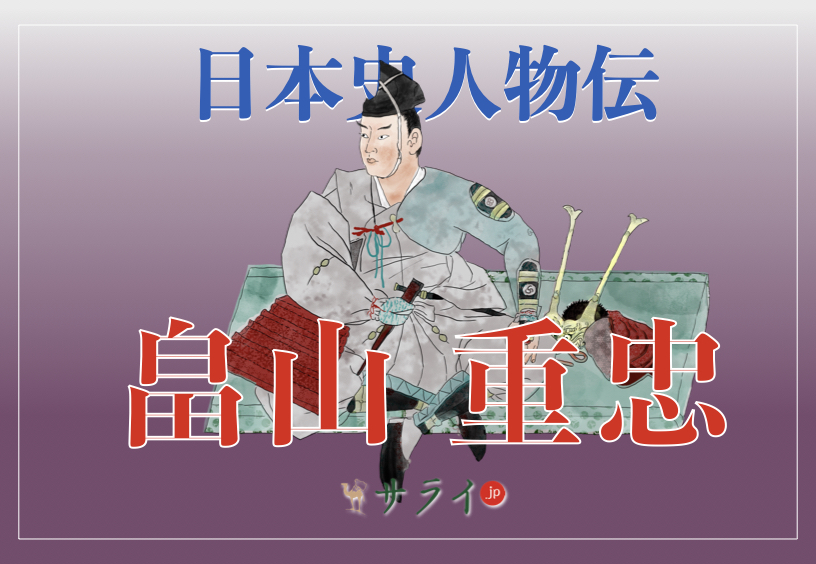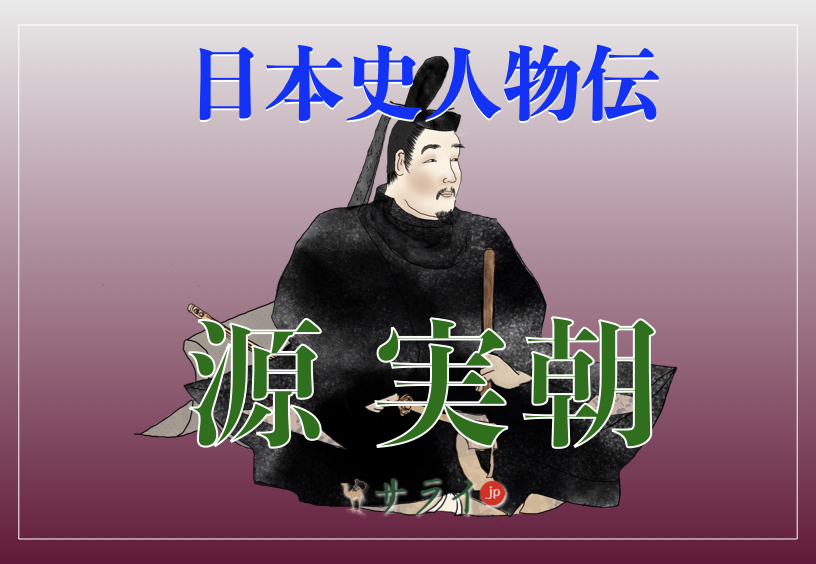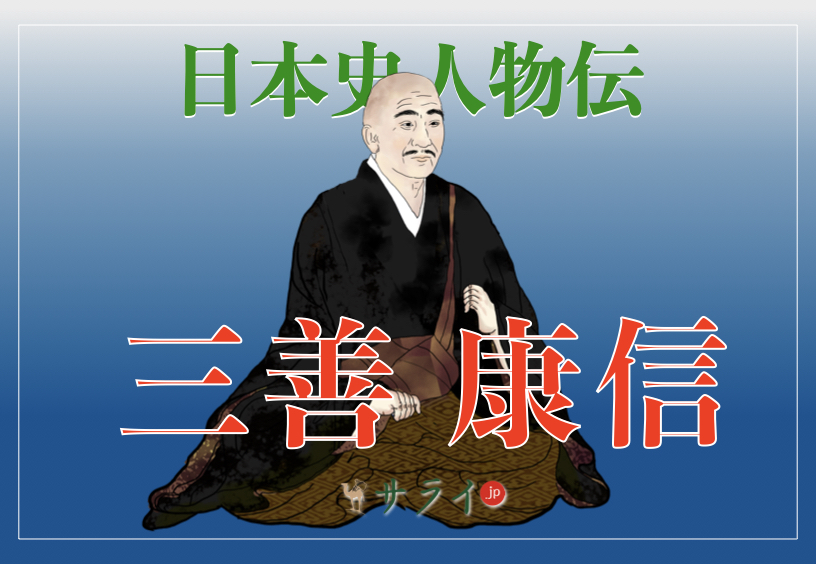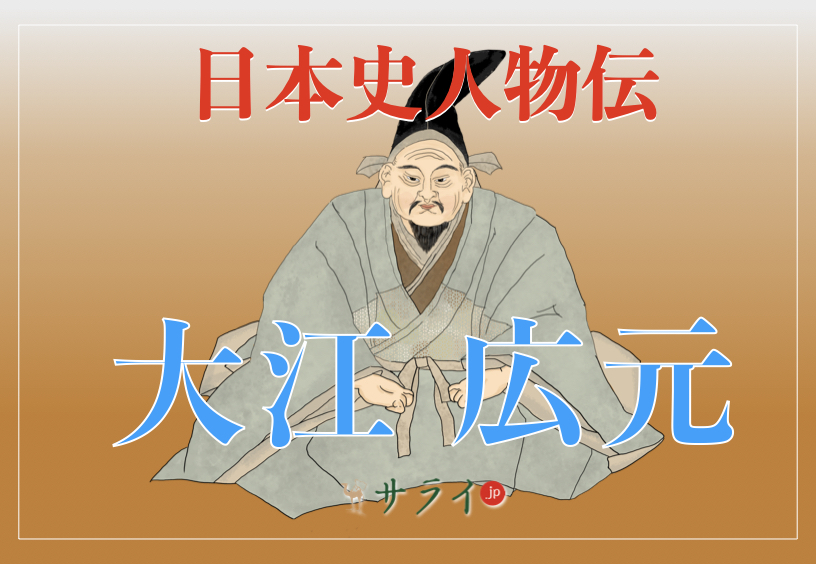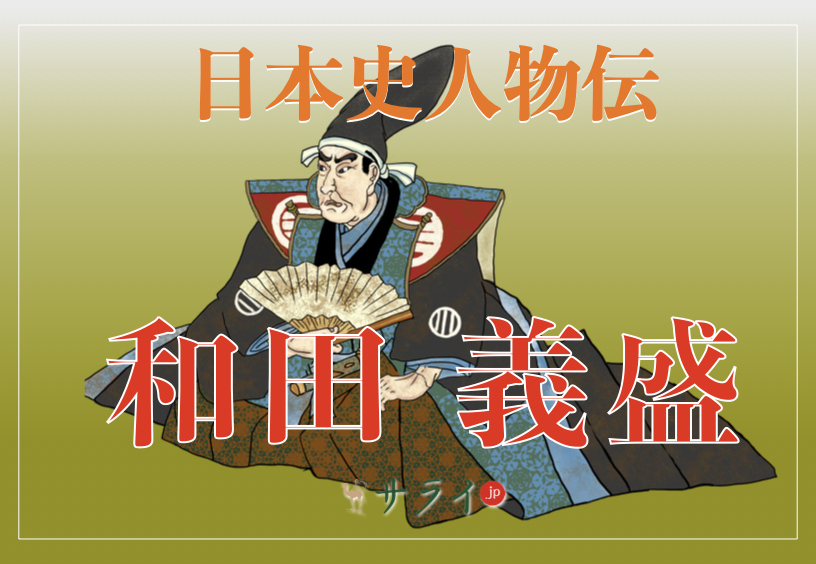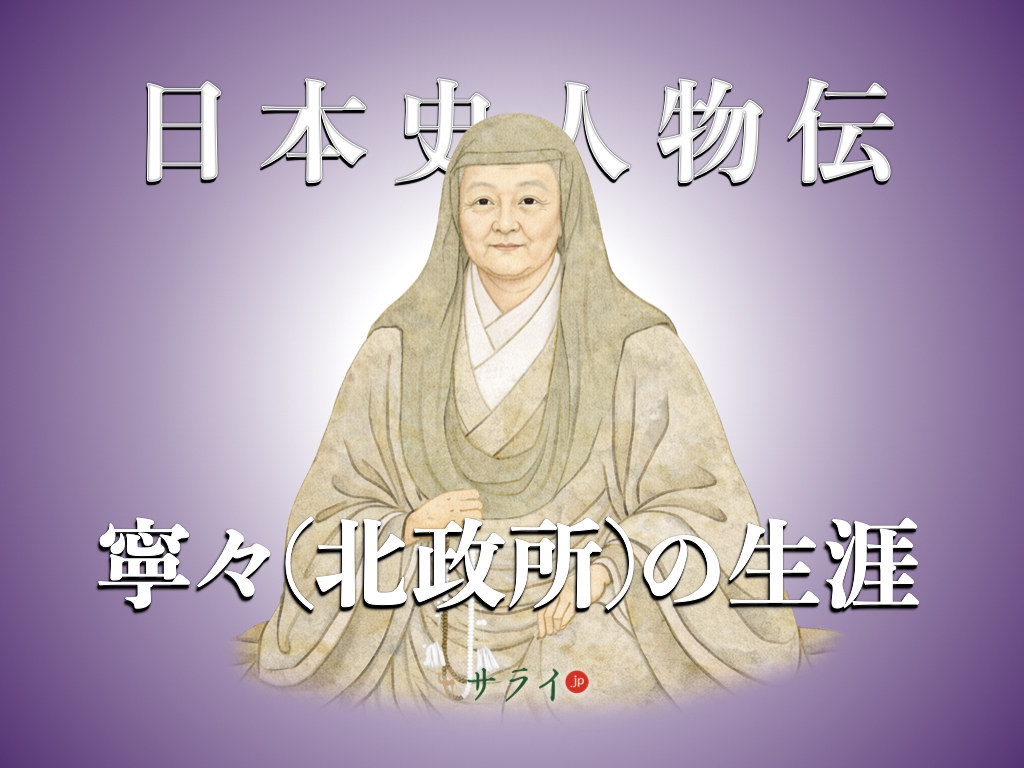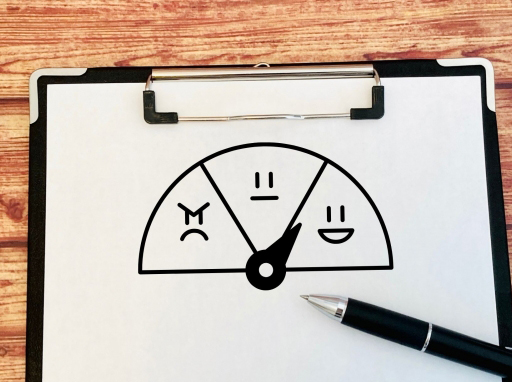はじめに-畠山重忠とはどんな人物だったのか
畠山重忠(はたけやましげただ)は、源頼朝に仕えた武蔵国(現在の埼玉県)の武将です。源義仲(みなもとのよしなか)追討、奥州征伐などで戦功を挙げ、信頼を得ました。しかし後に、北条氏に謀反の疑いをかけられ、義時と戦って亡くなります。
NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』では、武士の鑑といわれた鎌倉幕府の誇る若武者(演:中川大志)として描かれます。
目次
はじめにー畠山重忠とはどんな人物だったのか
畠山重忠が生きた時代
畠山重忠の足跡と主な出来事
まとめ
畠山重忠が生きた時代
畠山重忠が生きた時代は、源平の戦いが繰り広げられた、平安後期から鎌倉初期に当たります。貴族・武士・天皇・上皇の勢力が複雑に入り乱れ、権力を掌握した平氏と、それを追討する源氏の戦いが巻き起こった時代です。初めは平家に仕えていた畠山重忠でしたが、のちに頼朝に服従を誓うことになります。その後、数々の戦功を挙げ、草創期の鎌倉幕府の有力御家人として多くの功績を残すほどの人物になりました。
畠山重忠の足跡と主な出来事
畠山重忠は、長寛2年(1164)に生まれ、元久2年(1205)に没しています。その生涯を出来事とともに紐解いていきましょう。
平氏に仕える豪族・畠山氏に生まれる
畠山重忠は、武蔵国畠山荘(現在の埼玉県)を本拠とする畠山重能(しげよし)の子です。系図によれば桓武平氏の流れで、父・重能は平家に仕えていました。重忠は、幼名を庄司次郎(しょうじじろう)と称します。
平家軍として戦うも、頼朝に帰服する
治承4年(1180)8月、源頼朝が挙兵した際、父・重能が大番役(=京の警備を行う役)で在京中であったため、弱冠17歳の重忠が頼朝の追討に出陣。頼朝軍との合流を果たせず、本拠地に引き返す途中の三浦一族の軍と遭遇して、鎌倉由比ヶ浜で激戦を交えました。

この合戦は勝敗がつかず、重忠はいったん退き、あらためて河越重頼(かわごえしげより)らとともに三浦一族を相模国衣笠城に攻めて、これを陥れ、三浦義明(みうらよしあき)を自害させました。
しかし、同年10月、房総を平定した頼朝が武蔵に入ると、重忠は彼に服属します。その後、木曾義仲(きそよしなか)の追討、平家の追討に従軍し、宇治川の合戦や一ノ谷の戦いで活躍を遂げました。
勇猛な武士として、頼朝から信頼される
文治3年(1187)、重忠が地頭職を与えられていた伊勢国沼田御厨(ぬまたのみくりや=現在の三重県松阪市)である代官が乱妨を働き、重忠が訴えられる事件が起こります。捕らえられ、囚人となった重忠は、従兄弟の千葉胤正(ちばたねまさ)に預けられ、所領四か所を没収されてしまいます。
その際、梶原景時(かじわらかげとき)の讒言(ざんげん)によって、重忠は謀反の罪を着せられそうになりました。しかしその際に、頼朝に逆心を抱いていないこと、武士に二言はないから起請(きしょう)文など書く必要はないことを主張し、むしろ頼朝からの信用を得た、という話が伝えられています。
有力御家人として活躍する
文治5年(1189)、奥州藤原氏征伐の際、阿津賀志山(あつかしやま)の戦で、藤原国衡(ふじわらのくにひら)の首級を獲るなどの活躍をみせ、恩賞として陸奥国葛岡郡の地頭職を与えられています。
翌年の建久元年(1190)、頼朝上洛の際、先陣をつとめ、院参(=上皇・法皇の御所に参上すること)にも随従しました。同6年、再び頼朝が上洛したときも先陣で仕えています。
「鎌倉武士の鑑」としての姿
こうした活躍からも見て取れるように、重忠は将軍・頼朝をはじめとする御家人たちの信任が大変厚かったことで知られています。歴史書『吾妻鏡』では、彼は別格の存在として描かれています。
例えば、奥州征伐の後の一幕です。本来なら功績を上げたのは重忠でしたが、和田義盛(わだよしもり)が一番の功績は自分だと譲りませんでした。そこで重忠は身を引き、義盛に恩賞を譲りました。その姿勢に感銘を受けた頼朝が、両者に恩賞を与えたのでした。
こうした清廉潔白で誠実な態度から、重忠が当時絶大な人気を誇る武士であったことがうかがえます。
【北条氏の陰謀により、戦死する。次ページに続きます】