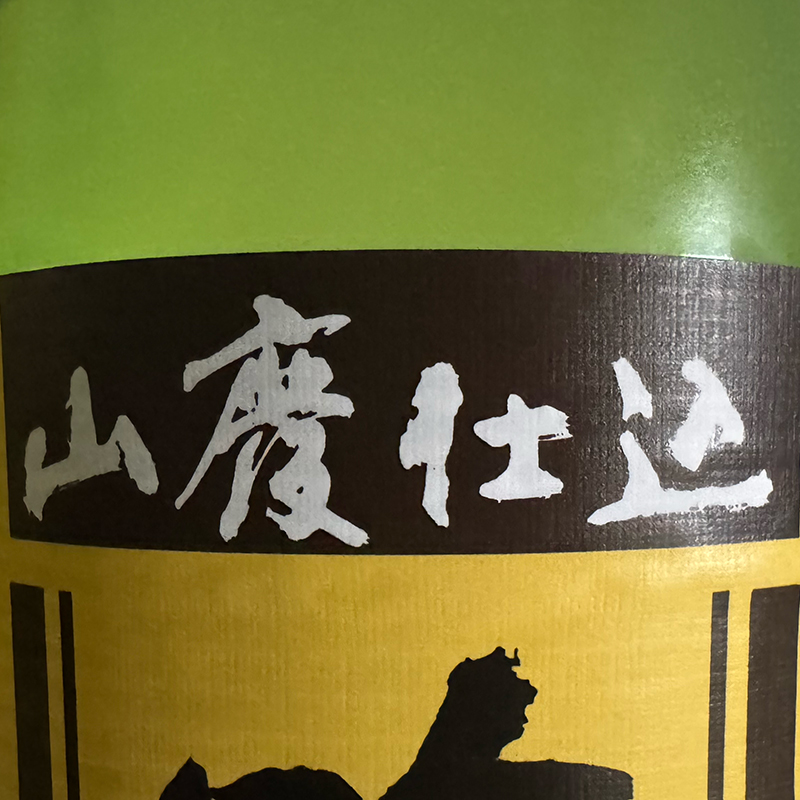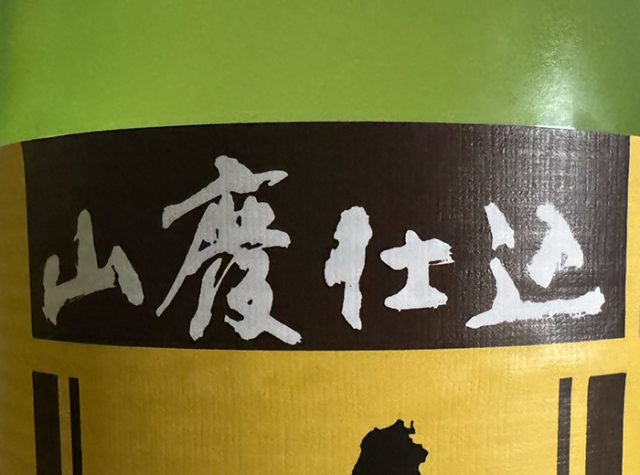
酒販店やデパートの日本酒売り場で、「山廃」という文字を目にしたことはありませんか? この「山廃(やまはい)」は、正式には「山卸廃止酛(やまおろしはいしもと)」という、明治時代の終わりに確立された日本酒の製法を指します。
本記事では、日本酒の山廃造りについて、分かりやすく解説していきます。
文/山内祐治
目次
山廃造りは、江戸時代の造り方から発展した伝統的な日本酒の製法
山廃造りの日本酒が持つ独特の特徴
生酛造りと山廃造り、その違いを知る
現代の主流「速醸造り」と山廃造りの違いを理解する
山廃純米酒の代表格「末廣」と、山廃酒を楽しむコツ
まとめ
山廃造りは、江戸時代の造り方から発展した伝統的な日本酒の製法
日本酒の歴史において、山廃造りとは伝統と革新が出合う転換点でした。なぜなら江戸時代から続く手作業中心の製法と、明治時代に芽生えた化学的アプローチが融合することで生まれた製法だからです。
当時の酒造りは、職人たちの経験と勘に支えられていました。しかし明治時代に入ると、微生物学の発展により、なぜその工程が必要なのか、どのような変化が起きているのかが、化学的に解明されていきました。
山廃造りは、そうした新しい知見を活かしながら、伝統的な味わいを守り続けた、日本の醸造技術の結晶といえるでしょう。
山廃造りの日本酒が持つ独特の特徴
山廃造りの日本酒の最大の特徴は、酸味の存在感と複雑な味わいの調和にあります。この酸味は乳酸由来のもので、シャープさではなく、まろやかさを感じさせるのが特徴です。
熟練の杜氏(とうじ)たちは、この酸味を「包み込むような」「丸みのある」と表現します。それは、一般的な酸味が持つ刺激的な印象とは異なり、口に含んだ瞬間から徐々に広がっていく優しい酸味なのです。
さらに特筆すべきは、その複雑な味わいの構成です。柔らかい旨味や心地よい苦みが幾重にも重なり、時には香ばしさも顔を覗かせます。これは山廃造り特有の乳酸菌の働きによるもので、長い時間をかけて醸成される味わいなのです。
また温度による味わいの変化も、山廃造りの日本酒ならではの魅力です。冷やして飲めば爽やかな印象が際立ち、常温では丸い酸味の存在感と旨味のバランスを楽しむことができます。さらにお燗にすると、香りが豊かに広がり、味わいに深みが増していきます。
また、乳酸由来の酸味を多めに持つことから、乳製品との相性が抜群です。特にチーズとの相性は秀逸で、両者の複雑な旨味が見事に調和します。和食だけでなく洋食との相性の良さも、山廃造りの日本酒の大きな特徴といえるでしょう。
生酛造りと山廃造り、その違いを知る
生酛(きもと)造りは江戸時代から続く古い製法で、山廃造りはその改良版といえます。両者の大きな違いは「山卸し」という作業工程の有無にありますが、その背景には当時の酒造りを取り巻く興味深い歴史があります。
生酛造りの特徴的な工程である「山卸し」とは、蒸したご飯と水を合わせてすりつぶす重労働。しかも真冬の寒い時期に行います。なぜこのような過酷な作業を行うのでしょうか。
それは、最も気温が低い時期に作業を行うことで、不要な雑菌の繁殖を抑制するためでした。当時は微生物の存在も知られていない時代。しかし、先人たちは経験的に、こうした作業を行うことで良質な酒が造れることを知っていたのです。
明治時代に入り、微生物学が発展すると、この工程で起きている化学変化が次第に解明されていきました。そして、山卸しという過酷な作業を行わなくても、同様の効果が得られる方法が発見されます。これが山廃造りの始まりでした。

現代の主流「速醸造り」と山廃造りの違いを理解する
現在流通している日本酒の約9割は「速醸(そくじょう)造り」という現代的な製法の系統で造られています。日本酒の製法は、江戸時代の生酛、明治時代の山廃、そして戦中戦後に普及した速醸と、時代とともに進化してきました。
速醸造りの最大の特徴は、その名の通り製造時間の短さです。生酛や山廃と比べて約半分の時間で醸造が可能です。これは単に効率が良いというだけでなく、醸造期間が短いことで雑菌の混入リスクを低減し、より安定した品質の実現を可能にしました。
山廃造りは時間をかけてじっくりと醸されることで、速醸造りでは出せない複雑な味わいや深みのある風味を生み出します。いわば、時間という名の職人が醸し出す味わいといえるでしょう。
山廃純米酒の代表格「末廣」と、山廃酒を楽しむコツ
山廃造りの日本酒は、実に多様な個性を持っています。熟成した味わいで香ばしく複雑な味わいを持つものから、普段飲む日本酒に近い印象のものまで、そのスペクトラムは実に幅広いものです。
その中でも「末廣」は、山廃造りの発祥の蔵だけあって特徴をバランスよく表現した代表的な銘柄として知られています。綺麗でありながらも深みのある味わいは、山廃造りの魅力を存分に感じられる逸品です。
山廃造りの日本酒を最大限に楽しむためには、温度管理が重要なポイントとなります。特に「吟醸」と表記されていない特別純米酒や純米酒の多くでおすすめなのが、常温まで戻してから飲むことです。冷酒で楽しむのも良いですが、常温からお燗にかけての温度帯で飲むことで、山廃造りならではの柔らかな酸味の存在感と旨味、複雑な味わいを存分に楽しむことができます。
また、季節によって温度を変えて楽しむのも一興です。夏場は冷やして爽やかに、寒い季節はお燗で体も心も温まる飲み方を。同じお酒でも、温度によって様々な表情を見せてくれるのも、山廃造りの日本酒の魅力といえるでしょう。
まとめ
山廃造りの日本酒は、日本の伝統的な醸造技術と、そこに込められた先人たちの知恵の結晶です。初めて試してみたい方は、「末廣」から始めるのがおすすめです。時間をかけてじっくりと醸された深い味わいを、ぜひ体験してみてください。

山内祐治(やまうち・ゆうじ)/「湯島天神下 すし初」四代目。講師、テイスター。第1回 日本ソムリエ協会SAKE DIPLOMAコンクール優勝。同協会機関誌『Sommelier』にて日本酒記事を執筆。ソムリエ、チーズの資格も持ち、大手ワインスクールにて、日本酒の授業を行なっている。また、新潟大学大学院にて日本酒学の修士論文を執筆。研究対象は日本酒ペアリング。一貫ごとに解説が入る講義のような店舗での体験が好評を博しており、味わいの背景から蔵元のストーリーまでを交えた丁寧なペアリングを継続している。多岐にわたる食材に対して重なりあう日本酒を提案し、「寿司店というより日本酒ペアリングの店」と評されることも。
構成/土田貴史