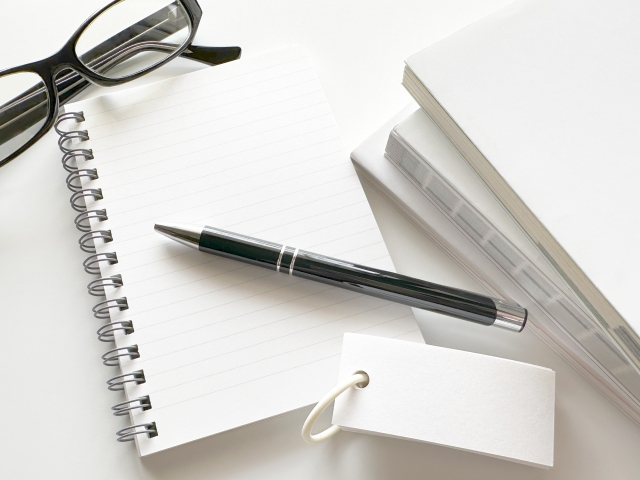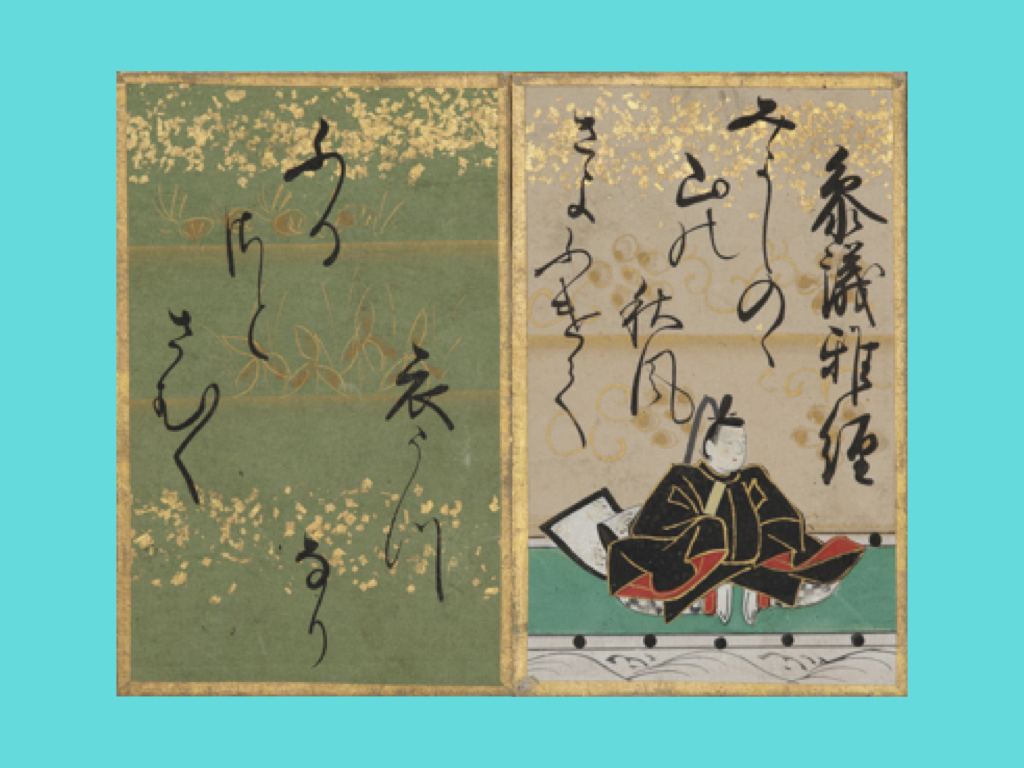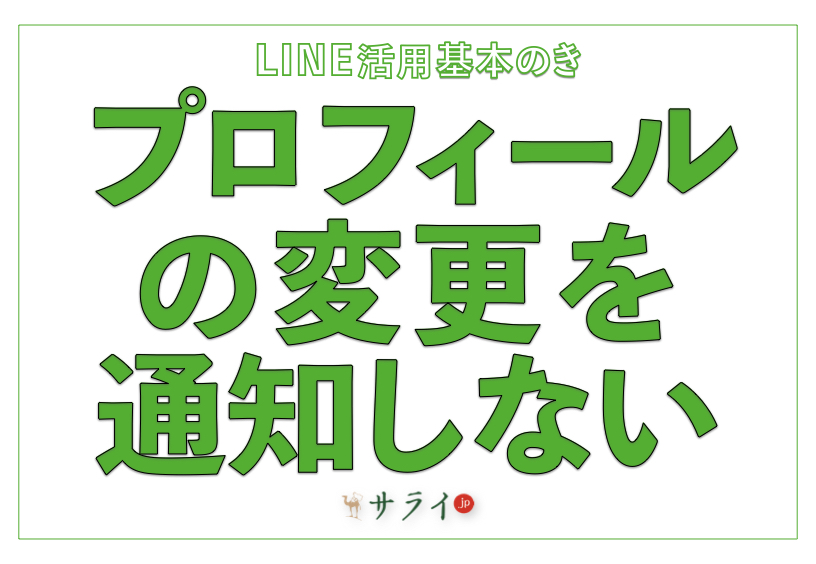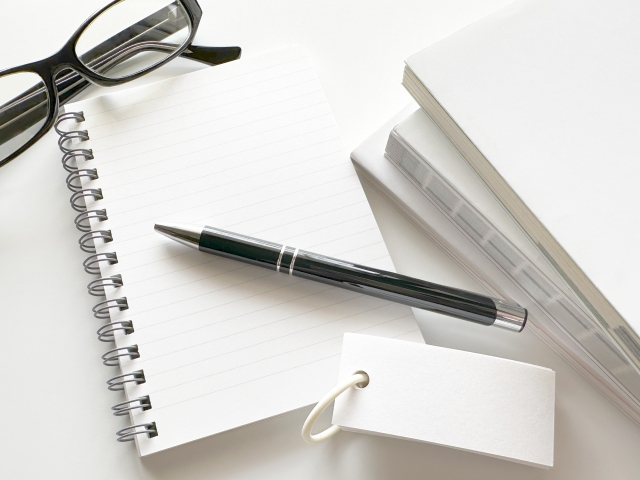
三日坊主という言葉が示すように、新しい習慣を身に着けるのに苦労している人は多いのではないでしょうか。自分は意志が弱いと落ち込んだり、続けられる人は特別だと思ったり。
じつはそれ、思い込みです。私たちの脳は「現状維持を好む」性質があり、新しい行動を始めるのが億劫だったり、続かなくなるのは脳の初期設定。そう教えてくれるのは70冊以上の著書を持つ言語学者の堀田秀吾先生。習慣は「原理とコツさえつかめれば、驚くほどスムーズに」身に着けることができるのだそうです。
堀田先生の最新著書『科学的に証明された すごい習慣大百科』(SBクリエイティブ)には、ハーバード、スタンフォード、オックスフォード……などの研究機関において証明された112個のテクニックが紹介されています。
今回はその本の中から、勉強を続けるために使える習慣をご紹介します。出来ることから少しずつ、自分のペースで始めてみてはいかがでしょうか。
文/堀田秀吾
ボールを握って記憶する
右手で握って暗記し、左手で握って思い出す
ボールを90秒間右手で握って暗記し、左手で握って思い出すと記憶効率が高まる
手を握るだけで脳の前頭葉が刺激され、記憶のインプット(暗記)とアウトプット(想起)をサポートする効果があります。
モンクレア州立大学のプロッパーの研究では、被験者(右利き51名)に72個の単語リストを提示し、ゴムボールを90秒間強く握ったあとに暗記を行い、さらにもう一度ボールを握ったあとに記憶した単語を思い出すという実験を行っています。
この実験では、左右の手で握ったあとに、異なる効果が得られるという興味深い結果が判明しています。
まず、被験者に次の5つのパターンで握ってもらうように指示しました。
(1) 暗記時も想起時も右手で握る
(2) 暗記時も想起時も左手で握る
(3) 暗記時は左手、想起時は右手で握る
(4) 暗記時は右手、想起時は左手で握る
(5) ボールを握らない
その結果、暗記時に右手、想起時に左手でボールを握ったグループ(4)がほかのグループよりも、暗記した単語数や正確に思い出した単語数が優れていたことがわかりました。
プロッパーは、左脳は記憶の蓄積(インプット)を担当し、右脳は記憶の引き出し(アウトプット)を担当するため、手を握る動作が、それぞれ対応する脳半球を活性化させることで、暗記や想起の効率が向上すると説明しています。
ですから、暗記する際は右手でボールを90秒間強く握り、思い出す際は左手でボールを90秒間強く握った場合にもっともよく効率よく暗記・想起できたわけです。
テストの最中などにボールを握ることはできませんが、原理としては右手や左手を動かして脳を刺激すればいいので、その場でできそうな動作を考えて実践してみましょう。
ちなみに、今回の実験は右利きの人に関してのみだったので、左利きの人に関しては今後の実験で検証していくとのことです。
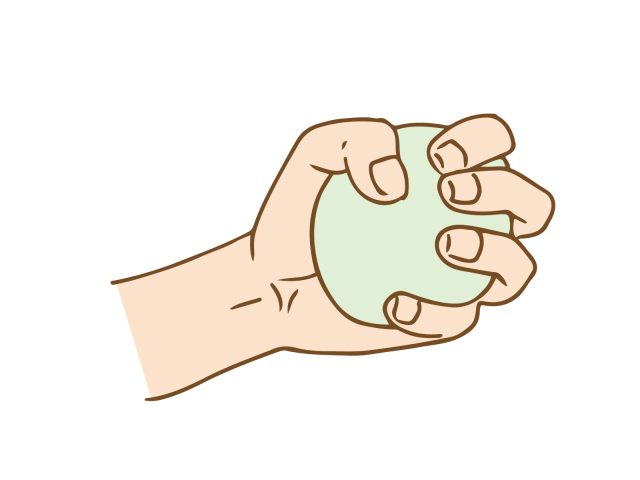
【手を握ると脳が刺激される。左脳はインプット、右脳はアウトプットを担当。右手で握って記憶し、左手で握って思い出す】
「誰かに教える」意識をもつ
あとで人に教える気もちで学ぶと学習効果が上がる
あとで人に教える意識をもつだけで成績がよくなった!
自分が学んだことを誰かに教えようとして、うまく説明できなかった経験をもつ人は、多いのではないでしょうか。教えるという行為は、教える側がしっかりと内容を理解し、整理してインプットすることが重要です。まばらに頭のなかに叩き込んでも、人にはうまく伝えることができません。
ワシントン大学セントルイス校のネストイコらは、「あとで人に教えるという意識をもって勉強すると、それだけで学習効果が上がる」という研究結果を報告しています。人に教えるという意識をもつからこそ、まばらにインプットしないようになる―そんな逆転の発想で、勉強をしようというわけです。実験では、56人の大学生を、次の3つのグループに分けて行いました。
(1) 人に教えることを前提にしたグループ
(2) あとでテストを受けることを前提にしたグループ
(3) とくに何も前提としないグループ
そのうえで、ある戦争映画における描写と史実に関する1541語からなる文章を読ませ、関係のないことをしばらくしてもらったあとに、学んだ内容についての自由記述および、内容に関する短答式(選択式)のテストを実施しました。
その結果、自由記述と短答式、双方において(1)の人に教えることを前提としたグループの成績がよくなったといいます。
伝えたいと思う気もちが理解を深める
教えることは、自分のもつ知識や技術を、学ぶ側(学生や部下など)に一方的に伝える作業に見えるかもしれませんが、学ぶことと教えることは表裏一体です。
みなさんも思い当たる節があるはずです。誰かに大事な伝言を伝えてくれと頼まれたとき、その内容はほかの記憶よりもちゃんと覚えているはずです。それは、あなたが正確に伝えたいという気もちがあるからこそ、頭のなかにインプットされやすくなり、理解につながるのです。
実際に教える機会があるとさらに学習効果がアップ
教えるという意識をもてば、緊張感や集中力、注意深さをもって、学んだり深掘りしたりできます。本当に教えなくても、ただそういう想定・意識で臨むだけで効果があるということがこの研究では示されています。とはいえ、その意識をもっているだけだと、脳が慣れてきて、「これはウソだな」と思ってしまうかもしれません。
それを回避するためには、実際に家族や友人、パートナーなどに、説明するような機会があることが望ましいです。「誰かに教えたい」、その気もちを忘れずに。
【家族・友人・パートナーに説明する意識をもって学習する。実際に説明する機会をもつとなおよし】
* * *
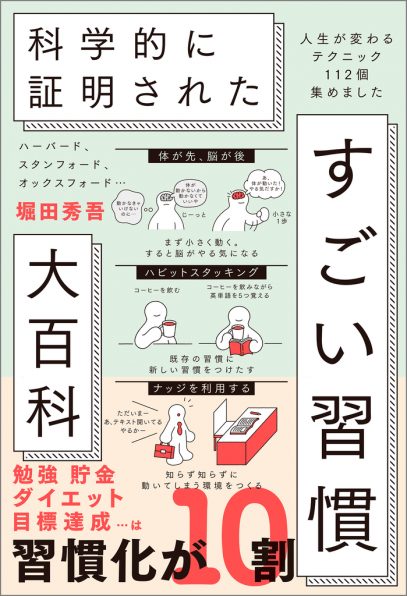
『科学的に証明された すごい習慣大百科』
著者/堀田秀吾
SBクリエイティブ 1760円(税込)
堀田秀吾
言語学者(法言語学、心理言語学)。明治大学教授。1999年、シカゴ大学言語学部博士課程修了(Ph.D. in Linguistics、言語学博士)。2000年、立命館大学法学部助教授。2005年、ヨーク大学オズグッドホール・ロースクール修士課程修了、2008年同博士課程単位取得退学。2008年、明治大学法学部准教授。2010年、明治大学法学部教授。
司法分野におけるコミュニケーションに関して、社会言語学、心理言語学、脳科学などのさまざまな学術分野の知見を融合した多角的な研究を国内外で展開している。また、研究以外の活動も積極的に行っており、企業の顧問や芸能事務所の監修、ワイドショーのレギュラー・コメンテーターなども務める。著書に『特定の人としかうまく付き合えないのは、結局、あなたの心が冷めているからだ』(クロスメディア・パブリッシング/共著)、『科学的に元気になる方法集めました』(文響社)、『最先端研究で導きだされた「考えすぎない」人の考え方』(サンクチュアリ出版)、『図解ストレス解消大全』(SBクリエイティブ)など多数。