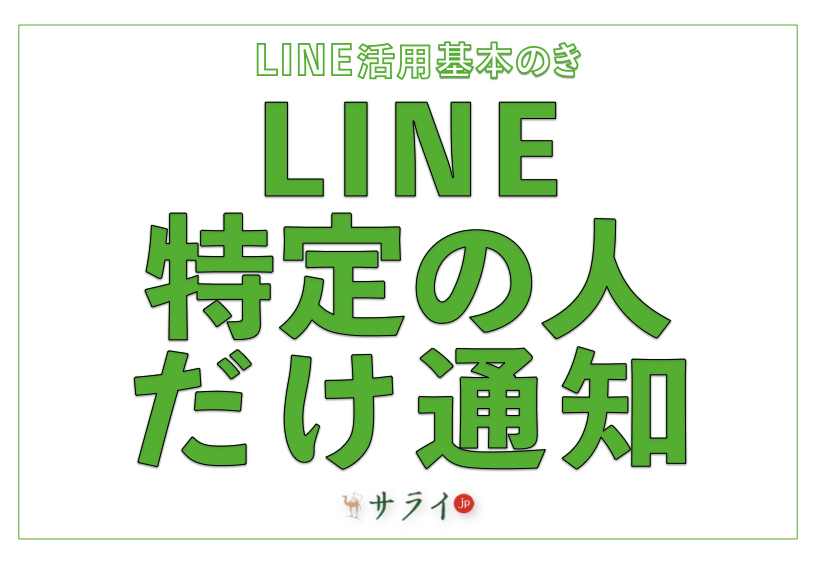マネジメント課題解決のためのメディアプラットホーム「識学総研(https://souken.shikigaku.jp)」が、ビジネスの最前線の用語や問題を解説するシリーズ。今回は、識学の視点からミスをした後の適切な対応について考察します。
はじめに
早いもので1年も半分が過ぎました。年始、新年度スタートで決めた新しいと取り組み、プロジェクトなどは現時点では納得いくものになっているでしょうか。もちろん、誰もが予定通りに事を運べるものではありませんし、予想した結果が得られないと、ついつい先送りにしてしまうこともあるでしょう。
識学では、研究や勉強、スポーツと同様にビジネスでも常に「トライ&エラー」をどこまで淡々と集中して繰り返せるか、が重要だとお伝えしております。「エラー」を「次への学び」と捉えるか、対応するかによって、個人や組織の「成長」に大きな差が生まれていくのです。
一方で、同じ間違いでも混同されやすいのは「(ケアレス)ミス」です。「こぼれたジュースは拭けばいい」で許されるのは、「こぼした」場面次第です。「ミス」と「エラー」のレベルは様々であり、内容に応じて指導方法を柔軟に変え、管理者・実行者それぞれが次に取るべきアクションをお伝えいたします。
ミスのレベルと特徴
| レベル | 内容 | 影響度 | 例 |
| レベル1 | 軽微なミス | ほぼ影響なし | 誤字脱字、軽い入力ミス |
| レベル2 | 小さな業務支障 | 社内での軽度な支障 | 社内連絡ミス、予定の食い違い |
| レベル3 | 中程度のミス | 顧客、他部署に影響 | 納期遅延、発注ミス、誤送信 |
| レベル4 | 重大ミス | 信用失墜、損害 | 契約違反、個人情報流出 |
| レベル5 | 致命的なミス | 法令違反、懲戒対象 | 業務上の横領、薬物所持、飲酒運転 |
このように、ミスのレベルによって影響範囲や深刻度が異なるため、画一的な指導ではなく、柔軟な対応が必要です。以下、「管理者」と「実行者=ミスをした本人」として分けて説明いたします。
「管理者」として取るべきアクション
(1)レベルに応じた対応判断
管理者は、まずミスの「事実確認」を冷静に把握します。その上で、影響範囲を考察し指導を使い分ける必要があります。
・レベル1〜2:口頭注意+簡単なアドバイス。感情的にならず、気づきを与える。
・レベル3:事実確認後、原因分析・再発防止策を本人と一緒に設計。場合によっては報告書提出。
・レベル4以上:上長・関係部門と連携し、正式な対応を取る(顧客への謝罪、社内処分検討など)。
例えば、営業会議で「目標数字の未達」の指導がレベル1になっていませんでしょうか。「未達=不足」と認識させ、なぜできなかったのか、どうすれば達成できたのか、と「レベル3」で管理することが成長させるためには必要です。
(2)指導の進め方
以下の3つの点に注意して指導をすることが大切です。
・叱責ではなく「問いかける」:「なぜそうなったのか?」「どうすれば防げたか?」
・改善策は一緒に考える:本人の視点を尊重しながら、現実的な対策を立てる。
・再発防止を「仕組み」に落とす:個人任せにせず、チェックリストやダブルチェックなどの仕組み化を図る。
解決策を管理者が示すのは簡単です。しかし、長い目で見ると「指示待ち」「言われたことだけをする」という思考になってしまいます。そうではなく、「では、どうすればいいと思うか」を考えさせることが成長へのステップです。
(3)信頼回復のサポート
ミスの後のフォローが極めて重要です。管理者としての責任を果たした後に、適切に「信頼の再構築」ができるよう、前向きな声かけを行います。
結果の責任は指示者である管理者自身にあります。管理者が責任から逃げることなく、部下の成長に責任をもって指導をする覚悟を持つようにしてください。
実行者(ミスをした本人)のアクション
実行者は下記の4つのステップで行動をしましょう。
(1)素直に事実を報告する
ミスが発覚したら、すぐに報告・共有します。隠蔽やごまかしは後々問題を大きくし、信頼を失う要因となります。
組織の一員であることは「ルールを守る」ことから始まります。小さな出来事が大きな炎上に発展する可能性がある時代です。個人的な主観、言い訳を考える前に、まず事実を管理者に報告することです。
(2)なぜ起きたかを自分で分析する
「確認を怠った」「情報が不足していた」「急いでいた」など、自分の行動を振り返りましょう。単なる「うっかり」で済ませず、背景にある原因(焦り・知識不足・理解不足)を深掘りします。
ミスをした認識をもつこと、そして「謝罪をする」ことから始めましょう。どれほど上手な言い訳があったとしても、個人的なミスか、組織的なミスかは相手にとって問題ではありません。そのため、実行者も管理者もミスを「自分のミス」と認めることが成長につながるのです。
(3)改善策を自分の言葉で提案する
上司に言われる前に「次回はこうします」と自分の行動計画を提示することで、信頼回復につながります。
例:「次からは提出前に同僚にチェックを頼むようにします」
まず、自分の不足が認識出来たら、改善策に進めます。不足の認識が誤っていたら、改善策も誤ってしまうのです。
(4)再発防止を習慣化する
・仕組みを作る(チェックリスト、マニュアルなど)。
・メモや記録を残す。
・苦手な業務の習熟や復習を行う。
上記は一例です。自分で習慣化しやすい方法は自分でしかわかりません。何度も何度も変更しながら、より効果的な方法を見つけてください。
管理者、実行者に共通する視点:ミスを成長のチャンスに変える
ミスは、責任の所在を明らかにすること以上に、「どうすれば次に同じことが起きないか」に目を向けることが大切です。責任追及だけに終始してしまうと、萎縮・不信感を招き、チームの力が落ちます。
指導や対応は、「人を責める」のではなく、「問題を共有し、乗り越える」という視点で行うことで、ミスを一つの学びに変え、組織全体の力に変えることができます。
失敗するかもしれない、怒られるかもしれない、という観点では常に、言い訳、アピールなど、本来行うべきタスク以外へ集中力を逸らしてしまうものです。
識学での失敗の定義は「期限内で基準をクリアできなかった状態」ということになります。しかし、期限を超えてトライを続け、基準を達成することで、その失敗は成功の糧となります。部下の失敗を「成長する機会」として管理者が前向きに受け入れ、コントロールする必要があります。
まとめ
ミスは誰にでも起こり得るものです。大切なのは、それをどう受け止め、次の一歩に変えていくかです。管理者は「責任と信頼のバランス」を保ちながら指導し、実行者は「誠実さ」と「前向きな改善意識」で行動しましょう。
失敗がOKの組織であれば、管理者は実行者に高い基準を与え続けることが可能となります。このような管理者の目線が、部下の成長実感をサポートするのです。日報、週報、週次会議、朝礼などで粗探しをするのではなく、これらを常に成長の機会として活用することで、チームの信頼と成果を築いてください。
識学総研:https://souken.shikigaku.jp
株式会社識学:https://corp.shikigaku.jp/