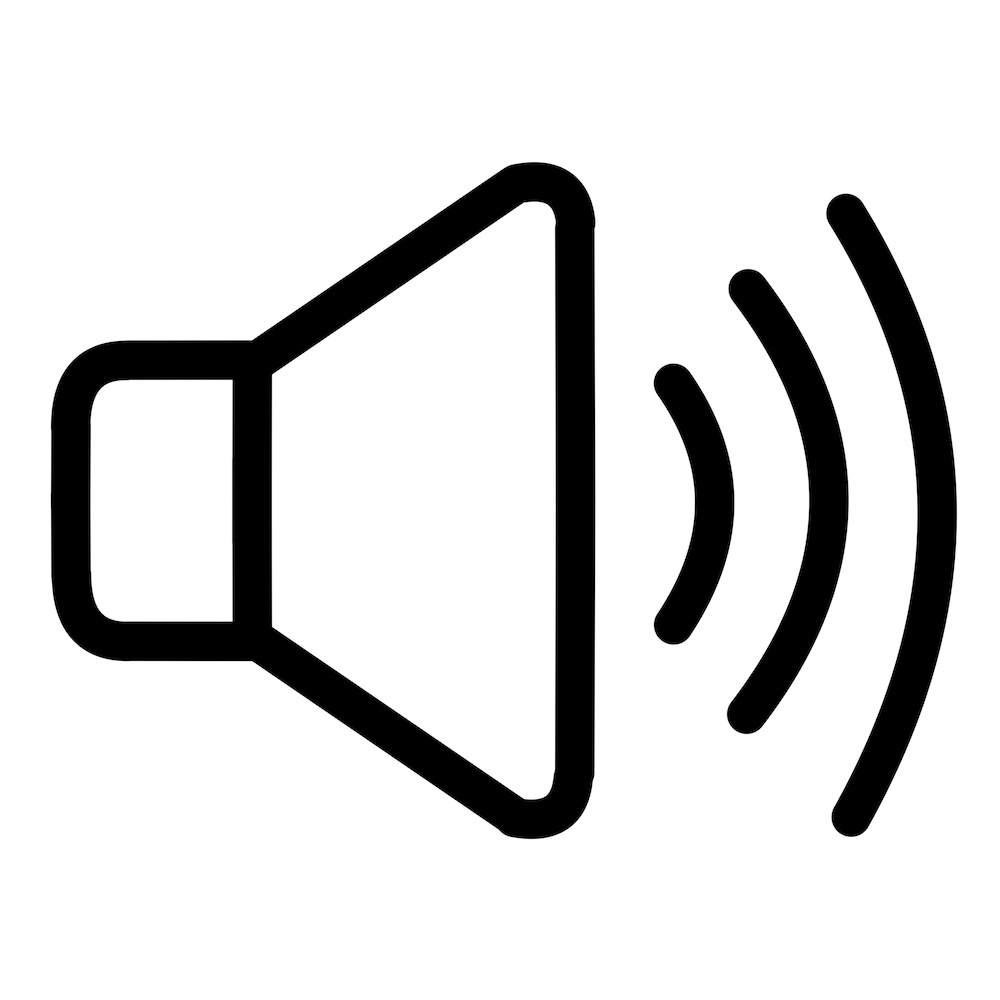取材・文/長嶺超輝

ひとり息子を育てるシングルマザー。彼女が出会った男は、自信満々で頼もしく見えた。
再婚すると同時に、その男は息子と養子縁組を結んでくれたことから「真剣にこの子の父親になろうとしてくれているんだ」と感激した。
ただ、間もなくして、旦那は息子を虐待し始めた。息子を置いて出かけるために、真っ暗なクローゼットに何時間も閉じ込めるようにもなったので、実の母親として注意しなければならないとも思っていた。
だが、自分も出かけるときに息子を邪魔だと思っていたので、旦那の真似をして、クローゼットに閉じ込める育児放棄の虐待を始めるようになった。
そこへきて、市民からの通報を受け、児童相談所の職員が実態を調査するため、一家の自宅を訪れたのである。
【前編はこちら】
* * *
■息子の顔に傷跡が見つかる
虐待事件が報道されると、まず真っ先に、児童相談所の職員が批判の的となる。「なぜ、早く見つけられなかったのか」「もっと積極的に介入すべきだったのでは」と責められてしまいがちである。
しかし、住居は究極のプライベート空間だ。強制捜査権がない児童相談所の職員が、外からズカズカと入り込むことはできない。まして、通報以外に大した証拠がないにもかかわらず、児童虐待があったと決めつけることもできない。
家人の許可を取った上、「児童虐待を未然に防ぐため、協力を求める」形で、慎重に調べを進めなければならないのである。
一家の自室にあがった職員は、家財道具や床、壁、天井などに異変がないかを、くまなく探している。母の身体は緊張感でこわばり、にわかに鼓動が激しくなる。
「息子さん、ケガしてますね。内出血ですか。どうしたんですか?」
虐待の可能性がある傷跡を、職員は鋭く察知して、その理由を問いただす。旦那が棒などで息子を引っぱたいたのかもしれない。「転んで顔を打っただけです」と、とっさに嘘を付くのが精一杯だった。
■ついに起きてしまった悲劇
母親の説明を受け、部屋をあちこち見てまわっても、児童虐待の決定的な証拠が見つからない。職員は緊急で子どもを保護しなければならないほどの切迫した状況にはないと判断し、いったん出直すことにしたのである。
惨劇は、そのわずか3日後に起きてしまった。息子が外傷性ショックで死亡したのである。息子の腹を蹴りつける暴行によって殺害した容疑で、旦那は逮捕された。
その日、妻は遊びに出かけていたが、生前の息子に対し、クローゼットに長時間閉じ込めていた行為が「監禁罪」にあたるものとして、裁判所に起訴された。監禁罪は、最高で懲役7年の刑が科される可能性があるほどの重罪である。
3歳になったばかりの息子の、小さな生命が、虐待の発覚と引き換えになってしまった。その命は、親から虐げられるために生まれてきたのであろうか。ありうるはずがない。
【これまで夫婦だけの極秘事項だった児童虐待の実態が、少しずつ明るみに出てきた。次ページに続きます】