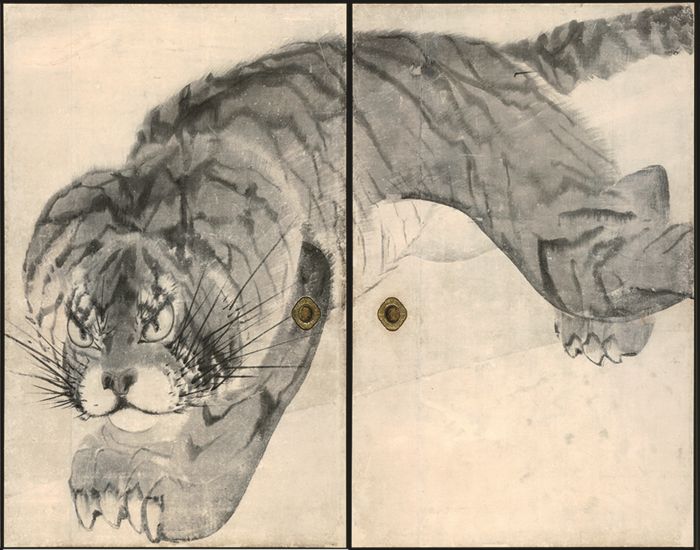文・吉村貴

曹洞宗 徳雄山建功寺 住職。庭園デザイナー (日本造園設計 代表)。多摩美術大学 環境デザイン学科 教授。
人生100年時代となって余生が伸びたことで、あらためて「終活」に注目が集まっています。しかし、実際に何から手をつけていいのか迷っている人が少なくないのではないでしょうか。禅の考え方から、終活の“定義”を「よく死ぬための準備」とするのは、先頃『定命を生きる よく死ぬための禅作法』(小学館刊)を出版した、曹洞宗建功寺住職の枡野俊明さんです。
その具体的な方法のひとつとして枡野さんは「自分史を書く」ことをすすめます。
「自分史を書くことは、自分の生きた証を残すことです。それは子から孫、その後の世代へと読み継がれていく。何代にもわたって子々孫々の心に生きつづけるといってもいいですね。禅では人は二度死ぬといういい方をするのです。一度目は文字どおりの死。二度目は身内や親しい人の心のなかから、自分の存在が消え去ってしまったときです。自分史を書いておけば、二度目の死を迎えることはありません。素敵なことだと思いませんか。これは、ぜひ、みなさんにしていただきたい“準備”ですね」(枡野さん)。
自分史というと、気負ったり、力んだりしてしまいそうな気がしますが、自分の歩んできた人生をゆっくり振り返りながら、心に残っていることできごとや印象深かった言葉、人との出会いやつながり、仕事をするなかで感じたさまざまな思い、といったものを率直に書いていく、というのが枡野流。これならグッとハードルは下がりそうです。
「子どもの頃からのアルバムを見返してみると、記憶が甦ってきて、『そういえば、あのとき、こんなことがあったな。これは書いておこう』ということになるはずですよ」そう枡野さんはアドバイスします。
終活といえばまっさきに思い浮かべるのが「相続」でしょう。今は預貯金や不動産を遺族に分け与えることですが、じつはこの言葉はもともと仏教語で、まったく違う意味で使われていたのです。枡野さんがいいます。
「本来、相続とはかたちのないものを受け継いでいくことをいった言葉なのです。いちばんいい例が、仏教において弟子が師から教えを受け継ぐということですね。みなさんにも子どもや孫に受け継いで欲しいことがあるのではないでしょうか。たとえば、生きるうえで自分が大切にしてきたこととか、これだけは守って欲しいと感じていること。後世に託したい思いなどは、誰もがもっているはずですね。それらも自分史に盛り込むといいのではないでしょうか」
どっしり腰を据えて、ゆっくり時間をかけ、やりがいをもって、とり組めるのが自分史だという気がしてきます。それはそれまでの人生の棚卸しでもあり、終活の土台ともなりそうです。同書にはそのほか、禅の教え、考え方に沿った、暮らしのなかでやっておきたい“準備”が数多く紹介されています。よき死、つまりは、安らかな死、穏やかな死、清々しい死……にたしかにつながっていく終活の実践的手引き書の趣です。
定命を生きる
よく死ぬための禅作法
著/枡野俊明

禅が教える、美しい生き方、そして逝き方。人生100年時代を生き抜く終活読本。詳細はこちら