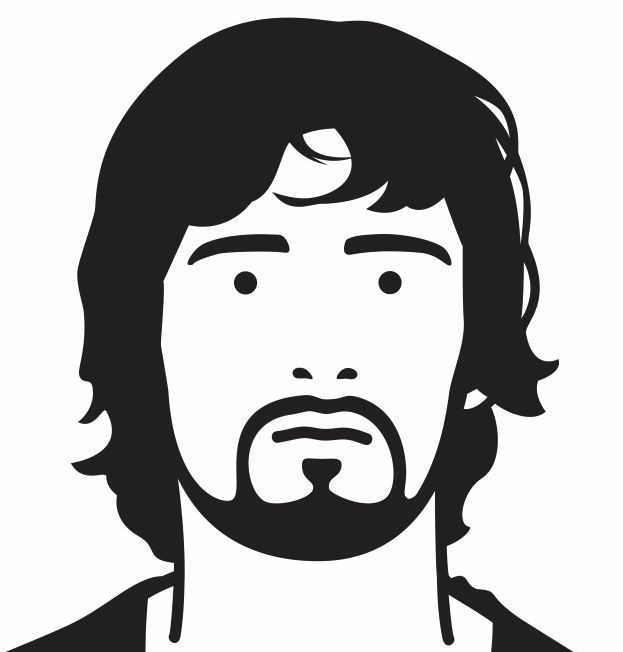取材・文/坂口鈴香

家入充子さん(仮名・75)は、首都圏にある「ひきこもり家族会」の役員として、引きこもりの家族がいる親が悩みや心配ごとを分かち合う場づくりに取り組んでいる。自身、引きこもり家族の先輩でもある。現在40代となる3人の子どもも、それぞれ大学生前後に引きこもった経験がある。同時期に、同居していた姑が60代後半で認知症を発症。20年以上在宅で介護もした。ダブルケアどころではない。そのころを振り返り、「地獄でした」とサラリと言う。その表情からは、どれほどの苦悩があったかはうかがえないが、ストレスからバセドウ病を起こし、風邪もしょっちゅうひいていたと明かす。家族会の役員を一緒に務めていた仲間は自死したと聞いて、言葉を失った。“地獄”の一端を見る思いがした。
現実を受け入れられず子どもを責めた
地獄のはじまりは、時を前後して長男と長女が引きこもったことだった。長男は地方の大学から大学院に進み、理系の研究をしていたが、通えなくなり自宅に連れて帰った。長女は第二志望だった大学に進学したが、3年生で通えなくなり中退した。2人とも、周囲とのコミュニケーションができず孤立し、大学生になるまでは苦しみながらも何とか学校には通っていたのだという。次男は大学受験に失敗して、自宅から出られなくなった。
家入さんのつらさは想像に余りある。
「現実を受け入れられなくて、子どもを責める毎日でした」
が、子どもを責めても何も変わらない。これではダメだと思うようになり、精神保健福祉センターなど相談機関を回って相談したり、引きこもりに関する本を読み漁ったりするうちに、子どものつらさは自分がつくり出したのではないかと自省するようになっていった。
「私たちが住んでいたのは姑の実家の土地で、周囲には夫の姉や伯母など親族がたくさんいるという環境でした。周りの目や評価ばかり気にして、子どもを見ていなかった。子どもの心を尊重していなかったと気づいたのです」
精神科受診が転機に
そして、精神保健福祉センターから勧められて子どもを精神科に連れていったところ、自閉スペクトラム症だと診断された。このことで長女は自分の生きづらさの原因がわかり、納得できたという。
「長男は口数が少ないので、どう感じたのかはわかりません。ですが、これをきっかけにデイケアに通うようになり、友人もできました。さらに2人は就労支援をする公的機関や訓練センターに通い、障がい者枠で就職することができたのです」
2人とも何度か転職はしたが、今長男は公務員として働いている。長女はその後も何度か引きこもりを繰り返しつつも在宅でできる仕事を見つけ、さらに昔からやりたかった英語を生かせる仕事に挑戦しようとインターン中だ。
「発達障害は親の育て方のせいではないと言われますが、私に関してはあてはまらないと思っています。私がこれまでの子育てを反省して、子どもに詫びの言葉を繰り返し伝えるうちに、子どもにも伝わっていったのだと。申し訳なかったという思いがあれば、おのずと子どもに向き合う姿勢も変わります。そうするうちに親子の関係もよくなっていったのです」
とはいえ診断を受けていない次男のことは、いまだ気がかりだ。職業訓練を受けて契約社員にはなったものの、壁に突き当たっているように感じている。
「何か言いたいことがあれば聞くよ、とは言っているのですが。ADHD(注意欠如・多動症)の傾向がある子だとは思っていますが、今は見守ることしかできません」
家入さんは最近、ある曲を聞いて強く共感したという。それは、“無条件に人を愛することを学ぶために生まれてきた”という歌詞だった。
【後編に続きます】
取材・文/坂口鈴香
終の棲家や高齢の親と家族の関係などに関する記事を中心に執筆する“終活ライター”。訪問した施設は100か所以上。20年ほど前に親を呼び寄せ、母を見送った経験から、人生の終末期や家族の思いなどについて探求している。