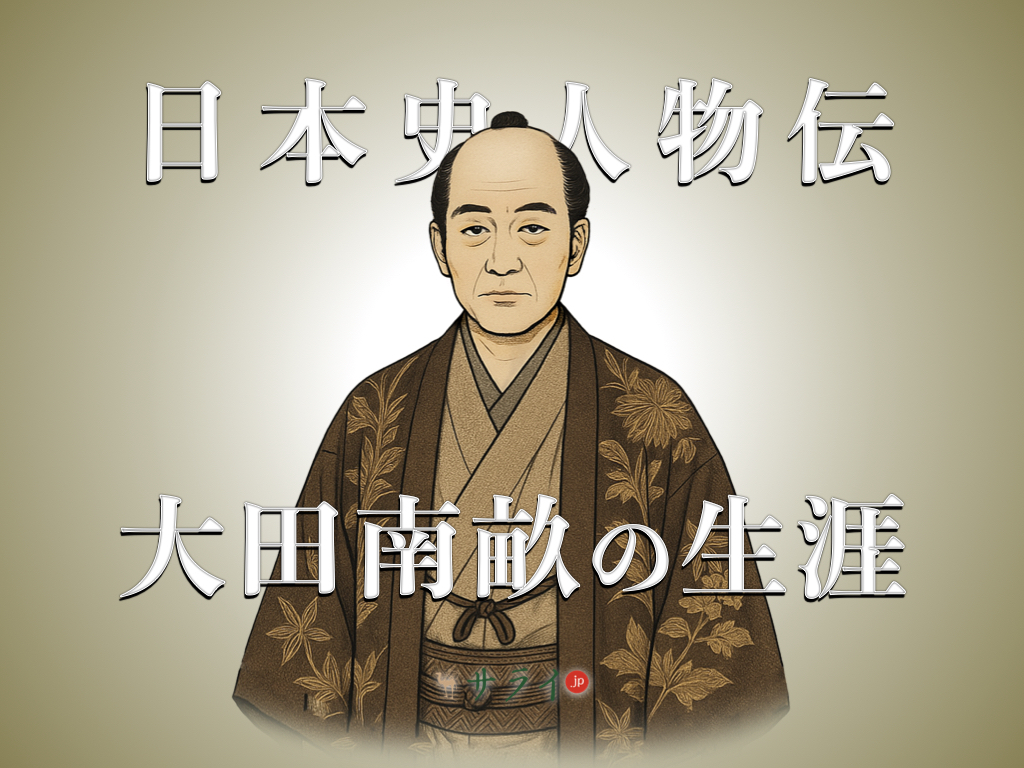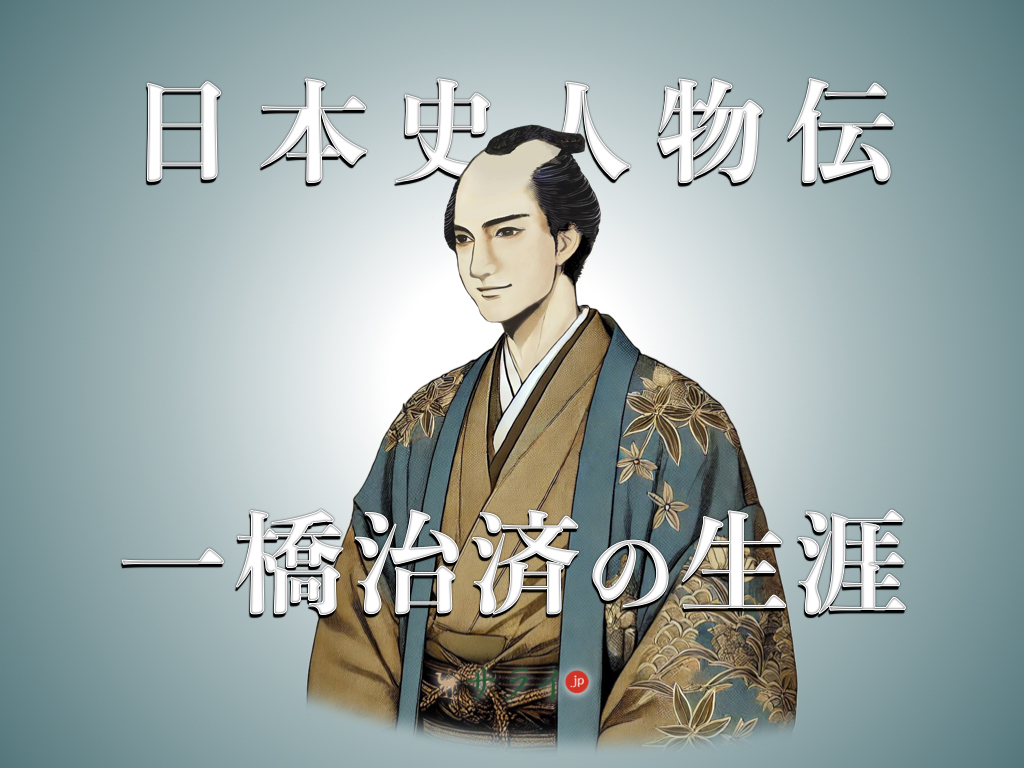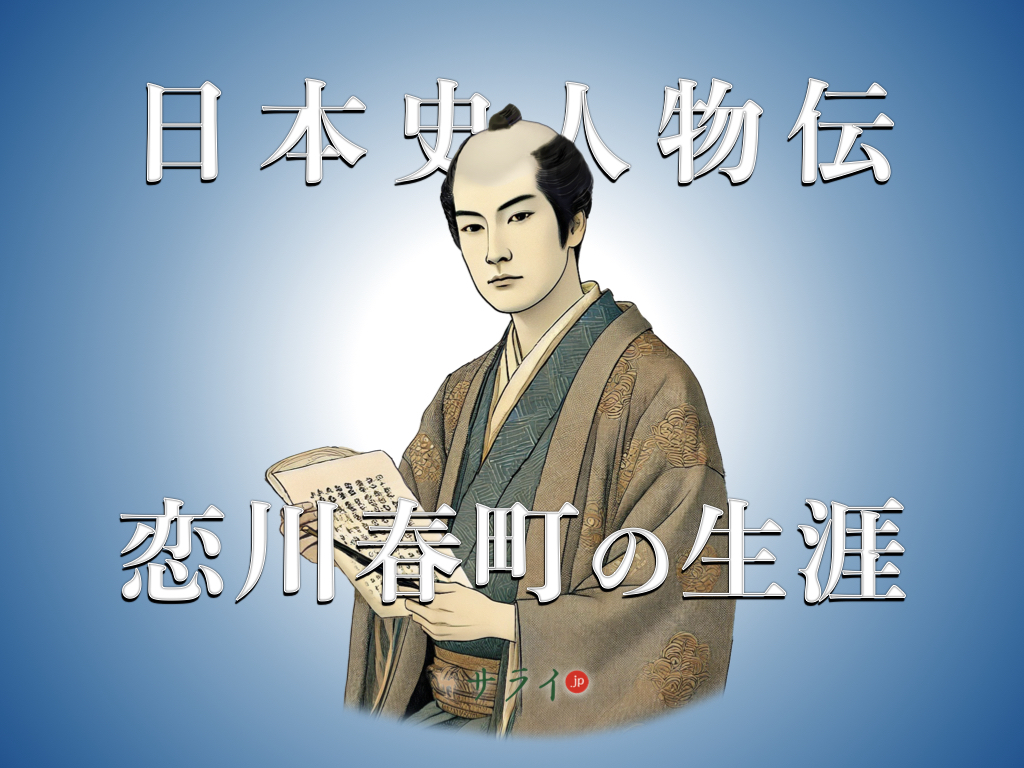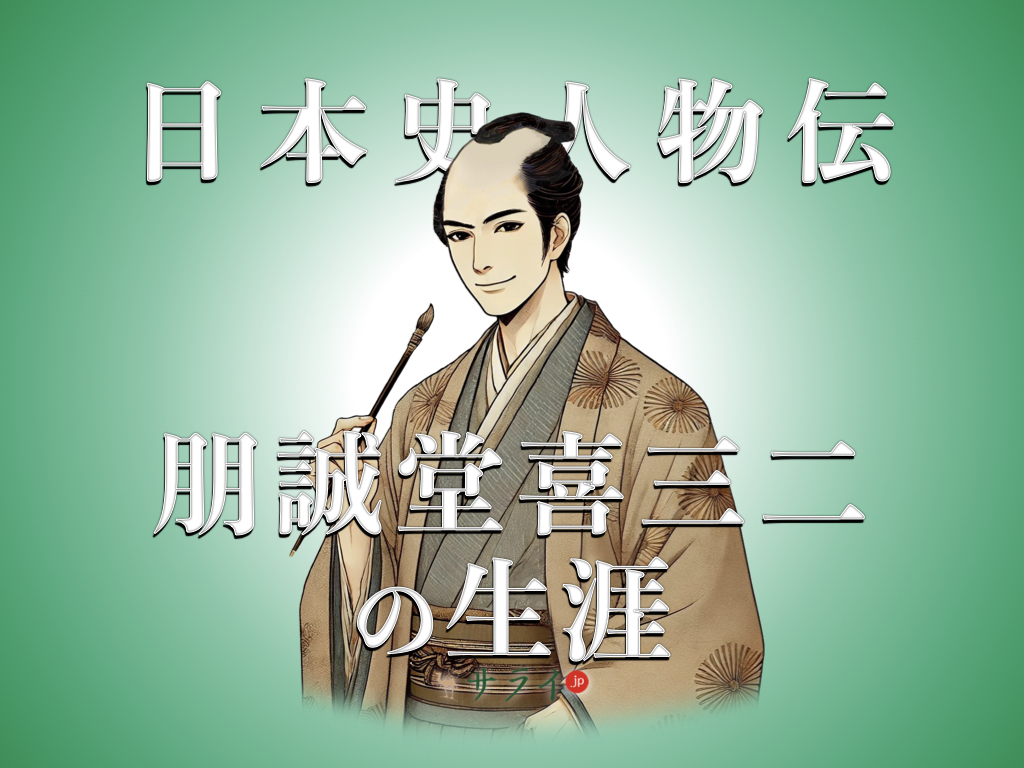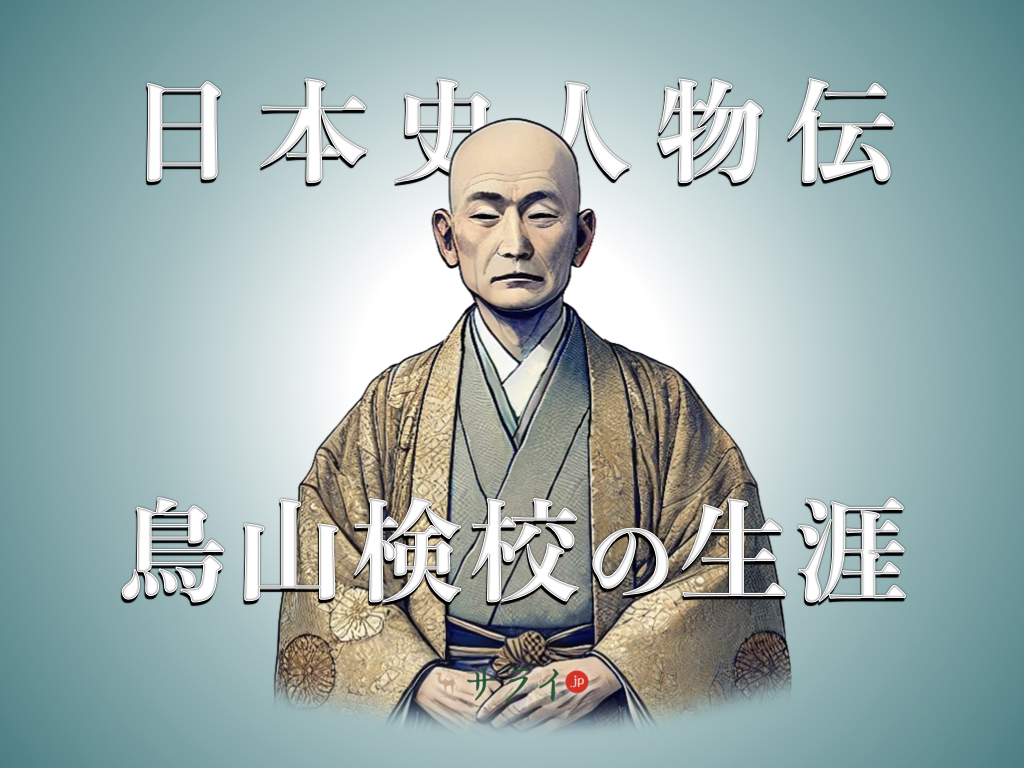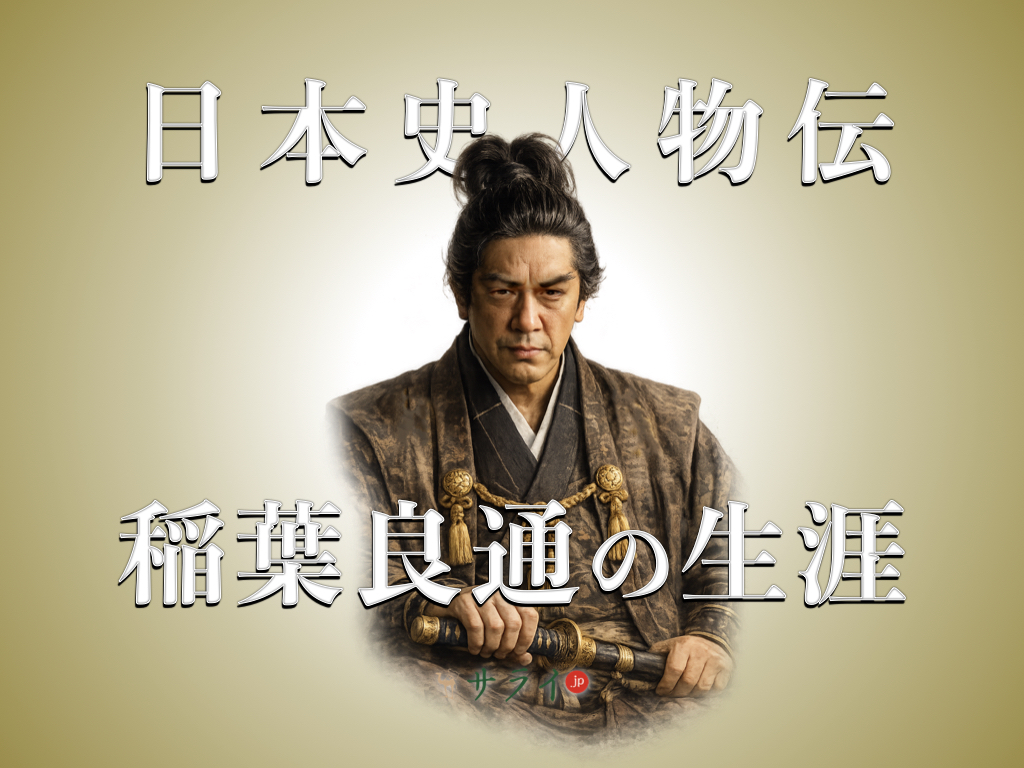大河ドラマや時代劇を観ていると、現代では使うことなどない言葉が多く出てきます。その言葉の意味を正しく理解していなくとも、場面展開から大方の意味はわかるので、それなりに面白くは観られるでしょう。
しかし、セリフの中に出てくる歴史用語をわかったつもりで観るのと、深く理解して鑑賞するのとでは、その番組の面白さは格段に違ってくるのではないでしょうか?
【日本史ことば解説】では、「時代劇をもっと面白く」をテーマに、“大河ドラマ”や“時代劇”に登場する様々な言葉を取り上げ、具体的な例とともに解説して参ります。時代劇鑑賞のお供としていただけたら幸いです。
さて、今回は「お救い小屋(御救小屋)」という言葉をご紹介します。
目次
「お救い小屋」とは?
「お救い小屋」の社会的・経済的な意味
「お救い小屋」ができた結果
まとめ
「お救い小屋」とは?
「お救い小屋」とは、飢饉、火事、水害、大地震などの災害時に、家を失い、食にも困った人々――いわゆる「窮民」を一時的に収容し、食糧などを提供するために設けられた仮設小屋のことです。
江戸時代を通じて幕府や町会所、寺社、富商などが設置主体となり、臨時的に建てられました。古くは応永28年(1421)、将軍・足利義持が京都・五条河原に設けた例もありますが、本格的に制度化されたのは江戸時代中期以降です。
特に、天保の大飢饉(1836〜1837年)では、江戸市中に21棟もの「お救い小屋」が建てられ、男女あわせて約5800人が収容されました。米や梅干し、握り飯などが配給され、体調を崩した者については医師が診療に当たったそうです。

「お救い小屋」の社会的・経済的な意味
「お救い小屋」は、単なる炊き出しとは違い、被災者や困窮者を日中は働きに出させ、稼ぎをまとめて小屋を出るときに“復興資金”として渡すなど、自立支援の場でもありました。
資金は町会所の積立金や豪商からの寄付によってまかなわれ、町単位で協力して支える仕組みが築かれていたのです。町人たちはこうした施設を「御仁恵御救小屋」と呼び、幕府や町の“恩恵”の象徴として捉えていたようです。
とはいえ、収容は町人に限定されることも多く、復帰のために「元手銭」を稼ぐことが求められたり、小屋入りは「百日まで」と期限が設けられたりと、生活全体を管理される側面もありました。そこには、町人社会の規律と復興への強い意識が反映されています。

「お救い小屋」ができた結果
「お救い小屋」の設置は、江戸の町に一定の秩序と安全をもたらしました。飢えた人々が路上にあふれることを防ぎ、犯罪の抑止にもつながったと考えられます。町人たちにとっても、「いざという時に頼れる場所」があることは、大きな安心材料だったでしょう。
また、町人が町人を支える共同体意識も育まれ、被災者の早期復帰を後押しする役割も果たしました。江戸の町が幾度もの大火や天災を経てなお再生し続けられたのは、「お救い小屋」のような仕組みがあったからかもしれません。
まとめ
現代の避難所や災害支援とは異なる点も多い「お救い小屋」ですが、江戸の町人たちが互いに支え合い、復興を目指していた姿は、現代にも通じるものがあります。
時代劇に登場する「お救い小屋」という言葉の背景に、こんなにも人々の知恵と努力が詰まっていることを知れば、きっと物語の見方も少し変わってくるのではないでしょうか。
※表記の年代と出来事には、諸説あります。
文/菅原喜子(京都メディアライン)
HP:http://kyotomedialine.com FB
引用・参考図書/
『日本大百科全書』(小学館)
『世界大百科事典』(平凡社)
『国史大辞典』(吉川弘文館)