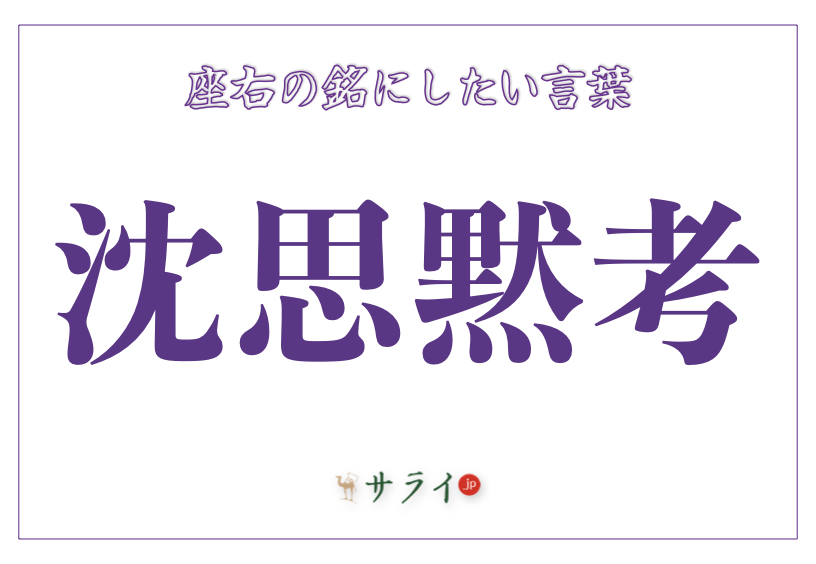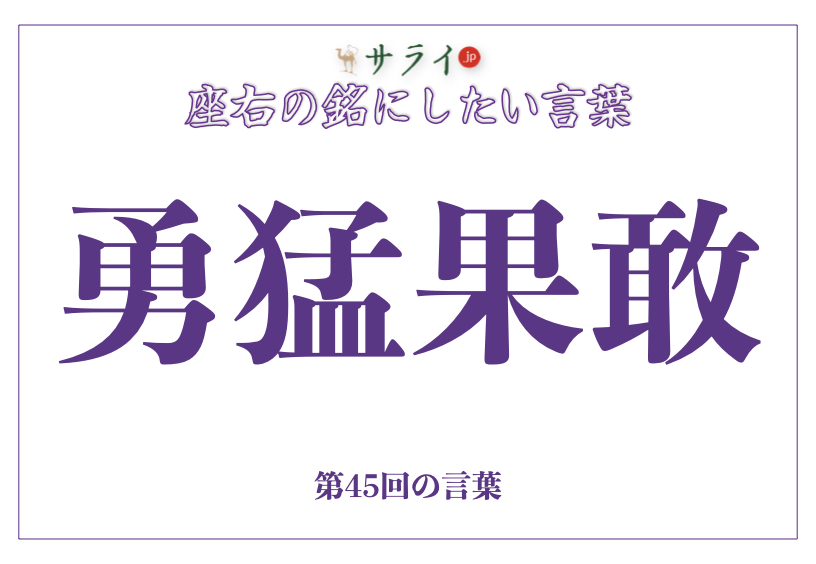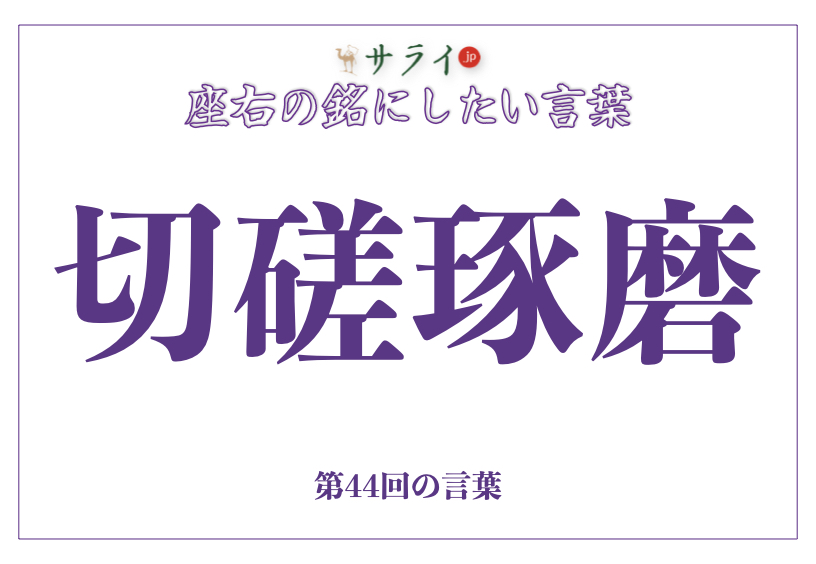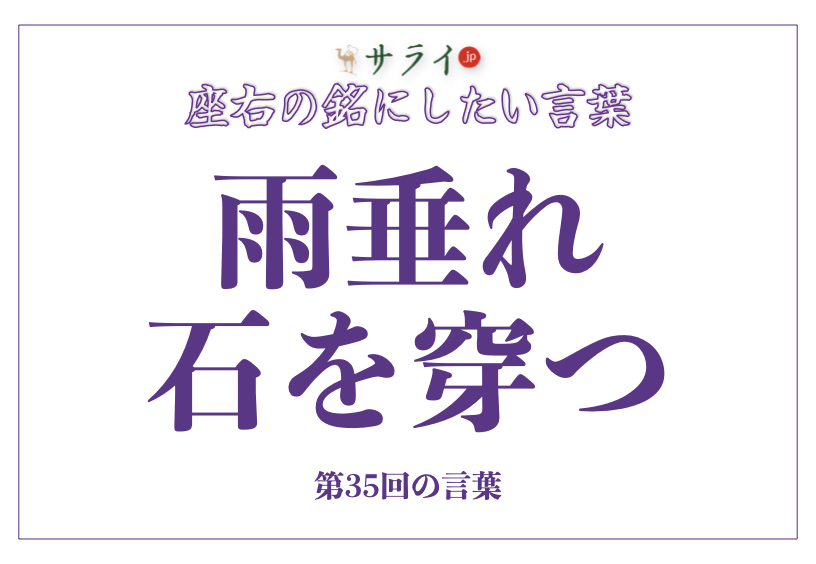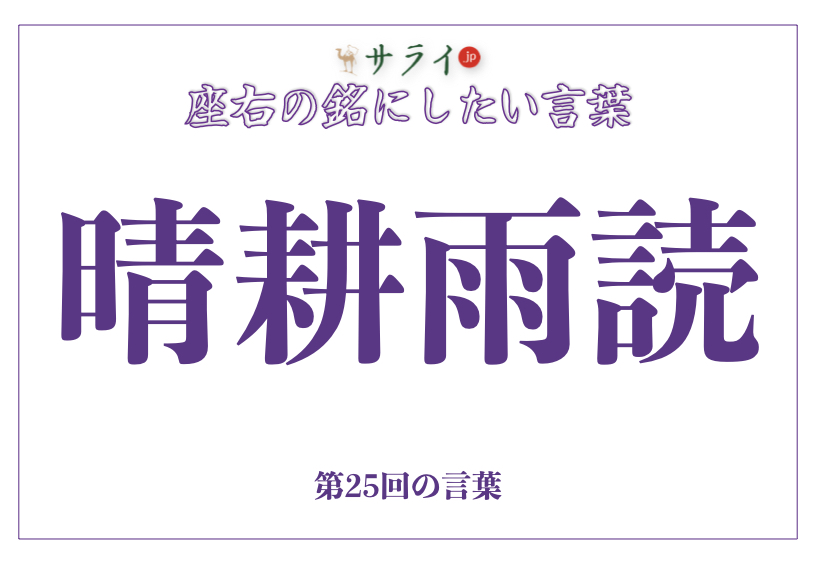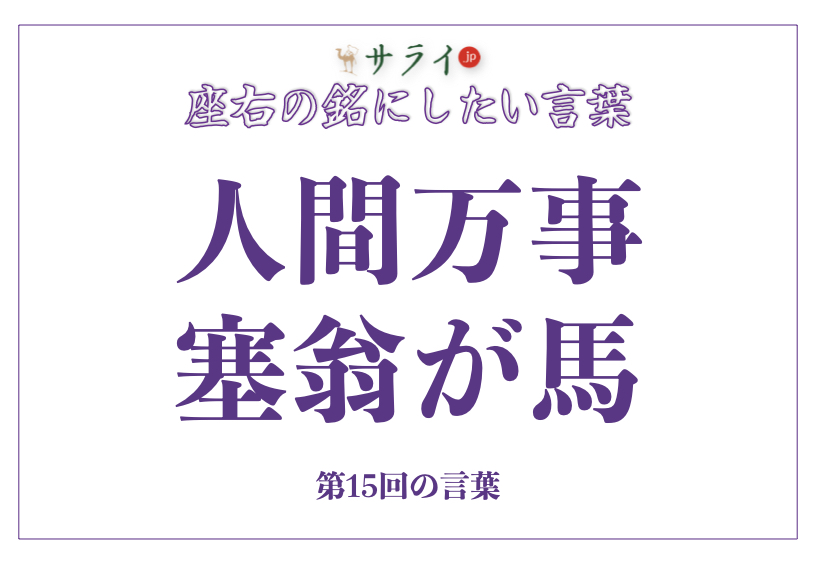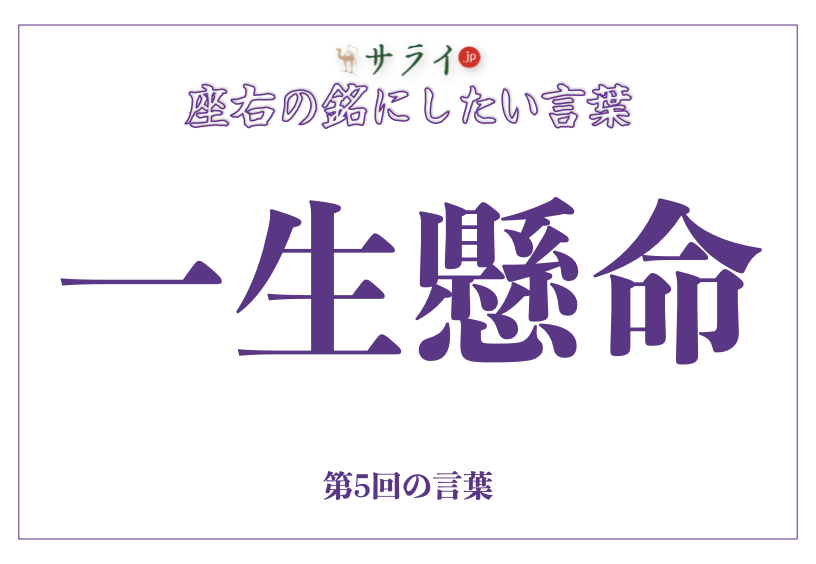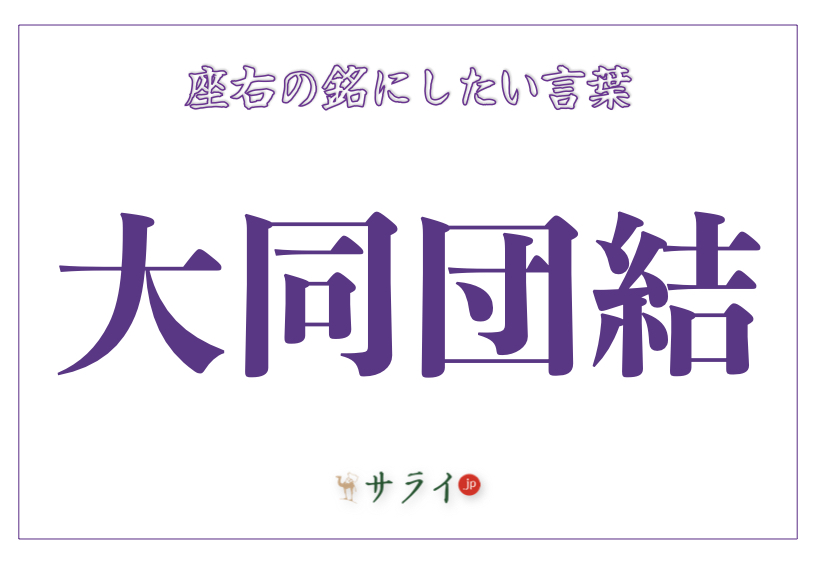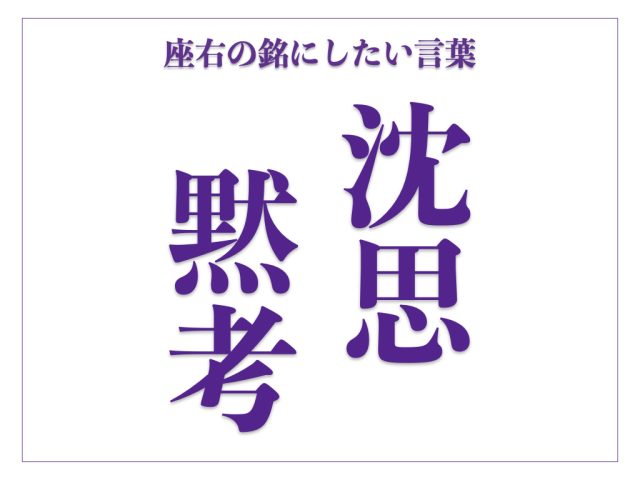
決して、人生「順風満帆」とは行かぬものです。
若い頃と違って、壮年期を過ぎてからの不幸な出来事や災難は、精神的にも大きなダメージとなります。そんな時でも、顔を上げ、前に進まなければならないのが人生ではないでしょうか?
何気ない友人や知人が掛けてくれた言葉が、深く傷を負った心を癒し、勇気づけてくれる場合もあります。また、先人が残した言葉を紐解けば、いくつもの教訓や悟りが残されており光明となることもあります。
そんな言葉の一つとなることを願い、今回の座右の銘にしたい言葉は「沈思黙考(ちんしもっこう)」 です。
目次
「沈思黙考」の意味
「沈思黙考」の由来
「沈思黙考」を座右の銘としてスピーチするなら
最後に
「沈思黙考」の意味
「沈思黙考」について、『⼩学館デジタル⼤辞泉』では、「沈黙して深く考えること」とあります。じっくりと思索にふけり、物事の本質を見極めようとする姿勢を表す言葉です。「沈思」と「黙考」はどちらも深く考えるという意味を持つため、熟語を重ねて意味を強調しています。
日々の喧騒から離れ、自分自身と向き合う時間を持つことは、心の安定をもたらし、新たな発見や気づきを与えてくれます。特に、多くの経験を積まれたシニア世代にとっては、過去を振り返り、未来を見据える上で、非常に重要な時間となるでしょう。
「沈思黙考」の由来
「沈思黙考」という言葉の明確な由来は特定されていませんが、「沈思」は深く考え込む様子を表しています。「黙考」も同様に、静かに考えをめぐらすという意味です。これらの言葉が組み合わさり、「沈思黙考」という熟語が生まれたと考えられます。
古来より、賢人や哲学者たちは、物事を深く考えることを重要視してきました。現代社会においても、情報に流されず、自分自身の頭で考える力はますます重要になっています。「沈思黙考」は、時代を超えて受け継がれてきた知恵といえるでしょう。
「沈思黙考」を座右の銘としてスピーチするなら
サライ世代である読者の方々にとっては、人生の経験を重ねたうえで「沈思黙考」を座右の銘とすることの意味は非常に深いものです。若い頃には気づかなかった心の静けさや、忙しない生活の中で忘れがちな「立ち止まること」の大切さを再認識することがあるかもしれません。
「沈思黙考」を実践することで、「何をすべきか」「どの道を選ぶべきか」といった重要な決断において、一段上の視野を持つことができます。特に家庭、仕事、趣味と多方面で活躍されているシニア世代にとって、大きな支えとなる言葉といえるでしょう。以下に「沈思黙考」を取り入れたスピーチの例をあげます。

立ち止まってゆっくり考えることの重要性を示すスピーチ例
私の座右の銘は「沈思黙考」です。この言葉は、深く静かに考えることの大切さを教えてくれます。人生には、仕事、家庭、人間関係など、様々な岐路があります。そんな時、私はこの言葉を思い出し、立ち止まって考えるようにしています。
若い頃は、目の前のことに追われ、じっくり考える時間を持つことができませんでした。しかし、年齢を重ね、経験を積む中で、「沈思黙考」の重要性に気づきました。静かに自分と向き合うことで、本当に大切なものが見えてくるのです。
例えば、定年退職を迎えた時、今後の人生について深く考えました。その結果、長年の夢だったボランティア活動を始めることにしました。今では、地域の方々との交流を通じ、充実した日々を送っています。
「沈思黙考」は、私にとって人生の羅針盤のようなものです。これからも、この言葉を胸に、悔いのない人生を歩んでいきたいと思っています。
最後に
情報があふれ、常に何かに追われる現代社会において、「沈思黙考」という言葉は、私たちに立ち止まって考えることの大切さを教えてくれます。特にシニア世代にとって、この言葉は単なる四字熟語以上の、人生の指針となり得るものです。
騒がしい世の中だからこそ、静かに考える時間の価値は高まっています。「沈思黙考」という座右の銘を胸に、心の静けさを大切にする生き方を実践してみませんか。きっと、これまでとは違った景色が見えてくるはずです。
●執筆/武田さゆり

国家資格キャリアコンサルタント。中学高校国語科教諭、学校図書館司書教諭。現役教員の傍ら、子どもたちが自分らしく生きるためのキャリア教育推進活動を行う。趣味はテニスと読書。
●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com