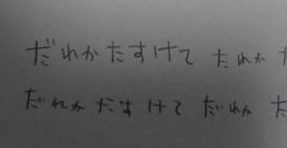文/砂原浩太朗(小説家)

「小牧・長久手の戦い」とは何だったのか(前編)はこちら
長久手の戦い
1584年3月末、秀吉・家康の両雄はついに対陣のときを迎えた。ここに至る約半月の戦闘を「小牧の戦い」と総称している。家康が本陣を置いた小牧山の名を取ったわけだ。この対陣中、家康配下の榊原康政が秀吉を「大逆無道」と罵る檄文を発し、大いに相手方を怒らせたというエピソードをご存じの方も多いだろう。
目立った戦闘もないまま月が替わり、4月に入って、池田恒興(前編参照)が徳川の本国・三河を突く作戦を具申した。いちどは難色をしめした秀吉だが、甥の秀次(1568~95。のちの、いわゆる「殺生関白」)がこれを支持したため、恒興の案を許可する。6日夜半、秀次を総大将として1万6000の兵が進発したのだった。
ところがこの動きは、端から徳川方に見破られていた。ひそかに本陣を出た家康は、先述の榊原康政率いる別動隊と示し合わせ、9日、長久手(愛知県長久手市)で秀次軍を挟撃する。池田恒興と長男の元助、鬼武蔵と異名をとった女婿の森長可がそろって討死にし、秀次はなす術もなく逃げ帰った。これが「長久手の戦い」であり、家康方の圧勝というほかない。
余談ながら、元助の弟が有名な輝政(1564~1613)で、初代姫路藩主。世界遺産の姫路城天守を建造した人物である。江戸期を通じて一族の合計石高が百万石近くになるなど、池田家繁栄の基を築いたが、兄の死により家督を継がなければ、かなり異なった人生を歩んでいただろう。歴史のふしぎさを感じる一齣である。
講和へ
ただちに徳川方を破るのはむずかしいと見た秀吉は、主力の軍勢を残し、自身は撤退を開始する。途中、信雄の支城をふたつ陥として、長久手の黒星を挽回した。この際、得意の水攻めなどをおこなったため、大坂に帰着したのは6月も末になっている。家康はすでに小牧山を離れ、清洲へ戻っていた。当面、大きな対決はないと見極めたのだろう。
この後、8月に入ってふたたび秀吉が出馬してきたが、全面的な戦いもないまま時が過ぎてゆく。長期の滞陣を避けたい秀吉は、信雄と家康の分断を試みる策に出た。信雄の居城・長島(三重県桑名市)を攻撃する構えを見せ、単独講和を持ちかけたのである。11月、圧力に屈した信雄がこれに応じたため、家康は秀吉に抗する大義名分を失った。次男・於義丸(のちの結城秀康)を秀吉の養子、実質は人質として差し出すことでようやく講和が成ったのである。およそ8ヶ月におよぶ戦いは、こうして終わったかに見えた。
終わりなき戦い
が、ふたりの駆け引きはこれからが本番といってよい。翌1585(天正13)年、紀州攻め、四国攻め、越中富山攻めと相次いで勝利をおさめ、関白職に就いて朝廷から豊臣姓を下賜(翌年12月説も)された秀吉だが、家康はいまだ臣従の姿勢を見せようとしなかった。長久手での敗戦は世の知るところだから、秀吉にしてみれば、そのままにはしておけない。和平を結んだことと、相手を屈服させたことはべつである。どうでも家康を上洛させ、臣従の礼を取らせなければ、天下にしめしがつかないと考えたのだった。
秀吉はついに、妹の旭(あさひ)を家康に嫁がせることとした。1586(天正14)年5月のことで、旭はこのとき44歳、ひとの女房になっていたのを離別させてまで遣わそうというのだから、秀吉の執念が伝わってくる。ちなみに旭の夫は佐治日向守とも副田甚兵衛ともいわれていて、厳密なところは不明である。
この先は家康の面目躍如ともいうべき展開となる。正室として旭を受け入れたものの、それでも動こうとしない。むろん秀吉を焦らす意図もあったにせよ、うっかり上洛などして討ち取られてはという懸念もあったと思われる。現代のわれわれは結果を知っているが、渦中にある家康からしてみれば、そういう可能性もじゅうぶんあると見えたはず。人質を犠牲にしても敵を葬る、というのは戦国の世に於いてめずらしい話ではなかった。
臣従の裏側
困り果てた秀吉は、とうとう生母・大政所を人質として差し出すという挙に出る。おなじ1586年の10月、旭のようす伺いという名目で、家康のもとへおもむかせた。これが最大にして最後の譲歩であることは、家康にもはっきりと伝わったはずである。儒教が行き渡る以前ではあるものの、やはり親を人質にというのは並たいていの覚悟ではない。小説的な想像だが、おさなくして生き別れたみずからの生母・お大(久松俊勝に再嫁)への思いが頭を過ぎった可能性もあるだろう。
ついに家康は上洛し、諸大名のまえで秀吉に臣従の姿勢をしめした。前夜、宿舎をおとずれた秀吉が、「あすは皆のまえで自分に頭を下げてほしい」と懇願したという有名なエピソードがある。ドラマなどでよく見る場面だが、これは徳川幕府の公式記録「徳川実紀」にある話。ふつう正史だから信憑性が高い、と思えるが、それゆえに「懇願されてやむなく臣従した」というくだりを作る必要があったともいえる。筆者自身は、そちらの見方にリアリティを感じている。前夜の家康訪問は事実だから、「明日はよろしく」くらいの念押しが、このように脚色されたということはじゅうぶんあり得る。
いずれにせよ、ようやく家康は秀吉に臣従の礼を取った。矛をまじえてから実に2年半、このときこそ「小牧・長久手の戦い」は終結したというべきである。かたちはともかく、家康の粘り勝ちと感じるのも筆者だけではあるまい。
終始、信長の同盟者でありつづけたのと同じく、家康は秀吉の生前、家臣筆頭の立場を全うし、ついに叛くことはなかった。関ヶ原に勝利し、天下の権を握ったのは14年後である。むろん、時来たれば自分が、との思いは持ちつづけていただろう。その持続力と強靭な意志、機を見極める洞察力には驚嘆せざるを得ない。筆者は戦国三英雄のなかでもっとも家康を好んでいるのだが、こうしたところになんとも惹かれるものを覚えるのだ。
文/砂原浩太朗(すなはら・こうたろう)
小説家。1969年生まれ、兵庫県神戸市出身。早稲田大学第一文学部卒業。出版社勤務を経て、フリーのライター・編集・校正者に。2016年、「いのちがけ」で第2回「決戦!小説大賞」を受賞。2021年、『高瀬庄左衛門御留書』で第165回直木賞・第34回山本周五郎賞候補。また、同作で第9回野村胡堂文学賞・第15回舟橋聖一文学賞・第11回本屋が選ぶ時代小説大賞を受賞。2022年、『黛家の兄弟』で第35回山本周五郎賞を受賞。他の著書に『いのちがけ 加賀百万石の礎』、『霜月記』、『藩邸差配役日日控』、共著に『決戦!桶狭間』、『決戦!設楽原(したらがはら)』、『読んで旅する鎌倉時代』、『どうした、家康』などがある。『逆転の戦国史「天才」ではなかった信長、「叛臣」ではなかった光秀』 (小学館)が発売中。
「にっぽん歴史夜話」が単行本になりました!
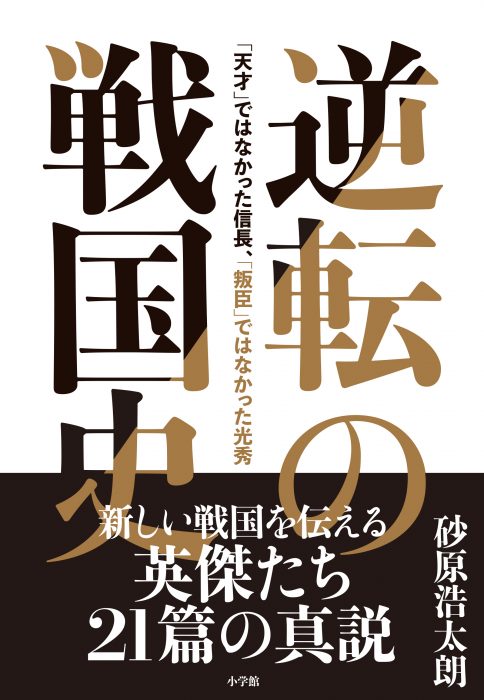
砂原浩太朗 著
小学館