
子どもの言葉が荒くなった、口をきいてくれなくなった、暴力をふるわれたなど、大人への移行期である思春期の子どもの心は不安定で、突然の変化に戸惑う親は多いと言われています。そこで、福岡県北九州市の土屋ホームで心に傷を抱えた子どもたちと暮らしながら、社会へと自立させてきた、日本でただひとりの「治療的里親」である土井髙徳さんの著書『思春期の子に、本当に手を焼いたときの処方箋33』から、どんな子どもにも効く思春期の子育てのコツを学びましょう。
文/土井髙徳
子どもの内面を侵さず、離れもしないという距離感を保つ
2012年に公開された映画『隣る人』は埼玉県の児童養護施設の子を追ったドキュメンタリーです。家庭環境を失った子どもたちが母親代わりの保育士たちと生活をしています。ここで描かれているのは「特別で特定」の人との愛着が、子どもたちにとって「安心で安定」の基盤であり、子どもの成長の上で欠くことのできないものであるということです。
小学生のムツミは田んぼのあぜ道を歩きながら「どうせおまえなんかいらない」「消えろ」とひとり言を繰り返します。それは幼いムツミ自身が家庭で言われ続けた言葉なのでしょう。そのムツミにショックな出来事が起こります。同居の少女マイカの担当保育士マキタが配置転換になり、マキタに泣いてすがるマイカが無理に引き裂かれる別れの場面に直面します。ムツミはいつも「隣にいる人」がいなくなるかもしれないという不安に襲われます。
その夜ムツミは、自分の担当保育士のマリコへの想いを「大好き」とノートが破れんばかりに繰り返し書きなぐります。そしてマリコの愛情を奪い合い、ときには対立してきた同部屋のマリナとふたりでマリコのふとんに顔をうずめ、「いいにおい」と語る場面は切なく、私たちの心を締めつけます。それは、人と人の普遍的な関係のありようを私たちの心に語りかけています。
砂場で遊んでいる子どもは、ときおり自分を見守る親のまなざしを確かめては安心し、少しずつ行動の範囲を広げていきます。泣くことがあれば親が駆けつけてくれます。こうした「応答」のおかげで子どもは自己と他者への基本的信頼感を養い育てていきます。この信頼感を基礎に子どもは、親からの自立と親への回帰を行きつ戻りつしながら自立への道を歩んでいくのです。
思春期の子どもはやっかいです。しかしそのやっかいな言動の背後には、親に対する子どもの切実なニーズがあります。そんな子どもへの無関心と養育の放棄であるネグレクトが子ども虐待のひとつの極なら、一方で、子どもを親の所有物と考え、子の内面にむやみに侵入し、親の思いのままにならぬと怒りを爆発させて体や心をしいたげるのがもうひとつの極です。
子どもの内面を侵さない代わりに離れもしない。隣からいつもメッセージを発し続けることが親のもっとも大事な役割なのです。「いつでもそばにいるよ」と。
【ひと口メモ】
映画『隣る人』を観た社会的養護(家庭環境を失った子どものケア)関係者からはふたつの異なる反応がありました。ひとつは保育士マリコのように献身的な育児をしようとすれば、到底結婚はおぼつかないというものです。実際、マリコは結婚もせず24時間の住み込み生活を送っています。そこまではできないという施設関係者の声です。
一方、どんなに献身的に尽くしても施設である限り人事異動からは逃れられません。またわが家を持ち、交代勤務になれば、職員はその疑似的な家に通ってくる人でしかなく、家庭的環境を失った子どもに家庭環境を与えることはできないという主張です。多くは里親の皆さんの意見でした。
主張が異なっていても共通していたのは、子どもは家庭生活を通じてその切実なニーズに応答される必要があるという点です。
* * *
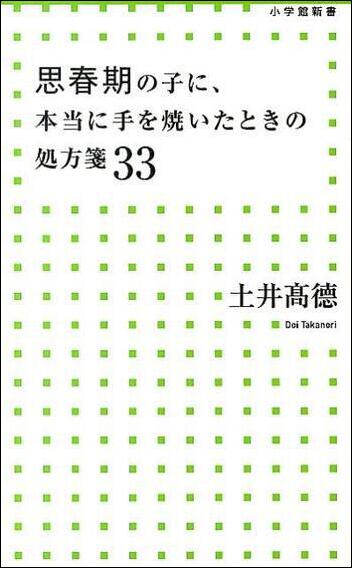
『思春期の子に、本当に手を焼いたときの処方箋33』(土井髙德 著)
小学館
土井髙德(どい・たかのり)
1954年、福岡県北九州市生まれ。里親。「土井ホーム」代表。保護司。学術博士。福岡県青少年育成課講師。北九州市立大学大学院非常勤講師。心に傷を抱えた子どもを養育する「土井ホーム」を運営。医師や臨床心理士など専門家と連携し、国内では唯一の「治療的里親」として処遇困難な子どものケアに取り組んでいる。2008年11月、ソロプチミスト日本財団から社会ボランティア賞を受賞。


































