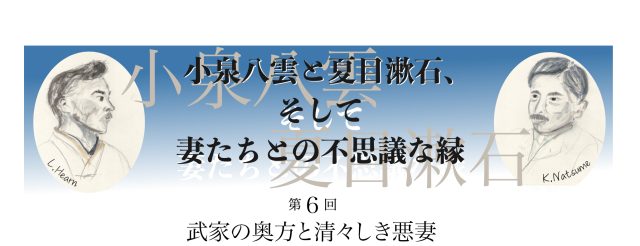
小泉セツ&小泉八雲の夫婦がモデルとなった朝の連続テレビ小説『ばけばけ』が注目されています。実はその小泉夫妻と、明治の文豪・夏目漱石と妻・鏡子は、不思議と重なり合う縁で結ばれていた、というのをご存じでしょうか。
夏目漱石の研究家として知られ、『心を癒す漱石の手紙』などの著書を持つ、作家で雑誌編集記者の矢島裕紀彦さんによると、二人の文豪とその妻たちには奇縁と呼ぶしかないような不思議なつながりがあると言います。
多数の文献や手記を紐解きながら、二組の夫婦の知られざる素顔を全26回の連載にて紹介します。
第6回では、小泉家、夏目家のそれぞれの妻たちの日常を比べてみます。
文・矢島裕紀彦
古式ゆかしき小泉家の日常

セツという伴侶を得た小泉八雲の日常の暮らしぶりは、次のチェンバレン宛て書簡に綴られている。日付は明治26年(1893)10月11日だから、八雲とセツはこのとき、セツの養父母らをともなって熊本に移り住んでいる。
きょうはわたしの一日の暮らしぶりを実例として御笑覧に供しましょう。(略)午前六時。――小さな目ざまし時計が鳴ります。家内が起きて、昔の武家時代の四角ばった挨拶で、わたしを起こします。(略)午前七時。――朝食。(略)家内が給仕します。わたしは家内にも、同じ膳ですこし食べることをすすめますが、家内はほんのまねごとしか食べません。あとで、家族の朝飯の席に出なければならないからです。
このあと、熊本五高に出勤する八雲のため、セツが着替えを手伝う。
わたしはヨーフクに着がえます。はじめのうちは、家内がシャツ、ズボン、上着と手順よく渡してくれたり、ポケットの中身をしらべてくれたりする日本の習慣が、どうも好きになれませんでした。それは人を怠惰にすると思ったからです。でも、それに反対すれば、相手の気を悪くして、せっかくの喜びをそこねることになるのがわかったので、いまは昔の慣例に従っています。
八雲の筆は、夕食後、就寝までの時間にも及ぶ。
わたしは眠りにつくまで、ときどき読書をすることがあります。ときには床のなかで鉛筆で書きつづけることもあります。家内はいつも昔からのしきたりで、お先に休ませていただきますといいます。あまりに卑下しすぎると思って、その習慣をやめさせようとしたこともありましたが、結局美しい習慣で、魂のなかに深く根をすえていることなので、やめさせることができませんでした。
少し長い引用になったが、これでも一部の抜き書きである。八雲は日本の旧来からの家族主義を引き受けながら、初めて家庭生活の温かさを知った。なんだかんだ言いながら、内心、ちょっと浮かれ調子だったのかもしれない。
セツは早くから生活の苦労をしていた。学校での勉強を早くに諦め、働きながら家事もこなしていたが、一方では武家の娘としてひと通りの嗜みは身につけていた。八雲と一緒になってからも、旧幕時代からの風習のまま、一家の主を立て、家事をこなし家庭を守る“武士の奥方”のような役割をつつがなくこなしていたことが窺える。
八雲一家は明治24年(1891)11月から27年(1894)10月まで、3年間、熊本の地で暮らした。この間、ふたりの間に長男の一雄が誕生している。
漱石と鏡子の新婚生活のスタート地点も、熊本であった。
東京での見合いから間もなく、漱石は熊本五高へ転任。つい1年半前まで八雲が立っていた同じ教壇に立つ身となった。結婚式も熊本で、ごく内輪で行われた。
漱石は新婚早々、妻にこんな宣告をしたという。
「俺は学者で勉強しなければならないのだから、おまえなんかにかまってはいられない。それは承知しておいてもらいたい」
随分な言いぐさだが、これはどうも宣告倒れで、鏡子がオトボケな失敗をすると、漱石はよく「おまえはオタンチンのパレオロガスだ」などと言って笑っていたという。鏡子は何やら難しい横文字と思っていたが、実際のところは、「間抜け」や「のろま」を揶揄する江戸の俗語「オタンチン」に、東ローマ帝国最後の皇帝コンスタンチン・パレオロガスの名前をひっかけて、漱石が洒落でつくり出した言葉だった。また、ひどい悪阻で鏡子の体調がすぐれないときには、漱石は傍らに付き添って見守り、「病妻の閨(ねや)に灯ともし暮るゝ秋」の一句を詠んだりもしている。
漱石一家の熊本での暮らしは5年に及び、この間、5度引っ越しをし6軒の家に住んだ。五高の学生の寺田寅彦(のちの物理学者)が「ぜひ書生に置いてほしい」と漱石夫妻に申し出てきたのは、第5番目となる内坪井町の家に暮らしているときだった。部屋数も少ないし別棟の物置なら、と案内すると、さすがに話は立ち消えになったという。ちなみに、数年前まで小泉八雲一家が暮らしていた坪井西堀端町の旧居はこのすぐ近所だった。
朝寝坊だが裁縫上手だった漱石の妻、鏡子

漱石は五高在任中に洋行することになるが、5年間の熊本暮らしの中で、新妻の鏡子は早くも朝寝坊ぶりを露呈していた。ときどき、朝食も食べさせず夫を学校へ送り出すこともあったという。のちに「悪妻」のイメージを着せられる所以でもあろうか。
漱石留学中の留守宅でも鏡子の朝寝坊は相変わらずで、漱石はロンドンからの手紙(明治35年5月14日付)で、
朝は九時十時迄も寝るよし。(略)朝は少々早く起きる様に注意あり度(た)し
と注意することになる。朝6時に起床し「昔の武家時代の四角ばった挨拶で」八雲を起こすセツとは、かけ離れている。
漱石は、続けて手紙にこう書いている。
相応の家に生れて相応の教育あるものは、斯様(かよう)のふしだらなものは沢山見当らぬ様に考へらる まづ矢来町三番を門並しらべて見よ 左様の妻君其許(そこもと)を除くの外例あるまじ、此事は洋行前にも常に申したる様に思へど其許は左程感ぜぬ様なりし 夏目の奥さんは朝九時十時迄寝るとあつては少々外聞わるき心地せらる(略)身体に異常なき限はつとめて早く起きる様心掛らるべし かつ小児の教育上にもよろしからざる結果ありと思ふ 筆などが成人して嫁に行つて矢張九時十時迄寝るとあつては 余は未来の婿に対して甚だ申訳なき心地せらる
手紙文中の「筆」は、熊本で、漱石と鏡子の間に生まれた長女(筆子と記されることも多い)のこと。漱石は娘の将来のことまで案じてしまっているのである。
鏡子は何事にも大雑把で、料理も苦手だった。娘の筆子は後年、雑誌のインタビューに答え、
私の母という人は、大体が細かい神経を持たない人なのですが、食物に至っては特にその傾向が強く、熱かろうが冷たかろうが、美味(おい)しかろうが不味(まず)かろうが、口に入れば結構というのですから、味付の雑な事と申しましたら、てんでお話になりません。(『文藝春秋』昭和41年3月号)
と語っている。
住み込みで家事や身の回りの世話をするために八雲のもとへ赴いたセツとは、出発点からして違うのだ。そもそもお嬢様育ちの上、見知らぬ土地に来て、買いものするにも家事をするにも、戸惑うことばかりなのである。
ただ、鏡子は裁縫は得意だった。こののち、7人の子どもを育てながら、自分たち夫婦や子どもたちの着るものを縫ったり繕ったり、洗い張りしたりと、いつも針仕事に精を出していたという。
鏡子の朝寝坊に関しては、鏡子本人が回想録『漱石の思い出』の中に、夫婦間で何度となく交わしたこんな会話を紹介している。
「おまえの朝寝坊ときたら、まことに不経済で、第一みっともないことこの上なしだ」
「しかし一、二時間余計にねかせてくださればそれで一日いい気持ちで何かやります。だから無理をして早く起きていやな気持ちでいるより、よっぽど経済的じゃありませんか」
夫が注意しても妻はうつむくどころか、真っ向から反論するのである。挙げ句、あっけらかんとした調子でこう記す。
こうしたお小言も毎々のことではありましたが、とうとう死ぬまでこのお寝坊ばかりはなおりませんでした。
ここまでくると、「ソクラテスの妻」と並べたがる後年の世評などどこへやら、いっそどこか清々しく、開放感のようなものまで感じさせる鏡子の“悪妻”ぶりなのである。作家の大庭みな子は、親交のあった漱石の孫・松岡陽子マックレインに対し、「現代的な女性として鏡子夫人を尊敬している」と語ったことがあったという。
根底には、時にすったもんだしながらも、危機を乗り越えて生涯添い遂げ、7人の子をなしていく漱石夫妻の機微がある。漱石は普段はおっとりして穏やかでやさしいが、神経衰弱が高じると、八雲と同じように猜疑心や強迫観念にとらわれ、抑えようもなく苛立つことがあったと言われる。そんな漱石の妻は、鏡子だからこそつとまったとの見方もある。結婚まる10年を経た明治39年(1906)11月7日付で、漱石が門弟の森田草平宛てに書いた次のような手紙からも、夫婦の機微の一端が読み取れる。
子を生ませたつていゝさ。僕なんか何人も製造して嫁にやるのに窮してゐる。然も細君にさう惚れてる訳でもないんだから出来て見ると少々汗顔の至りだ。大方向(むこう)でもさうだろう。
悩みを訴える門下生への返書の中にせよ、照れ屋の漱石が「細君にさう惚れてる訳でもない」と言い訳めいた台詞を綴るのは、すなわち「それほど大層なものじゃないが、それなりに女房に惚れている」ことの表明に他ならないのである。
* * *

矢島裕紀彦(やじま・ゆきひこ)
1957年、東京都生まれ。早稲田大学政経学部卒。作家・雑誌編集記者。文学、スポーツ、歴史など幅広いジャンルをフィールドに“人間”を描く。著書に『心を癒す漱石の手紙』『文士の逸品』『文士が愛した町を歩く』『鉄棒する漱石、ハイジャンプの安吾』『ウイスキー粋人列伝』『著名人名づけ事典』『こぼれ落ちた一球』『石橋を叩いて豹変せよ』『あの人はどこで死んだか』など多数。グランドセイコー広告の掌編小説シリーズ『時のモノ語り』で2018年度朝日広告賞朝日新聞特別賞受賞。https://atelier1328.com
(この連載を通しての主な参考文献)
『漱石全集』全28巻、別巻1(岩波書店、1993~1999年)/夏目鏡子述・松岡譲筆録『漱石の思い出』(文春文庫、1994年)/夏目伸六『父・夏目漱石』(文春文庫、1991年)/夏目伸六『父・漱石とその周辺』(芳賀書店、1967年)/高浜虚子『回想子規・漱石』(岩波文庫、2002年)/松岡陽子マックレイン『漱石夫妻 愛のかたち』(朝日新書、2007年)/荒正人『増補改訂漱石研究年表』(集英社、1984年)/江藤淳『漱石とその時代』第1部~5部(新潮新書、1970~1999年)/『新潮日本文学アルバム夏目漱石』(新潮社、1983年)/『別冊國文学 夏目漱石事典』(学燈社、1990年)/『夏目漱石の美術世界』(東京新聞、NHKプロモーション、2013年)/出久根達郎『漱石先生とスポーツ』(朝日新聞社、2000年)/江戸東京博物館・東北大学編『文豪・夏目漱石』(朝日新聞社、2007年)/平岡敏夫『「坊つちやん」の世界』(塙新書、1992年)/恒松郁生『漱石 個人主義へ』(雄山閣、2015年)/小泉節子、小泉一雄『小泉八雲 思い出の記 父「八雲」を憶う』(恒文社、1976年)/小泉八雲、平井呈一訳『日本瞥見記』上・下(恒文社、1975年)/小泉八雲、平井呈一訳『東の国から・心』(恒文社、1975年)/小泉八雲、平川祐弘編『怪談・奇談』(講談社学術文庫、1990年)/小泉八雲、池田雅之編訳『虫の音楽家』(ちくま文庫、2005年)/『明治文学全集48 小泉八雲集』(筑摩書房、1970年)/小泉時共編『文学アルバム小泉八雲』(恒文社、2000年)/小泉凡監修『小泉八雲、開かれた精神の航跡。』(小泉八雲記念館、2016年)/池田雅之監修『別冊太陽 小泉八雲』(平凡社、2022年)/池田雅之『小泉八雲』(角川ソフィア文庫、2021年)/田部隆次『小泉八雲』(北星社、1980年)/長谷川洋二『八雲の妻』(今井書店、2014年)/関田かをる『小泉八雲と早稲田大学』(恒文社、1999年)/梶谷泰之『へるん先生生活記』(恒文社、1998年)/池野誠『松江の小泉八雲』(山陰中央新報社、1980年)/工藤美代子『神々の国』(集英社、2003年)/工藤美代子『夢の途上』(集英社、1997年)/工藤美代子『聖霊の島』(集英社、1999年)/平川祐弘編『小泉八雲回想と研究』(講談社、1992年)/平川祐弘『世界の中のラフカディオ・ハーン』(河出書房新社、1994年)/熊本大学小泉八雲研究会『ラフカディオ・ハーン再考』(恒文社、1993年)/西川盛雄『ラフカディオ・ハーン』(九州大学出版会、2005年)/西成彦『ラフカディオ・ハーンの耳、語る女たち』(洛北出版、2024年)/池田雅之『日本の面影』(NHK出版、2016年)/ラフカディオ・ハーン『小泉八雲東大講義録』(KADOKAWA、2019年)/芦原伸『へるん先生の汽車旅行』(集英社インターナショナル、2014年)/嵐山光三郎『文人暴食』(新潮文庫、2006年)/河東碧梧桐『子規を語る』(岩波文庫、2002年)/『正岡子規の世界』(松山市立子規記念博物館、1994年)/『子規全集』18巻、19巻(講談社、1979年)/『志賀直哉全集』第8巻(岩波書店、1999年)/『芥川龍之介全集』第4巻(岩波書店、1996年)/瀬沼茂樹『評伝島崎藤村』(筑摩書房、1981年)/矢島裕紀彦『心を癒す漱石の手紙』(小学館文庫、2009年)/矢島裕紀彦『鉄棒する漱石、ハイジャンプの安吾』(NHK生活人新書、2003年)/矢島裕紀彦『文士が愛した町を歩く』(NHK生活人新書、2005年)/矢島裕紀彦『文士の逸品』(文春ネスコ、2001年)






























