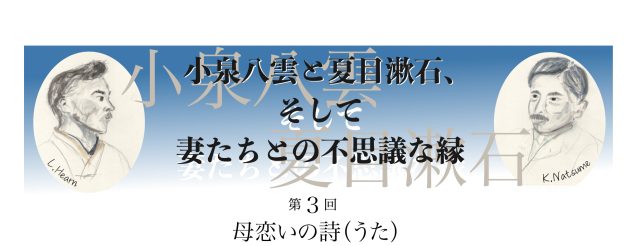
小泉セツ&小泉八雲の夫婦がモデルとなった朝の連続テレビ小説『ばけばけ』が注目されています。実はその小泉夫妻と、明治の文豪・夏目漱石と妻・鏡子は、不思議と重なり合う縁で結ばれていた、というのをご存じでしょうか。
夏目漱石の研究家として知られ、『心を癒す漱石の手紙』などの著書を持つ、作家で雑誌編集記者の矢島裕紀彦さんによると、二人の文豪とその妻たちには奇縁と呼ぶしかないような不思議なつながりがあると言います。
多数の文献や手記を紐解きながら、二組の夫婦の知られざる素顔を全26回の連載にて紹介します。
第3回では、小泉八雲と夏目漱石のそれぞれの幼少期から見えてくる母への心情を読み解きます。
文・矢島裕紀彦
幼くして父母と離れた小泉八雲の生い立ち
小泉八雲ことラフカディオ・ハーンは、1850年6月27日、ギリシアのイオニア諸島のひとつ、レフカダ島で生まれた。日本の年号でいえば嘉永3年。ペリーの黒船来航の3年前に当たる。ちなみに、「レフカダ」の島名は、ギリシア語で「彷徨う」の意味を語源に持つという。その後、世界各地を経巡って極東の国・日本にたどりつく八雲の生涯を思い合わせるとき、何か象徴的なものを感じないでもない。
父親はアイルランド人で英国陸軍軍医のチャールズ・ブッシュ・ハーン。母親はギリシア人でキシラ島の旧家の娘ローザ・アントニウ・カシマチ。父チャールズがこの島に駐屯中に母ローザと結ばれ、八雲が誕生したのだった。
父のチャールズはまもなく単身、西インド諸島へ赴任。母子は、八雲2歳の折、父の実家があるアイルランドのダブリンに移り住み、父方の大叔母サラ・ブレナンの世話を受けるようになる。
翌年、父チャールズもダブリンに帰還するが、もともとが誰にも祝福されない結婚で、父の母に対する愛情は早くも冷めていた。父チャールズがクリミア戦争に出征すると、見知らぬ土地で気候や言葉、宗教などの違いにも馴染めず暗鬱たる日々を送っていた母のローザは、4歳の八雲を大叔母のもとに残しキシラ島へ帰る。以降、八雲は二度と母の顔を見ることは叶わなかった。
さらに3年後には父チャールズと母ローザの離婚が正式に成立。父は再婚してインドへ赴任する。その後、八雲は厳格なキリスト教徒である大叔母のもとで養育される。

ちなみに、日本、とくに松江や熊本の学校関係者の間では、八雲のことを「ハーン」でなく「ヘルン」の呼称で親しむ人が多かった。八雲の東京帝国大学(現・東大)時代の教え子の田部隆次も、その著『小泉八雲』の標題にわざわざ「ラフカディオ・ヘルン」というルビを付し、序文冒頭にこう記している。
ラフカディオ・ヘルンという読み方はもと文部省か島根県の役人の始めたものであろうが、先生はこれを採用して(略)夫人もいつもヘルンと呼んでいた。夫人の話によれば、ハーンと書くあの中の線が嫌いであったということである。松江時代、熊本時代の教え子たちはヘルン先生のことをハーンと呼ばれては別人のようで感じが出ないという程だから、私もそれに従ってヘルンと呼ぶことにしている。
呼称の由来を調査した松江時代の八雲の教え子の太田台之丞によれば、ことの経緯は以下のようなことだったらしい。当時の島根県知事・籠手田(こてだ)安定が文部省へ行き、松江で適当な英語教師を採用したいが誰かいないかと尋ねた。すると、文部省ではハーン(八雲)を推薦した。知事に随行していた毛利八弥という事務官が、「辞令を出さねばならないがどういう名前でしょうか」と確認すると、何をどう間違えたのか、「ラフカヂオ・ヘルンという名だ」と伝えられた。そこで「ヘルン」と書いた辞令(条約書)を作成した。その辞令を本人に渡すと、八雲は「自分はヘルンではないが、しかしそれでも分かるからどちらでもよろしい」と言って、そのまま定着した――。
八雲(ハーン)は松江の人々によって「ヘルン」と呼ばれることがむしろ楽しかったらしく、松江中学教頭の西田千太郎の日記(明治23年12月4日)によると、松江着任の3か月後、市内の判子屋に行って「遍留ん(へるん)」の印をつくっている。
八雲に似た漱石の幼少期の悲しい体験
夏目漱石も、八雲同様、幼時に悲しい体験があった。
漱石は八雲に遅れること17年、明治維新の前年の慶応3年1月5日(1867年2月9日)に、江戸牛込馬場下横町(現・東京都新宿区喜久井町)に生まれている。生家は近隣を支配する町方名主だったが、明治維新後、次第に衰微した。夏目家の紋が「井桁に菊」(正式には「平井筒に菊」)だったことから喜久井町という名称が生まれ、地下鉄早稲田駅西口を出た先にいまも「夏目坂」という坂の名が残るのも、かつての町方名主の権勢の名残りである。
父は夏目小兵衛直克、母は千枝。5男4女の末子で、金之助と名づけられた。生まれたのが庚申(かのえさる)の申の刻で、「庚申の日に生まれた者は出世すれば大いに出世するが、ひとつ間違うと大泥棒になる、それを免れるには、名前に金の字か金偏の字を入れるとよい」との言い伝えを踏まえた命名だったという。子どもの頃は「金ちゃん」と呼ばれたらしい。
子だくさんの上、両親が高齢だったため、金ちゃんの漱石は生後まもなく古道具屋へ里子に出された。毎晩、道具屋のガラクタと一緒に四谷の夜店に曝されていたのを、ある晩、漱石の姉が通りかかって見つけ、可哀相に思い、懐へ入れて連れ帰った。
が、ほどなくして、今度は内藤新宿の塩原昌之助・やす夫妻のもとに養子に出された。養父母の不仲や離婚騒動などがあって、夏目家に戻されたのが8歳の頃。幼い心は、品物のようにやりとりされることに傷つかずにはおれなかっただろう。実家に戻った漱石は、実の父母を祖父母だと思い込み、その後しばらく父母のことを「おじいさん」「おばあさん」と呼んでいたという。
ある日、お手伝いのひとりが、漱石にそっと教えた。
「あなたが御爺さん御婆さんと思っていらっしゃる方は、本当はあなたのオトッさんとオッカさんなのですよ。さっきね、大方そのせいであんなにこっちの宅(うち)が好きなんだろう、妙なものだな、と言って二人で話していらしったのを私が聞いたから、そっとあなたに教えてあげるんですよ。誰にも話しちゃいけませんよ。よござんすか」
幼い漱石は、伝えられた事実より、お手伝いの親切がとても嬉しかったという。
父親は漱石に冷淡で、子どもである漱石の側にも同様の感慨しか残さなかったが、母親の存在は違った。晩年の随筆『硝子戸の中』で、漱石は
宅中(うちじゅう)で一番私を可愛がつて呉れたものは母だといふ強い親しみの心が、母に対する私の記憶の中には、何時でも籠つてゐる。
母はたしかに品位のある床しい婦人に違(ちがひ)なかつた。
と懐旧し、さらに次のように綴っている。
母の名は千枝といつた。私は今でも此(この)千枝といふ言葉を懐かしいものの一つに数えてゐる。だから私はそれがただ母の名前で、決して外の女の名前であつてはならない様な気がする。幸ひに私はまだ母以外の千枝といふ女に出会つた事がない。
これは、控え目ながら、間違いなく、母恋いの詩(うた)であろう。

八雲も、幼くして別れた母への思慕と同情を、終生消えることなく持ち続けた。後年、八雲が紡ぎ出した再話文学『泉の乙女』や『雪女』における女(精霊)たちの姿にも、黒髪の母ローザの面影がちらついている。八雲は「西」という方角が好きで、書斎も西向きを好んでいたが、ここにも心の奥底の、我知らぬ望郷と、その先につながる母への思慕が隠されていたように思えなくもない。
『夏の日の夢』(来日第2作『東の国から』所収)に綴られる次のような一文も、八雲が生母ローザと過ごしたはるかな追憶の幻影であろう。
わたくしに、ある場所と、あるふしぎな時の記憶がある。(略)いまでもよく憶えているが、そのころは、いちにちの長さすらが、いまよりずっと長くて、まいにちまいにちが、わたくしにとって新しい驚異であり、よろこびなのだった。(略)わたくしはどうかすると、(略)神さまのようなその人のことを、よく手こずらせたものであった。(略)日が暮れて、月がまだ空へのぼらないまえ、月しろの静けさがあたりにしっとりと降りると、やさしいその人は、わたくしを指の先から足の先まで嬉しさでぞくぞく疼かせるような、いろんな話をして聞かせてくれたものだ。あれからこっち、わたくしはあのころの半分も美しい話をすら聞いたことがない。わたくしの嬉しがりようがはなはだしくなると、やさしいその人はきまって、なにかこの世のものとは思われないような、ふしぎな歌をうたってくれたものだ。
この幻影にはやがて、セツという存在が重なっていくことになる。
* * *

矢島裕紀彦(やじま・ゆきひこ)
1957年、東京都生まれ。早稲田大学政経学部卒。作家・雑誌編集記者。文学、スポーツ、歴史など幅広いジャンルをフィールドに“人間”を描く。著書に『心を癒す漱石の手紙』『文士の逸品』『文士が愛した町を歩く』『鉄棒する漱石、ハイジャンプの安吾』『ウイスキー粋人列伝』『著名人名づけ事典』『こぼれ落ちた一球』『石橋を叩いて豹変せよ』『あの人はどこで死んだか』など多数。グランドセイコー広告の掌編小説シリーズ『時のモノ語り』で2018年度朝日広告賞朝日新聞特別賞受賞。https://atelier1328.com
(この連載を通しての主な参考文献)
『漱石全集』全28巻、別巻1(岩波書店、1993~1999年)/夏目鏡子述・松岡譲筆録『漱石の思い出』(文春文庫、1994年)/夏目伸六『父・夏目漱石』(文春文庫、1991年)/夏目伸六『父・漱石とその周辺』(芳賀書店、1967年)/高浜虚子『回想子規・漱石』(岩波文庫、2002年)/松岡陽子マックレイン『漱石夫妻 愛のかたち』(朝日新書、2007年)/荒正人『増補改訂漱石研究年表』(集英社、1984年)/江藤淳『漱石とその時代』第1部~5部(新潮新書、1970~1999年)/『新潮日本文学アルバム夏目漱石』(新潮社、1983年)/『別冊國文学 夏目漱石事典』(学燈社、1990年)/『夏目漱石の美術世界』(東京新聞、NHKプロモーション、2013年)/出久根達郎『漱石先生とスポーツ』(朝日新聞社、2000年)/江戸東京博物館・東北大学編『文豪・夏目漱石』(朝日新聞社、2007年)/平岡敏夫『「坊つちやん」の世界』(塙新書、1992年)/恒松郁生『漱石 個人主義へ』(雄山閣、2015年)/小泉節子、小泉一雄『小泉八雲 思い出の記 父「八雲」を憶う』(恒文社、1976年)/小泉八雲、平井呈一訳『日本瞥見記』上・下(恒文社、1975年)/小泉八雲、平井呈一訳『東の国から・心』(恒文社、1975年)/小泉八雲、平川祐弘編『怪談・奇談』(講談社学術文庫、1990年)/小泉八雲、池田雅之編訳『虫の音楽家』(ちくま文庫、2005年)/『明治文学全集48 小泉八雲集』(筑摩書房、1970年)/小泉時共編『文学アルバム小泉八雲』(恒文社、2000年)/小泉凡監修『小泉八雲、開かれた精神の航跡。』(小泉八雲記念館、2016年)/池田雅之監修『別冊太陽 小泉八雲』(平凡社、2022年)/池田雅之『小泉八雲』(角川ソフィア文庫、2021年)/田部隆次『小泉八雲』(北星社、1980年)/長谷川洋二『八雲の妻』(今井書店、2014年)/関田かをる『小泉八雲と早稲田大学』(恒文社、1999年)/梶谷泰之『へるん先生生活記』(恒文社、1998年)/池野誠『松江の小泉八雲』(山陰中央新報社、1980年)/工藤美代子『神々の国』(集英社、2003年)/工藤美代子『夢の途上』(集英社、1997年)/工藤美代子『聖霊の島』(集英社、1999年)/平川祐弘編『小泉八雲回想と研究』(講談社、1992年)/平川祐弘『世界の中のラフカディオ・ハーン』(河出書房新社、1994年)/熊本大学小泉八雲研究会『ラフカディオ・ハーン再考』(恒文社、1993年)/西川盛雄『ラフカディオ・ハーン』(九州大学出版会、2005年)/西成彦『ラフカディオ・ハーンの耳、語る女たち』(洛北出版、2024年)/池田雅之『日本の面影』(NHK出版、2016年)/ラフカディオ・ハーン『小泉八雲東大講義録』(KADOKAWA、2019年)/芦原伸『へるん先生の汽車旅行』(集英社インターナショナル、2014年)/嵐山光三郎『文人暴食』(新潮文庫、2006年)/河東碧梧桐『子規を語る』(岩波文庫、2002年)/『正岡子規の世界』(松山市立子規記念博物館、1994年)/『子規全集』18巻、19巻(講談社、1979年)/『志賀直哉全集』第8巻(岩波書店、1999年)/『芥川龍之介全集』第4巻(岩波書店、1996年)/瀬沼茂樹『評伝島崎藤村』(筑摩書房、1981年)/矢島裕紀彦『心を癒す漱石の手紙』(小学館文庫、2009年)/矢島裕紀彦『鉄棒する漱石、ハイジャンプの安吾』(NHK生活人新書、2003年)/矢島裕紀彦『文士が愛した町を歩く』(NHK生活人新書、2005年)/矢島裕紀彦『文士の逸品』(文春ネスコ、2001年)






























