
文/印南敦史
読み手の関心を無理なく惹きつける、なんとも魅力的な文章を書く人だなと感じた。しかし、それもそのはず。『定年からの台所入門』(実業之日本社)の著者・北 連一氏は、幅広い分野において活躍してきた元編集者だというのだ。
定年退職後、奥様に代わって台所に入るようになり、三度三度の食事をつくるようになったのだという著者。意識の根底に根差すのは、「まったくの素人ではない」という自負だ。少年時代にはかまどでごはんを炊いたことがあり、学生時代には自炊の経験もあったためである。
とはいえ、だからといって意気揚々と料理をはじめたというわけではないようだ。著者は定年退職の日が近づくにつれ、自由な時間に思いを馳せ、その日を待ち望んでいたという。だがそれでも、多くの定年退職者も直面する壁に直面してしまうのだ。
定年後、料理は夫が担当、妻は片付け担当に
何もすることがないのである。いや、何もする気にならないのである。私は、定年後は自ら求めて仕事はしない、と決めていた。少なくとも、再び組織の中に入って働くことだけはやるまい、と考えていた。定年後せっかく自由の身になれるのに、なんで自ら求めて不自由な世界に再び身を投じることなどするものか。私は、定年前そう考えていた。もちろん、定年後もこの考えは変わらなかった。しかし、何もする気にならないのには参った。(本書「はじめに」より引用)
ゆっくり読書をしようと思っていたものの、気が入らず、夜が明けてから日が暮れるまでの一日が長い。1日三食を夫婦で食べるようになると、やがて「妻の料理の腕などたかがしれている」と不満を抱くようになる。
その結果、「そんなに文句ばっかりいうなら、自分の好きなようにやったら」「ああ、オレがつくるほうがよっぽどマシだ」……ということになり、著者が料理担当、奥様が後かたづけ、という役割分担が成立したというのである。
買い出しや献立を考えるという作業も含めて考えれば、毎日三食の食事の支度はなかなか大変だ。ましてや、現役時代の三分の一の収入(年金)の範囲内で食費を賄わなければならないという問題もある。決して楽なことばかりではないわけだが、著者はそのかいあって2年目くらいから「主夫感覚」を身につけることができたのだという。
本書では、そんな経緯ではじまった「主夫稼業」で身につけた食材調達の知恵と料理の数々が披露される。だから、内容の大半はレシピである。が、それはよくある料理本のように複雑なものではなく、体裁はエッセイ風。しかも、いたってシンプルだ。たとえばこんな具合。
男子厨房に入るべし
タイめし
長女が友人の結婚式に出席して、いまどきの結婚式にしてはめずらしく、引き出物にタイの塩焼きを持って帰ってきたことがある。時間が経っているので、タイの塩焼きはかちんかちんに固くなっている。そのまま食べてもおいしくない。そこでつくって見たのがタイめし。研いで30分ほど水に浸したコメと昆布を土鍋に入れて、ふつうに炊き上げ、ごはんがふつふつとたぎってきたところに、あらかじめ、しょうゆと酒で煮て味をつけておいた油揚げの細切りを煮汁ごと入れ、タイの塩焼きも入れて、15分ほど蒸らし、タイを取り出して、身だけをほぐしてごはんに戻して混ぜ込んだ。なかなか好評だった。(本書より)
私も含め、「料理はしてみたいけれど、勝手がわからないし、難しそう」だという思いを抱いている男性諸氏は少なくないだろう。しかし著者のレシピ(というより「つくりかた」と表現したい)に目を通していると、試してみれば自分にもできそうな気がしてくる。
それに「朝ごはんを極める」「旬を味わう」「酒の肴をたのしむ」「鍋とどんぶりは男の料理」「晩ごはんの副菜をつくる」「晩ごはんの主菜をつくる」と目的ごとに分けられているため、読んでいるといつのまにか、「やってみるか!」という気持ちになってくる。和食が中心で、当然のことながら季節感がしっかり考慮されているところもいい。
そしてもうひとつ。各章の冒頭に、そのテーマに則したエッセイがはいっているのだが、その文章がとても味わい深い。「食べる」という行為を通じ、著者の暖かさが伝わってくるような気がするのだ。
男子こそ厨房に入るべし、という勇気をもらえる一冊だ。
【今回の定年本】
『定年からの台所入門』
(北 連一著、実業之日本社)
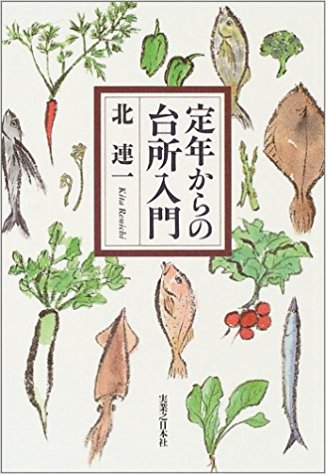
文/印南敦史
作家、書評家、編集者。株式会社アンビエンス代表取締役。1962年東京生まれ。音楽雑誌の編集長を経て独立。複数のウェブ媒体で書評欄を担当。雑誌「ダ・ヴィンチ」の連載「七人のブックウォッチャー」にも参加。著書に『遅読家のための読書術』(ダイヤモンド社)『プロ書評家が教える 伝わる文章を書く技術』(KADOKAWA)『世界一やさしい読書習慣定着メソッド』(大和書房)などがある。




































