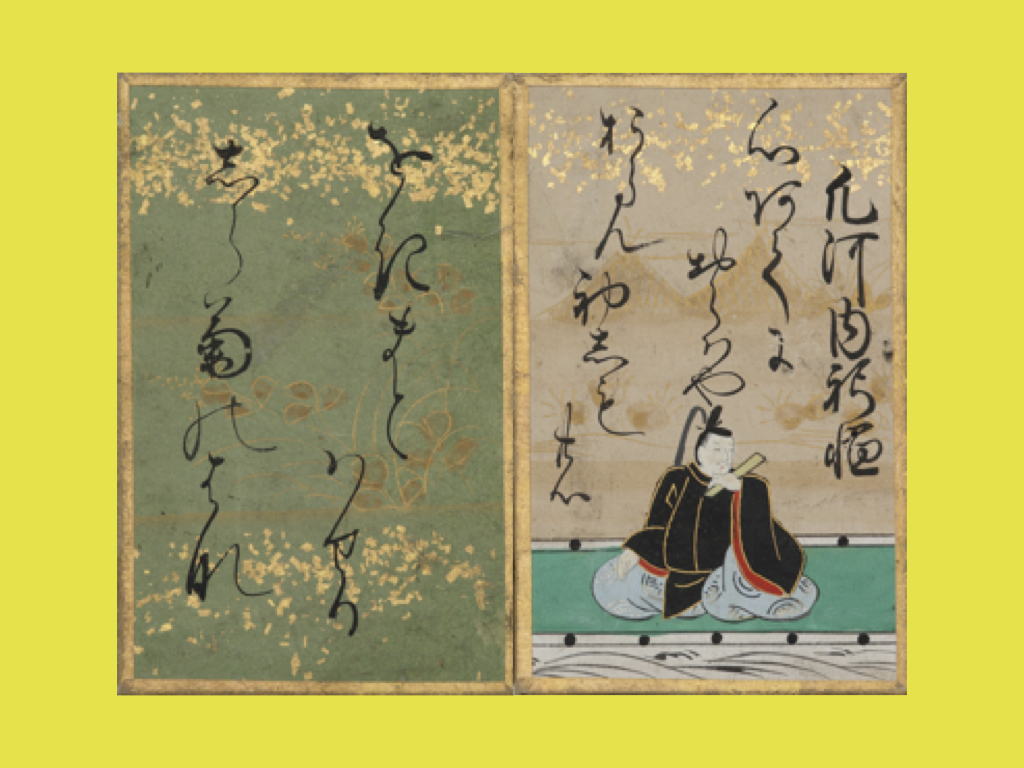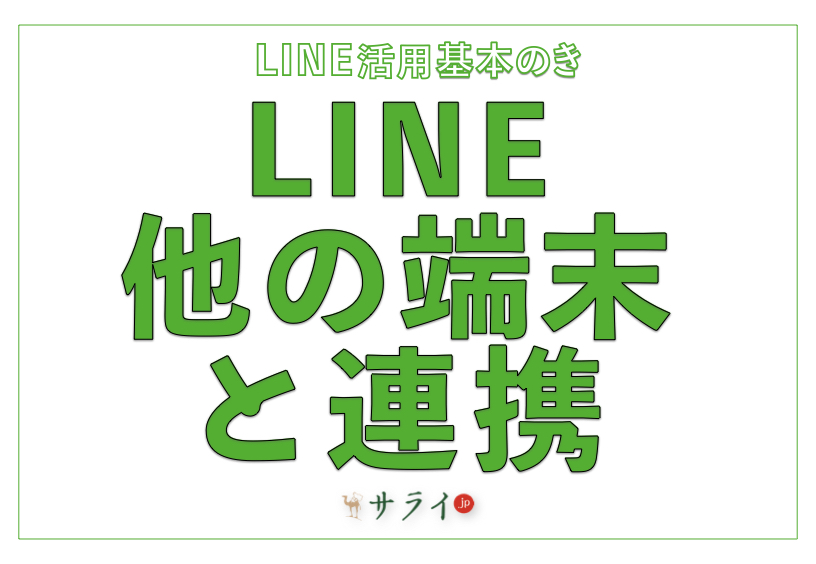「町中華」はすでに日本の郷土料理のひとつといえる。その土地、土地の名産食材や気候風土、独特の食文化によって育まれ、地元民に愛される「町中華」の魅力とは何か。日本各地で進化を続ける名店にて、その真髄を探る。
ソースで味変したっていいんです。伊那名物の“ローメン”

長野県の南信、伊那市とその周辺の限られたエリアで食べられているご当地食が「ローメン」だ。ローメンとは何か? その発祥の店である『萬里』を訪れた。同店2代目の馬場元(はじめ)さんはこう語る。
「ローメンは先代の伊藤和弌(わいち)が発案した麺料理で、蒸した中華麺をキャベツと羊肉と合わせスープで煮込んで作ります。初めて出したのが昭和30年(1955)で『炒肉麺』(チャーローメン)と名付けました。次第に『炒』が取れ『肉麺』と呼ばれるようになりました」

中華麺を蒸したのは冷蔵庫が普及していなかった当時、保存のための策だった。羊毛業が盛んだった伊那では羊肉が入手しやすく、地場産のキャベツと合わせて煮込んでみると、蒸し麺がスープとからみこれまでにない味を醸した。
「あるときお客さんが卓上の調味料をかけてみたら、味が変化しておいしくなった。以来、お客さんがソースや酢、ゴマ油などをかけ、自分好みの味付けにして食べるようになりました」(馬場さん)

鶏ガラ、香味野菜、豚の頭で取った『萬里』のスープは、旨味に溢れるが薄味に仕立ててある。地元の人は躊躇なく卓上のソースや酢などに手を伸ばし、素早く味付けをして食べ始める。テーブルに運ばれてから客の手により味が完成する、“味変”前提の料理だ。
「麺はのびにくく、時間がたつと味が染みておいしくなります」


中国風菜館 萬里

長野県伊那市坂下3308
電話:0265・72・3347
営業時間:11時~14時、17時~20時
定休日:月曜
交通:JR飯田線伊那市駅より徒歩約5分
※この記事は『サライ』本誌2025年3月号より転載しました。