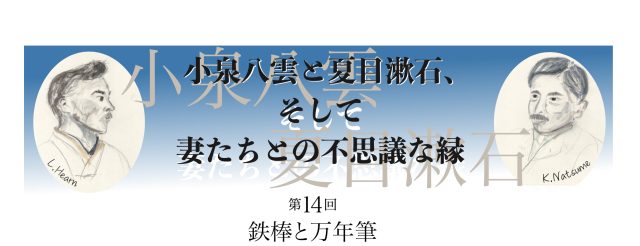
小泉セツ&小泉八雲の夫婦がモデルとなった朝の連続テレビ小説『ばけばけ』が注目されています。実はその小泉夫妻と、明治の文豪・夏目漱石と妻・鏡子は、不思議と重なり合う縁で結ばれていた、というのをご存じでしょうか。
夏目漱石の研究家として知られ、『心を癒す漱石の手紙』などの著書を持つ、作家で雑誌編集記者の矢島裕紀彦さんによると、二人の文豪とその妻たちには奇縁と呼ぶしかないような不思議なつながりがあると言います。
多数の文献や手記を紐解きながら、二組の夫婦の知られざる素顔を全26回の連載にて紹介します。
第14回では、共通して器械体操が得意という、文系らしからぬ姿をご紹介。さらに、鉄棒の最中に万年筆を壊した漱石のエピソードから、ふたりのそれぞれの愛用のペンについても考察します。
文・矢島裕紀彦
軍御用達の器械体操の用具を自宅に揃えた八雲

小泉八雲は、夏の水泳のみならず、好んで長い散歩をするなど、日常的に体を動かすことを心掛けていた。
八雲一家の東京の住まいは、はじめ市谷富久町の借家だった。その裏庭には、わざわざ鉄棒などの器械体操の用具が設えられた。「陸軍士官学校御用」の大看板を掲げた四谷の運動具屋から購入し、整備したものだった。6年後、一家は市外西大久保に建てた新居に移り住むが、体操用の用具も旧居から移設されている。
上京時の八雲は齢46。目が悪いこともあって、危険の伴うあまり激しい運動は控えていたが、子どもらや書生とともに日課のように器械体操をしたという。
そんなとき、八雲が長男の一雄に必ずやらせたのが鉄棒の「谷渡り」。鉄棒にぶら下がったまま、右端から左端、左端から右端へ、腕の力だけで移動するトレーニングだった。いろいろな鉄棒の技の練習も実施された。八雲の指示に従って、まず書生の新美資良が見本を示し、そのあと一雄が実践を試みる。新美は痩身長駆で器械体操の達人だった。
鉄棒を中心点に体を風車の如く廻したり、竿の如くに水平に揺ったり、海老の如く跳ね上ったり如何にも身軽に美しい線を描いて動いた。
という(小泉一雄『父「八雲」を憶う』)。
八雲自身も鉄棒に手をかけた。軽業めいたことはやらなかったが、鉄棒へいつまでもぶら下がっていて平然としていた。一雄によれば、八雲は身長5尺2寸(約158センチ)と小柄ながら、尻は大きく太鼓腹で体重は18貫(約68キロ)前後あった(身長は5尺3寸=約161センチとする証言もある)。夏目漱石の一高在学中の身体検査の自筆メモを見ると、身長は1・587メートル、体重は13・950貫(約52・31キロ)とある。背丈は両者同じくらいだが、体重は八雲が16キロほど重い。その肥満気味の体重を支え、八雲は鉄棒にぶら下がって悠々と葉巻をふかし、苦もなく一本吸い終えたという。
泳ぎが得意で、海の上にふうわりと浮いていたという八雲の姿と、重なり合うものがある。
漱石の同級生でスポーツ好きといったら、忘れてならないのは正岡子規だろう。子規は学生時代、ベースボール愛好家としてその名を轟かせていた。本名・常規、通称は升(のぼる)。郷里の松山では「のぼさん」と呼ばれていた。
漱石と同じ慶応3年(1867)の生まれ。松山中学(松山東高の前身)を中退して15歳で上京し、アメリカから渡来して日の浅いベースボールというスポーツに出会った。翌年、大学予備門(のちの一高)に入学すると、早速、同校のベースボール会に入会。強打の名捕手としてプレーを愉しむ傍ら、「打球」「走者」「死球」「直球」「飛球」など、いまも使われる多くの訳語を考案した。
競技名としての「野球」という言葉はまだこの頃広く浸透していないが、子規は自身の通称の升にひっかけて「野球(の・ボール)」という雅号まで使っていた。「元祖野球少年」と言っていい存在で、ユニフォーム姿でバットを持った雄姿が、写真として残されている。
上京後、松山に里帰りしたときには、高浜虚子や河東碧梧桐ら、故郷の友人や後輩たちにこのスポーツの魅力を伝達してもいる。虚子と碧梧桐は、俳人としての子規より先に野球人としての子規に接していたことになる。とくに碧梧桐は、技術論やルールから実技指導まで、事細かに教えを受けた。回想録『子規を語る』にも、
まだ第一高等学校の生徒位にしか知られていなかったベースボールを、私が習った先生というのが子規であった。
と綴っている。
ベースボールの楽しさを、子規は歌にも詠んでいる。
「若人のすなる遊びはさはにあれどベースボールに如くものはあらじ」
「打ち揚ぐるボールは高く空に入りてもまたも落ちくる人の手の中に」
「今やかの三つのベースに人満ちてそぞろに胸の打ち騒ぐかな」
しかしながら、漱石には、子規とともにベースボールを楽しんだ記録は見当たらない。
実は、漱石には子規と親しく交流する以前、人数合わせで動員された「ノックあそび」で、飛んできたボールを受け損ね「急所」に当ててしまうという、男子ならではの痛くて苦い思い出があった。翌日から漱石は学校を休み、一緒に遊んでいた太田達人は、あのアクシデントが尾を引いているのかと心配した。実際のところは盲腸炎に罹患しての欠席だったが、どうも、このとき以来、漱石は二度とベースボールをやらなかったらしい。
子規とは、ともに寄席通いが好きだったことがきっかけで親しくなり、互いの文学的才能と人間性に惹かれ無二の友となった。
万年筆が折れるほどの鉄棒の技を持っていた漱石

漱石がもっとも得意としていたスポーツは、実は、小泉八雲父子も自宅の裏庭でしていた器械体操であった。漱石の学生時代からの友人で、のちに留学生仲間ともなった藤代禎輔が、
夏目君は学生時代には文科には珍しい機械〔器械〕体操の名人であつた
と書き残しているのだ(『夏目君の片鱗』)。だが、その名人ぶりが手痛い失敗につながったことがある。
明治33年(1900)秋、漱石は英国留学へ赴いた。
八雲がそうだったように、このころ海外へ向かう交通手段は外国航路の大型汽船。漱石を乗せ9月8日に横浜港を出発したドイツ汽船プロイセン号は、神戸、香港、シンガポール、ペナン、コロンボなどに寄りながら、10月19日にイタリアのジェノバに到着した。およそ40日間にわたる航海だ。ロンドンへは、そこからさらに列車と船を乗り継いでいく。
長い船旅の退屈と運動不足の解消を考えて、漱石は汽船プロイセン号の中で鉄棒を使って体操をしている。ところが、あるとき、万年筆をポケットに入れっぱなしにしていたため、何かの拍子にポキリと折ってしまった。
この万年筆は、漱石の妻・鏡子の妹である時子が、洋行する漱石のためにプレゼントしてくれた品だった。当時、時子は建築家の鈴木禎次と結婚して大阪にいたが、汽船が神戸に寄港したところへわざわざ見送りにやってきて、餞別に贈ってくれたのである。
漱石は万年筆が壊れる不吉な音にひどく慌てふためいたはずだが、後の祭り。仕方なく航海途中、鏡子に宛てて、こんな手紙を書き送っている。
時さんの呉れた万年筆は船中にて鉄棒へツカマツテ器械体操をなしたる為打ち壊し申候洵(まこと)に申訳無之(これなく)御序(ついで)の節よろしく御伝可被下(おつたえくださるべく)候(明治33年10月8日付)
当時の万年筆は、いまよりずっと高価な舶来の貴重品。少しでも多くの研究書物を求めるため昼食代わりにビスケットをかじるような留学生活の中では、新たに購入できるはずもなく、漱石は結局、留学期間中ずっと、何文字か書いてはインクをつける「つけペン」を使うことになる。
漱石が再び万年筆を使いはじめるのは、教職を辞し専業作家として脂がのってきた明治40年(1907)過ぎ。英国ドゥ・ラ・リュー社製品の「ペリカン」を購入し使用した。インクは一般的なブルー・ブラックの色調を嫌い、セピア色を好んだ。原稿用紙は、橋口五葉デザインの、「漱石山房」の篆書を左右から竜頭がはさむ特注の原稿用紙(19字詰め10行)を使っていた。現在、神奈川近代文学館に漱石の遺品として保管されている万年筆は、晩年になって、評論家で「丸善」の顧問だった内田魯庵から進呈された同じドゥ・ラ・リュー社製の「オノト」。インクのボタ落ちを気にする漱石のため、内田は漏出防止つきのものを選んだ。ペン先が失われているのは、漱石の没後、鏡子が副葬品として埋葬したためという。
ちなみに、八雲が愛用したのは万年筆ではなく、米国から持参のペン。いわゆる「つけペン」で、ペン先はスペンセリアン製の細書き用を使っていたという。原稿用紙は、日本橋の「榛原」でつくった、縦20センチ、横14センチの特注品。英語で横書きに書きつけるから枡目はない。孫(長男・一雄の息子)の小泉時がこう記している。
片方の眼が悪かったので、もう一方の眼を擦りつけるように原稿紙に近よせながら、これも常用していたスペンセリアンのペンを走らせて原稿を書きました。静かな書斎からサラサラと流れてくるスペンセリアンの、異様に冴えた感じの音は、「パパのお勉強の音」として、幼かった一雄の耳に残り、今でも聞こえる気がすると、後年、一雄が八雲の遺品となったペン軸、ペン、インク壺などを取り出す機会があるたびに、よく家族の者に話したものでした。(『祖母のこと、父のこと』)
八雲は亡くなる数日前、セツと一雄のため、アメリカからウォーターマン社製の万年筆を取り寄せてプレゼントしたという。
それにしても、鉄棒につかまった漱石は、万年筆をへし折るほどの勢いで、どんな動きをしていたのだろう。もちろん、現在の五輪体操選手のような豪快、華麗な演技に比するべくはずもないが、ただの「逆上がり」じゃあ「器械体操の名人」の名が泣く。
小泉家の書生だって、「体を風車の如く廻したり、海老の如く跳ね上ったりしていた」というのだから、漱石も「蹴上がり」から「大車輪」にもっていくくらいの本格的な技は披露してくれていたのではないか。だいぶ年代は異なるが、時代小説家の藤沢周平も、若き学校教師時代は鉄棒で大車輪をしていたという。
想像してみてほしい。鉄棒につかまって大車輪で回っている漱石を。これまでと違った尊敬の念と、親しみの感情がじわりと湧いてきませんか。
* * *

矢島裕紀彦(やじま・ゆきひこ)
1957年、東京都生まれ。早稲田大学政経学部卒。作家・雑誌編集記者。文学、スポーツ、歴史など幅広いジャンルをフィールドに“人間”を描く。著書に『心を癒す漱石の手紙』『文士の逸品』『文士が愛した町を歩く』『鉄棒する漱石、ハイジャンプの安吾』『ウイスキー粋人列伝』『著名人名づけ事典』『こぼれ落ちた一球』『石橋を叩いて豹変せよ』『あの人はどこで死んだか』など多数。グランドセイコー広告の掌編小説シリーズ『時のモノ語り』で2018年度朝日広告賞朝日新聞特別賞受賞。https://atelier1328.com
(この連載を通しての主な参考文献)
『漱石全集』全28巻、別巻1(岩波書店、1993~1999年)/夏目鏡子述・松岡譲筆録『漱石の思い出』(文春文庫、1994年)/夏目伸六『父・夏目漱石』(文春文庫、1991年)/夏目伸六『父・漱石とその周辺』(芳賀書店、1967年)/高浜虚子『回想子規・漱石』(岩波文庫、2002年)/松岡陽子マックレイン『漱石夫妻 愛のかたち』(朝日新書、2007年)/荒正人『増補改訂漱石研究年表』(集英社、1984年)/江藤淳『漱石とその時代』第1部~5部(新潮新書、1970~1999年)/『新潮日本文学アルバム夏目漱石』(新潮社、1983年)/『別冊國文学 夏目漱石事典』(学燈社、1990年)/『夏目漱石の美術世界』(東京新聞、NHKプロモーション、2013年)/出久根達郎『漱石先生とスポーツ』(朝日新聞社、2000年)/江戸東京博物館・東北大学編『文豪・夏目漱石』(朝日新聞社、2007年)/平岡敏夫『「坊つちやん」の世界』(塙新書、1992年)/恒松郁生『漱石 個人主義へ』(雄山閣、2015年)/小泉節子、小泉一雄『小泉八雲 思い出の記 父「八雲」を憶う』(恒文社、1976年)/小泉八雲、平井呈一訳『日本瞥見記』上・下(恒文社、1975年)/小泉八雲、平井呈一訳『東の国から・心』(恒文社、1975年)/小泉八雲、平川祐弘編『怪談・奇談』(講談社学術文庫、1990年)/小泉八雲、池田雅之編訳『虫の音楽家』(ちくま文庫、2005年)/『明治文学全集48 小泉八雲集』(筑摩書房、1970年)/小泉時共編『文学アルバム小泉八雲』(恒文社、2000年)/小泉凡監修『小泉八雲、開かれた精神の航跡。』(小泉八雲記念館、2016年)/池田雅之監修『別冊太陽 小泉八雲』(平凡社、2022年)/池田雅之『小泉八雲』(角川ソフィア文庫、2021年)/田部隆次『小泉八雲』(北星社、1980年)/長谷川洋二『八雲の妻』(今井書店、2014年)/関田かをる『小泉八雲と早稲田大学』(恒文社、1999年)/梶谷泰之『へるん先生生活記』(恒文社、1998年)/池野誠『松江の小泉八雲』(山陰中央新報社、1980年)/工藤美代子『神々の国』(集英社、2003年)/工藤美代子『夢の途上』(集英社、1997年)/工藤美代子『聖霊の島』(集英社、1999年)/平川祐弘編『小泉八雲回想と研究』(講談社、1992年)/平川祐弘『世界の中のラフカディオ・ハーン』(河出書房新社、1994年)/熊本大学小泉八雲研究会『ラフカディオ・ハーン再考』(恒文社、1993年)/西川盛雄『ラフカディオ・ハーン』(九州大学出版会、2005年)/西成彦『ラフカディオ・ハーンの耳、語る女たち』(洛北出版、2024年)/池田雅之『日本の面影』(NHK出版、2016年)/ラフカディオ・ハーン『小泉八雲東大講義録』(KADOKAWA、2019年)/芦原伸『へるん先生の汽車旅行』(集英社インターナショナル、2014年)/嵐山光三郎『文人暴食』(新潮文庫、2006年)/河東碧梧桐『子規を語る』(岩波文庫、2002年)/『正岡子規の世界』(松山市立子規記念博物館、1994年)/『子規全集』18巻、19巻(講談社、1979年)/『志賀直哉全集』第8巻(岩波書店、1999年)/『芥川龍之介全集』第4巻(岩波書店、1996年)/瀬沼茂樹『評伝島崎藤村』(筑摩書房、1981年)/矢島裕紀彦『心を癒す漱石の手紙』(小学館文庫、2009年)/矢島裕紀彦『鉄棒する漱石、ハイジャンプの安吾』(NHK生活人新書、2003年)/矢島裕紀彦『文士が愛した町を歩く』(NHK生活人新書、2005年)/矢島裕紀彦『文士の逸品』(文春ネスコ、2001年)





























