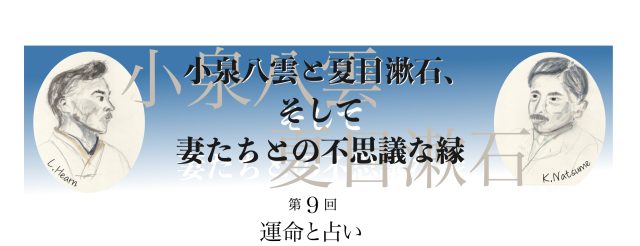
小泉セツ&小泉八雲の夫婦がモデルとなった朝の連続テレビ小説『ばけばけ』が注目されています。実はその小泉夫妻と、明治の文豪・夏目漱石と妻・鏡子は、不思議と重なり合う縁で結ばれていた、というのをご存じでしょうか。
夏目漱石の研究家として知られ、『心を癒す漱石の手紙』などの著書を持つ、作家で雑誌編集記者の矢島裕紀彦さんによると、二人の文豪とその妻たちには奇縁と呼ぶしかないような不思議なつながりがあると言います。
多数の文献や手記を紐解きながら、二組の夫婦の知られざる素顔を全26回の連載にて紹介します。
第9回では、小泉八雲とセツ、夏目漱石と鏡子、それぞれの身の上に訪れた運命的とも言える出来事をご紹介します。
文・矢島裕紀彦
導かれるように出会った小泉八雲とセツ

振り返ってみると、誰の生涯にも、ひとつやふたつ、行く末を暗示するような因縁めいた話や運命的な出来事が横たわっているものなのかもしれない。
夏目漱石は大学を卒業し大学院に籍を置いていた一時期、東京・小石川の伝通院近くにある別院(法蔵院)に下宿していたことがあった。法蔵院の和尚は内職に「身の上判断」を行っていた。算木と筮竹などを使いながら相談事を占って助言を与えるのである。漱石は元来、こうしたことには余り関心を持たない方だが、あるとき何かの拍子に、人相とか方位といった話題になり、つい「私の未来はどうでしょう?」と冗談半分に尋ねてみた。すると和尚は漱石の顔をじっと眺めて、「あなたは親の死に目には会えませんね」と言った。「あなたは西へ西へと行く相がある」とも言った。あとになってみると、これは両方とも当たっていた。漱石は結局、両親の死に目に会えなかったし、このあと間もなく松山、熊本、さらにイギリスへと向かうことになったのである。
小泉セツにも、幼少時、自分の将来を暗示するような出来事があった。
セツが3歳の頃、母親や親戚に連れられて、調練場へ歩兵隊の行進を見物に行った。そこには大勢の見物が押しかけていた。明治維新後、新政府は各知藩事に命じて、それぞれの石高に応じて新規の軍を編成させた。その教練のため、ふたりのフランス人下士官が松江へ派遣されていた。その下士官のひとり、大男のヴァレットが、教練のあと、セツに近づいてきて年齢を尋ねた。セツは臆することなく小さな指で年齢を示し、すると、大男はその手に四角い小さな物を握らせてくれたという。息子の一雄が、後年、母から聞いた話を次のように伝えている。
大勢の子供たちがいる中で、特別に自分だけが選ばれたように異郷の人から頭を撫でられ、しかも品物までもらったことを、嬉しく、また誇りやかに感じたとのことです。もらった品は、小さな折畳み式真鍮製の枠のついた虫眼鏡でした。(『亡き母を語る』)
こうした幼少期の体験が、セツの外国人に対する親しみの感情の素地となったというのである。
また、娘時代にはこんなこともあった。ある日、セツは友だちと3人で、縁結びの神として知られる松江郊外の八重垣神社に参詣した。境内の池には古い言い伝えがあって、紙でこしらえた小さな船に1厘銭をのせて浮かべると、それが次第に底に沈み、池に棲むヤモリが寄ってきて船にさわると恋が成就するというのである。3人が結婚を占って船を浮かべると、友だち2人の船はすぐに沈んだのに、セツの船だけはなかなか沈まず、はるか池の端の方まで流れていって、やっと沈んだ。ふたりの友だちはまもなく近所の青年と結婚し、セツはやがて遠い異国の人、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)と結ばれることになった。
この八重垣神社は、奇しくも、のちにラフカディオ・ハーンが帰化して「八雲」と改名する際の、名前の起原となった和歌の生まれた場所でもあった。
小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が米国ニューオリンズで開催されている万国産業綿花百年記念博覧会を訪れたのは、1885年(明治18年)1月から2月にかけてのことだから、ちょうど娘時代のセツが八重垣神社を詣でたのと、時間的には同じ頃だったかもしれない。
八雲34歳のときのこの博覧会訪問は、ニューヨークの出版社ハーパー社から発行されている雑誌『ハーパーズ・マンスリー』に記事を書き送る取材のためであった。八雲は20代の頃から東洋に深い関心を持ち、古書店などで関連文献を収集していた。日本館を訪れて強く興味を惹かれ、同時に日本政府派遣の事務官・服部一三と親しくなった。服部は八雲が投げかける日本に関する詳細な質問に驚かされたという。八雲が、『ハーパーズ・マンスリー』の美術主任ウィリアム・パットンからチェンバレン英訳の『古事記』を借りて読み、深い感銘を受けたのは、それから数年後のことだった。このふたつの出来事が、八雲が日本へ行くことを決断する大きなきっかけとなったという。
明治23年(1890)4月4日に横浜に到着した八雲は、通信記者としてのハーパー社との契約解除を決意し、パットンからの紹介状を頼りに、東京・赤坂台町に住むチェンバレン宛てに手紙を送り仕事を斡旋してくれるよう依頼した。その手紙文中には、服部一三の名を記すことも忘れなかった。チェンバレンからは4月6日付ですぐに返書が届いた。
拝復 あなたのお名前は、ご著書『中国霊異談』などでよく存じています。私の微力の及ぶ限り、お役に立つことが出来れば嬉しく思います。一、二日中に文部省の服部局長に面会するか、局長不在の場合は、省内の他の知人に面会します。
こうしてチェンバレンの推薦と文部省上級官吏たる服部の協力で、八雲の松江行きの話が実現したのである。奇しくも服部は、当時、文部省の普通学務局長であり、職域として全国の中学校、師範学校、小学校などを主管していた。松江では前任の英語教師のカナダ人宣教師タットルの評判が悪く、中途解約となり、後任の人材を求めていた。
松江の八雲は、易者の高木苓太郎から「これまでの運勢は余りよくなかった。力はあれどもとかく世に現れない。たとえばダイヤモンドが他の石に包まれたような形である」と言われたことがあった。八雲は「それでは死んだら名が出るということだろうか」と応じたという。
占い好きの鏡子が頼った易者「天狗」

漱石夫人の鏡子の占い好きと迷信担ぎは、相当のものだった。迷い込んだ猫を可愛がりはじめたのも、出入りの按摩のお婆さんから「これは福猫」と進言されたためだった。その後、「天狗」という通称の易者を知って何かと相談を持ちかけ、漱石から「おまえはいつも亭主より先に天狗に相談する」と笑われたり注意されたりしていた。漱石没後、晩年に移り住んだ池上の高台の家では、庭に稲荷祠をつくっていたし、毎夜、就寝前、トランプ占いに興じている姿を、孫たちに目撃されてもいる。
明治43年(1910)8月、43歳の漱石が胃潰瘍手術のあと、静養先の修善寺で体調を悪化させたときも、鏡子は心配になって天狗に手紙を書き、占いと祈祷を頼んだ。
天狗は、出た易が非常に悪い、祈祷を続けるから1週間ごとに容態を知らせるように、と返事をしてきた。その直後、漱石は大量の血を吐いて瀕死の状態に陥った。医師の手当てもあって奇跡的に持ち直し、2か月の療養を経て帰京し、かかりつけの長与胃腸病院に戻ることができた。
この間、鏡子は天狗に言われた通り容態を知らせる手紙を書き、心配を脱し容態が落ち着いたところで、天狗に礼状を書いた。すると、天狗から不思議な出来事を伝える返書があったという。回想録『漱石の思い出』に、鏡子は記している。
なんでも私からの手紙をうけとった二十四日の二、三日前、どこからともなくみなれない黒猫が天狗の家に入って来まして、そのまま逃げもせず家にいついてしまって、ご飯をやればたべるし、すわっていれば膝に来て抱かれるといったぐあいでありました。ところが私の手紙で、これから祈祷をしようと壇を組んだりしていますと、いつの間にやら姿を隠して、それからというもの幾日たってもかえって参りません。妙な猫だなと時々思いながら祈祷を続けておりますうち、満願に近づいてひょっくり入って来まして、そうして血を吐いて死んだそうです。どうも猫が身代わりになったのじゃないかなどと申しておりました…
八雲が聞いたら喜びそうな、怪談めいた話であった。
天狗からの一方的な話で真偽は怪しいが、漱石もさすがに感じるところがあったのか、「あまり天狗などの云ふ事ばかり信用しないがいい」と言いながらも、長与胃腸病院の退院の日取りは鏡子が天狗から進言されたという日程を受け入れたのだった。
なお、修善寺の漱石が病床から初めて起き直って顔を洗い髪を梳ったのは、ちょうど八雲の7回忌に当たる9月26日(明治43年)だった。私には、このことも奇縁に思える。
自身の病が快方に向かう中、入れ違いのように亡くなった人へ思いを馳せ、このあと漱石は一句詠んでいる。
「逝く人に留まる人に来る雁」
* * *

矢島裕紀彦(やじま・ゆきひこ)
1957年、東京都生まれ。早稲田大学政経学部卒。作家・雑誌編集記者。文学、スポーツ、歴史など幅広いジャンルをフィールドに“人間”を描く。著書に『心を癒す漱石の手紙』『文士の逸品』『文士が愛した町を歩く』『鉄棒する漱石、ハイジャンプの安吾』『ウイスキー粋人列伝』『著名人名づけ事典』『こぼれ落ちた一球』『石橋を叩いて豹変せよ』『あの人はどこで死んだか』など多数。グランドセイコー広告の掌編小説シリーズ『時のモノ語り』で2018年度朝日広告賞朝日新聞特別賞受賞。https://atelier1328.com
(この連載を通しての主な参考文献)
『漱石全集』全28巻、別巻1(岩波書店、1993~1999年)/夏目鏡子述・松岡譲筆録『漱石の思い出』(文春文庫、1994年)/夏目伸六『父・夏目漱石』(文春文庫、1991年)/夏目伸六『父・漱石とその周辺』(芳賀書店、1967年)/高浜虚子『回想子規・漱石』(岩波文庫、2002年)/松岡陽子マックレイン『漱石夫妻 愛のかたち』(朝日新書、2007年)/荒正人『増補改訂漱石研究年表』(集英社、1984年)/江藤淳『漱石とその時代』第1部~5部(新潮新書、1970~1999年)/『新潮日本文学アルバム夏目漱石』(新潮社、1983年)/『別冊國文学 夏目漱石事典』(学燈社、1990年)/『夏目漱石の美術世界』(東京新聞、NHKプロモーション、2013年)/出久根達郎『漱石先生とスポーツ』(朝日新聞社、2000年)/江戸東京博物館・東北大学編『文豪・夏目漱石』(朝日新聞社、2007年)/平岡敏夫『「坊つちやん」の世界』(塙新書、1992年)/恒松郁生『漱石 個人主義へ』(雄山閣、2015年)/小泉節子、小泉一雄『小泉八雲 思い出の記 父「八雲」を憶う』(恒文社、1976年)/小泉八雲、平井呈一訳『日本瞥見記』上・下(恒文社、1975年)/小泉八雲、平井呈一訳『東の国から・心』(恒文社、1975年)/小泉八雲、平川祐弘編『怪談・奇談』(講談社学術文庫、1990年)/小泉八雲、池田雅之編訳『虫の音楽家』(ちくま文庫、2005年)/『明治文学全集48 小泉八雲集』(筑摩書房、1970年)/小泉時共編『文学アルバム小泉八雲』(恒文社、2000年)/小泉凡監修『小泉八雲、開かれた精神の航跡。』(小泉八雲記念館、2016年)/池田雅之監修『別冊太陽 小泉八雲』(平凡社、2022年)/池田雅之『小泉八雲』(角川ソフィア文庫、2021年)/田部隆次『小泉八雲』(北星社、1980年)/長谷川洋二『八雲の妻』(今井書店、2014年)/関田かをる『小泉八雲と早稲田大学』(恒文社、1999年)/梶谷泰之『へるん先生生活記』(恒文社、1998年)/池野誠『松江の小泉八雲』(山陰中央新報社、1980年)/工藤美代子『神々の国』(集英社、2003年)/工藤美代子『夢の途上』(集英社、1997年)/工藤美代子『聖霊の島』(集英社、1999年)/平川祐弘編『小泉八雲回想と研究』(講談社、1992年)/平川祐弘『世界の中のラフカディオ・ハーン』(河出書房新社、1994年)/熊本大学小泉八雲研究会『ラフカディオ・ハーン再考』(恒文社、1993年)/西川盛雄『ラフカディオ・ハーン』(九州大学出版会、2005年)/西成彦『ラフカディオ・ハーンの耳、語る女たち』(洛北出版、2024年)/池田雅之『日本の面影』(NHK出版、2016年)/ラフカディオ・ハーン『小泉八雲東大講義録』(KADOKAWA、2019年)/芦原伸『へるん先生の汽車旅行』(集英社インターナショナル、2014年)/嵐山光三郎『文人暴食』(新潮文庫、2006年)/河東碧梧桐『子規を語る』(岩波文庫、2002年)/『正岡子規の世界』(松山市立子規記念博物館、1994年)/『子規全集』18巻、19巻(講談社、1979年)/『志賀直哉全集』第8巻(岩波書店、1999年)/『芥川龍之介全集』第4巻(岩波書店、1996年)/瀬沼茂樹『評伝島崎藤村』(筑摩書房、1981年)/矢島裕紀彦『心を癒す漱石の手紙』(小学館文庫、2009年)/矢島裕紀彦『鉄棒する漱石、ハイジャンプの安吾』(NHK生活人新書、2003年)/矢島裕紀彦『文士が愛した町を歩く』(NHK生活人新書、2005年)/矢島裕紀彦『文士の逸品』(文春ネスコ、2001年)





























