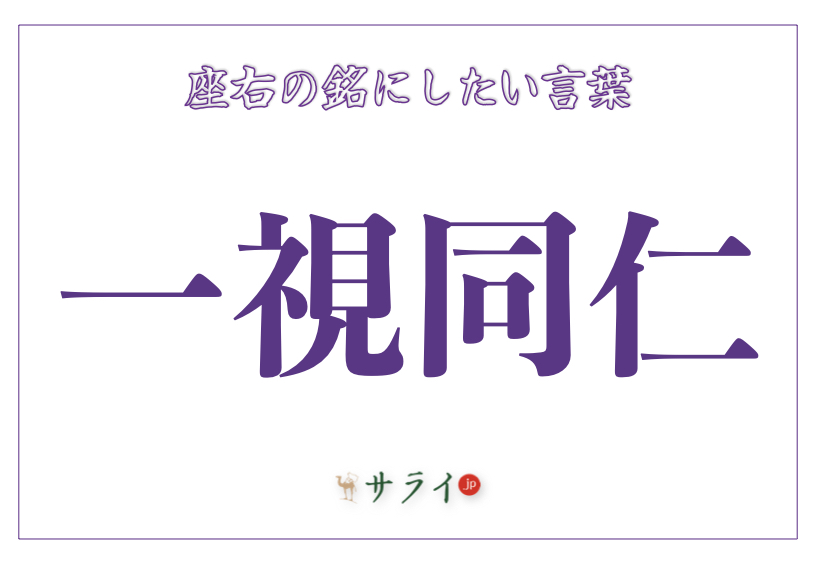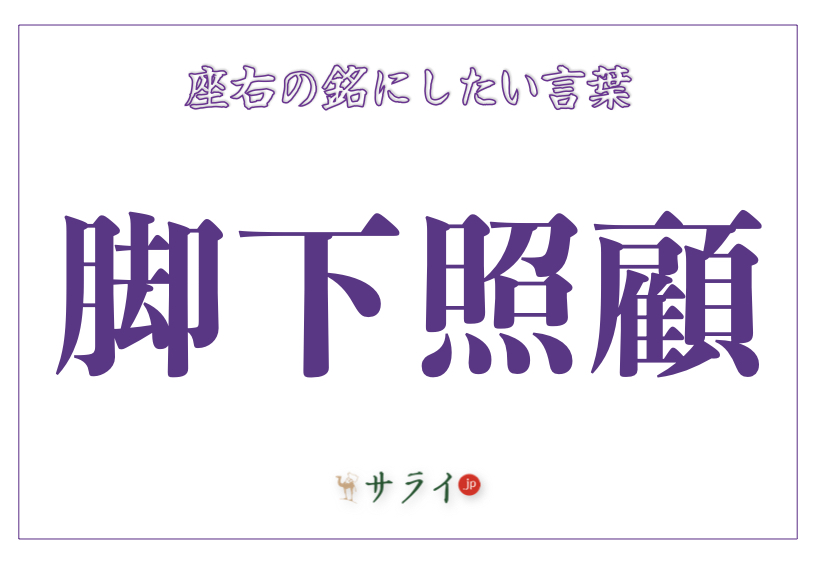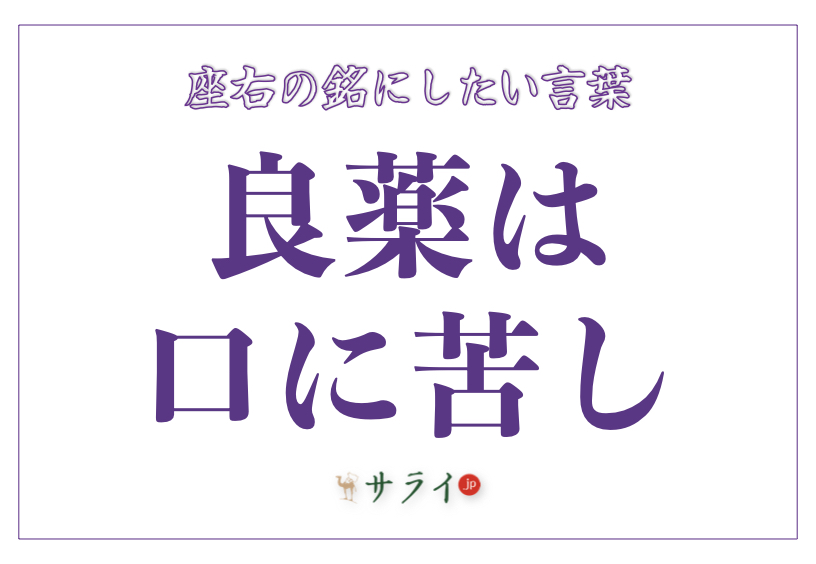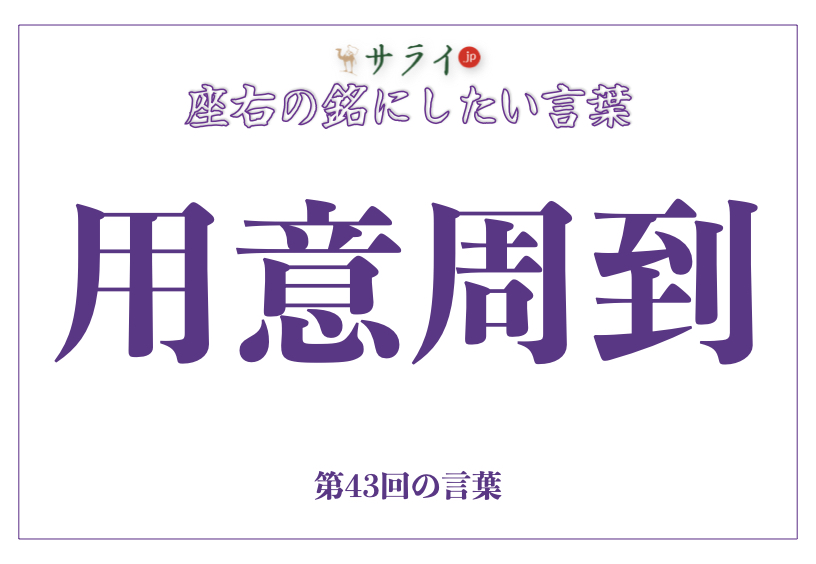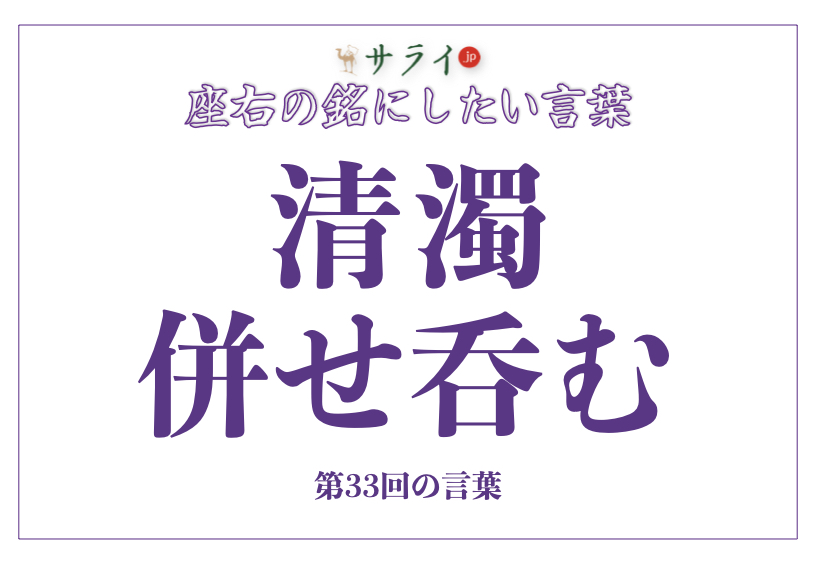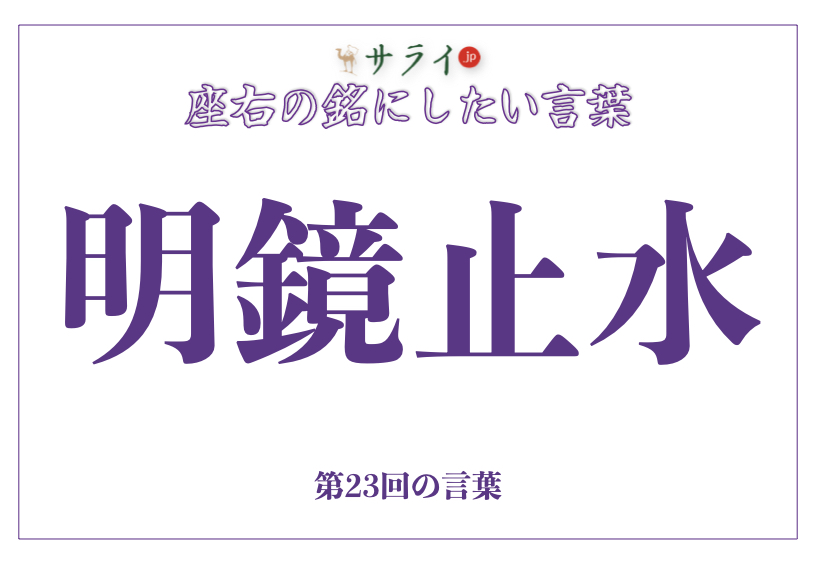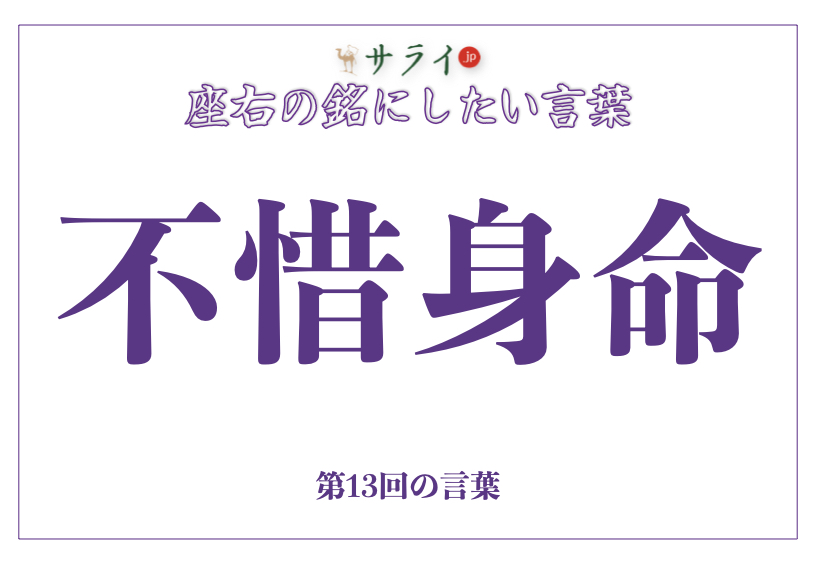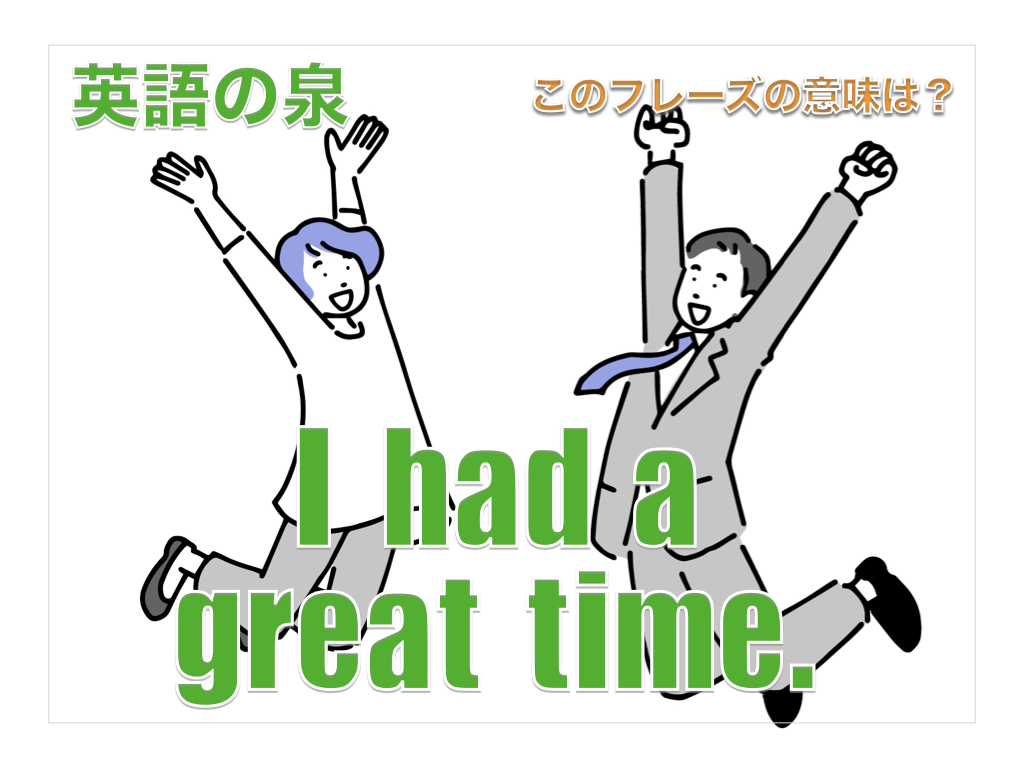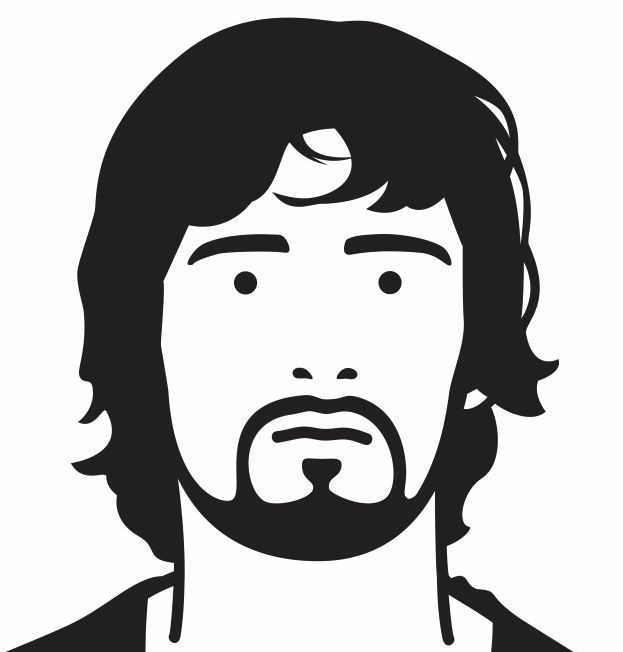ある程度の歳になりますと、よほど親しい友人でもない限り、本音で意見してくれたり、苦言を提してくれる人などいないものです。若い人からも、徐々に敬遠されるようになってきますと、諫言(かんげん)されることもなくなります。そうなってから始まる「長い老後」と呼ばれる生活にあって、考え方の柔軟さを保ち、激しく変化する社会へ順応するためには、何らかの指針を持っていた方がいいのかもしれません。
温故知新のことわざのごとく、先人が残してくれた言葉や金言にヒントを得てみてはいかがでしょう。
今回の座右の銘にしたい言葉は「一視同仁」(いっしどうじん) です。
「一視同仁」の意味
「一視同仁」について、『デジタル⼤辞泉』(小学館)では、「すべての人を差別なく平等に愛すること」とあります。「一視」は、一つの視点で見ること、つまり誰に対しても同じ目で見ることを表します。「同仁」の「仁」は、思いやりや慈しみの心を指します。したがって「同仁」は、すべての人に対して同じように仁愛の心を持つという意味になります。
相手の地位や貧富、賢いか愚かか、好きか嫌いかといった個人的な感情や利害関係で態度を変えることなく、誰に対しても同じように、公平な心で接する。まさに、理想的なリーダーや人格者のあり方を示す言葉といえます。
「一視同仁」の由来
この言葉のルーツは、中国・唐時代の文人・韓愈(かんゆ)の著書『原人(げんにん)』にあります。『原人』には、
「聖人は一視にして同仁、近きに篤(あつ)くして遠きを挙ぐ」という一節があり、「聖人たるものは、人や生き物を区別なく、すべてを等しく愛し、身近な者に親切にし、遠いものにも同じ愛情を及ぼす」という精神が説かれています。
「仁」を「人」と書き間違えやすいですが、この「仁」が「思いやり」を表すことこそ、この言葉の本質なのです。

「一視同仁」を座右の銘としてスピーチするなら
「一視同仁」を座右の銘として語る際には、自分の人生経験を交えつつ、普遍的な価値観を示すことが大切です。しかし、この言葉は高い理想を掲げるものですから、上から目線にならないよう注意しましょう。
以下に「一視同仁」を取り入れたスピーチの例をあげます。
生き方の指針としてのスピーチ例
私の座右の銘は「一視同仁」という四字熟語です。
これは、すべての人を分け隔てなく、平等に大切にするという意味です。
40年近く会社勤めをしてまいりましたが、振り返ると、役職や立場にとらわれて人を見ていた時期がありました。部下には厳しく、上司には気を使い、取引先によって態度を変える。そんな自分に気づいた時、これでいいのかと疑問を感じたものです。
定年を迎え、肩書きを離れた今、改めて「一視同仁」という言葉の重みを感じています。地域のボランティア活動では、年齢も経歴も様々な方々と一緒に汗を流しています。そこには上下関係も損得勘定もありません。ただ、一人の人間として向き合う。そんな関係が、実は一番心地よいのだと気づきました。
もちろん、私自身まだまだ未熟で、つい先入観を持ってしまうこともあります。ですが、この「一視同仁」という言葉を心に留めることで、立ち止まって考え直すきっかけになっています。
人生100年時代と言われる今、これからも様々な世代、様々な背景を持つ方々と出会うでしょう。その時、相手が誰であれ、一人の人間として誠実に向き合っていく。そんな生き方を、この言葉を道しるべに続けていきたいと思っています。
最後に
「一視同仁」は、単なる理想論ではなく、人生経験を重ねたからこそ理解できる深い教えです。若い頃は、どうしても人を立場や肩書きで判断してしまいがちです。しかし、年を重ね、様々な人生の機微に触れることで、人間の本質は表面的な違いとは別のところにあることが見えてきます。
サライ世代の皆様は、まさにそうした境地に達しておられるのではないでしょうか。相手を見た目や立場で判断せず、誠実に向き合う姿勢は、人生の品格を高め、周囲に温かい影響を与えるのです。
●執筆/武田さゆり

国家資格キャリアコンサルタント。中学高校国語科教諭、学校図書館司書教諭。現役教員の傍ら、子どもたちが自分らしく生きるためのキャリア教育推進活動を行う。趣味はテニスと読書。
●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com