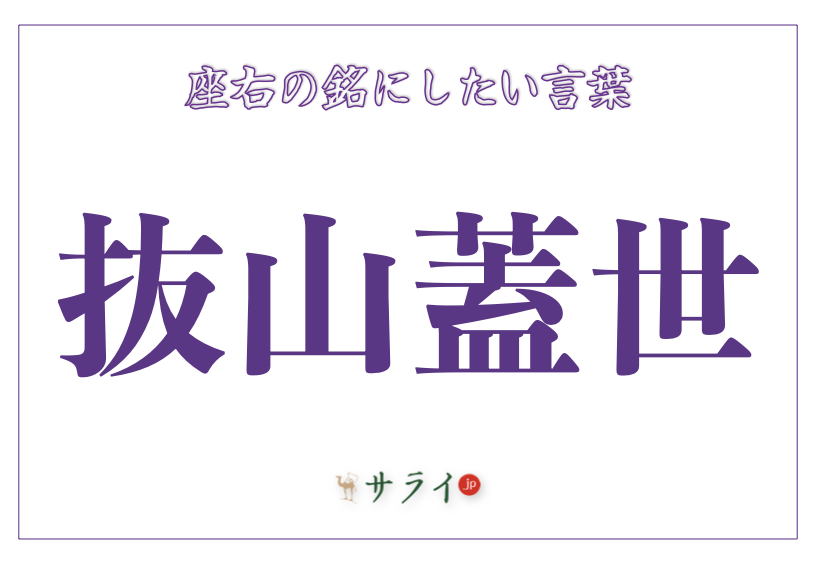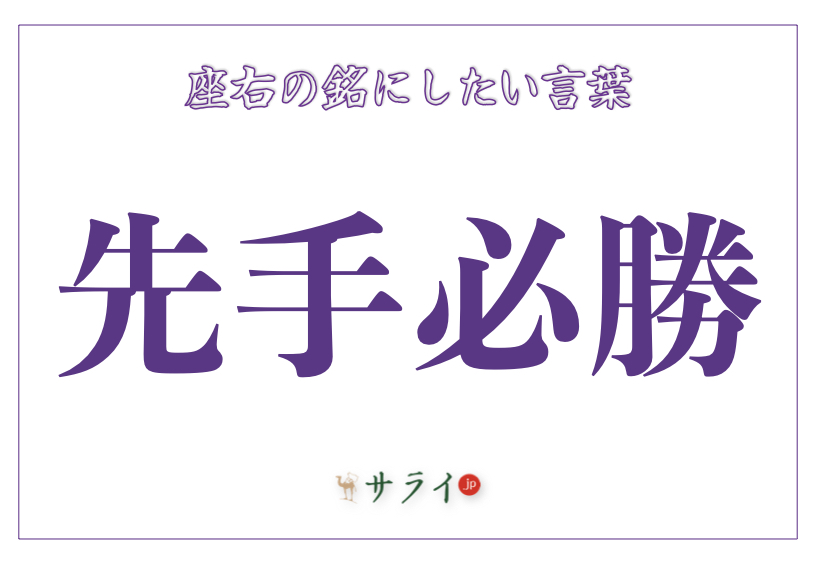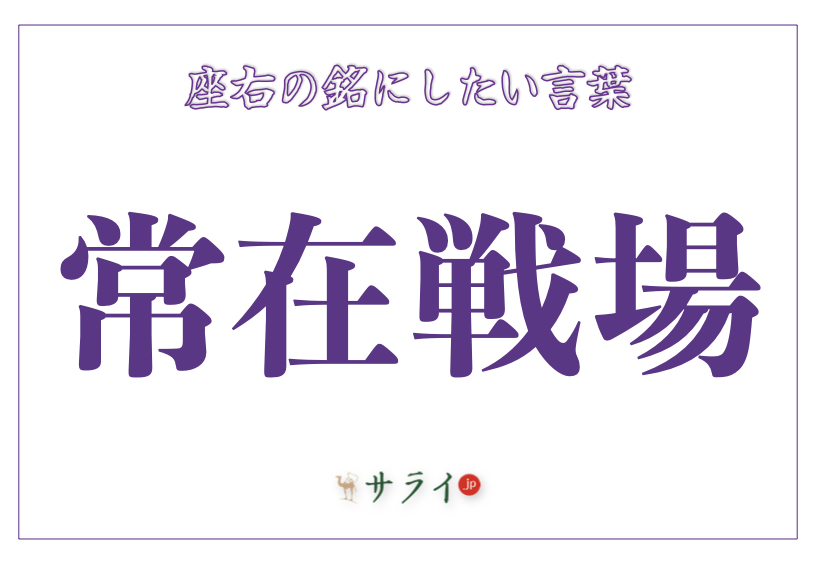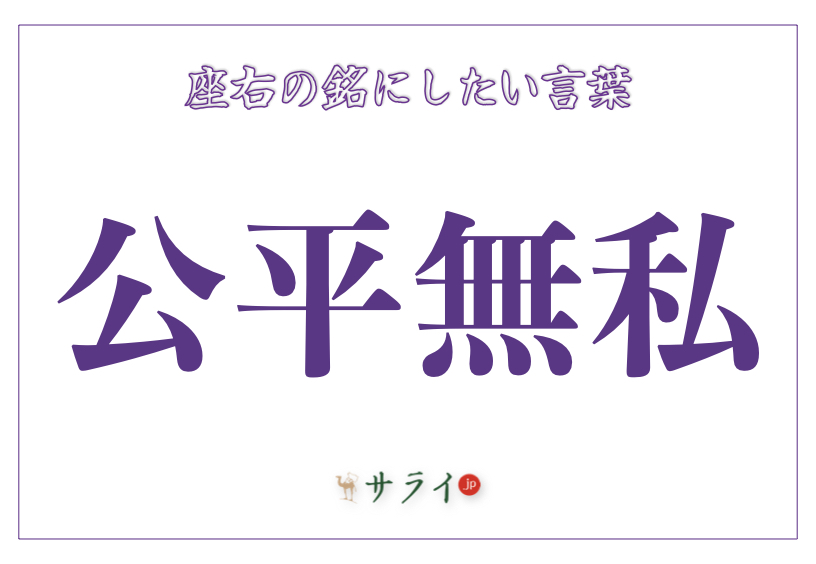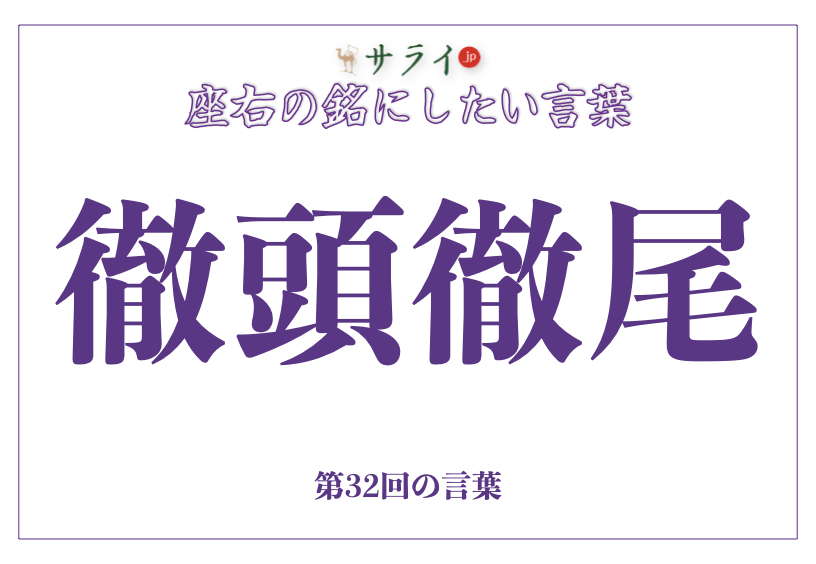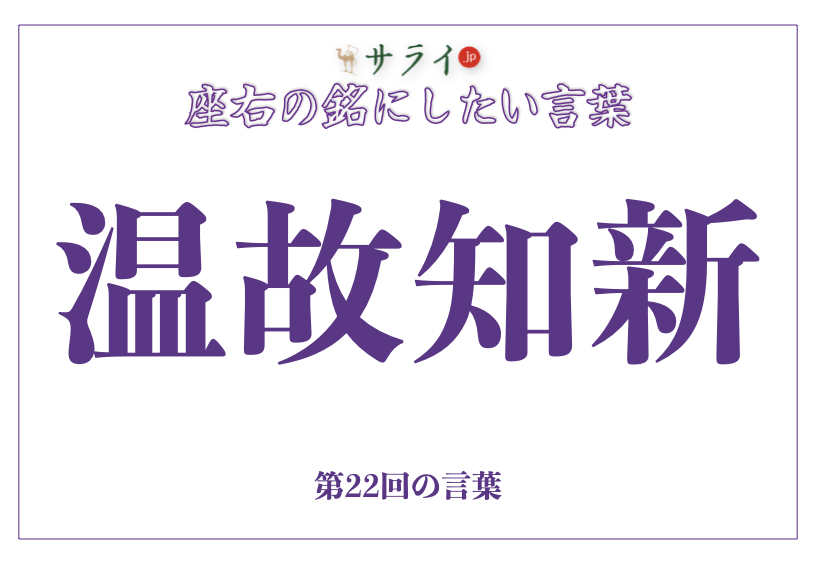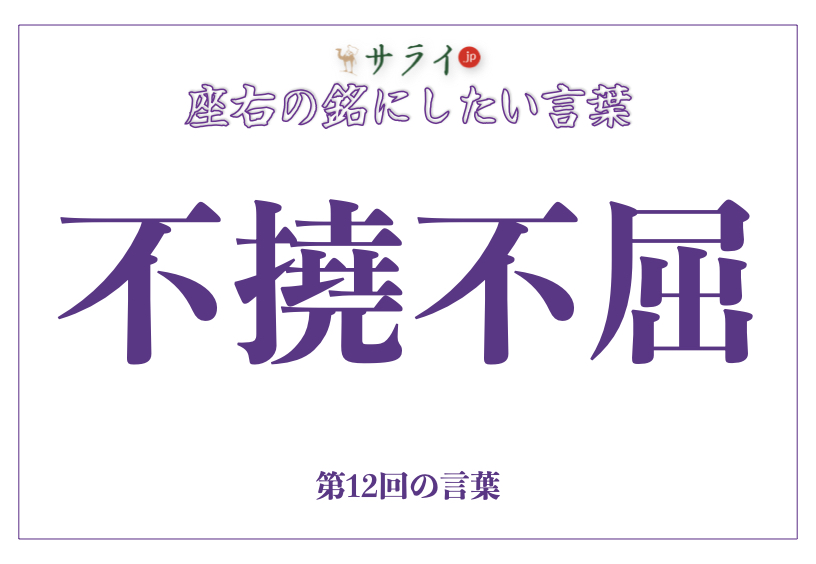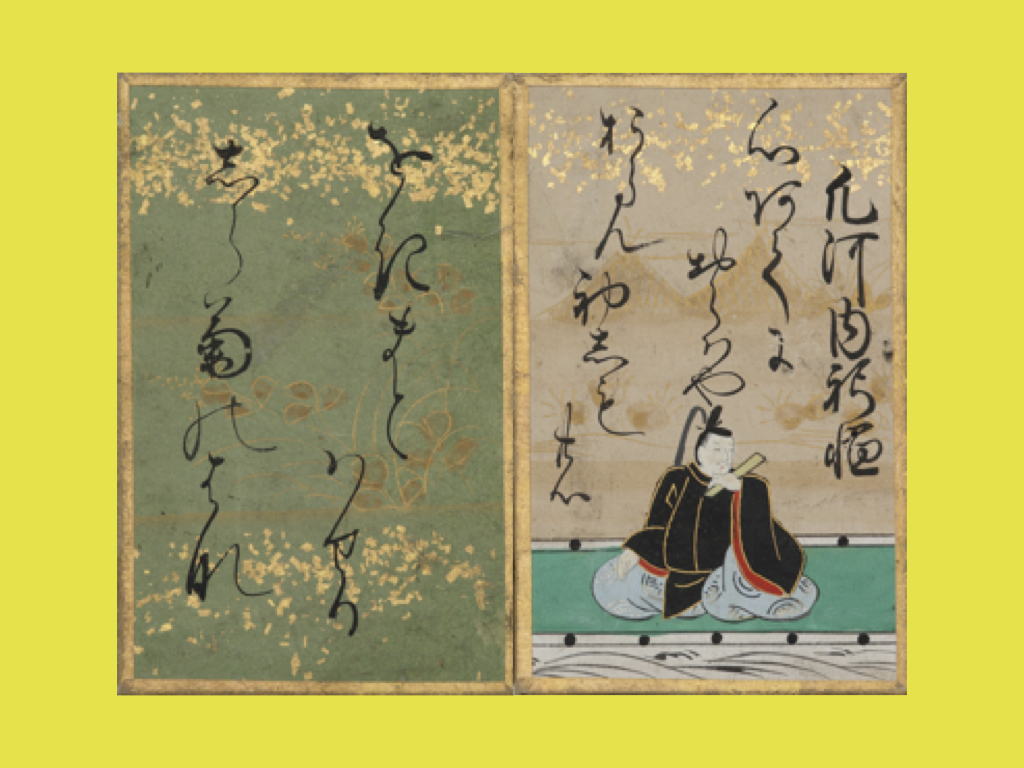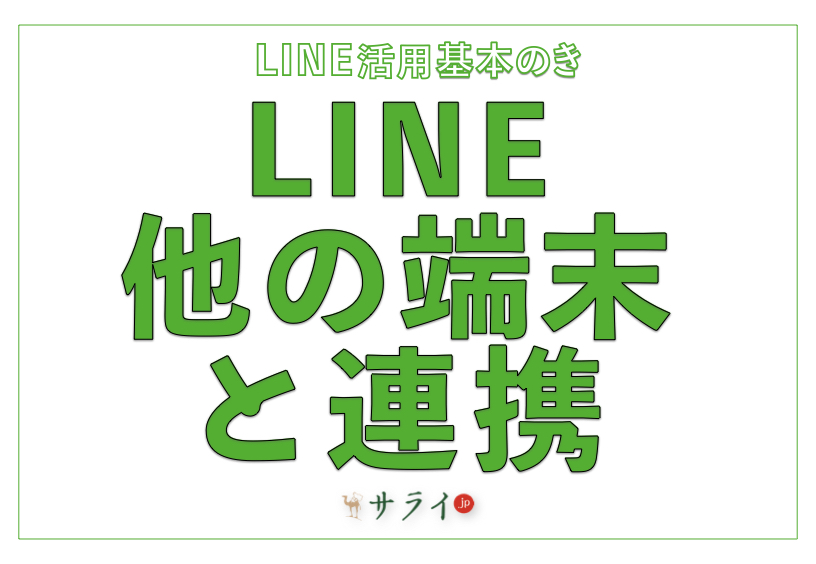実にありがたいことに、人生をやり直せる時代になりました。人生百年時代となった今では、定年退職は、第二の人生のスタートのようにいわれています。そうは言っても「どこまでも続く人生」と思っていた、若き時とは違います。
溢れる情報に惑わされず、巧妙で狡猾な罠を見破り、第二の人生を生きなければなりません。しかし、自分だけの知識や経験だけでは心許ないところも……。ならば、賢者の知恵を頼みとするのも一つの方法ではないでしょうか?
そうした賢者が残した一つの言葉をご紹介します。今回の座右の銘にしたい言葉は「抜山蓋世」(ばつざんがいせい)です。
「抜山蓋世」の意味
「抜山蓋世」について、『⼩学館デジタル⼤辞泉』では、「山を抜き取るほどの力と、世をおおいつくすほどの気力があること」とあります。単なる腕力を指すのではなく、人の心を圧倒するほどの威勢や、スケールの大きな気概を表します。
まさに、エネルギーに満ち溢れ、天下を動かすほどの勢いを持つ人物を形容するのに、これほどぴったりの言葉はないでしょう。
これまでの仕事や家庭で、困難なプロジェクトを成し遂げたり、家族を守り抜いたりと、まさに「山を抜く」ほどの力で奮闘されてきた皆様の姿に、この言葉は重なるのではないでしょうか?
「抜山蓋世」の由来
この「抜山蓋世」という言葉の背景には、一つの壮絶な物語があります。出典は、中国の歴史家・司馬遷が著した『史記』の中の「項羽本紀」。秦の始皇帝が没し、天下が乱れた時代、楚の国の英雄として歴史に名を刻んだ項羽(こうう)の詠んだ詩に由来します。
圧倒的な武勇を誇り、連戦連勝を重ねた項羽でしたが、劉邦(りゅうほう)との最終決戦「垓下(がいか)の戦い」で、ついに絶体絶命の窮地に陥ります。敵である漢の軍勢に幾重にも包囲され、夜になると四方から故郷である楚の国の歌が聞こえてくる。これを聞いた項羽は、「漢はすでに楚の地をすべて手に入れたのか。なんと(漢に制圧された)楚の人間の多いことか」と嘆き、敗北を悟ります。これが有名な「四面楚歌」(しめんそか)の故事です。
もはやこれまでと覚悟を決めた項羽は、最後の夜に宴を開きます。傍らには、常に寄り添ってきた愛馬・騅(すい)と、最愛の女性・虞美人(ぐびじん)。彼は、自らの運命を嘆き、悲壮な覚悟を込めて、即興で詩を詠みます。
力抜山兮気蓋世 力は山を抜き 気は世を蓋(おお)う
時不利兮騅不逝 時に利あらず 騅(すい)は逝(ゆ)かず
騅不逝兮可奈何 騅の逝かざるを 奈何(いかん)すべき
虞兮虞兮奈若何 虞(ぐ)や虞や 若(なんじ)を奈何せん
(私の力は山を引き抜くほど強く、気力は世を覆うほど盛んであった。しかし、時の運に見放され、愛馬の騅も前に進もうとしない。進まない騅を、どうすることができようか。ああ、虞よ、虞よ。お前をいったい、どうしてやれようか)
この詩にある「力抜山兮気蓋」から、「抜山蓋世」という言葉が生まれました。最強の英雄が、人生の最後に詠んだ悲壮な詩。この言葉には、ただ力強いだけでなく、栄光と挫折、そして愛する者への想いといった、人間の持つ深い情念が込められているのです。
だからこそ、単なる威勢のよさとは一線を画し、私たちの心を強く揺さぶるのでしょう。

「抜山蓋世」を座右の銘としてスピーチするなら
この言葉を座右の銘として披露する際には、いくつか注意すべき点があります。
まず、「抜山蓋世」という言葉は非常に力強く、場合によっては自己顕示的に聞こえる可能性があります。ですから、この言葉を選んだ理由や、自分なりの解釈を添えることで、謙虚さと深みのあるスピーチになります。以下に「抜山蓋世」を取り入れたスピーチの例をあげます。
人生の節目で語るスピーチ例
私の座右の銘は「抜山蓋世」です。初めてこの言葉に出会ったとき、その力強い響きに惹かれました。これは中国の古い歴史書『史記』に登場する、項羽という武将が詠んだ詩の一節から生まれた言葉です。「山を引き抜き、世を覆うほどの力」という意味ですが、私はこれを単なる物理的な力ではなく、困難に立ち向かう精神力として捉えています。
還暦を過ぎた今、若い頃のような体力はありません。しかし、人生経験という別の力を手に入れました。この力こそが、私にとっての「抜山蓋世」なのです。興味深いことに、この言葉を残した項羽は、最終的に戦いに敗れた人物です。つまり、必ずしも勝者の言葉ではありません。むしろ、逆境の中でも誇りを失わず、自分の信念を貫いた人の言葉だからこそ、深い意味があるのだと思います。
私たちシニア世代は、人生という長い道のりで様々な山を越えてきました。しかし、その全てが今の自分を形作っています。これからの人生においても、年齢を言い訳にせず、自分なりの「山を抜く」挑戦を続けていきたい。
若い世代に伝えたいのは、力とは必ずしも若さや体力ではないということです。経験、知恵、そして何より諦めない心こそが、本当の意味での「抜山蓋世」の力なのだと、私は信じています。
最後に
この言葉は、若き日の燃えるような情熱とエネルギーの象徴であると同時に、人生の黄昏時に、その力の意味を問い直させてくれる、奥深い言葉です。栄光、挫折、愛、そして感謝。さまざまな経験を重ねてこられたサライ世代の皆様だからこそ、この言葉の持つ多面的な輝きを、ご自身の人生に重ね合わせることができるのではないでしょうか。
●執筆/武田さゆり

国家資格キャリアコンサルタント。中学高校国語科教諭、学校図書館司書教諭。現役教員の傍ら、子どもたちが自分らしく生きるためのキャリア教育推進活動を行う。趣味はテニスと読書。
●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com