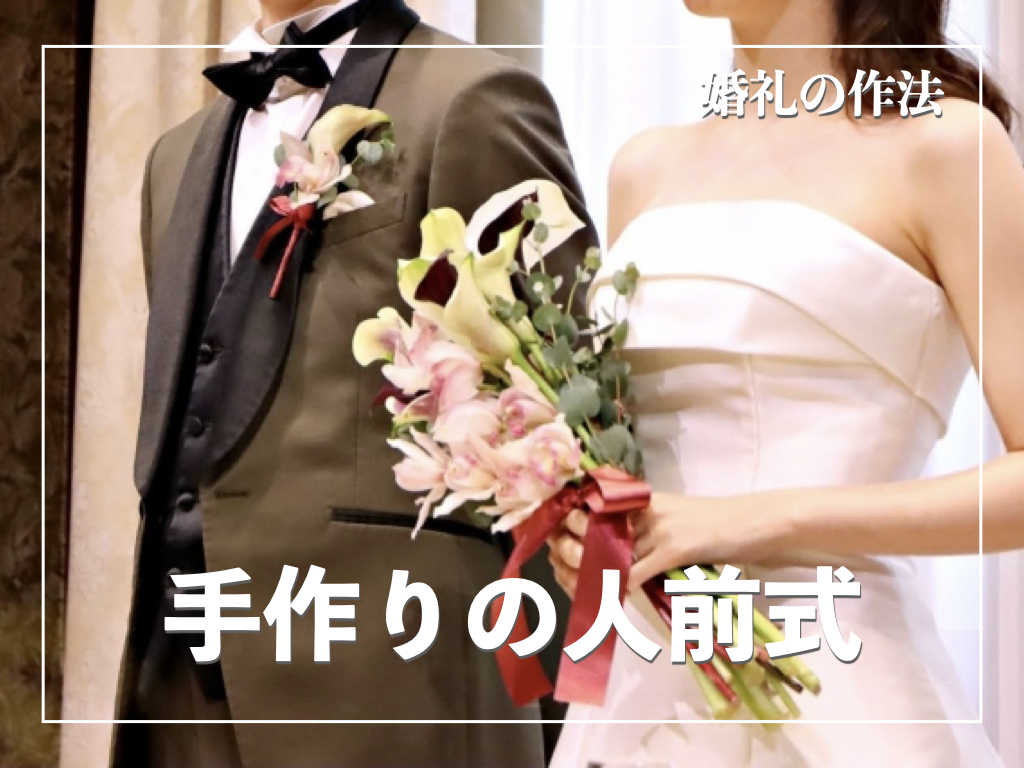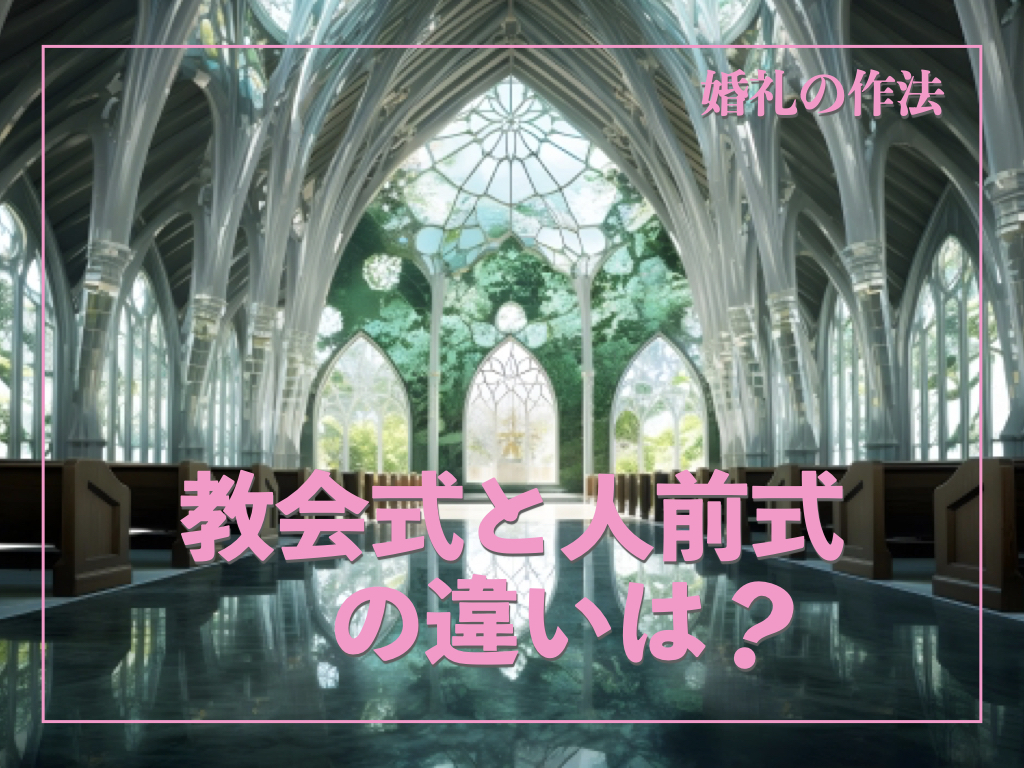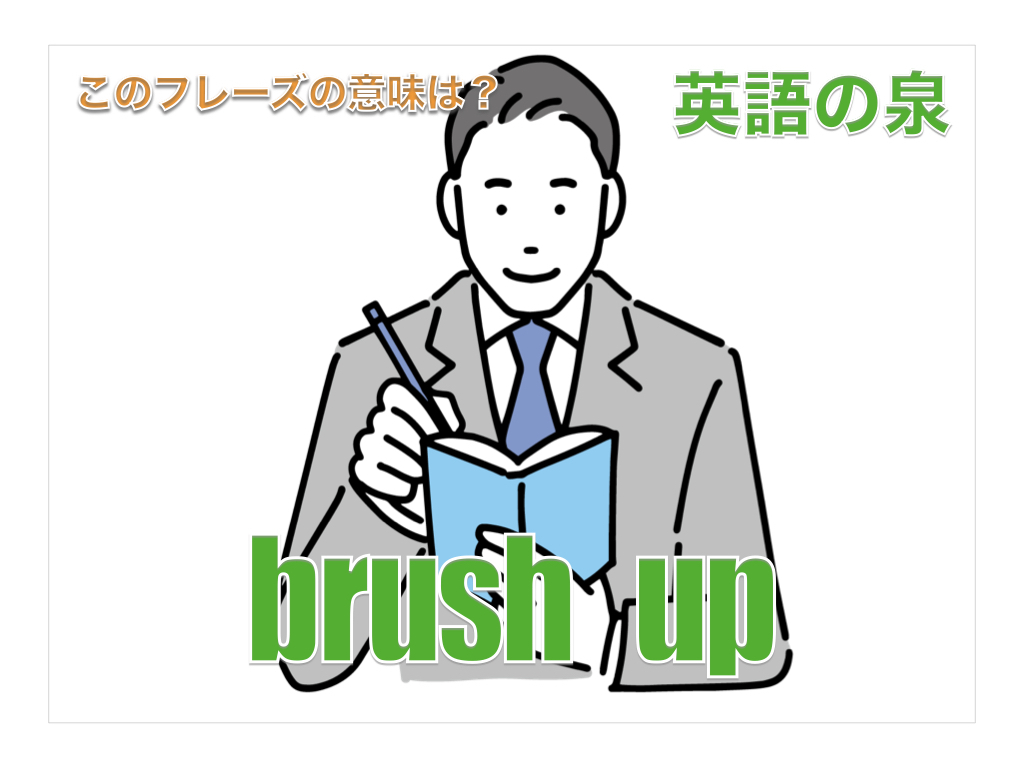自由なスタイルで人気が高まる「人前式」は、ふたりらしさを大切にする結婚式として親世代からも注目されています。特に誓約書や誓いの言葉を自分たちで用意する“手作りの人前式”は、温かみがあり記憶に残るセレモニーです。
本記事では、子どもの結婚式を控える親世代の方へ向けて、人前式の基礎知識から誓約書・台紙の準備、当日の進行、親の関わり方までを解説します。
目次
手作りの人前式とは? 親世代も知っておきたい基本の形
結婚証明書はどうする? 手作りアイテムの工夫
人前式の演出アイデア集|個性が光る工夫とゲスト参加型の例
当日の進行や流れ|親世代が押さえておきたい式の順序
最後に
手作りの人前式とは? 親世代も知っておきたい基本の形
人前式は、宗教的な儀式ではなく、列席者の前でふたりが誓い合う形式の結婚式です。最近では、演出や準備に「手作り」の工夫を取り入れることが増え、個性や感謝の気持ちが自然に表現される場面も見られます。
ここでは、基本的な式の構成や親として知っておきたい考え方を整理します。

「人前式」のスタイルとは?
人前式では、教会式や神前式のような決まった儀式の流れに従う必要はありません。誓いの言葉や進行内容を自分たちで決められるため、会場も屋内・屋外問わず、選択の幅が広がっています。
「手作り」とは、どこまで自分たちで用意するのか?
手作りという言葉から、すべてを自前で準備する印象を受けるかもしれませんが、実際は「ふたりらしさ」を形にする部分を自作することが多いです。具体的には、誓いの言葉や誓約書の台紙、演出小物などポイントを絞って準備します。専門業者のサポートを受けながら、部分的に手作りするケースも増えています。
親はどのように向き合えばいいのか?
人前式では、必ずしも形式にとらわれる必要はありません。ただし、自由な分だけ「どのように進めるのか」が見えづらいこともあるため、事前に内容を共有してもらえると当日の安心感につながります。
「口を出しすぎてはいけないが、まったく無関心にもなれない」と感じる人もいらっしゃるでしょう。ふたりの考えを聞きながら、必要なときに相談に乗る程度の距離感が、親として心地いい立ち位置になります。
「自分たちの時代と違う」と感じたときには、その理由を理解しようとする姿勢が、子どもたちにとっては何よりの支えです。
結婚証明書はどうする? 手作りアイテムの工夫
人前式では、結婚証明書を自作することがあります。素材選びや文言の内容に個性が表れやすいので、式の印象を左右する重要なものです。ここでは、結婚証明書についてご紹介します。
台紙づくりの工夫とおすすめ素材
結婚証明書や誓いの言葉を記す台紙には、市販のテンプレートを使うこともありますが、和紙や生成りの紙など質感のある素材が好まれる傾向があります。
印刷する際には、文字が見えやすく、装飾が過剰にならないよう意識しましょう。和装の式の場合であれば、折り紙をあしらった飾りつけや、水引を添えることで、品のある一枚になります。

結婚証明書に込められる意味と保管の仕方
人前式で用いられる結婚証明書は、公的な効力を持つものではありませんが、ふたりの意思を記した大切な記録になるものです。ゲストの署名を集めたり、家族の名前を記載したりすることで、参加型の演出としても機能します。式が終わった後も、額縁に入れて飾るほか、アルバムに収納するアイデアもあるでしょう。
人前式の演出アイデア集|個性が光る工夫とゲスト参加型の例
人前式は、ふたりの個性や想いを込めた工夫を盛り込みやすいため、参列者と心を通わせる瞬間が多く生まれます。ここでは、近年取り入れられることが増えている演出例を、場面別にご紹介します。
ゲストが参加する「承認の演出」
式の中でゲストが新郎新婦の結婚を「承認」する演出は、人前式ならではの場面です。「承認の拍手」は、誓いの言葉のあとに全員で拍手を送り、ふたりの結婚を見届けます。
ゲスト一人一人に署名をもらう「証明書署名」や、指輪の交換時の「指輪リレー」など、全体の一体感を高める演出も人気があります。
親や親族による「誓いの言葉の問いかけ」
親世代が式に関わる演出の一例に「誓いの言葉の問いかけ」があります。新郎新婦に向かって、将来への意志や感謝を引き出すような言葉を問いかける形式です。
具体例としては、「困難なときでも、ふたりで助け合って乗り越えますか」といった質問を通して、ふたりの言葉を引き出します。親が問いかけ役を務める場面では、控えめながらも温かさが伝わる瞬間となるでしょう。
ふたりらしさを引き出す演出
演出の中には、新郎新婦の趣味や出会いのエピソードにちなんだ小物や背景を活用する工夫もあります。例えば、「旅行好きなふたりが地図を使って結婚証明書を作る」、「趣味の楽器を式中に披露する」といったアイデアです。
親世代にとっては珍しく感じる演出でも、ふたりなりの意味づけがある場合が多いため、事前に話を聞いておくと理解が深まります。
当日の進行や流れ|親世代が押さえておきたい式の順序
親として式当日に安心して臨むためにも、事前に大まかな流れや自分たちの立ち位置を確認しておくことが肝要です。ここでは、当日の一般的な進行例をもとに、親世代が知っておきたいポイントを整理します。

当日によく見られる人前式の流れ
人前式に決まった形式があるわけではありませんが、次のような順序が一般的とされています。
1.開式の挨拶(司会者)
2.新郎新婦の入場
3.誓いの言葉の朗読
4.指輪の交換
5.結婚証明書への署名
6.承認の演出(拍手やゲスト署名など)
7.閉式の挨拶
親が入退場を見守る位置やタイミングは、式場ごとで異なる場合があります。不安なときは、リハーサルや事前の進行表で確認する機会を設けてもらうと安心です。
和装人前式の進行と特徴的な演出
和装での人前式では、「水合わせの儀」など、伝統的な所作を取り入れた進行が加えられることもあります。
ただし、宗教儀式として行なうわけではないため、意味や形式がアレンジされていることもあります。内容に不安がある場合は、事前に進行を確認させてもらうことで誤解が生まれにくくなるでしょう。
最後に
人前式は、伝統的な儀式とは異なりますが、家族やゲストと心を通わせる演出にあふれています。親としては「違う」と感じる部分があっても、まずは話を聞き、意図を理解することでふたりの門出を支えることができるでしょう。
監修/トップウエディング https://top-wedding.jp/
構成・執筆/吉川沙織(京都メディアライン)
https://kyotomedialine.com FB