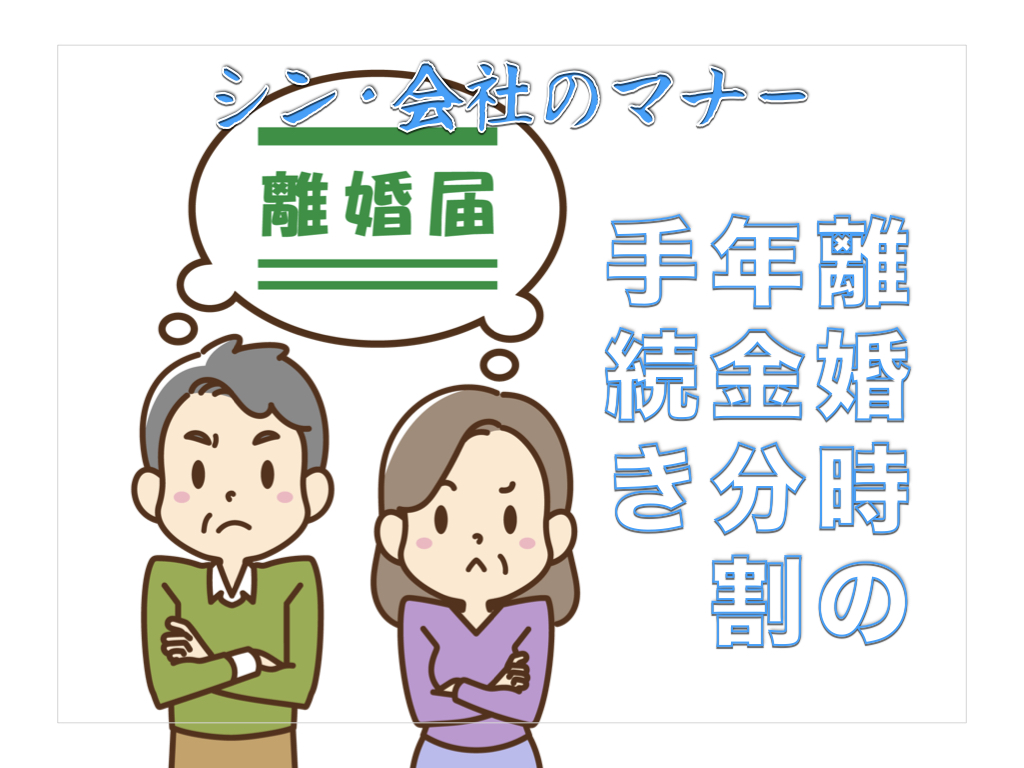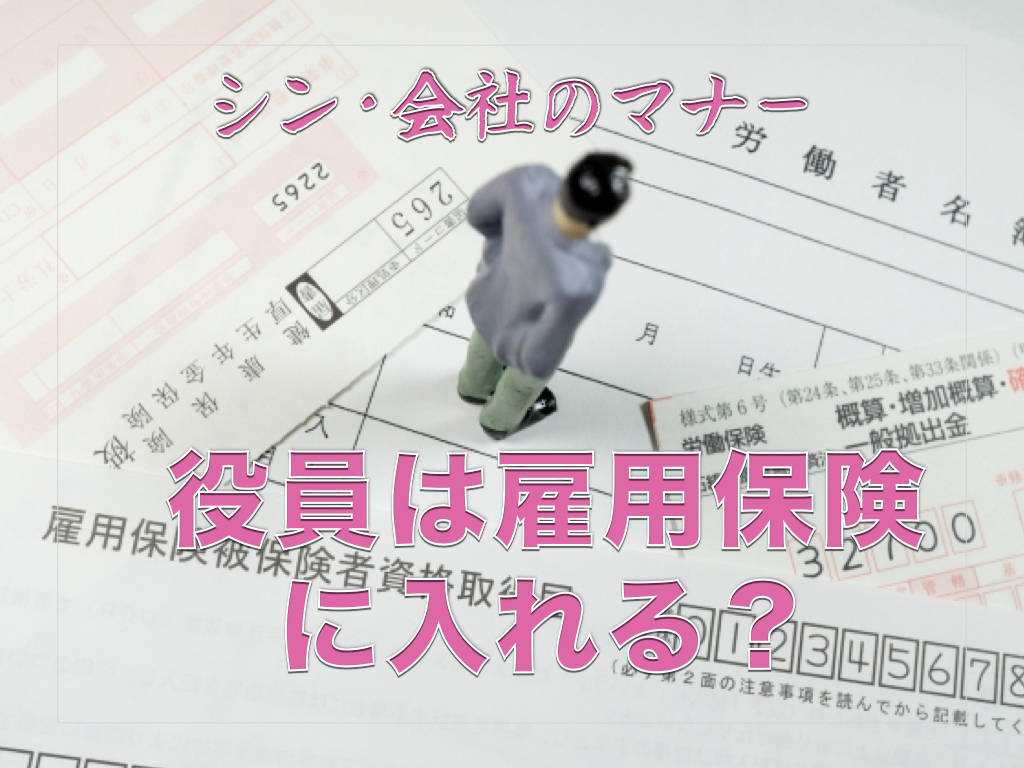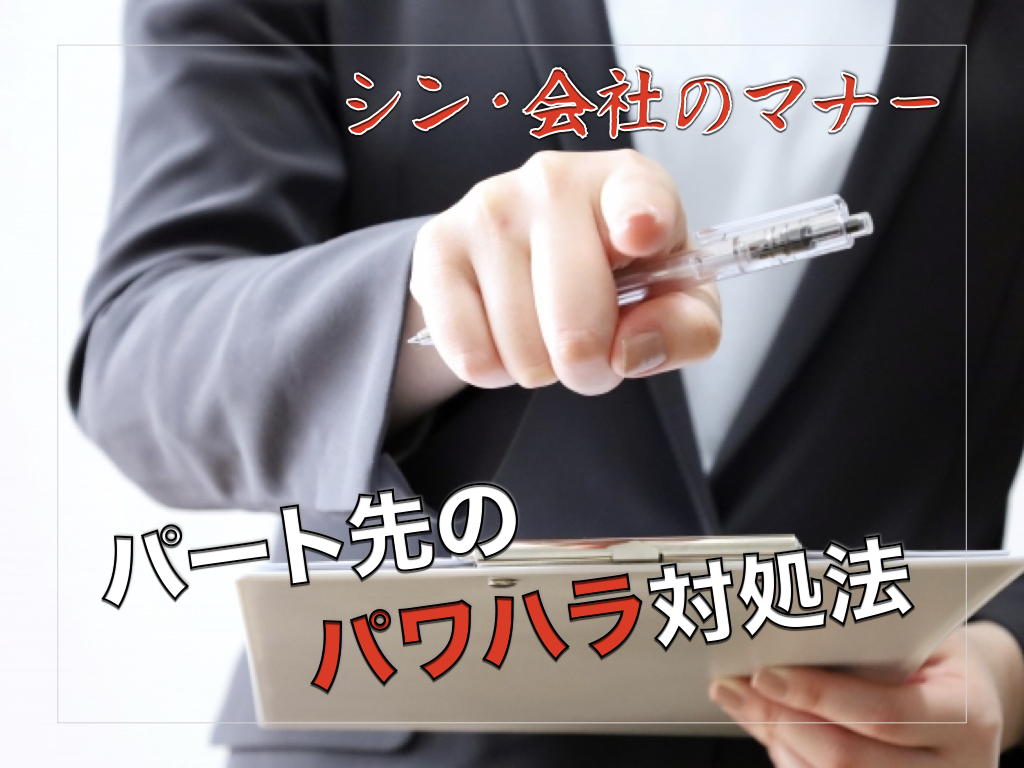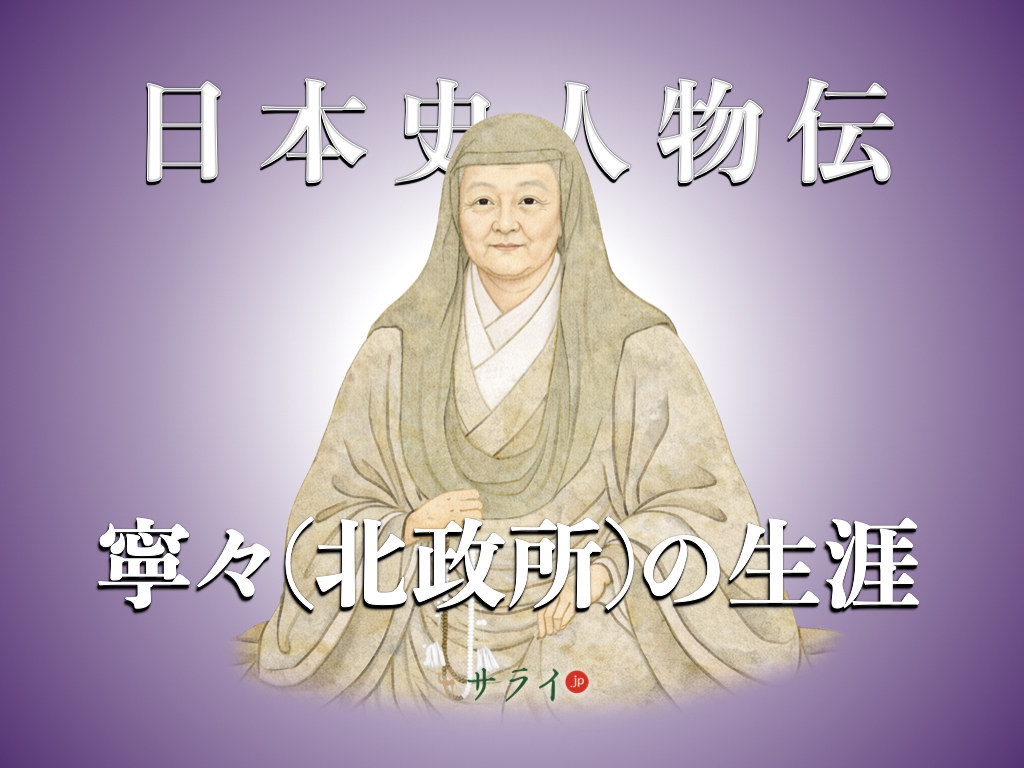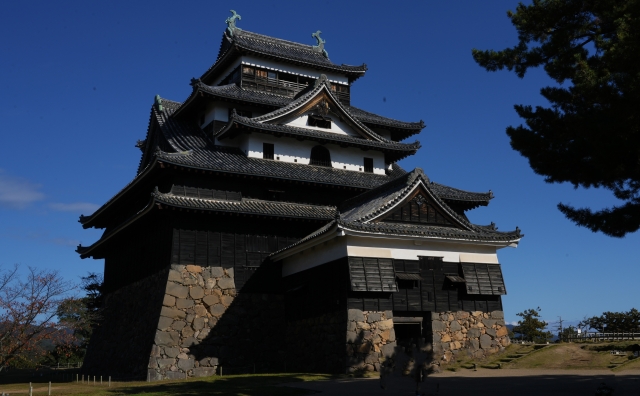多くの会社には就業規則があり、従業員に周知されています。就業規則とは別に賃金規程を整備している会社も少なくありません。賃金規程とは、就業規則と異なるものなのでしょうか?
今回は人事・労務コンサルタントとして「働く人を支援する社労士」の小田啓子が、就業規則と賃金規程について解説していきます。
目次
賃金規程とは? 就業規則との違いをわかりやすく解説
賃金規程の開示義務と違反時の対応策
賃金規程を整備して職場環境を改善
まとめ
賃金規程とは? 就業規則との違いをわかりやすく解説
賃金規程とは一般にどのような内容になっているのでしょうか? 就業規則との関係を含めて見ていきましょう。
賃金規程とは? 基本的な定義と役割を解説
労働基準法では、常時10人以上の労働者(パート・アルバイトを含む)が働いている事業場では、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ることが義務とされています。
さらに必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)も以下の通り、法で決められています。
(1)始業および終業の時刻、休憩時間、休暇、交代制勤務の場合は就業時転換に関する事項
(2)賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り、支払いの時期、昇給に関する事項
(3)退職に関する事項(解雇の事由を含む)
賃金規程とは、(2)の賃金・給与に関する事項についての社内の取り決めをまとめたものです。賃金は労働者にとって非常に重要な事項であり、詳細なルールも多いので就業規則の本則とは別に、賃金規程として整備されているケースが多く見られます。
就業規則と賃金規程の違いはある? 別に作成する意義
就業規則と賃金規程は別物というわけではありません。賃金規程は就業規則の中の一部といえます。
必要事項の漏れがなければ、就業規則のなかに賃金に関する条文を組み込んでもさしつかえありません。けれども、就業規則は労働条件や服務規律・懲戒・安全規程など内容が多岐にわたります。
賃金に関連した規程も数多くあるので、必要な条文を探すのに苦労する場合もあります。そのために、多くの会社では賃金に関する規程だけを別冊として「賃金規程」を作成しているのです。
賃金に関する項目は、変更することが多いものです。就業規則の変更は届出が必要ですが、賃金ルールだけの変更なら、賃金規程の変更届を提出するだけでいいというメリットもあります。
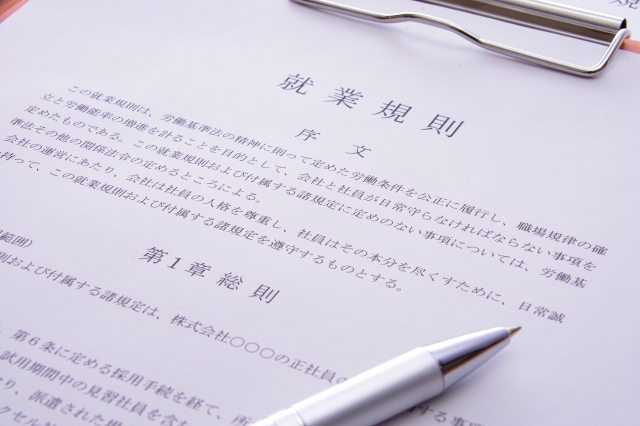
賃金規程の開示義務と違反時の対応策
従業員が賃金規程を見たことがない、周知されていないという会社もあると思います。こうした場合の対応策について解説します。
賃金規程には開示義務がある? 労働者が知っておくべき権利
当然のことながら、社員個別の給与というのは開示する情報ではありません。けれども、賃金規程に記載されているのは、対象となる従業員全員に適用するルールです。
賃金の締め日、支払日、昇給・賞与の時期、時間外労働・休日労働の割増賃金の計算方法など、これらは就業規則の絶対的必要記載事項であり、会社は従業員に開示する義務があります。
就業規則は、労働者に周知させることによって効力を発揮するものなのです。会社は就業規則や賃金規程は、常に閲覧可能な状態にしておかなければなりません。 賃金規程を見たい場合は、堂々と閲覧請求しましょう。
賃金規定を見せてもらえない場合の対処法
賃金規程の閲覧を求めても見せてくれない会社もあるかもしれません。これは単純に、会社の担当者が就業規則の周知義務について知らない場合もあります。
そのため、特別な理由がなければ見せる必要がないと考えている可能性もないわけではありません。その場合は法律で義務があることを伝えるのも一つの方法です。
労働者への「周知義務違反」があると、会社は労働基準監督署から是正勧告を受けたり、罰金などの処罰を課せられることもあります。
閲覧請求は、できるだけ同僚などと一緒に複数ですると良いでしょう。 会社も法的に問題があるとなると、無視することはできなくなります。
賃金規程に違反があった場合の対応策
会社が賃金規程の開示を拒む理由として、規程の内容に不備がある場合もあります。時間単価の設定、割増賃金の計算などに不適切な記述があるのかもしれません。割増賃金の基礎となる単価が低くなるように設定されていたり、法令に違反した割増率になっていることもありえます。また、昇給や賞与に関して従業員が知らない基準が書かれていた例もあります。
会社が賃金規程を閲覧させてくれないときは、労働基準監督署に閲覧を申請することも可能です。申請時には、会社が就業規則を周知させていない状況や閲覧を拒否されたかどうかなどについて伝える必要があります。
会社とのやりとりなどはメモなどを取って記録しておきましょう。会社に法律違反があった場合は、労働基準監督署から是正勧告や指導が入ります。

賃金規程を整備して職場環境を改善
賃金規程を整備することは職場環境の改善に役立ち、会社にとってもメリットがあります。会社・労働者双方のメリットについて見てみましょう。
賃金規程を明確にすることで労働者の安心感が向上
働いても給与がどのように決まるかわからないと、人は意欲を持って働き続けることができるでしょうか?
賃金規程には、給与の日払い方法や時間外・休日の割増賃金の計算方法のほか、給与体系や昇給や賞与などについて記載されています。これらの基準を明確にすることによって、従業員は安心して働くことができ、職場環境の改善につながります。
定期的な見直しと改訂でトラブルを未然に防ぐ
賃金規程も就業規則本則と同様、定期的な見直しが必要です。
賃金に関する法改正は今まで何度も実施されてきました。毎年の最低賃金改定のほか、育児休業中の賃金、時間外勤務の割増率などです。
法改正に気づかず、改訂をしていないと後からトラブルになりがちです。また、各種手当の変更など、給与の社内与ルールが変わることは多いものです。就業規則本則と同様、賃金規程が変わった場合も変更の届出をしなければなりません。
厚生労働省のホームページではモデル就業規則とともに、賃金規程のモデルも公開しています。こうした資料を参考にすることにより、ミスや記載漏れなどを防ぐことができます。
まとめ
賃金に関する規程は就業規則の中でも重要な事項です。賃金規程を就業規則から切り離して作成することで、従業員の誰が見てもわかりやすいものとなります。
会社にとっても賃金のルールを明確にすることにより、労使のトラブルを防止し、従業員のモチベーションを上げるというメリットがあります。
●執筆/小田 啓子(おだ けいこ)

社会保険労務士。
大学卒業後、外食チェーン本部総務部および建設コンサルタント企業の管理部を経て、2022年に「小田社会保険労務士事務所」を開業。現在人事・労務コンサルタントとして企業のサポートをする傍ら、「年金とライフプランの相談」や「ハラスメント研修」などを実施し、「働く人を支援する社労士」として活動中。趣味は、美術鑑賞。
●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com