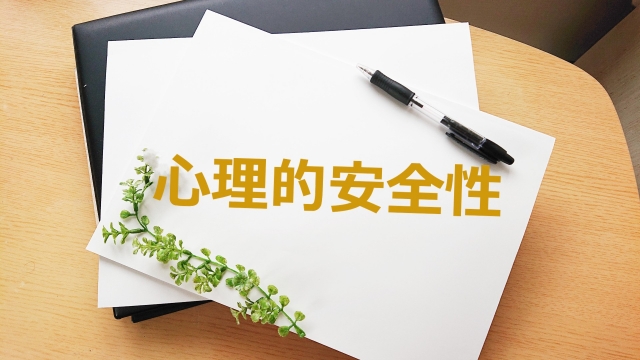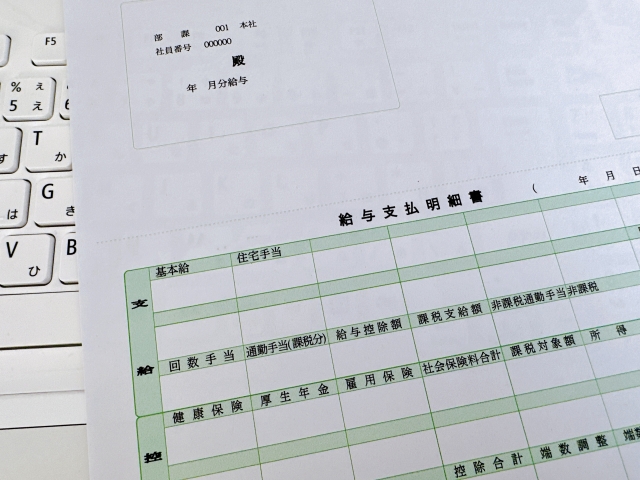マネジメント課題解決のためのメディアプラットホーム「識学総研(https://souken.shikigaku.jp)」が、ビジネスの最前線の用語や問題を解説するシリーズ。
はじめに
「ルールに縛られない、自由な職場」――なんと魅力的な響きでしょう。しかし、あなたの職場で「なぜか会話が噛み合わない」「ささいなことで感情的な衝突が起きる」「人が定着しない」といった問題が起きていませんか? もしかしたら、その原因は「自由」という名の“無法地帯”にあるのかもしれません。
この記事では、一見働きやすいように見える「ルールのない組織」に潜む危険性を、交通ルールでおなじみの「信号機」を比喩に用いて解説します。読み終える頃には、あなたの組織の課題を明らかにし、無用な事故(トラブル)を防ぐための具体的なヒントが得られるはずです。
「自由」の落とし穴。ルールがない職場が危険なワケ
もし、あなたが車が行き交う大きな交差点の真ん中に、信号機も交通整理の警察官もいない状態で立っているとしたらどうでしょう? きっと、どのタイミングで渡ればいいか分からず、立ち往生してしまいますよね。最悪の場合、あちこちから走ってくる車とぶつかって、大事故につながるかもしれません。
実は、ルールがない組織もこれと全く同じ状態なのです。
ルールがないと、何を基準に判断すれば良いのかが分からなくなり、働く人はかえって迷いを増やしてしまいます。そして、それぞれが「自分はこう思う」「普通はこうでしょ?」 という自分だけのルール、いわば「マイルール」に基づいて行動を始めてしまうのです。
例えば、信号機の「赤は止まれ」というルール。これは社会全体の共通ルールなので、ほとんどの人が同じ行動をとります。しかし、これが「黄色」になるとどうでしょう? 「スピードを落として安全に止まろう」と考える人もいれば、「急いでいるから進んでしまえ!」と考える不届きな人もいるかもしれません。ここに、個人の判断、つまり「マイルール」のズレが生まれるのです。
ルールがない、あるいは曖昧な職場とは、この「黄色信号」や、そもそも信号機自体が存在しない交差点のようなもの。良かれと思って取った行動が、他の人の「マイルール」と衝突し、結果として大きなトラブル(事故)を引き起こす危険性を常にはらんでいるのです。
あなたの常識はみんなの非常識? 「マイルール」が引き起こす感情的な衝突
「ルールがない会社」と一口に言っても、実は二つのパターンがあります。
一つは、もともと考え方が近いメンバーが集まっており、わざわざルールを決めなくても「暗黙の了解」で物事がスムーズに進む、奇跡的にうまくいっている状態です。
もう一つは、お互いに深く干渉せず、それぞれの価値観(マイルール)のままに仕事をしている状態です。
しかし、多くの「ルールがない」と評される会社で起きているのは、悲しいかな、それぞれの「マイルール」が激しくぶつかり合っている状態なのです。
考えてみてください。職場の「整理整頓」について。デスクの上が完璧に片付いていないと気が済まないAさんと、資料が山積みでもどこに何があるかを把握できているから問題ない、と考えるBさんがいたとします。AさんはBさんを見て、「なんでちゃんと片付けないんだろう」とイライラしているかもしれません。この「イラッ」とする気持ちこそが、マイルールの違いから生まれる“感情”なのです。
この感情を口に出せば、周りからは「感情的な人だ」と見られます。逆に、ぐっと堪えればストレスが溜まっていきます。このように、個人のこだわりや正義感、つまり「マイルール」が強いほど、他者とのズレに対して感情が生まれやすくなるのです。
職人やクリエイターにこだわりが強い方が多いように、マイルールそのものは、その人の「個性」でもあります。しかし、組織においてその個性が何の共通認識もなくぶつかり合えば、それは新しいものを生み出す化学反応ではなく、ただの不要な摩擦になってしまう場合がほとんどなのです。
信号機に学べ! 組織に必要な「ちょうどいい」ルールのさじ加減
再び、信号機の例で考えてみましょう。もし、見通しの良い一本道に、10メートルおきに信号機が設置されていたらどうでしょう? きっと、ひどい交通渋滞が起きて、前に進むことすら困難になりますよね。逆に、交通量の多い交差点に信号がなければ、事故が多発するのは目に見えています。
組織のルールも全く同じで、多すぎても少なすぎてもいけないのです。そのバランスが非常に重要です。
かつての終身雇用が当たり前だった時代は、多くの人が同じような価値観を共有していたため、細かなルールを設けなくても組織はうまく機能していました。しかし、現代は「多様性」の時代です。様々なバックグラウンドや価値観、つまり、多種多様な「マイルール」を持った人々が一緒に働くようになりました。
このような時代に「うちは自由だから」とルール作りを怠ってしまうと、どうなるでしょうか。それぞれのマイルールが暴走し、自分勝手な判断や利己的な行動につながりかねません。
同じ目的、同じ目標に向かって進むチームだからこそ、「私たちはこの交差点を、このルールで渡ります」という共通認識が必要不可欠なのです。変化の激しい現代社会において、会社の向かうべき方向を示し、メンバーが安心して進むための道しるべとなるルールは、以前にも増して重要になっています。
“無用な事故”を未然に防ぐために、今すぐできること
ここまで読んで、「うちの会社、もしかしてルールが足りないのかも……」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。
もし、あなたの会社が、積極的に採用活動を行っているのであれば、ルールの「明文化」はもはや避けて通れない課題です。新しく入ってきたメンバーは、社内の「暗黙の了解」など知る由もありません。明文化されたルールがなければ、彼らは手探りで進むしかなく、ちょっとした認識のズレがエラーやトラブル、最悪の場合は早期離職といった「事故」につながってしまうでしょう。
今あなたの職場で起きている感情的なやり取りや、頻発するミスは、「ルールがない」からではなく、「本来あるべきルールを明文化していないだけ」が原因なのかもしれません。
まずは、あなたの組織の現状を注意深く見つめ直してみましょう。
・メンバー間で、言葉の定義や仕事の進め方に解釈のズレはありませんか?
・「あの人はいつもこうだから」といった、個人への不満が溜まっていませんか?
・同じようなミスやトラブルが、繰り返し起きていませんか?
もし、一つでも思い当たることがあれば、それがルールを見直す、あるいは新しく作るべきサインです。どのようなルールが必要かは、どのような組織にしたいかによって決まります。最初から完璧なルールブックを作る必要はありません。まずは、事故が起きやすい危険な交差点に、小さな「信号機」を一つ設置することから始めてみてはいかがでしょうか。
識学総研:https://souken.shikigaku.jp
株式会社識学:https://corp.shikigaku.jp/