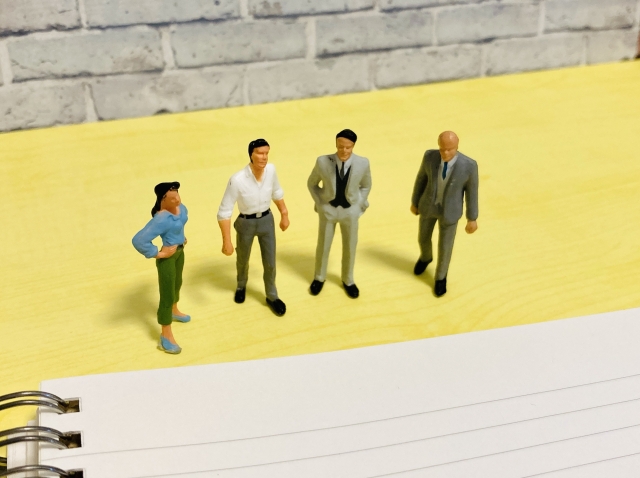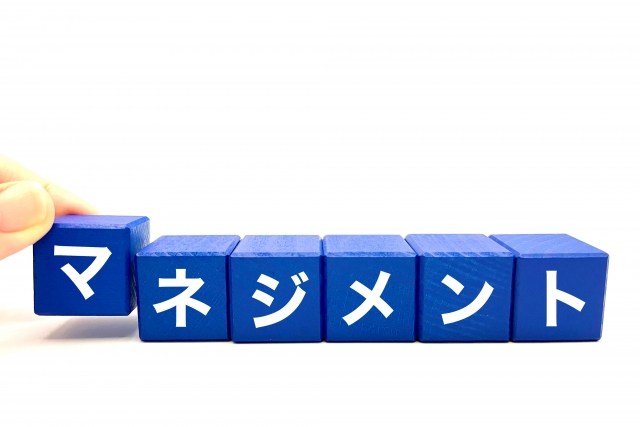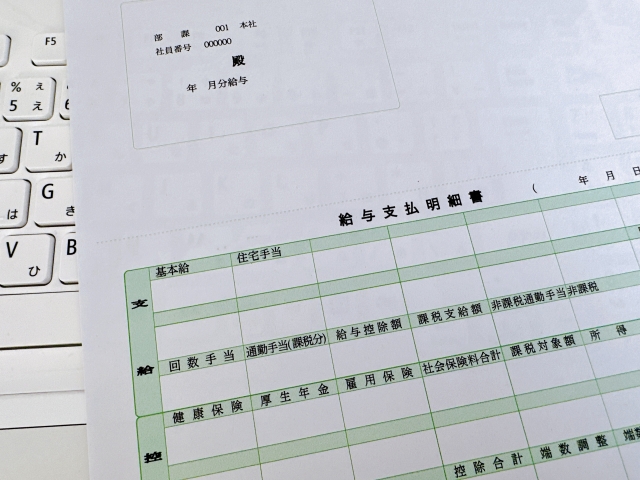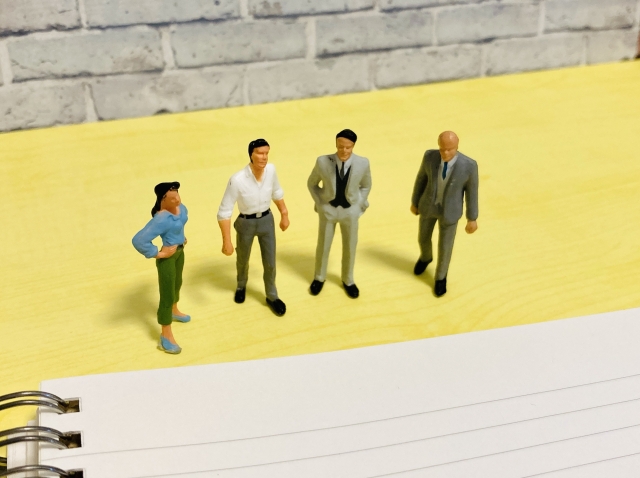
チームとしての成果を上げたい。リーダーとしてはごく当然に思うことでしょうが、なかなかうまくいかないのが現実です。マネジメント課題解決のためのメディアプラットホーム「識学総研(https://souken.shikigaku.jp)でチームの成果を上げる方法を学びましょう。
* * *
「みんな、一生懸命頑張っているのに思うように成果が上がらない。どうすればいいんだろう?」と、頭を抱えているリーダーは多いのではないでしょうか。
この課題に対する一般的な問題点を識学で考えてみたとき、本当の原因と解決するための行動が明確になるはずです。この記事を読んで、問題の表面ではなく、本質と解決のアクションを実践しましょう。そのために、まずは一般的に原因だと言われていることから検証してみましょう。
1.明確な目標の欠如
チームが何を達成すべきか、どの方向に進むべきかが明確でない場合、メンバーの努力が分散してしまい、成果が上がりにくくなり、目標が曖昧だとモチベーションも低下しがちということが原因だと一般的には言われます。
果たしてそうでしょうか? 目標を明確にしたが、部下が動かない。余計にモチベーションが下がっているといった経験はありませんか? 上司が明確に目標設定したと思っている目標は、必ずしも部下にとって明確ではないということです。
では、目標が明確というのはどういうことでしょうか? その目標はいつまでに達成すべきでしょうか? また、部下はその達成するイメージがあるでしょうか?
人は行きたいと思っていても行けないと思っている時点で行動が止まります。100階建てのビルを想像してください。ビルの屋上まで今から5分以内に来てくださいと指示を出しました。ただし、そのビルは階層ごとに行けるエレベーターが別々です。どのエレベーターがどこにあってエスカレーターや階段、地図の場所がわからない人がその期限内に到達できるでしょうか?
答えは否です。迷っている間に5分を過ぎる、もしくは初めから5分以内で行くことをあきらめる、という状況が起きますよね。これでは、目標が目標ではなくなっています。部下自身が自分の中で下方修正したということです。そうならないためには何が必要でしょうか?
事前に地図を渡しておく必要がありますよね。その上でどのルートを通れば時間内に到達できるかを前もって考えさせておく必要があります。渡すだけで考えさせずにいれば渡していないのと同じです。また、考えさせずに上司がルートを教えたとしたら、イレギュラーが発生した場合、教えられたルートしか知らないため、たどり着けなかった理由を他人のせいにします。
重要なことは、結果に到達するまでに必要な手段と結果を設定し、到達できるイメージを事前に持たせるということです。上司ができると思っていることと部下ができると思っていることは違って当たり前です。それを正しく事実で認識を合わせるからこそ頑張る方向が一致するのです。
2.コミュニケーション不足
メンバー間やリーダーとの情報共有が不十分だと、誤解やタスクの重複、進捗の遅れが生じ、効果的なコミュニケーションがなければ、チームとしての連携が取れないということが言われますが、そもそもの問題点は「そのコミュニケーションは本当に必要か?」というところにあります。
もし、お互いの認識が異なるところで、コミュニケーションという価値観の対決が行われているとするならば、成果を上げるために必須である「時間」というものを無駄に消費している状態です。コミュニケーションによって価値観のすり合わせが必要だと思っていること自体が成果を上げる事から離れていっていることに気づく必要があります。
上司は部下よりも成果に繋げるための最短ルートを知っているからこそ、上司なのではないでしょうか? その経験によってしか埋まらない溝をコミュニケーションで埋めようという思考が最大の敵です。
コミュニケーションを取ることによって共通認識を持つことは可能ですが、それでは時間がかかります。ポイントは共通事項を先に決めた上でそこで起きた問題を基に報告、事実を基に修正することが本来必要なコミュニケーションとなります。
お互いの意見を言い合うようなコミュニケーションは、自分と違う意見同士がぶつかり合うことによって、より長い時間を必要とし、余計に連携が取れなくなっていく原因になっている事に気づく必要があります。
3.役割と責任の不明確さ
誰が何を担当するのかがはっきりしていないと、仕事の漏れや責任の押し付け合いが発生します。これにより効率が落ち、パフォーマンスが低下します。
そのため、誰がその結果に責任を持つのか、また、責任がある人がその責任を果たすために持つべき権限を持っていなければいけません。責任だけが明確でもその責任を果たせるだけの能力や決定権がなければその責任は果たせないため、責任放棄の思考になってしまうからです。
責任の所在をはっきりさせ、かつ、その責任を果たすための権限を与えることで、チームは責任に向かって走れるはずです。 あとはチームが成果を上げるために必要な各役割が設定できているかがポイントです。
4.スキルやリソースの不足
チームメンバーに必要なスキルが欠けていたり、業務を遂行するためのツールや予算が不足している場合、期待される成果を出すのは難しくなる、というように考えがちになりますが、この考えは間違いです。
人の成長段階でスキルが足りないことや企業に潤沢な予算がないことは当たり前に起こることだからです。それを言い訳にするのであればチームで成果を上げることは不可能です。
必要なことは、目標を達成できるとイメージすることと、その本人の今のスキルより少し上のチャレンジをチーム全員がすることです。かつ、予算をかけずに達成確率を上げるためにはスピードを上げることが最善となるため、前述の1~3が重要となります。
5.モチベーションの低下
報酬、承認、成長機会の不足など、メンバーのやる気を維持する要素が欠けていると、積極性や生産性が下がります。チームの士気が低いと全体のパフォーマンスも落ちる。その上、これらの要因は相互に関連している場合も多く、特定の問題を解決することで他の部分も改善されることがあるため、状況に応じて優先順位をつけて対処するのが効果的だという意見が散見しますが、こちらは捉え方を間違うと危険です。
重要なことはモチベーションは与えられない、その個人の中で自己発生するものだということです。要するにやる気スイッチなんてものはないということです。
出来ないことを訓練し、出来るようになり、その出来ることの範囲が拡大するからこそ、様々な失敗の確率が下がり、成果を上げるまでの時間が短縮するという結果に繋がります。 そのためには、前述の1~4の成長やロスタイムの最小化の環境を与え、新たなチャレンジを部下がする上での迷いを排除するコミュニケーションこそが必要です。
まとめ
ここまで解説してきたように、チームの成果を上げるための一般論は、捉え方を間違えると、成果を上げるどころか、離職を促進させ、より成果を下げることにもなりかねません。この記事が、成果の上がるチーム作りに役立てば幸いです。
【この記事を書いた人】
識学総研 編集部/株式会社識学編集部です。『「マネジメント」を身近に。』をコンセプトに、マネジメント業務の助けになる記事を制作中。3,000社以上に導入された識学メソッドも公開中です。
引用:識学総研 https://souken.shikigaku.jp/
コンサルタント紹介はこちらから https://corp.shikigaku.jp/introduction/consultant