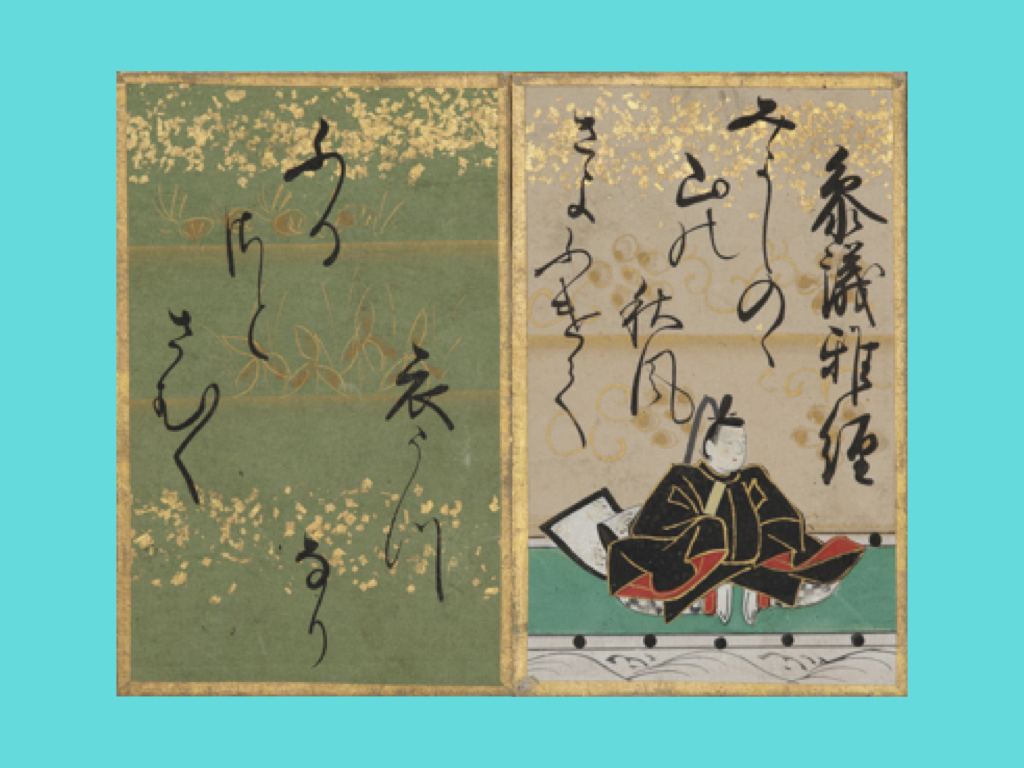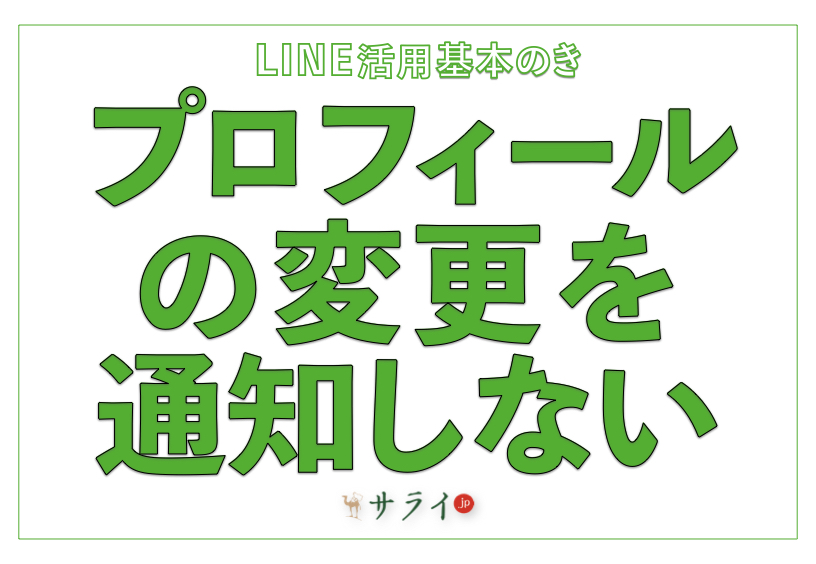マネジメント課題解決のためのメディアプラットホーム「識学総研(https://souken.shikigaku.jp)」が、ビジネスの最前線の用語や問題を解説するシリーズ。今回は、オーディション番組から組織マネジメントについて考察します。
オーディション番組の面白さの核にある「成長」と「競争」
近年、オーディション番組がこれほどまでに人気を博している最大の要因は、参加者の目覚ましい「成長」にあります。審査員から求められる結果が出せなければ脱落するという「平等な条件」の下、参加者たちが「熾烈な競争環境」の中で才能を開花させ、大きく成長していく姿は、視聴者に驚きと感動を与えてくれます。
この「成長」と「競争」のメカニズムは、まさに組織マネジメントにおいて社員の育成を考える上で非常に重要なヒントを与えてくれます。
では、このオーディション番組の面白さを、識学の観点から掘り下げ、部下が成長する正しい競争環境の作り方やマネジメントについて考えていきましょう。
識学では、部下を成長させるためには「部下において結果が明確な状態を作ること⇒結果設定、結果に向かうことへの認識のズレをなくす」ことが重要であると伝えています。オーディション番組の成功は、まさにこの識学の原則に沿っていると言えます。
オーディション番組×識学=「成長する競争環境」の作り方
(1)公平な「位置=役割」の明確化
オーディション番組では、参加者は練習生という共通の「位置」に属し、それぞれが歌、ダンス、ラップといった特定の「役割」を担い、そのパフォーマンスで評価されます。そして、審査員、トレーナー、MC、視聴者といった、それぞれが番組内での明確な「位置」と「役割」を持っています。
これと同じことが会社組織においても言えます。組織内で自分の役割や責任範囲が不明確だと、無駄な衝突や責任の押し付け合いが生じ、成長の機会が奪われます。 そのため、社員が会社の中でどのポジションを担う人間なのかを明確にすることが重要です。
●実践のポイント
・役割と責任の明確化:各社員のポジションにおける役割と、その責任範囲を具体的に定めます。
・権限と責任の一致:役割に応じた適切な権限を与え、その範囲内で裁量と責任を持たせることで、主体的な行動を促します。
(2)明確な「目標」と「結果」の共有
オーディション番組では、「合格する」「デビューを勝ち取る」といった明確な目標が参加者全員に共有されています。そして、その目標達成に向けた「審査基準」「投票数」といった共通のルールや具体的な結果指標が提示され、それに基づき公平な評価が行われます。
同様に、組織において目標や評価基準が曖昧だと、社員はどこに向かって頑張ればいいか分からず、行動に迷いが生じます。オーディション番組のように、誰が見てもわかる明確なゴールがあることで、社員は迷いなく努力できます。評価者も誰が目標達成に近づいているのか、目標達成ができてない場合は達成に向けてどんな努力が必要なのかをお互い握ることができます。
●実践のポイント
・具体的で測定可能な目標設定:「〇月までに〇〇を達成する」「△△のスキルを習得する」など、数値で測れる目標を設定しましょう。
・結果指標の透明化:誰が見ても納得できる評価基準や、目標達成度を測る指標を明確に示し、定期的にフィードバックを行います。
識学では上記の実践ポイントを【結果の完了=PDCAを回す】と呼んでおり、【結果の明確化⇒不足の明確化⇒不足を埋める為の行動変化⇒次の約束(結果設定)】を実施することにより出来なかったことが出来るようになる、つまり、社員が自分の役割に集中し、成長できる環境を作ることが重要であるとお伝えしております。
(3)得られる成果の明確な提示
合格すれば「デビュー」「スターへの道」という「メリット」が、不合格であれば「脱落」という「デメリット」が明確に存在します。この明確な結果が、参加者の努力を最大化させます。
会社組織においても目標達成の先に具体的なメリット(報酬、昇進、成長機会など)が、未達成の場合に具体的なデメリット(評価の低下、改善点の指摘など)があることを社員が明確に認識していることで、行動意識が生まれます。
また、結果が出た社員には、公明正大に評価し、それにふさわしい報酬や昇進の機会を与えます。逆に、成果が出ない社員には、感情的にならず、原因と具体的な改善策を提示し、必要であれば適切な指導を行います。
●実務のポイント
・評価と連動した報酬・昇進制度:「入社後〇年で〇〇のスキルを習得し、△△の役割を担えるようになれば、待遇がこうなります」といった具体的な成長曲線とメリットを提示し、社員の自己成長意欲を刺激します。
・改善点(次のチャンス)の明確化:成果が出なかった場合も、感情的にならず、具体的な改善点と期待される行動を明確に伝えます。
(4)無駄な「感情」を排し、「事実」に基づく評価
オーディション番組では、参加者の人間ドラマが描かれる一方で、最終的な判断は「パフォーマンスの質」や「投票数」といった客観的な「事実」に基づき下されます。審査員も、個人的な感情ではなく、プロとしての基準で評価します。
組織のマネジメントにおいて、「好き嫌い」や「個人的な感情」で評価や判断をしてしまうと、メンバーは不公平感を感じ、不信感が生まれます。オーディション番組のように、「事実」に基づいた評価を徹底することで、社員は結果を受け入れやすくなり、次への行動に繋げることができます。また、感情を排する為には社員と適切な距離感を置くことも重要です。
●実務のポイント
・客観的な評価基準の徹底:「感覚的」ではなく、数値や具体的な行動など、誰が見ても分かる客観的な事実に基づいて評価を行います。
・感情マネジメントの意識:マネージャー自身が感情に流されず、常に冷静に事実に基づいた判断を下すことを意識します。
まとめ
オーディション番組が示す「平等な条件」「明確な目標」「熾烈な競争」は、まさに人が最大限のパフォーマンスを発揮し、成長するための最適な環境を創り出していると言えるでしょう。識学では、人が最高のパフォーマンスを出すためには「認識のズレ」をなくし、明確な状態を作ることが重要だと考えます。この観点から、オーディション番組の成功要因を組織運営に落とし込むと社員の成長=組織の成長に繋げられます。
あなたの組織でも、これらの要素を取り入れ、社員が自律的に成長し、組織全体の力を高める「オーディション番組的」なマネジメントを実践してみてはいかがでしょうか。
識学総研:https://souken.shikigaku.jp
株式会社識学:https://corp.shikigaku.jp/