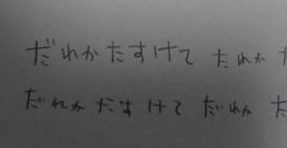加害者に怒鳴ろうとするも力が入らない
病院に行き妻の遺体と対面する。用心深い妻は、フルフェイスのヘルメットをかぶっていたので、顔はキレイだった。すぐに息を吹き返しそうだったという。
「ドラマとかでは慟哭するんだろうけど、実際に遭遇すると、全然わからないんですよ。感情が全く出てこない。心の底が空いて、感情やエネルギーがザーッと流れていく音がするようにも感じました」
加害者は20代前半の若者で、自家用車で上京したばかりだった。すぐに、故郷から両親が飛んできた。
「3人が泣きながら謝っているのを、遠い世界のことのように聞いていました。心の中には『お前らのせいで妻は死んだんだ!』と叫ぶ私がいるのに、体に力が入らず、叫ぶことさえできない。どうしていいかわからず、涙が流れるままになっていました」
警察や加害者、保険会社とのやり取り、葬式の手配は、息子夫婦と、妻の妹夫婦がやってくれた。康夫さんが現実を認知し始めたのは、妻の死から1週間後。
「ほぼ、何も食べず、風呂にも入らず妻のベッドで寝ていました。そうしないと呼吸ができないように感じられた。ダイニングテーブルに、はずしたエプロン、作るつもりだったピクルスの空瓶、カフェオレが半分入ったマグカップがある。ベランダを見れば、妻が干した洗濯物が風になびいて動いている。さっきまでそこにいたのに、もういない。その重さに、膝を抱えて床に這いつくばる。すると床には妻の足跡があるんです。何もかもに妻の跡が残っている。これは辛いですよ」
10日後にやっと仕事に復帰し、それからは全てを忘れるため、猛烈に働いた。
「集中している間は忘れられるので、早朝から深夜まで働いていました。タクシーで酒を飲みながら帰宅し、死んだように眠る。それでも、妻の死と向き合えず、生きるほどに空しくなっていくんです」
そんな康夫さんに転機が訪れたのは、奥様が亡くなってから2年目のこと。
「体重も10キロ落ち、アルコール依存症になりかけていた時に、彼女の先輩の女性から、配偶者を亡くした人々の自助グループを紹介されたんです。グループディスカッションをするのですが、会話の途中で不意に涙が出ても、誰も奇異な目線をよこさない。涙を流し、慟哭しながら、自分の思いを語る。すると、心が少しだけ落ち着いていくのです」
妻の死は「ただ、そこに彼女がいない」という時間の積み重ねだった。
「今もエンジニアの息子に、『タイムマシンを開発して、事故の日の朝に連れて行ってくれ』と本気で言ってしまう。息子もそのたびに目を真っ赤にしている。やっぱり癒えないんですよ。今も、夜眠る前に『愛しているよ。ありがとう』って言うんです。生きているうちにもっと伝えたかった。後悔するほど、自分の中に暗い穴が広がっていくような気持ちになるんです。悲しみの夜明けはまだ来ませんし、来てほしくない自分がいます」
取材・文/沢木文
1976年東京都足立区生まれ。大学在学中よりファッション雑誌の編集に携わる。恋愛、結婚、出産などをテーマとした記事を担当。著書に『貧困女子のリアル』『不倫女子のリアル』(小学館新書)がある。