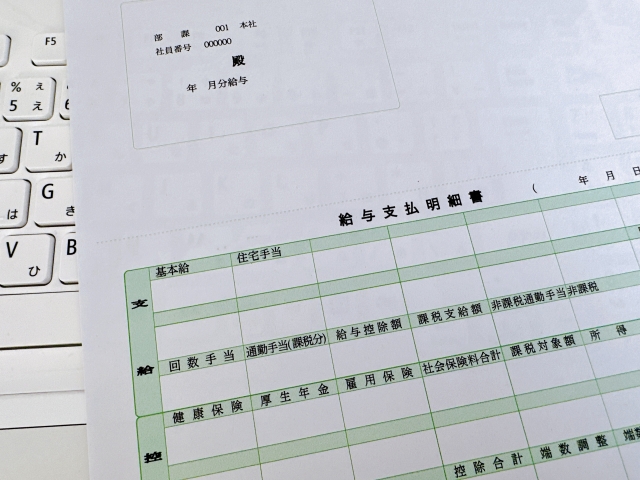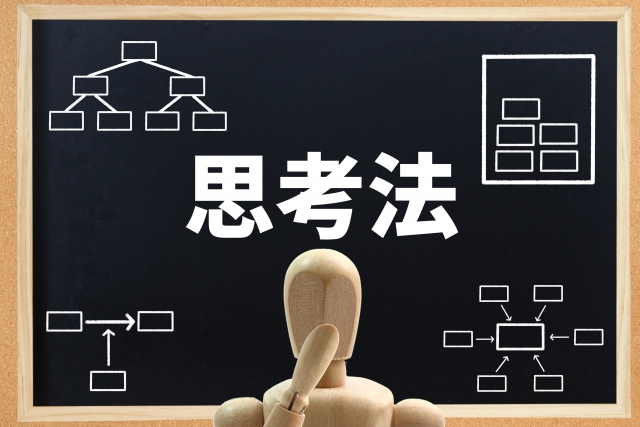マネジメント課題解決のためのメディアプラットホーム「識学総研(https://souken.shikigaku.jp)」が、ビジネスの最前線の用語や問題を解説するシリーズ。
みなさんはどんなコミュニティに所属していますか? なぜ自分がそのコミュニティの一員だと認識していますか? 普段はあまり深く考えることのないテーマではないでしょうか。しかしながら、会社などの組織運営をしていく上で理解しておくべき重要な理論なのです。この記事では、人とコミュニティの関係を体系的に説明し、社員や部下の方にチームへの帰属・所属意識を高める具体的な方法をお伝えします。
人がコミュニティを作る理由
「家族」「友達関係」「学校」「会社」「地域」……ほとんどの人は複数のコミュニティに所属しながら人生を歩んでいます。無人島でたった一人で生きている人でもない限り、必ず何らかのコミュニティに所属しています。
人はなぜコミュニティを作ろうとするのでしょうか? 正解は「ヒト(ホモ・サピエンス)だから」です。トンチではありません(笑)。大昔、我々の祖先がまだ一介の野生動物だったころ、周りには1対1ではまず敵わないような大きくて強い動物がたくさんいました。そこで、ヒト(の祖先)は生き残るために“群れ”を作るようになりました。これが功を奏してヒトは地球の支配者とも呼べる存在になったわけです。なのでコミュニティを作るのはヒトの習性ということになります。
人はなぜ自分がコミュニティの一員だと認識するのか?
この記事を読んでいただいているみなさんも「〇〇家の一員」「〇〇会社の社員」など自分がコミュニティに所属している認識をお持ちかと思います。みなさんはなぜそのコミュニティの一員だと認識しているのでしょうか?
あるコミュニティとそれ以外を区分けする境界線の正体は「ルール」です。つまり、そのコミュニティにおける取り決めを守っているかどうかということです。例えば、会社であれば、雇用契約、就業規則、出勤場所、お昼は食堂で食べるなど、大きいものから小さいものまで様々なルールが存在し、それによって外部と線引きされています。家族でも、あいさつ、門限、食事のときはテレビを見ないなど、何かしらのルールが存在するでしょう。
人はその組織のルールを守ることで、組織の一員であると強く認識する生き物です。また、自分と同じルールを守っている人を“仲間”と認識するクセもあります。
例えば、東京と大阪ではエスカレーターの立ち位置が違います(東京は左、大阪は右)。東京で右側に立っている人を見ると「大阪の人かな?」と思ったりすると思いますし、逆もしかりです。そして、また、そう思うということは、自分のコミュニティのルールから外れている人を「自分とは違うコミュニティの人である」と認識しているということです。
※エスカレーターは、2列乗りや立ち止まって乗ることが推奨されています。
海外旅行先でふと日本語が聞こえてくると、見ず知らずの人であっても「あ、日本人かな」と親近感がわくことがあります。テレビから故郷の方言が聞こえてくるとついつい見てしまうのも仲間意識が働いているからと言えます。
会社組織における帰属・所属意識の重要性
会社組織をうまく運営していく上で、社員に会社への帰属・所属意識をしっかりと持ってもらうのは非常に大切なことです。チームの一員である意識のない人がチームのために何かやるでしょうか? やらないですよね。
実はこれが多くの経営者やマネージャーがはまってしまう落とし穴です。マネジメントの一般論として、部下に目標設定をして、その達成に導くのがマネージャーとしての重要な役割になります。ですが、そもそも帰属・所属意識のない、もしくは希薄な人にいくら目標を与えても全力でやるわけがありません。「自分はこのチームの一員であり、チームのために行動しないといけない立場なんだ」という土台がないままにいくら目標を与えて、上司が必死にサポートしたとしても部下は動いてくれません。
帰属・所属意識の醸成方法
では、どうすれば社員や部下は会社やチームへの帰属・所属意識をもってくれるのでしょうか? 答えはすでにご説明しました。
「ヒトはそのコミュニティにおけるルールを守ることで、自分がその組織の一員であると認識し、かつ同じルールを守っている人のことを仲間であると認識する生き物」です。なので、ルールを明確に設定して、徹底的に守らせればよいのです。ここで設定するルールはどんなものでもかまいません(組織のリーダーが“守ってほしい”と考えるもの)。
例えば、「出社時に大きな声であいさつする」「会議には全員が時間通りに必ず出席する」など、なんでもOKです。暗黙裡にほぼできているようなことをあえて言語化して意識してもらってもよいのです。
コツはルールとして設定したからには徹底的に守ってもらうことです。門限を決めたのに子供が全く守らない、それを親も容認していては意味がないですよね。会社や上司が決めたルールを守らせるという当たり前がちゃんとできているかどうかで、その組織の業績や運営難易度が大きく変わります。
「帰属・所属意識を醸成する」という目的の他にも、「会社が決めたことを守る」という規律のある組織にすること、「守らなければ上司から指摘される」という上下の関係を正しく認識させることなど、会社組織においてメリットとなることがたくさん発生します。
一方で、ルール違反を指摘しても直らない・直す気がない人はコミュニティに置き続けることはできません。例えば、日本国内で日本の法律を守らない人が大勢いたらどうでしょうか? 国という組織の規律が崩壊して体制を保てないですね。会社でも同じことです。決まり事を守らないと組織の規律が乱れる原因となりますし、真面目にやっている人がバカを見ることになります。
部下の成長を願い、それに伴って会社を強く大きくしていきたいのであれば、まずは帰属・所属意識という土台を作った上で、目標を与えて成長させていく必要があります。
まとめ
ヒトは習性として群れをつくる生き物です。自分が群れの一員かどうかはその群れのルールを守っているかどうかが意識上での判断基準になります。
チームへの帰属・所属意識がないままに目標を与えても全力でやろうとはしません。リーダーはまずそのチームで守るべき約束=ルールを明確に設定し、メンバーに守らせてください。そうすることで、自然とチームとしての一体感が出てくるはずです。これは是非とも騙されたと思って一度やってみてください。みなさんが率いるチームが強固な一枚岩になるかは、リーダーであるみなさんのアクションにかかっています。
識学総研:https://souken.shikigaku.jp
株式会社識学:https://corp.shikigaku.jp/