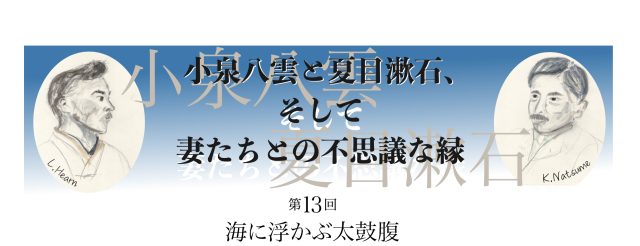
小泉セツ&小泉八雲の夫婦がモデルとなった朝の連続テレビ小説『ばけばけ』が注目されています。実はその小泉夫妻と、明治の文豪・夏目漱石と妻・鏡子は、不思議と重なり合う縁で結ばれていた、というのをご存じでしょうか。
夏目漱石の研究家として知られ、『心を癒す漱石の手紙』などの著書を持つ、作家で雑誌編集記者の矢島裕紀彦さんによると、二人の文豪とその妻たちには奇縁と呼ぶしかないような不思議なつながりがあると言います。
多数の文献や手記を紐解きながら、二組の夫婦の知られざる素顔を全26回の連載にて紹介します。
スポーツはひと通り楽しんだという漱石。一方、泳ぐのが大好きだったという八雲。第13回では八雲がどれほど泳ぐのが好きだったかがわかる、微笑ましいエピソードをご紹介します。
文・矢島裕紀彦
『坊っちやん』の素材となった嘉納治五郎との会話

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が、米国の出版社ハーパー社の通信記者として英国籍汽船アビシニア号に乗って横浜港に到着したのは、40歳を間近に控えた明治23年(1890)4月4日のことだった。晴れた空に鯉の吹き流しが泳ぎ、富士の霊峰が遠く夢幻の如く美しく輝いて見えたという。7年後の夏、松江中学の教え子・藤崎八三郎のサポートを得て、憧れの富士登山を果たすことは、八雲自身まだ予見していない。藤崎によれば、八雲は「富士山が曾て悪い事をしてその霊が他に逃げた。然るに何処に行っても床の間に、自分の人相書の姿が掲げられてあるのを見て、逃がるべからざる事を知り元に戻った」という昔話にも強い興味を示していたという。
八雲は船の旅を好んだ。洋行する汽船の中で、留守宅の妻・鏡子宛ての手紙に「船はきらい」「横浜出帆以来眼が余程くぼみ申候」などと愚痴めいたことを書きつけていた夏目漱石とは対照的だ。
八雲は水泳が得意で、とくに海で泳ぐのが大好きだった。
原点は、幼少時の体験。アイルランドのトレモアで水泳を習い、体全体が水に包まれるような浮揚感を味わった。その甘美な思い出が、八雲を水泳好きにした。その後、変遷する暮らしの中でも、八雲は海に親しんだ。ニューオリンズ時代はグランド島に通い、ニューヨーク時代はカリブ海のマルティニーク島に長く滞在し、その印象記『仏領西インド諸島の二年間』をまとめている。
横浜到着後まもなく、契約条件への不満から八雲は通信記者を辞任。『古事記』の英訳者としても知られる帝国大学(現・東京大学)教授のチェンバレンの支援で、英語教師として松江に赴任した。9月から教壇に立って、翌明治24年(1891)、初めての夏休みを迎えると、八雲の水泳好きの血が騒いだ。
2度目の出雲大社詣でを主軸とした旅で、旅館「いなばや」が海岸(稲佐の浜)近くに建てた別館「養神館」に2週間ほど滞在、毎日のように海水浴を楽しんだ。旅館の娘の宇家タニの談話が伝わっている。
ヘルン先生が初めて大社、当時の杵築においでの時は、わたしが十八、九のころでした。(略)二十四年の夏には、稲佐で海水浴をなさいました。ちょうど、いなばやが稲佐へ養神館を建てて経営していましたので、わたしと女中のクニさんとがお世話に行くことになりました。初め松江の中学校の西田先生がいっしょで、あとから奥さまがおいででした。(略)たいへん泳ぎが上手で、波の荒い日でも笹子島から向こうまで泳いで行かれるので、奥さまとわたしたちは、お帰りになるまでずいぶん心配しましたが、先生は平気で(略)朝と午後の二回、必ずお泳ぎになりました。(梶谷泰之『へるん先生生活記』)
宇家タニはこの談話の中で、八雲のセツへの熱愛ぶりも語っている。人力車に乗ってセツが旅館に到着したとき、待ち焦がれていた八雲は玄関前まで走っていき、セツを俥から抱き下ろしたというのである。
八雲はこのあと続けて、セツとともに加賀の潜戸を訪ねている。加賀の浦から潜戸まで1里余り(約4キロ)の海路で、八雲は小船の後になり先になりしながらさまざまな泳法を披露して、ご満悦だった。さらに、いったん船に戻って、複雑に波が打ち寄せている新潜戸の岩屋に入ると、海流の中を泳ぎたくなって、船から海に飛び込もうとして、船頭や周囲の者に止められた。
『日本瞥見記』(『知られぬ日本の面影』)に八雲は書く。
下をさしのぞくと、ちょうどガラス越しに物を見るように、深い水底にある岩礁が手にとるように見える。わたくしは、この岩屋の中を泳ぎぬけて、冷たい影のなかを海流のままに浮き流れて行ったら、これに過ぎる快事はなかろうと思った。ところが、わたくしが今やまさに飛びこもうとすると、船中の人たちが、いっせいに声を荒げて止めだてた。
「死んでしまうに! 半年ほど前に、ここへ飛びこんだ人があったが、今に行き方知れずだ! ここは神さまの海だでな!」
それでもなお思い留まらぬ様子の八雲を、最後に押しとどめたのは、船頭の発した「サメ!」の一語だった。神への畏れより鮫への恐怖。案外とリアリストの八雲なのである。
小泉八雲が来日し横浜の青空を見上げていた頃、漱石はまだ一高に在籍する一介の学生の身である。
学生時代の漱石は、なかなかの実践的スポーツマンだった。仲間うちには、ボート競技で優勝する中村是公(のちの満鉄総裁)のような強者もいた。漱石自身は何かひとつの種目に打ち込んで腕を上げ、選手として大活躍するといったことはなかったが、ボート、水泳、テニス、乗馬、登山(八雲来日の翌年夏には富士登山も敢行)など、ひと通りのスポーツを楽しんだ。自らの学生時代を振り返った談話『一貫したる不勉強』の中でも、本人が
どちらかと云へば運動は比較的好きの方であつた
と語っている。
一高の前身である大学予備門時代からの同級生だった太田達人は、漱石に誘われてよく両国の水泳場まで通ったという。また、『予備門時代の漱石』という一文にこう記す。
講道館へは、夏目君は通つたかしら? 何でも遣りよつたから、多分少しは通つたらうと思ひます。
まだ髭のない青年の漱石が、柔道着を着て相手と組み合っている姿を思い浮かべると、ちょっと微笑ましい気持ちになる。なお、講道館柔道の創始者である嘉納治五郎は、教育家でもあり、のちに熊本五高の校長として八雲を熊本に迎え、さらに東京高等師範学校校長として漱石を同校へ招き入れてもいる。漱石の談話が残る。
丁度私が大学を出てから間もなくのこと、或日外山正一氏から一寸来いと言つて来たので、行つて見ると、教師をやつて見てはどうかといふことである。(略)外山さんは私を嘉納さんのところへやつた。嘉納さんは高等師範の校長である。其処へ行つて先づ話を聴いて見ると、嘉納さんは非常に高いことを言ふ。教育の事業はどうとか、教育者はどうなければならないとか、迚(とて)も我々にはやれさうにもない。今なら話を三分の一に聴いて仕事も三分の一位で済まして置くが、その時分は馬鹿正直だつたので、さうは行かなかつた。そこで迚も私には出来ませんと断はると、嘉納さんが旨い事をいふ。あなたの辞退するのを見て益(ますます)依頼し度(たく)なつたから兎に角やれるだけやつてくれとのことであつた。さう言はれて見ると、私の性質として又断り切れず、とう/\高等師範に勤めることになつた。(『時機が来てゐたんだ――処女作追懐談』)
漱石と嘉納治五郎のこのときのやりとりは、後年、小説『坊っちやん』の中の主人公と校長の会話に生かされることになる。また、外山正一は、先に記した通り、こののち小泉八雲を帝国大学講師に招いた人物でもある。
焼津の荒波と素朴な土地柄を愛した八雲

さて、小泉八雲は、東京帝国大学に招聘され、明治29年(1896)9月から始めた東京暮らしでも、夏休みとなると毎年のように、子らを連れて静岡・焼津に出かけている。避暑というより、海で泳ぐのが目的だった。
はじめ、元松江中学の教諭で浜松中学へ転任していた田村豊久が、舞坂や浜松の海岸へ案内したが、普通の海水浴客なら大歓迎の遠浅の海を八雲は好まなかった。焼津へ案内すると、海が深く波が荒いので喜んだという。定宿にしたのも、旅館ではなく、山口乙吉という男が営む魚屋の2階。正直で誠実な乙吉の人柄や、焼津という土地の昔ながらの素朴さが大いに八雲の気に入っていた。
焼津の八雲は、自分が泳ぎを楽しみつつ、長男の一雄にも熱心に指導した。その際、まずは水に楽々と浮く術を教え込んだ。両手を頭の下で組み合わせ、両足を揃え、臍下丹田に力を込めて水面にプカリと仰向けに浮くのである。一雄のみならず、同行の人にあまり水泳が得意でない人がいれば、八雲は同じようにした。のちに一雄は綴る。
父の持論は、人間は如何に水に馴れた者、泳達者といえども結局は陸上に棲息すべく祖先以来癖付けられている動物に過ぎないのだから、水中に棲む動物と比して泳いでも疲労が早い。水中で疲れた時、どんなに泳達者でも水の中で休むことを知らなければ溺れてしまう。水の中で休息するのはこの浮く術あるのみだ。だからまず水泳を覚えるに先だち浮くことを会得しておけと申すのです。(『父「八雲」を憶う』)
浮くことがある程度身につくと、次は背泳ぎの練習へ。やがて一雄は、《土地の漁師の子等と比して何等遜色なきまでに泳ぎ得る子供》になったという。
八雲はその言葉通り、ゴム製の浮袋の如く軽々と浮くことのできる人だった。すでに40代半ばを過ぎた八雲は太鼓腹だったというが、その太鼓腹が海の上にふわりと浮いている姿を思い浮かべると、なんだか楽しい気分になる。
あるとき、湘南の鵠沼で、友人の米国海軍主計大佐で屈強な体躯のミッチェル・マクドナルドと泳いだときも、豪壮な泳ぎのスピードではマクドナルドに譲っても、ふうわりと軽く水上にいつまでも身を浮かせているのは八雲だったという。ふたりと一緒に鵠沼の水泳を楽しんだ雨森信成はこう記している。
鵠沼に遊んだあの午後のひとときを、私は忘れることができない。ぼくらはみんなで浜辺に下りていった。天気は絶好だった。(略)ぼくらは裸になって、打ち寄せる波の中に身をおどらせる。ぼくらは泳いだ。水泳の達人であったラフカディオは、わが技を見よとばかりに水中で何度も宙返りを打った。みながみな御機嫌は最高だった。(『人間ラフカディオ・ハーン』)
私はここで、漱石の愛弟子・芥川龍之介の一高時代の同級生だった菊池寛(文藝春秋創業者)の言葉を思い出す。香川・高松の海の近くで生まれ、小学1年から7~8年ほど、古式泳法・水府流の先生について泳ぎの稽古をしたという菊池寛は、「心臓のつづく限り泳いでみせる」と豪語していた。菊池寛の水着姿の写真が残るが、これもなかなか立派な恰幅である。そして、菊池寛も小泉八雲も、実は心臓に弱点を持っていた――。
* * *

矢島裕紀彦(やじま・ゆきひこ)
1957年、東京都生まれ。早稲田大学政経学部卒。作家・雑誌編集記者。文学、スポーツ、歴史など幅広いジャンルをフィールドに“人間”を描く。著書に『心を癒す漱石の手紙』『文士の逸品』『文士が愛した町を歩く』『鉄棒する漱石、ハイジャンプの安吾』『ウイスキー粋人列伝』『著名人名づけ事典』『こぼれ落ちた一球』『石橋を叩いて豹変せよ』『あの人はどこで死んだか』など多数。グランドセイコー広告の掌編小説シリーズ『時のモノ語り』で2018年度朝日広告賞朝日新聞特別賞受賞。https://atelier1328.com
(この連載を通しての主な参考文献)
『漱石全集』全28巻、別巻1(岩波書店、1993~1999年)/夏目鏡子述・松岡譲筆録『漱石の思い出』(文春文庫、1994年)/夏目伸六『父・夏目漱石』(文春文庫、1991年)/夏目伸六『父・漱石とその周辺』(芳賀書店、1967年)/高浜虚子『回想子規・漱石』(岩波文庫、2002年)/松岡陽子マックレイン『漱石夫妻 愛のかたち』(朝日新書、2007年)/荒正人『増補改訂漱石研究年表』(集英社、1984年)/江藤淳『漱石とその時代』第1部~5部(新潮新書、1970~1999年)/『新潮日本文学アルバム夏目漱石』(新潮社、1983年)/『別冊國文学 夏目漱石事典』(学燈社、1990年)/『夏目漱石の美術世界』(東京新聞、NHKプロモーション、2013年)/出久根達郎『漱石先生とスポーツ』(朝日新聞社、2000年)/江戸東京博物館・東北大学編『文豪・夏目漱石』(朝日新聞社、2007年)/平岡敏夫『「坊つちやん」の世界』(塙新書、1992年)/恒松郁生『漱石 個人主義へ』(雄山閣、2015年)/小泉節子、小泉一雄『小泉八雲 思い出の記 父「八雲」を憶う』(恒文社、1976年)/小泉八雲、平井呈一訳『日本瞥見記』上・下(恒文社、1975年)/小泉八雲、平井呈一訳『東の国から・心』(恒文社、1975年)/小泉八雲、平川祐弘編『怪談・奇談』(講談社学術文庫、1990年)/小泉八雲、池田雅之編訳『虫の音楽家』(ちくま文庫、2005年)/『明治文学全集48 小泉八雲集』(筑摩書房、1970年)/小泉時共編『文学アルバム小泉八雲』(恒文社、2000年)/小泉凡監修『小泉八雲、開かれた精神の航跡。』(小泉八雲記念館、2016年)/池田雅之監修『別冊太陽 小泉八雲』(平凡社、2022年)/池田雅之『小泉八雲』(角川ソフィア文庫、2021年)/田部隆次『小泉八雲』(北星社、1980年)/長谷川洋二『八雲の妻』(今井書店、2014年)/関田かをる『小泉八雲と早稲田大学』(恒文社、1999年)/梶谷泰之『へるん先生生活記』(恒文社、1998年)/池野誠『松江の小泉八雲』(山陰中央新報社、1980年)/工藤美代子『神々の国』(集英社、2003年)/工藤美代子『夢の途上』(集英社、1997年)/工藤美代子『聖霊の島』(集英社、1999年)/平川祐弘編『小泉八雲回想と研究』(講談社、1992年)/平川祐弘『世界の中のラフカディオ・ハーン』(河出書房新社、1994年)/熊本大学小泉八雲研究会『ラフカディオ・ハーン再考』(恒文社、1993年)/西川盛雄『ラフカディオ・ハーン』(九州大学出版会、2005年)/西成彦『ラフカディオ・ハーンの耳、語る女たち』(洛北出版、2024年)/池田雅之『日本の面影』(NHK出版、2016年)/ラフカディオ・ハーン『小泉八雲東大講義録』(KADOKAWA、2019年)/芦原伸『へるん先生の汽車旅行』(集英社インターナショナル、2014年)/嵐山光三郎『文人暴食』(新潮文庫、2006年)/河東碧梧桐『子規を語る』(岩波文庫、2002年)/『正岡子規の世界』(松山市立子規記念博物館、1994年)/『子規全集』18巻、19巻(講談社、1979年)/『志賀直哉全集』第8巻(岩波書店、1999年)/『芥川龍之介全集』第4巻(岩波書店、1996年)/瀬沼茂樹『評伝島崎藤村』(筑摩書房、1981年)/矢島裕紀彦『心を癒す漱石の手紙』(小学館文庫、2009年)/矢島裕紀彦『鉄棒する漱石、ハイジャンプの安吾』(NHK生活人新書、2003年)/矢島裕紀彦『文士が愛した町を歩く』(NHK生活人新書、2005年)/矢島裕紀彦『文士の逸品』(文春ネスコ、2001年)




























