
小泉セツ&小泉八雲の夫婦がモデルとなった朝の連続テレビ小説『ばけばけ』が注目されています。実はその小泉夫妻と、明治の文豪・夏目漱石と妻・鏡子は、不思議と重なり合う縁で結ばれていた、というのをご存じでしょうか。
夏目漱石の研究家として知られ、『心を癒す漱石の手紙』などの著書を持つ、作家で雑誌編集記者の矢島裕紀彦さんによると、二人の文豪とその妻たちには奇縁と呼ぶしかないような不思議なつながりがあると言います。
多数の文献や手記を紐解きながら、二組の夫婦の知られざる素顔を全26回の連載にて紹介します。
文豪と言われる夏目漱石も小泉八雲も、それぞれにコンプレックスやハンディキャップを抱えていました。第7回では、それらを乗り越え、文章へと昇華した二人に迫ります。
文・矢島裕紀彦
見た目よりも中身を磨いていった漱石
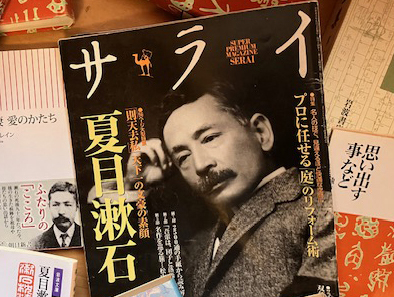
夏目漱石は、鼻の頭にアバタがあった。
明治3年(1870)に太政官で「種痘令」が布告されたのを受けて、漱石は4~5歳の頃、腕に種痘を受けた。幼くして養子に出され、塩原金之助と名乗っていた頃のことだ。ところが、この種痘がもとで却って疱瘡をわずらうことになり、かゆみを我慢できずに顔中を掻きむしったため、鼻の頭とほっぺたにアバタが残ってしまったのである。
象徴的に見れば、西洋近代との初めての接触が孤独な幼児にもたらした、小さいが、しかし容易に消えることのない傷跡であったと言えるのかもしれない。
鏡子との見合いのときも、鏡子本人はもちろん、同席した母親や給仕役をつとめた妹の時子の目線も漱石の鼻の上に注がれた。仲立ちをした紹介者のもとに見合い写真を持参した漱石の兄が、「これは大変きれいに写っているが、あばたはありませんよ」とわざわざ断っていったと、伝えられていたためだった。おそらく、「写真はきれいに修正してあるけれど、あばたが少しあります」とでも言うべきところを、紹介者が言い間違えたらしかったが、その妙な言葉つきが、鏡子たちの頭にこびりついてしまっていた。
見合いが終わって漱石を玄関から送り出したあと、おきゃんな時子が鏡子に言った。
「ねえ、ちょいと、お姉さん、夏目さんの鼻の頭、横から見ても縦から見てもでこぼこしているのね。あれ、確かにアバタじゃない」
「そう、私もそう思ったわ」
鏡子が相槌を打ち、母親もほっと解放されたような気分で同調する。それを、父親の中根重一が「そんなこというもんじゃない」と、たしなめたという。
鏡子が《非常に渋好みのくせに大のおしゃれ》と語っているように、漱石はなかなかのスタイリストだった。それだけに余計に、このアバタはずっとコンプレックスとしてつきまとっていたかもしれない。英国留学への途上、万博開催中のパリから鏡子へ出した手紙にも、
当地ニ来テ観レバ男女共色白ク服装モ立派ニテ(略)小生如キアバタ面ハ一人モ無之(これなく)候
という記述がある。だが、漱石は、ただねじけて打ちひしがれっぱなしになるのでなく、コンプレックスをバネに、負けん気を養い、内面を磨いた。

漱石のデビュー作にしてベストセラーとなった『吾輩は猫である』には、こんな一節も読める。
主人は痘痕(あばた)面である。(略)吾輩は主人の顔を見る度に考へる。まあ何の因果でこんな妙な顔をして臆面なく二十世紀の空気を呼吸して居るのだらう。昔なら少しは幅も利いたか知らんが、あらゆるあばたが二の腕へ立ち退きを命ぜられた昨今、依然として鼻の頭や頬の上へ陣取つて頑として動かないのは自慢にならんのみか、却ってあばたの体面に関する訳だ。(略)主人は折々細君に向つて疱瘡をせぬうちは玉の様な男子であつたと云つて居る。浅草の観音様で西洋人が振り反つて見た位奇麗だつた抔(など)と自慢する事さへある。成程さうかも知れない。たゞ誰も保証人の居ないのは残念である。
ここでは、自己のコンプレックスを戯画化して笑い飛ばし、作品の中にユーモラスに昇華させている。実際、漱石はなかなかの好男子であった。次男の伸六が長じて、祇園の芸妓に学生時代の父漱石の写真を見せると、こんなやりとりになったという。
「へえ、これがあんたはんのお父はんの写真どすか。あんたはんより、よっぽどええ男どすな」
「しかしだな、これにゃアバタは写ってないんだぜ」
「へえ、そんなにアバタがおありやしたか…。そやかて、やっぱり、ええ男どすがな」
「聴く力」が研ぎ澄まされていった八雲
小泉八雲の肖像写真を見ると、決まって左向きの横顔か、左下方に視線を伏せた斜めからのショットである。夫婦ふたりの写真でも、学校で大勢の人間と写した集合写真でも、これは変わらない。
八雲は幼くして両親と離れ、敬虔なカトリック教徒であった大叔母サラ・ブレナンのもとで育てられた。その大叔母の意向で、13歳のときイングランド北東部ダラム市近郊の全寮制の神学校セント・カスバート・カレッジ(アショー校)に入学した。16歳のある日、校庭でジャイアント・ストライド(回旋塔)という遊具であそんでいたとき、飛んできたロープの結び目で左眼を強打し、失明してしまった。以来、正面を向いた肖像写真は撮ろうとしなかったのである。
こうして八雲は、目にハンディキャップを抱えたが、視ること以外の感覚は却って研ぎ澄まされていった。同校の厳格な宗教教育と僧侶の偽善的なふるまいに反発を覚え、多神教の世界に共感を強めたのも、同じ頃であった。思えば、八雲の生まれ故郷のギリシアの神話にも多くの神様たちが登場しているのだった。
導かれるように神々の棲む「出雲の国」へ赴き、松江で迎えた朝を音で綴る印象記の、なんと生き生きしていることか。これも八雲の「聴く力」が研ぎ澄まされた成果であったろう。
松江で、朝寝ていると響いてくる最初の物音は、ちょうど枕につけた耳の下に、どきんどきんと、大きく、ゆっくりと波打って聞こえる、あの心臓の脈搏に似た音だ。(略)この音は、ほかでもない、米を搗く太い杵の音なのだ。(略)この音は、日本人の生活のなかにあるあらゆる物音のうちで、ことに哀れ深いもののように、わたくしには思われる。じっさい、この音は日本の国の脈搏の音だ。この杵の音のつぎに、洞光寺という禅宗の寺にある大きな釣鐘の音が、町の空にひびきわたる。これが鳴ると、つづいてわたくしの家のじき近くの、材木町にある小さな地蔵堂から、朝の勤行を告げる寂しい太鼓の音がきこえだす。やがて、いちばんあとから、早出の振り売り八百屋の呼び声が「ダイコやい! カブやカブ!」、それから炭をおこす焚きつけの木を売りにくる女の哀れっぽい声が「モヤや、モヤ!」と呼んでくる。(『日本瞥見記』)
また、八雲本人は顔立ちにコンプレックスを持っていたが、のちに妻となるセツは初対面からそうは感じなかったようだ。高い鼻は形がよく、女性的な細面で、広い額は利口そうで、良いほうの目には柔和な光が感じられたという。
その後の読書や執筆で酷使したこともあって、八雲は右目も極端な近視となった。それでも、特製の脚高の机に目をこすりつけるような姿勢で、原稿を書き続けた。逆境にもめげず、自ら志した仕事に邁進した八雲だった。後年、セツは次のように回想している。
ペンを取って書いています時は、眼を紙につけて、えらい勢いでございます。こんな時には呼んでも分りませんし、何があっても少しも他には動きませんでした。あのような神経の鋭い人でありながら、全く無頓着で感じない時があるのです。(『思い出の記』)
ある日の深夜には、ランプから黒煙が立ち上って臭いとともに室内に充満し、息ができぬほどになっているのに、カサカサとペン先で音を立てながら一心不乱に書き続けていて、セツが駆けつけ、ひと騒動となったこともあったという。
松江の小泉八雲記念館を訪れて、そこに保存・展示される八雲遺愛の机や椅子を眼前に見ると、胸に迫るものがある。
そのようにして仕事に取り組む思いと覚悟を、八雲は友人で創作の協力者でもあった雨森信成あての書簡の中にこんなふうに綴っている。
人の考えが成功するか否かについて、心配は無用です。思い切って発表するがよいのです。遂には世間がその価値を認めるようになるでしょう。――仮にそれが著者の姿が街頭から消えてしまった後であろうとも。時が安っぽい成功の過ちや愚かしさを淘汰して、真実を守ってくれます。真実は竜舌蘭と同じで、花が咲くまでに長い時間を要します。しかしそれだけその花は貴いといわなければなりません。
美しい文章である。
私はふと、ラテン語の「ars longa,vita brevis.」(アルス・ロンガ, ウィータ・ブレウィス)という言葉を想起する。これは、もとは古代ギリシアの医師ヒポクラテスの言葉で、一般に「芸術は長し、人生は短し」と解釈される。漱石はこのラテン語の言葉を自筆で書いて印章にし、自身が装幀デザインした『こころ』の単行本の「見返しの裏へつける判」として使った。最近では、音楽家の坂本龍一が愛した言葉としても知られる。
漱石は門弟たちへの手紙の中に、こんな志も綴っていた。
死ぬか生きるか、命のやりとりをする様な維新の志士の如き烈しい精神で文学をやつて見たい。
余は吾文を以て百代の後に伝へんと欲する。
* * *

矢島裕紀彦(やじま・ゆきひこ)
1957年、東京都生まれ。早稲田大学政経学部卒。作家・雑誌編集記者。文学、スポーツ、歴史など幅広いジャンルをフィールドに“人間”を描く。著書に『心を癒す漱石の手紙』『文士の逸品』『文士が愛した町を歩く』『鉄棒する漱石、ハイジャンプの安吾』『ウイスキー粋人列伝』『著名人名づけ事典』『こぼれ落ちた一球』『石橋を叩いて豹変せよ』『あの人はどこで死んだか』など多数。グランドセイコー広告の掌編小説シリーズ『時のモノ語り』で2018年度朝日広告賞朝日新聞特別賞受賞。https://atelier1328.com
(この連載を通しての主な参考文献)
『漱石全集』全28巻、別巻1(岩波書店、1993~1999年)/夏目鏡子述・松岡譲筆録『漱石の思い出』(文春文庫、1994年)/夏目伸六『父・夏目漱石』(文春文庫、1991年)/夏目伸六『父・漱石とその周辺』(芳賀書店、1967年)/高浜虚子『回想子規・漱石』(岩波文庫、2002年)/松岡陽子マックレイン『漱石夫妻 愛のかたち』(朝日新書、2007年)/荒正人『増補改訂漱石研究年表』(集英社、1984年)/江藤淳『漱石とその時代』第1部~5部(新潮新書、1970~1999年)/『新潮日本文学アルバム夏目漱石』(新潮社、1983年)/『別冊國文学 夏目漱石事典』(学燈社、1990年)/『夏目漱石の美術世界』(東京新聞、NHKプロモーション、2013年)/出久根達郎『漱石先生とスポーツ』(朝日新聞社、2000年)/江戸東京博物館・東北大学編『文豪・夏目漱石』(朝日新聞社、2007年)/平岡敏夫『「坊つちやん」の世界』(塙新書、1992年)/恒松郁生『漱石 個人主義へ』(雄山閣、2015年)/小泉節子、小泉一雄『小泉八雲 思い出の記 父「八雲」を憶う』(恒文社、1976年)/小泉八雲、平井呈一訳『日本瞥見記』上・下(恒文社、1975年)/小泉八雲、平井呈一訳『東の国から・心』(恒文社、1975年)/小泉八雲、平川祐弘編『怪談・奇談』(講談社学術文庫、1990年)/小泉八雲、池田雅之編訳『虫の音楽家』(ちくま文庫、2005年)/『明治文学全集48 小泉八雲集』(筑摩書房、1970年)/小泉時共編『文学アルバム小泉八雲』(恒文社、2000年)/小泉凡監修『小泉八雲、開かれた精神の航跡。』(小泉八雲記念館、2016年)/池田雅之監修『別冊太陽 小泉八雲』(平凡社、2022年)/池田雅之『小泉八雲』(角川ソフィア文庫、2021年)/田部隆次『小泉八雲』(北星社、1980年)/長谷川洋二『八雲の妻』(今井書店、2014年)/関田かをる『小泉八雲と早稲田大学』(恒文社、1999年)/梶谷泰之『へるん先生生活記』(恒文社、1998年)/池野誠『松江の小泉八雲』(山陰中央新報社、1980年)/工藤美代子『神々の国』(集英社、2003年)/工藤美代子『夢の途上』(集英社、1997年)/工藤美代子『聖霊の島』(集英社、1999年)/平川祐弘編『小泉八雲回想と研究』(講談社、1992年)/平川祐弘『世界の中のラフカディオ・ハーン』(河出書房新社、1994年)/熊本大学小泉八雲研究会『ラフカディオ・ハーン再考』(恒文社、1993年)/西川盛雄『ラフカディオ・ハーン』(九州大学出版会、2005年)/西成彦『ラフカディオ・ハーンの耳、語る女たち』(洛北出版、2024年)/池田雅之『日本の面影』(NHK出版、2016年)/ラフカディオ・ハーン『小泉八雲東大講義録』(KADOKAWA、2019年)/芦原伸『へるん先生の汽車旅行』(集英社インターナショナル、2014年)/嵐山光三郎『文人暴食』(新潮文庫、2006年)/河東碧梧桐『子規を語る』(岩波文庫、2002年)/『正岡子規の世界』(松山市立子規記念博物館、1994年)/『子規全集』18巻、19巻(講談社、1979年)/『志賀直哉全集』第8巻(岩波書店、1999年)/『芥川龍之介全集』第4巻(岩波書店、1996年)/瀬沼茂樹『評伝島崎藤村』(筑摩書房、1981年)/矢島裕紀彦『心を癒す漱石の手紙』(小学館文庫、2009年)/矢島裕紀彦『鉄棒する漱石、ハイジャンプの安吾』(NHK生活人新書、2003年)/矢島裕紀彦『文士が愛した町を歩く』(NHK生活人新書、2005年)/矢島裕紀彦『文士の逸品』(文春ネスコ、2001年)





























