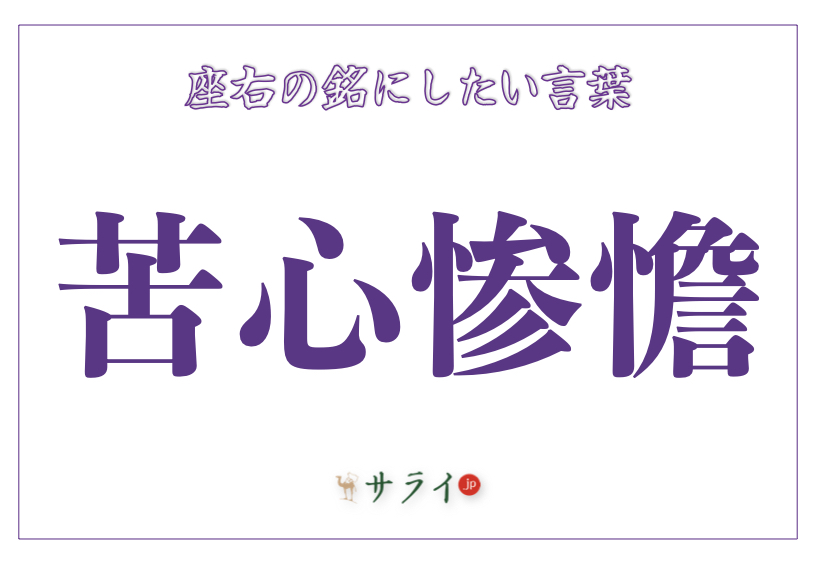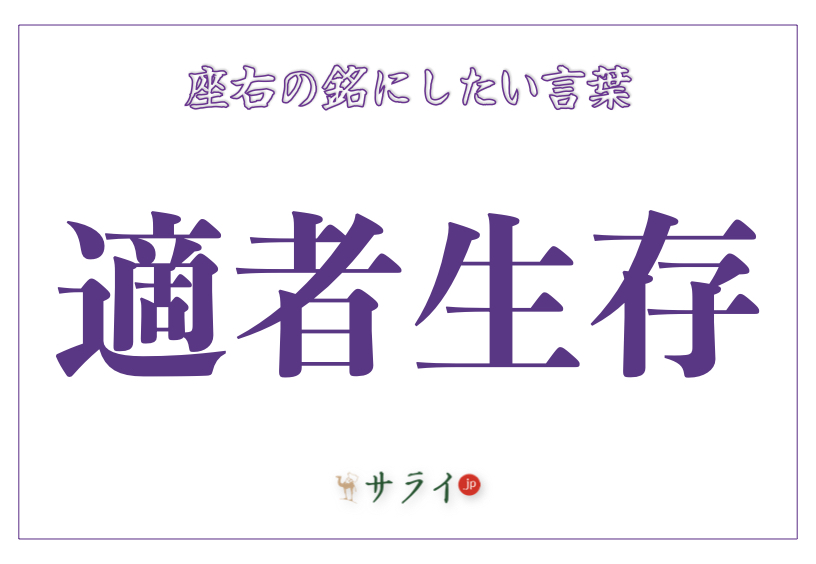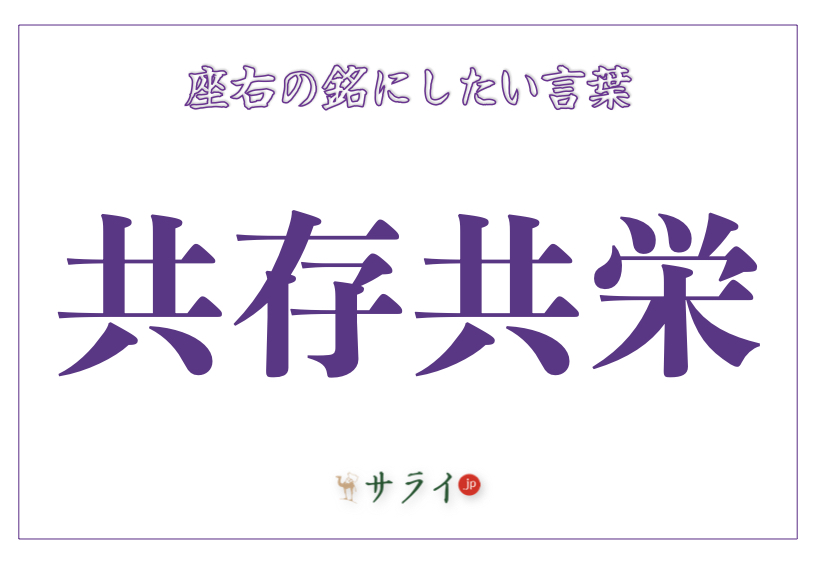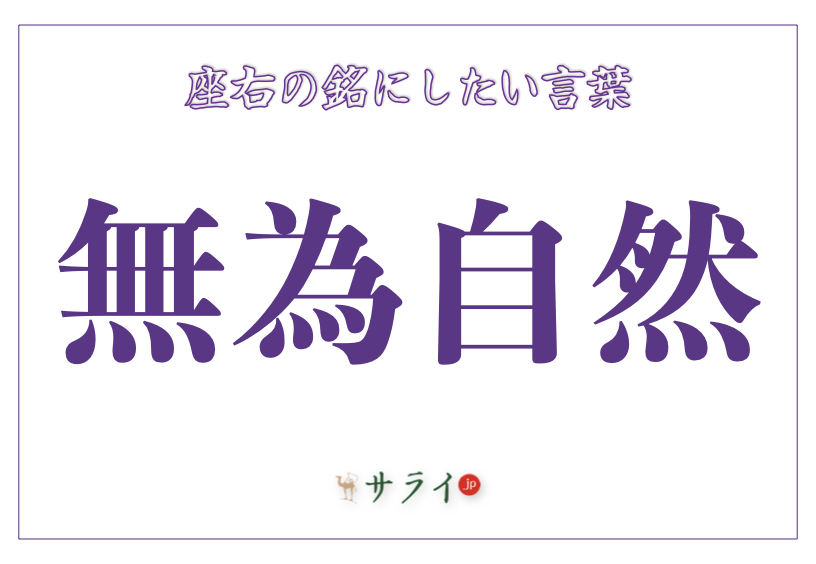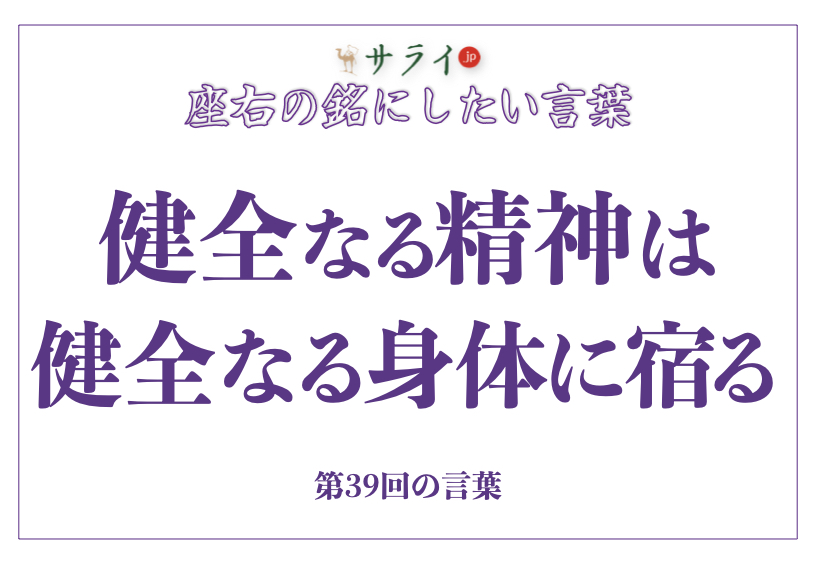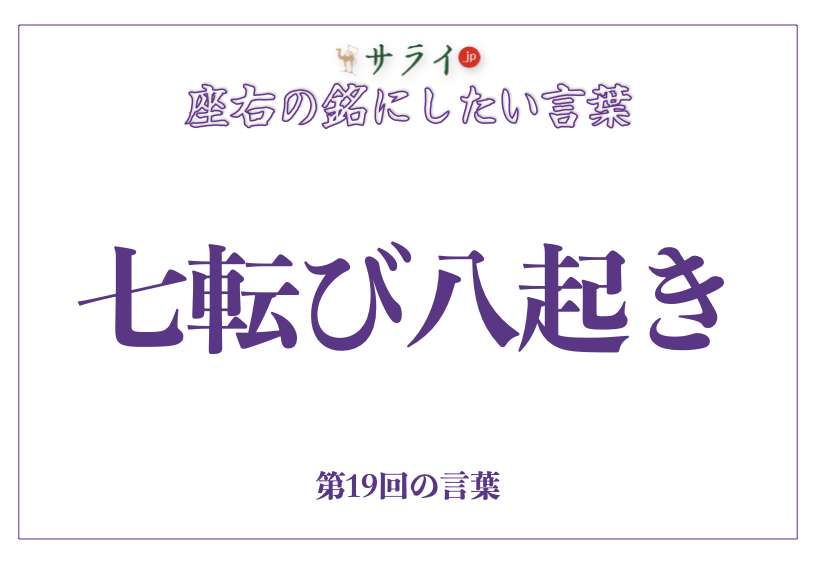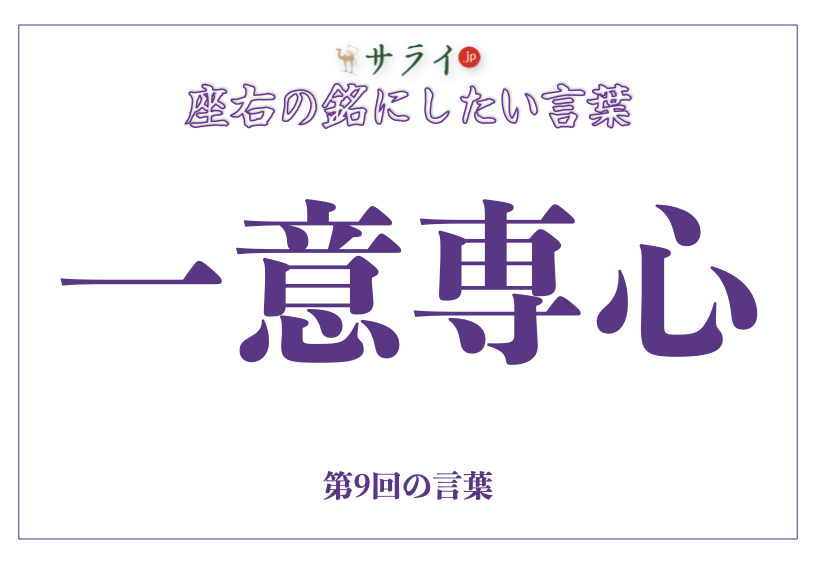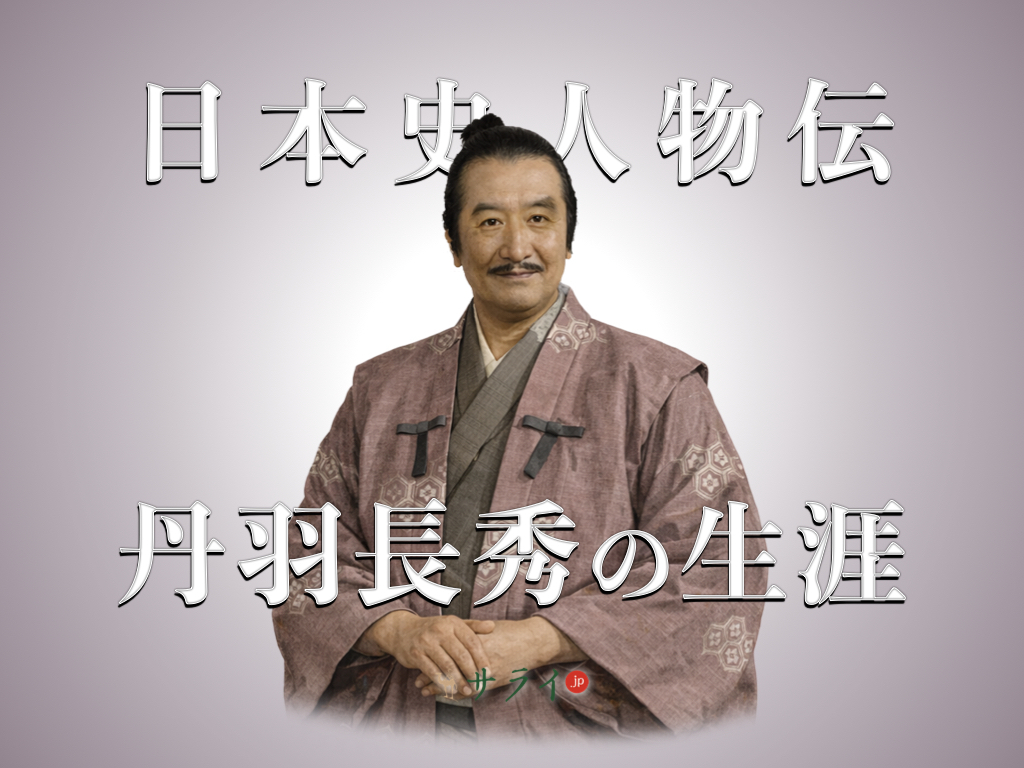迂闊に人生を語り、昔の経験を口にすれば「老害」と揶揄される昨今。しかしながら、たとえ陰で「老害」と呼ばれようとも、申しておかなければならない「一言」はあるもの。さりとて、長々と諭してみたところで、相手の心に伝わるとは限りません。貴重な時間が、無駄になってしまうこともしばしば。
ならば、先人が残した言葉や金言を用いることで、あなたの真意や願いが相手に伝わる良案となるかもしれませんね。そんな時に役立つ言葉をご紹介いたしましょう。今回の座右の銘にしたい言葉は「苦心惨憺(くしんさんたん)」 です。
「苦心惨憺」の意味
「苦心惨憺」について、『⼩学館デジタル⼤辞泉』では、「非常に苦心していろいろやってみること」とあります。
この言葉には単に「大変だった」というだけでなく、そこには骨身を削るほどの努力や工夫、そして精神的な苦悩があったというニュアンスが含まれます。簡単に事が運ばなかったからこそ、考え抜き、試行錯誤を重ねた。その濃密な時間と労力が、「苦心惨憺」という四文字に凝縮されているのです。
若い頃の「がむしゃらな努力」とは一味違い、経験を積んだからこそ分かる、緻密な工夫や精神的な葛藤を含んだ苦労。それこそが、シニア世代の皆様が経験されてきた「苦心惨憺」ではないでしょうか。
「苦心惨憺」の由来
この言葉は二つの部分から構成されています。「苦心」は、あれこれと心を砕いて考えることを意味し、「惨憺」は心を悩まし、困りながらも努力を続けることを表します。つまり、「苦心惨憺」は同じような意味を持つ言葉を重ねることで、その困難さと努力の深さを強調した表現なのです。
現代社会では、何事もスピードや効率が重視されがちですが、「苦心惨憺」という言葉には、時間をかけてじっくりと取り組む姿勢の尊さが込められています。

「苦心惨憺」を座右の銘としてスピーチするなら
この言葉はやや難解ですから、スピーチで使う際は、まず意味をわかりやすく説明することが大切です。さらに、自分の人生経験と重ねて「なぜこの言葉を大切にしているか」を語ると、聞き手の共感を得られます。硬すぎず、少し柔らかい表現を加えると親しみやすくなります。以下に「苦心惨憺」を取り入れたスピーチの例をあげます。
サラリーマン人生を振り返るスピーチ例
私の座右の銘は、「苦心惨憺」です。少し物々しい言葉に聞こえるかもしれませんね。ですが、私の社会人人生は、まさにこの言葉に支えられてきたように思います。
今でも忘れられないのが、入社10年目の秋、前例のない新製品開発のリーダーを任された時のことです。当初の計画は全くうまく進まず、技術的な壁に何度もぶつかりました。予算は削られ、チーム内では意見が対立し、一時期はプロジェクトの解散も囁かれるほどでした。
夜も眠れず、解決策を探して資料の山に埋もれる日々。まさに暗いトンネルの中を手探りで進むような、出口の見えない毎日でした。これこそが「苦心惨憺」の日々であったと、今、改めて思います。
しかし、そんな八方塞がりの状況だったからこそ、私たちは部署の垣根を越えて知恵を出し合い、それまでになかった発想で、なんとか困難を乗り越えることができました。そして、あの時生まれた製品が、今も会社の主力商品の一つとして皆様に愛されていることは、私の生涯の誇りであります。
この経験を通して私が学んだのは、簡単に手に入る成功よりも、苦しみ抜いた先にあるものの方が、何倍も価値があり、人を成長させる、ということです。
これからの人生も、安易な道を選ぶのではなく、時には敢えて困難な道に挑戦し、苦心惨憺することすら楽しむくらいの気概を持って、学び続けていきたいと考えております。
最後に
「苦心惨憺」という言葉には、単なる苦労を表すのではなく、目標に向かって諦めずに工夫を重ねる美しい姿勢が込められています。シニア世代の皆様にとって、これまでの人生で培ってきた経験と努力を表現する言葉として、この四字熟語は特別な意味を持つのではないでしょうか。
●執筆/武田さゆり

国家資格キャリアコンサルタント。中学高校国語科教諭、学校図書館司書教諭。現役教員の傍ら、子どもたちが自分らしく生きるためのキャリア教育推進活動を行う。趣味はテニスと読書。
●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com