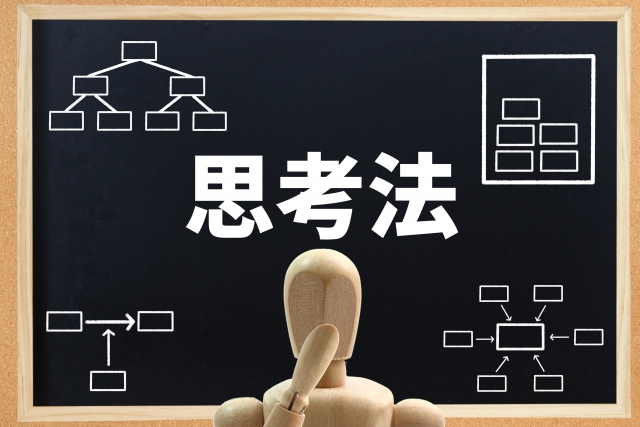ライターI(以下I):『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(以下『べらぼう』)第28回は、佐野政言(演・矢本悠馬)が若年寄田沼意知(演・宮沢氷魚)に斬りかかるという前週からの続きが描かれました。佐野は、「覚えがあろう」と叫びながら斬りかかりました。江戸城内で刃傷沙汰を起こしたらどうなるか、知らないわけはないでしょうから、相当思いつめての凶行だったと思われます。
編集者A(以下A):江戸城内での刃傷事件についてまとめた『営中刃傷記』の表現では「山城殿、御覚えこれあるべし」です。この言葉を3回繰り返したとも書かれています。同書はわりと細かい描写がありまして、佐野に襲われた意知は、指が所々切れていたそうです。そのうちの1本は斬り落とされたとも、落ちてはいなくて落ちかけていたともいった描写があります。
I:なんでも、佐野政言が刃傷に及ぶにあたって、懐中に「七か条の口上書」を持っていたそうですが、事件後に燃やされたそうです。ところが、『営中刃傷記』には、写しがとられていたとして、その内容が伝わっています。
A:そうなんです。劇中で描かれた将軍御成の狩りの際に、佐野が1羽仕留めたのに、仕留めた獲物や矢が見当たらなかったというエピソードもここに書かれているものです。事件の背景には「陰謀があった」というオランダのカピタン(オランダ東インド会社商館長)のティチングの記録もよく引用されますが、彼は薩摩藩の島津重豪(演・田中幸太朗)とは昵懇の仲だったことが知られています。
I:劇中でも、島津重豪と一橋治済(演・生田斗真)が一緒にいる場面が幾度か登場しています。第11代将軍になる家斉の正室が島津重豪の娘茂姫なのですから、あたりまえといえばあたりまえなのですが。
A:実は、『営中刃傷記』には、劇中で描かれた一橋と松前藩との関係につながるような話も書かれているのですよ。同書によれば、佐野政言は意知襲撃にあたって、刀身に「鳥頭」を塗っていたというのです。トリカブトの毒のことですね。そうすれば「浅手にても死に候」と記されています。そして、このことは松前氏から先君に伝えられたというのです。「先君」とは、家重なのか吉宗なのかまでは書かれていませんが、なんだか怪しげな記述ですよね。
十七箇条の書き置きをみれば「深い陰謀」がみえてくる

A:佐野政言は意知を襲うに際して、前述の口上書のほかに、自邸に17箇条もの「書き置き」を遺していたと『営中刃傷記』には記されています。その断片を引いた記事はいくつも出てくるでしょうから、多少煩雑ではありますが、当欄では17箇条すべてを紹介したいと思います。
I:先にネタばらししますが、17箇条といいながら、〈罪七〉が重複していて、実際は「18の罪」になっています(笑)。
A:まずは、「主殿頭(とものかみ=意次のこと)不肖にして、天下の執権職となる」から文章は始まります。幕閣までのぼりつめながら、将軍の恩を忘れ、私欲をほしいままにし、無道の行ないが多いと断じています。それが、〈其罪一〉です。
I:〈其罪二〉は、「依怙贔屓(えこひいき)を以て、諸士を立身致させ」で始まります。依怙贔屓で役人を出世させ、不正な人事を行なっていると断じているわけです。
A:田沼派の老中水野忠友(演・小松和重)は、意次の四男を養子にして「水野忠徳」と名乗らせていましたが、そのことも「水野家を奪い取り」と指弾されています。
I:実は、『営中刃傷記』には、佐野は取り立ててもらうために、田沼家に620両もの金を渡していたと、懐中に入れていた「口上書」に記していたようです。不正な人事を糾弾しながら自分は賄賂を贈っているわけですから、天に唾するとはまさにこのこと、とちょっとモヤモヤしました。
A:さて、〈其罪三〉です。「十七日は神祖の御忌日」で始まります。初代将軍家康の亡くなった17日に、「翫童卑妾を集め、酒宴遊興、乱淫致候」、つまりどんちゃん騒ぎをしていたという指摘です。〈其罪四〉は、「歴々の御旗本へ(中略)成り上がりの己が家来の賤女を以て、縁談取り結ばせ候」と、由緒ある旗本に、成り上がりの田沼家家臣の娘を嫁がせたといって問題にしているのです。
I:そして、〈其罪五〉です。金貨を鋳造する「金座」の当主後藤庄三郎配下の人間らに偽金を造らせようと企んだとあります。事実なら極悪非道なことですが、この口上書は、建付けとしては佐野政言が刃傷を起こすにあたって自邸に置いてきたものです。実際に佐野がまとめたということだったら、とっても優秀な「記者」だったんだろうと思います。
A:〈其罪六〉は、勲功之家柄の者を差し置き、忰の山城守を若年寄に抜擢したことが罪だといっているのです。これは、田沼意次(演・渡辺謙)に対する批難ですね。〈其罪七〉は、小納戸役の人事の際に、金子(きんす/賄賂のことか)をとっていたことを指摘し、大奥の実力者「玉沢」と申し合わせて、「我儘も取り計らい」、つまり大奥にいろいろ便宜を取り計らったというのです。そして、そういう行為は「君を穢し奉る」と断じます。じつは〈其罪七〉がもうひとつあって、「己が屋敷内にお部屋様を請侍し」「乱淫をなさんと謀る」――。お部屋様というのは将軍の側室のことですから、事実ならこちらも「君を穢し奉る」行為ですね。
I:〈其罪八〉「加恩の節」で始まるのですが、田沼家の領地がご加増された際に、大名や旗本の「宜所を奪取」と指弾されているのです。600石から最終的に5万7000石までに立身する中で、新たに宛がわれた領地を吟味すれば、その当否が明らかになるとは思います。
A:そして、〈其罪九〉では、「本家の系図をかり」「己が家を本家の様に致さんため」――とあります。田沼家は佐野家の家来筋だったものを、逆にしようとしたということなのですが、『べらぼう』劇中で、田沼意次が、佐野家の系図を池に放り投げた場面に象徴されるように、田沼意次は系図だとか出自に頓着するような人物ではなかったような気がするのですよ。
I:なるほど。系図や出自、家格にこだわるのは守旧派の考えであって、田沼意次はそんなことにはこだわっていなかったのではないかということですね。そして、〈其罪十〉です。田沼意次は、運上、つまり税金を課して、幕府財政の回復に努めましたが、その運上金が庶民を苦しめたと罪状のひとつにあげているわけです。
A:〈其罪十一〉は、死罪になすべき者を、「己が依怙を以て死刑に致さず」、天下の定法を乱すと指摘しています。〈其罪十二〉では蓄財した金を利子を取って町人に貸し出しているというのです。
I:そして〈其罪十三〉です。諸大名や旗本の家中で法を犯して追い出された者を、ろくに吟味することなく召し抱えたことも罪だというのです。
A:〈其罪十四〉では、代々将軍家の馬方を務める諏訪部文九郎の名が登場します。諏訪部から、代々の将軍が正月の初乗りの際に用いた鞍(くら)をもらい受け、その鞍を私物化したということが罪だというのです。
I:〈其罪十五〉縁家土方家の先祖の名を田沼家でそのまま名付けてしまったことを断罪しています。この縁家の土方家は伊勢菰野藩の土方家で意次の六男が養子に入って土方雄貞と名乗っていたそうです。
A:〈其罪十六〉は、〈衆道を以て立身出世して武功の家を謾(あなど)る〉とあります。意次のことなのか意知のことなのか判然としませんが、男色で出世したということをいっているわけです。そして、最後の〈其罪十七〉です。倅の意知が若年寄になったはいいが、諸人は困窮している。そんななかで米5000俵を天下の定法に背いて下野屋十右衛門が請取申し候とあります。要するに不正をしたということを指弾しているのです。
I:さきほども言及しましたが、建付けとしては、佐野政言がまとめた書き置きなのですが、ひとりでこんなに情報を集めることができたのでしょうか。そして、こうやって全部まとめてみると、明らかに組織が関与しているにおいがします。
A:これはもう田沼派とアンチ田沼派の合戦ですね。情報戦といってもいいのかもしれません。これらがでっち上げなのか、半ば事実なのかどうかは判別しませんが、単に意知を殺害するだけではなく、情報戦をしかけて、「田沼=悪」を強く印象付ける作戦が実行されたということでしょう。
【扇動したのも「丈右衛門だった男」という衝撃。次ページに続きます】