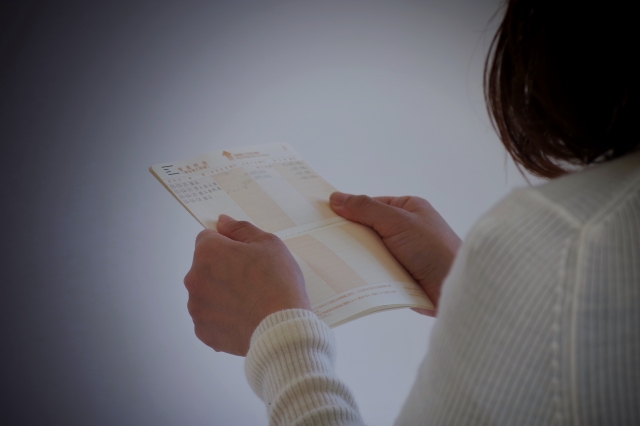取材・文/ふじのあやこ

日本では婚姻届を役所に提出し、受理されると夫婦と認められる。夫婦となり、パートナーのことを家族だと受け入れられるものの、パートナーの両親やきょうだい、連れ子などを含め、「みんなと家族になった」とすんなり受け入れられる人もいれば、違和感を持つ人もいるという。また、ずっと家族として生活していたものの、分かり合えない関係のまま離れてしまった人もいる。家族について戸惑った経験がある人たちに、家族だと改めて感じられたきっかけを聞いた。
*
株式会社エムフロが運営するクラウディアアシスタントは「職場勤務と在宅ワークどっちが理想かに関する意識調査」(実施日:2025年8月1日~8月3日、有効回答数:全国の子育て中の女性300名(20代 16.0%/30代 55.7%/40代 24.3%/50代以上 4.0%)、インターネット調査)を実施。この調査にて、全国の子育て中の女性に「職場勤務と在宅ワークどっちが理想?」を聞いたところ、1位は「在宅ワーク(85.0%)」だった。2位「職場通勤(10.7%)」、3位「どちらでもいい(2.7%)」、4位「どちらも理想ではない/働きたくない(1.7%)」だったことから、在宅ワークが圧倒的に人気だということがわかる。次に、実際の働き方と理想の働き方との違いを調べたところ、現在「職場通勤」と回答した人のうち77.5%が「在宅ワーク」を理想としていた。理想は在宅ワークでも、職場に通勤している人が多いことがわかった。
今回お話を伺った美冬さん(仮名・45歳)は、仕事人間の両親に育てられ、寂しい子ども時代だったと振り返る。
母親に甘えられた記憶はない
美冬さんの両親は、美冬さんが学生時代は飲食店を経営していた。経営は厳しく、人件費を賄えないことから、いつも両親はお店に出ていた。小さい頃は夜までは祖父母の家で過ごすことが多かったという。
「朝だけは3人揃ってご飯を食べて、私は学校終わりに近所で暮らす父方の祖父母の家に行き、夜遅く眠たくなった頃に母親が迎えに来て、一緒に家に帰るというような生活でした。
祖父母の家から家に戻るときの時間が私にはとても大切だったのですが、そのときの母親は疲れ切った表情で父親の愚痴を言い続けていました。母親がしんどそうだったので、私は自分の学校の話をするよりも母親の話を聞いてあげないといけないと思っていましたね」
その生活は、母親が妊娠したことで少し変化する。母親はギリギリまでお店に出続けたが、その無理が影響して入院に。その間の仕込みなどは祖母が手伝うことになり、美冬さんは学校終わりには病院に母親の様子を伺い、その後は祖父母の家で寝泊まりするようになった。
「母親が妊娠したのは私が小学校4年生のときなんで、弟とは11歳違いです。妊娠がわかった後もしばらくは生活はそのままだったんですが、母親が入院してからは祖父母の家で寝泊まりするようになりました。それに、昼間は母親の様子を見に行って、その後は誰もいない祖母の家に戻っていました。父が1人では私の世話はできないからって。祖母も母親が入院した後には仕込みやお店の手伝いで家に居ないことが多くなって、疲れていて前より私に構ってくれなくなっていました。
母親が入院してから、以前よりも私の孤独感は強くなっていきました。母の病院に行かなければいけなかったから、友人とも遊べなくなっていましたから」
弟が産まれてからは、母親や祖母と一緒に弟の面倒を見る日々だった。弟は可愛かったが、母親をとられた思いが強く、優しくできなかったと美冬さんは振り返る。
「弟は私にとても懐いてくれましたが、母親や祖母が笑顔で弟の世話をしている姿を見ると、自分の居場所をとられたような気持ちになってしまって。私の後をついてくる弟に対して、『あっちに行け』『来るな、鬱陶しい』というような酷い言葉を何度も言ってしまったことがあります」
【両親から見て私は子どもではなく、弟を育てる一員だった。次ページに続きます】