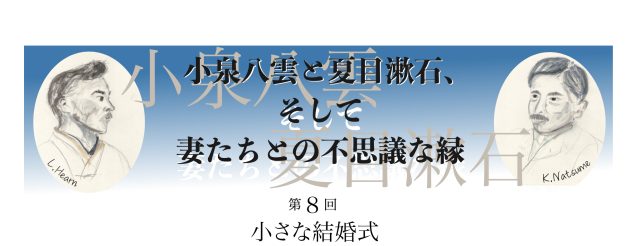
小泉セツ&小泉八雲の夫婦がモデルとなった朝の連続テレビ小説『ばけばけ』が注目されています。実はその小泉夫妻と、明治の文豪・夏目漱石と妻・鏡子は、不思議と重なり合う縁で結ばれていた、というのをご存じでしょうか。
夏目漱石の研究家として知られ、『心を癒す漱石の手紙』などの著書を持つ、作家で雑誌編集記者の矢島裕紀彦さんによると、二人の文豪とその妻たちには奇縁と呼ぶしかないような不思議なつながりがあると言います。
多数の文献や手記を紐解きながら、二組の夫婦の知られざる素顔を全26回の連載にて紹介します。
第8回では、夏目漱石と小泉八雲の、それぞれの結婚式から見えてくる当時の心情や暮らしぶりを読み解きます。
文・矢島裕紀彦
三々九度の盃さえ足りなかった漱石の結婚式

夏目漱石と鏡子の結婚式は、明治29年(1896)6月9日に執り行われた。会場は、熊本市下通町(通称・光琳寺町)にある漱石の自宅離れの6畳間だった。
この家は、漱石が熊本市内を探し回って、ひと月前にようやく見つけた借家だった。漱石は、松山で中学校教師をしていた前年暮れに、東京で鏡子とお見合いをした。結婚とその後の新生活は東京で始められればと思っていたが、意に反し、4月に熊本五高に転任することとなった。熊本ですぐに借家は見つからず、当座、同じ五高に勤務していた友人の菅虎雄の住む借家(熊本市薬園町)の離れに居を構えた。
結婚を前に、花嫁の父・中根重一から「あんまり汚い家では、若い娘がいやがるかもしれないな」と注文をつけられた。漱石は慌てて家探しに奔走し、下通町へ引っ越しを敢行したのだった。
新しく見つけた借家の間取りは、玄関に続いて10畳、6畳の部屋、4畳の茶の間、湯殿と板蔵もついていて、他に6畳と2畳の離れがあった。家賃は8円。庭には青桐と椋の木が植えられていた。漱石は、中根重一に新居を見つけたことを報告し、こんなふうに付け加えた。
「なかなかいいところはありませんが、亭主がそれで辛抱するのですから、細君もそれで我慢してくれなくては困ります」
新婚夫婦の住む家としては十分とも思える間取りなのに、随分と遠慮気味の物言いになっているのは、ひとつは、漱石の頭の中に、見合いをした際の中根家の住まい(貴族院書記官長の官舎)の和洋2棟の立派過ぎるほどの佇まいが、無意識裡の比較対象として浮かんでいたせいもあるかもしれない。もうひとつ知っておいていいのは、当時の中流家庭のスタイルとして、住み込みのお手伝いがいるのが一般的であり、また多少の余裕があれば書生を置くことも少なくなかったという事情である。教師の家では、教え子の学生を置いたりもしていた。
小泉八雲の住まいはどうだったか。八雲は、ついこの2年前(明治27年)の秋まで熊本にいた。その住まい(熊本市坪井の第2旧居)は、松の木や庭石の配された古雅な趣の庭を持つ和風建築。東向き中央に、入口に続く3畳の玄関の間があり、その左手(北側)に6畳の茶の間と4畳半、2畳の間、さらにその北側に竈と井戸のある広い台所があった。一方、玄関の間の右手(南側)には、8畳の本座敷と6畳の次の間、3畳間。この母屋から廊下でつながった西側奥の8畳の離れが八雲の書斎で、寒さ対策のため改装を施し、薪ストーブと断熱用の硝子入り障子を入れていた。セツの養父母や養祖父、赤ん坊(長男の一雄)、お手伝い、書生、お抱えの車夫まで、ここに多いときには11人で暮らしていたという。
漱石と鏡子の結婚式は、まことに小さなものだった。
花婿の漱石は暑さをこらえて冬用のフロックコートを着用し、花嫁の鏡子は夏の振袖で畏まっている。親族の出席者は、中根重一ひとり。三三九度のお酌をしながら仲人役も兼ねるのは、東京から鏡子についてきた婆やだった。しかも、三つ組みであるべき三三九度の盃が、上か下かがひとつ足りなくて、2つしかない。婆やと車夫が台所で働いていたかと思うと、式に列席する客に早変わりするのが滑稽だった。
名義上の媒酌人は、中根重一が旧知の地位のある人に頼んでいた。内閣の恩給局長をしていた井上廉という人だった。この人物は故実に通じていて、古式にのっとった目録儀式などを書いた「御婚礼式」という文書をつくって中根の家へ送ってきた。そこには結婚式における座敷飾りのこと、着座の次第および式三献、色直し、さらには岩田帯は足利将軍がどうしたこうしたとか、その出典その他の故事来歴が詳細にしたためられていた。
中根重一がこれをそのまま漱石に送ったところ、もともと儀式ばったことの苦手な漱石はびっくり仰天して、
「どうか一番手数のかからない略式で勘弁していただきたい」
と願い出た。そんな経緯があって、こんな形の質朴の結婚式となっていた。花嫁を伴った中根家から夏目家(東京の実家)への挨拶は、熊本に来る直前に済ませていた。それにしても、なんとささやかな! 漱石の願いをすんなりと聞き入れた花嫁とその父は、形式ばらない、進んだ精神の持ち主だったのだろう。
もちろん、賑やかな披露宴などもあるわけがない。あとで仕出屋の勘定書きを見ると、婆やと車夫の分も含め、しめて7円50銭。これが漱石夫妻の結婚式にかかった総費用であった。
出雲大社詣でが結婚式替わり!? 八雲とセツの場合

八雲とセツのふたりには、結婚式に相当するようなものはあったのだろうか。もしかすると、2度目の出雲大社詣でがそのときであったのかもしれない。
八雲は松江入りして間もない明治23年(1890)9月、尋常中学教頭・西田千太郎の紹介状を携えて出雲大社を参詣し、宮司の千家尊紀とも面談し、西洋人として初めての昇殿を許された。2度目の大社詣では、翌明治24年の夏休みである。7月26日、西田千太郎とともに旅に出た八雲は、杵築(現・出雲)の海水浴場の旅館に逗留。セツも呼び出されてすぐに合流し、三人で出雲大社や日御碕を訪れた。このときの大社訪問が、結婚のためのけじめの意味をこめた参拝だったように見受けられるのだ。
それを窺わせるのが、西田の日記。
7月29日
ヘルン氏ト共ニ大社ニ昇殿。(略)非常ニ鄭重ナル饗応ヲ受ケ、夜半ヲ過ギテ帰ル。ヘルン氏大酔
8月7日
ヘルン氏ト日御碕神社ニ詣ズ。宮司小野氏(セツ氏ノ縁家)方ニ午飯ノ饗応ヲ受ク
7月29日に、大社参詣のあと宮司の家で手厚い饗応を受け、八雲が上機嫌のうちに、いつになく飲み過ごして大酔してしまったのは、区切りをつけて、胸にこみ上げる特別な思いがあったからなのではないか。続いて8月7日に訪問した日御碕神社の宮司の小野男爵家は、セツの実母方の従姉の嫁ぎ先である。八雲とセツが、晴れて夫婦となった区切りの思いを胸に、通訳兼介添え役の西田を伴ってセツの親戚のもとへ挨拶に出向いたとも解釈できる。これまで西田が日記に「妾セツ」と記していたのが、このとき以降は「セツ氏」(あるいは「セツ子氏」)に変わっているのも見逃せない。西田の中で、明らかにひとつの線引きがなされている。
当時の国際結婚は、手続きの上でも、さまざまな権利上の問題からも、現今よりずっと厄介だった。それでも、けじめの大社参拝をしたあとの八雲は、戸籍まで含んだ正式な結婚手続きについて真剣に考えはじめた。この旅から帰った直後に書いたと思われる、アメリカの友人ページ・M・ベーカー宛て書簡に、八雲はこんなふうに書いている。
ここで是非とも申し上げなくてはならぬのは、私の結婚のことです。私はただ今のところでは日本風に結婚したばかりである、と申さねばなりません。(略)現在の法律では、外国人がイギリスの法律に従ってその土地の女と結婚しますと、その結婚した女性はイギリス国民となり、その子供は、もし子供があれば、イギリスの臣民となります。そんなわけですから、私の妻は外国人に対する法律によりまして居留地内に住み、事実上その同胞からは分離しなければなりません。だから、私が法律上日本人になるまでにイギリスの法律に従って彼女と結婚すれば、それは彼女の破滅になります。――もし私が死んでしまいましたら、彼女は自分の国民としての権利の喪失を後悔する重大な理由をもつことになります。
自分はセツより18歳年上。先に死を迎えるのが自然である。残される家族の行く末までも考えねばならない。熊本での長男の誕生が覚悟を促すことともなったのか、やがて八雲は、自分がイギリス国民としての資格を放棄し、セツの婿となって小泉家に入籍し帰化するしかないとの決断を下していく。熊本から神戸に移った明治28年(1895)8月頃から、実際に、手間をいとわず、セツの戸籍のある松江の役場とも連絡をとって、もろもろ模索しながら手続きを進めた。そうして、明治29年(1896)2月10日、とうとう帰化が承認された。このときからラフカディオ・ハーンは「小泉八雲」となった。「八雲」の名は、『古事記』にある日本最古の和歌「八雲立つ 出雲八重垣 妻籠(つまごみ)に 八重垣作る その八重垣を」からとったもので、セツの養祖父・稲垣万右衛門による命名と言われている。
* * *

矢島裕紀彦(やじま・ゆきひこ)
1957年、東京都生まれ。早稲田大学政経学部卒。作家・雑誌編集記者。文学、スポーツ、歴史など幅広いジャンルをフィールドに“人間”を描く。著書に『心を癒す漱石の手紙』『文士の逸品』『文士が愛した町を歩く』『鉄棒する漱石、ハイジャンプの安吾』『ウイスキー粋人列伝』『著名人名づけ事典』『こぼれ落ちた一球』『石橋を叩いて豹変せよ』『あの人はどこで死んだか』など多数。グランドセイコー広告の掌編小説シリーズ『時のモノ語り』で2018年度朝日広告賞朝日新聞特別賞受賞。https://atelier1328.com
(この連載を通しての主な参考文献)
『漱石全集』全28巻、別巻1(岩波書店、1993~1999年)/夏目鏡子述・松岡譲筆録『漱石の思い出』(文春文庫、1994年)/夏目伸六『父・夏目漱石』(文春文庫、1991年)/夏目伸六『父・漱石とその周辺』(芳賀書店、1967年)/高浜虚子『回想子規・漱石』(岩波文庫、2002年)/松岡陽子マックレイン『漱石夫妻 愛のかたち』(朝日新書、2007年)/荒正人『増補改訂漱石研究年表』(集英社、1984年)/江藤淳『漱石とその時代』第1部~5部(新潮新書、1970~1999年)/『新潮日本文学アルバム夏目漱石』(新潮社、1983年)/『別冊國文学 夏目漱石事典』(学燈社、1990年)/『夏目漱石の美術世界』(東京新聞、NHKプロモーション、2013年)/出久根達郎『漱石先生とスポーツ』(朝日新聞社、2000年)/江戸東京博物館・東北大学編『文豪・夏目漱石』(朝日新聞社、2007年)/平岡敏夫『「坊つちやん」の世界』(塙新書、1992年)/恒松郁生『漱石 個人主義へ』(雄山閣、2015年)/小泉節子、小泉一雄『小泉八雲 思い出の記 父「八雲」を憶う』(恒文社、1976年)/小泉八雲、平井呈一訳『日本瞥見記』上・下(恒文社、1975年)/小泉八雲、平井呈一訳『東の国から・心』(恒文社、1975年)/小泉八雲、平川祐弘編『怪談・奇談』(講談社学術文庫、1990年)/小泉八雲、池田雅之編訳『虫の音楽家』(ちくま文庫、2005年)/『明治文学全集48 小泉八雲集』(筑摩書房、1970年)/小泉時共編『文学アルバム小泉八雲』(恒文社、2000年)/小泉凡監修『小泉八雲、開かれた精神の航跡。』(小泉八雲記念館、2016年)/池田雅之監修『別冊太陽 小泉八雲』(平凡社、2022年)/池田雅之『小泉八雲』(角川ソフィア文庫、2021年)/田部隆次『小泉八雲』(北星社、1980年)/長谷川洋二『八雲の妻』(今井書店、2014年)/関田かをる『小泉八雲と早稲田大学』(恒文社、1999年)/梶谷泰之『へるん先生生活記』(恒文社、1998年)/池野誠『松江の小泉八雲』(山陰中央新報社、1980年)/工藤美代子『神々の国』(集英社、2003年)/工藤美代子『夢の途上』(集英社、1997年)/工藤美代子『聖霊の島』(集英社、1999年)/平川祐弘編『小泉八雲回想と研究』(講談社、1992年)/平川祐弘『世界の中のラフカディオ・ハーン』(河出書房新社、1994年)/熊本大学小泉八雲研究会『ラフカディオ・ハーン再考』(恒文社、1993年)/西川盛雄『ラフカディオ・ハーン』(九州大学出版会、2005年)/西成彦『ラフカディオ・ハーンの耳、語る女たち』(洛北出版、2024年)/池田雅之『日本の面影』(NHK出版、2016年)/ラフカディオ・ハーン『小泉八雲東大講義録』(KADOKAWA、2019年)/芦原伸『へるん先生の汽車旅行』(集英社インターナショナル、2014年)/嵐山光三郎『文人暴食』(新潮文庫、2006年)/河東碧梧桐『子規を語る』(岩波文庫、2002年)/『正岡子規の世界』(松山市立子規記念博物館、1994年)/『子規全集』18巻、19巻(講談社、1979年)/『志賀直哉全集』第8巻(岩波書店、1999年)/『芥川龍之介全集』第4巻(岩波書店、1996年)/瀬沼茂樹『評伝島崎藤村』(筑摩書房、1981年)/矢島裕紀彦『心を癒す漱石の手紙』(小学館文庫、2009年)/矢島裕紀彦『鉄棒する漱石、ハイジャンプの安吾』(NHK生活人新書、2003年)/矢島裕紀彦『文士が愛した町を歩く』(NHK生活人新書、2005年)/矢島裕紀彦『文士の逸品』(文春ネスコ、2001年)






























