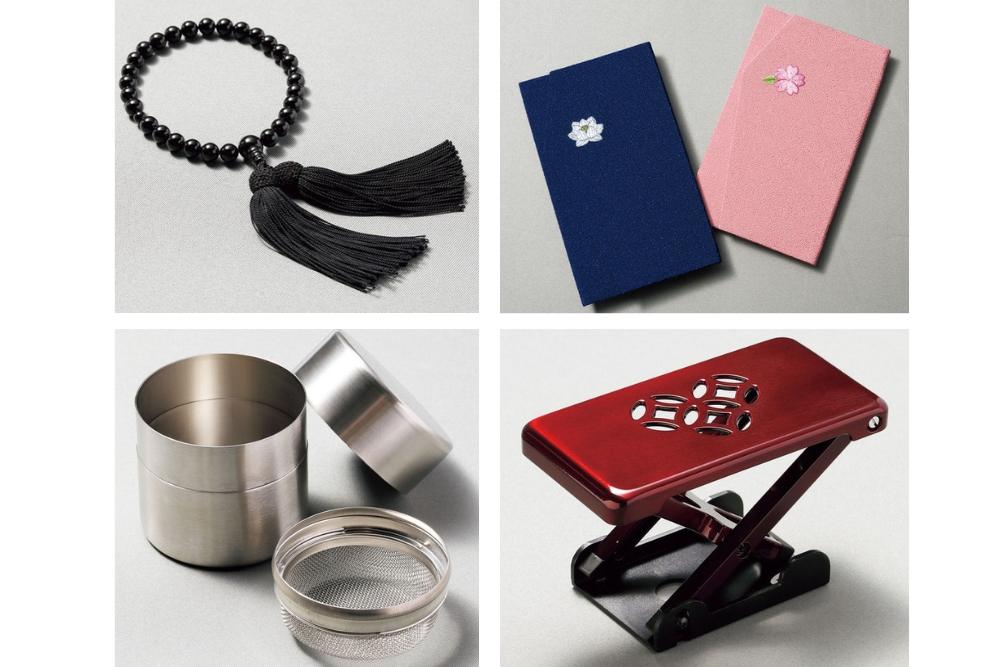メイクアップ・アーティストの小林照子さんは、1935年、東京生まれ。23歳のときに『小林コーセー』(現・『コーセー』)に美容指導員として入社。その後、数々のヒット商品を手がけるとともに、「ナチュラルメイク」の理論を確立するなどして、1985年、同社初の女性取締役に就任しました。しかし、その後、56歳で退社して独立。これまで美に関する種々の研究所や学校を、設立・運営してきました。現在も、美容ビジネスの企業経営や後進を育てる学校『[フロムハンド]メイクアップアカデミー』ほか、美に特化した高等学校および『アマテラス アカデミア』を運営しています。
人生の少し先を歩く「姉」たちから「妹」たちへ
そんな小林照子さんが語る「妹」たちへのメッセージとは……。『50代からの生き方のカタチ――妹たちへ――』(関西学院大学ジェネラティビティ研究センター 編)は、小林さんをはじめとする12人の「姉」たちが、これから人生の半分を生きる、すべての「妹」たちへ贈るメッセージ集。「花人日和」読者にとって学びの多いこの一冊を携えて、小林さんのいつまでも溢れ出るパワーの源を探ろうと、生き方のヒントを伺いました。
今回は、メイクアップ・アーティストになるという夢を目指したきっかけから『コーセー』入社のエピソードまで、夢を実現するための過程に迫ります。
取材・文/山津京子
「メイク」という言葉や概念がまだない時代
――メイクアップ・アーティストになろうと思われたのは、18歳のときに山形で演劇サークルを立ち上げたのがきっかけと伺いました。演劇には昔から興味を持たれていたのですか?
私は小学生の頃から主役を演じることが多くて、“学芸会の花形”と呼ばれていたんです(笑)。
第二次世界大戦での東京大空襲を機に、私は小学4年生のときに東京から山形へ疎開して、その後、山形で終戦を迎えました。当時の山形では、学校の先生をはじめ、クラスメイトも皆、東北弁で会話をしていたため、脚本を標準語で読める人がいなかったんですよね。そのため、私が同級生にセリフを教えたり、主役を務めることが多くて、いつの間にか演劇に興味をもつようになって、気がついたら演劇サークルを立ち上げるほどハマっていたんです。
――演じる立場から、メイクアップ・アーティストになりたいと思うようになったのはどうしてですか?
設立した劇団は小さな素人劇団ですから、役者をはじめ、裏方仕事もすべて自分たちで行なっていたのですが、そうしていろいろな仕事をしているうちに、役者とは別の立場で舞台をつくる裏方の仕事の方がおもしろくなったのです。
舞台装置や照明などさまざまな仕事がある中で、メイクアップに興味を持ったのは裏方仕事の中でもいちばん苦労したからです。
役者として舞台に立つときにも実感したのですが、老人に扮するとき、単純に顔にシワを描けば老人らしくなるわけではないんですよね。善いお爺さん、悪いお爺さんをどうやってメイクで表現したらいいのかということも、とても悩みました。
また、公演を重ねていくうちに、メイクというのは役者にとって演技とともに、とても重要な要素だということも気がついたのです。役者の風貌というのはとても大事で、演技だけではカバーできないリアルさをメイクアップで表現できると思いました。
大道具などは、劇団員の中に大工の息子がいたりして見様見真似でカタチにできたのですが、当時の日本には、「メイクアップ・アーティスト」とか「メイク」という言葉や概念がまだない時代。ましてやメイクのための理論や知識は誰も持っていなかったんですよね。だから、メイクをどうしたらいいのか悩むことが多々あって、舞台のメイクアップ・アーティストを目指したいと思うようになったんです。

――その決意が美容学校での学びに、やがては『小林コーセー』(現・『コーセー』)への入社応募へとつながっていったのですね。
ええ。舞台メイクの専門家になろうと決意して私は山形から上京し、保険のセールスをしながら夜間の美容学校に1年半通いました。ところが、美容学校では髪の毛のことは教えてくれても、顔のメイクのことはほとんど教えてもらえなかったんですよね。化粧の演習は、ほぼできませんでした。
そうして美容学校を卒業したときに、『小林コーセー』の「美容指導員募集」の広告を新聞で見つけたのです。「化粧品メーカーならメイクの勉強ができるかもしれない」と思って、迷わず応募しました。
――そうして、何千人もの応募者の中から見事合格しました。それは何が決め手だったと思われますか?
今から思うと、『コーセー』の創業者である小林孝三郎社長と、運命的なご縁があったからだと思います。
就職試験を何度も重ねてふるいに掛けられていくうちに、残っていたライバルたちは、皆、私より美人だし、教養もあって優秀な方ばかり……。選考が進むほど自信がなくなっていきましたが、私は小林社長と専務との最終面接まで進むことができました。
就職試験での逆転劇
けれども、その面接の最初に失敗してしまったのです。
社長に「コーセーを知っていましたか?」と問われたときに、私は「知りませんでした」と正直に答えてしまったのです。私のその返答を聞いて社長さんがっかりされたのがわかり、いっきにその場の空気が暗く重くなって、私は一瞬で「落ちた」と思いました。
ところが、そのとき社長の背後にある棚に、私が日ごろ使っていた化粧品が飾られているのを発見したのです。思わず「あれはコーセーの商品ですか? あれを使っています」と言いました。そうしたらその場の空気が一変して和み、会話が弾んだんですよね(笑)。
「そうだよ。うちの商品だよ。どこのお店で買っているの?」と問われて、私がお店を答えたら、購入していたお店のご主人のことを社長がご存じで、思わずお互いに大爆笑でした。
それが決め手となったみたいで、選考会議のときに社長が「あの子は笑顔がいい」と推していただいたそうで、難関を突破することができまして、美容指導員として入社することができました(笑)。それまでお芝居では、私はお婆さんの役が多かったのもあって、笑顔を褒められたことなどなかったのですが、自然に出た笑顔が良かったのかもしれませんね。

営業トークをせず、ひたすら「お化粧」したら売り上げ上々に
――23歳で『コーセー』へ入社。その後、「世界初の美容液の開発」や「ナチュラルメイク理論の確立」など、多くの功績を打ち立てられました。
私が入社した時代は、まだ職場は男性中心社会で、社員時代は紆余曲折がたくさんありました。でも、ここまで来れたのは、いつも「仕事をするのはメイクアップ・アーティストになるという夢を実現するため」と思って仕事をしてきたからです。
入社後、配属されたのは「まずは現場を体験せよ」ということで、当時、全国でいちばん難しい県と言われていた山口県へ派遣され、販売店やデパートで美容部員として2年間働きました。メイクアップ・アーティストを目指していた私にとって、それは何百人~何千人ものお客様のメイクアップをさせていただけるという、ありがたくかけがえのない機会となりました。
お客様には商品の営業トークはせずに、ただ「お化粧をさせてください」と言って、メイクをさせていただいていたのですが、そうした体験を重ねることで私のメイクの腕は上がりました。また、お化粧をさせていただいたお客様には、皆さんとても喜んでいただけて、化粧品を自ら購入してくださったんです。商品の売り上げは上々なので、会社も喜んでもらえました。まさに三方よしの2年間でした。
その後、本社に戻ってからは、メイクの仕方を美容指導員や販売店の方に教える仕事に就きました。
当時の講義は、黒板に顔の絵を描いて型にはまったメイクの仕方を解説するというのが一般的だったのですが、私は、人の顔はそれぞれ個性が異なるのに、みんなに同じ顔に近づけるメイクはおかしいと思っていました。メイクアップ・アーティストというのは、さまざまな役者さんにメイクをするからです。だから、私は実際に人をモデルにして講義を行なったんですよね。でも、それが生徒さんたちには理解してもらいやすくて、技術力がぐんぐん上がっていくことにつながったのです。
やがて、「化粧の仕方がうまいなら、商品開発もしてみろ」ということになりまして、美容研究者として配属されたのですが、そのときもメイクアップ・アーティストを目指す者として、私が使いたい化粧品のコンセプトを提案して、化粧品を作っていたんですよね。
けれども、それが世の女性たちのニーズとうまく合致して、ヒット商品につながりました。私自身が化粧を使う実践者であると同時に、メイクの専門家を目指していたので、一般女性の技術力との差がわかって、その差をカバーするにはどうしたらいいのかという想いを常に抱いていたことも、ヒット商品を生み出せたポイントになったと思います。
このように、メイクアップ・アーティストへの夢をあきらめなかった結果が、今の私につながっているのです。
*
次回は「コーセー」初の役員になった経緯や定年後の人生の描き方、「妹」世代へのメッセージをうかがいます。

小林照子(こばやし・てるこ)
1935年、東京生まれ。メイクアップアーティスト。小林コーセー(現・コーセー)に美容指導員として入社。数々の商品開発を手掛け、1985年に同社初の女性取締役に就任。その後、独立し、美容ビジネスの企業経営や後進を育てる学校[フロムハンド]メイクアップアカデミーほか、美に特化した高等学校およびアマテラス アカデミアを運営。
* * *

『50代からの生き方のカタチ――妹たちへ――』
(関西学院大学ジェネラティビティ研究センター 編)
アルソス
『50代からの生き方のカタチ――妹たちへ――』(関西学院大学ジェネラティビティ研究センター 編)は、小林照子さんをはじめとする12人の「姉」たちが、これから人生の半分を生きる、すべての「妹」たちへ贈るメッセージ集。
未来に対する不安や迷いと向かいつつ、「真に自分らしく生きる」にはどうしたらいいのか。「そっと背中を押すような」珠玉の言葉が詰まっている。