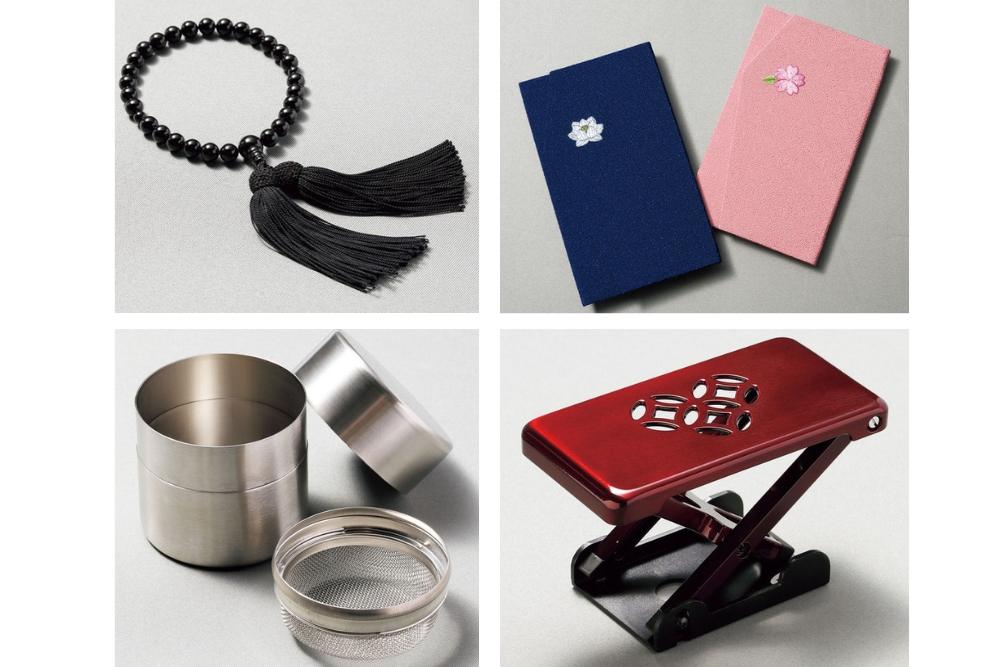壁一面に飾られている植物は、近年、注目を集めている彫刻家・モリソン小林さんの作品です。一見、野に咲く草花を標本にして額縁の中に飾ったように見えますが、この作品は、植物とはまったく異質な素材の金属、鉄でできています。
この事実を初めて知った人は、そのほとんどが驚きます。
なぜなら素材が金属と知ってから眺めても、額縁の中の植物は本物と見間違うほど繊細で、可憐な美しさを放っているからです。花も葉も、茎も根も、瑞々しくはなく色褪せているのですが、かつて命を宿していたような存在感があります。
いったい、どのような道のりを経て、このような作品を創作するようになったのでしょう。モリソンさんのアトリエで、作品に込めた想いとともにお話を伺いました。
店舗のデザインや内装の仕事をしながら創作活動を開始

――モリソン小林さんというお名前から、お目にかかるまでは外国の方かと思っていました。
僕は東京生まれ。生粋の日本人です(笑)。フリーランスになる前は、美術大学を卒業後、内装会社を経て、インテリアショップ『イデー』に5年間在籍してアパレルブランドの店舗設計を手がけていたのですが、『イデー』に入社するときの面接で「君はビートルズとストーンズ、どちらが好き?」と聞かれて、「僕はドアーズのジム・モリソンが好きです」と答えたら、以来、社内では「モリソン小林」と呼ばれるようになりまして、それがいつのまにか通称になったんです。今から思い返しても、自由な気風にあふれたユニークな会社だったと思います(笑)。
――当初から彫刻家になることを目指していたのですか?
いいえ。大学ではプロダクトデザインを専攻していまして、当初はインテリア関連の仕事に就こうと思っていました。だから、卒業後はそれに即した仕事をしていたのです。ところが『イデー』に入り、社内にある鉄や木工の工房で、仕事に関連した家具やオブジェなどを作っているうちに、徐々に大量に生産するプロダクトではなく、アートワーク的な仕事をしてみたいと思うようになったのです。
その思いが強くなり、2000年に『イデー』を退社。2001年にアトリエを開いて、店舗やギャラリーのデザインや設計施工など内装の仕事をする傍ら、創作活動をスタートしました。
――当初から、現在のような作品だったのでしょうか?
いいえ。当初は木彫を創作していました。山の中へ出かけて行って、そのとき自分が受けた自然の印象を擬人化してカタチにしていたんです。木の中にいる神様を掘り起こす感じで作品を作っていました。


それが、あるとき内装を担当させていただいた取引先のお店で山岳写真家の田淵行男先生の写真集を見て、衝撃を受けたんです。
ナチュラリストでもある田淵先生がとらえた自然や、写真に添えられた詩的な文章にとても感動しました。それがきっかけとなって、そこから生まれたインスピレーションをカタチにするようになっていったのですが、それが現在の作品につながっていると思います。

希少な高山植物は採集できない。だったら作品にしてみよう
――現在は高山植物をモチーフになさっていますが、それは最初からですか?
いいえ。最初は、近場の森林公園とかで植物を採集して作っていたのですが、段々と自分が見たことがない植物を手がけてみたいという想いがつのって、どんどんフィールドが広がっていき、高い山へ登るようになっていったのです。


でも、高山植物は希少なもので採集できないじゃないですか。だったらそれを作品にしてみようと思うようになったんです。山へ通い、創作を重ねるうちに自然への想いが強くなっていきまして、この美しいものたちを未来に伝えたいと願うようになったのも今の創作活動に影響していると思います。
僕が創作する植物は、野山へ行って心に響いた草花を原寸大でスケッチしたり、写真で撮影したりしたものを、アトリエで鉄を使って造形。それをさらに錆びさせて、色付けをして完成します。でも、作品としては、それを額縁の中に入れて完成すると考えています。
植物を愛する人たちが、かつて植物採集をして標本にしていたのと同じように、造形した植物を標本のように飾ることで、百年後の人たちにこんな植物があったんだということを“記録”として伝えられたらと思っているんです。そのため現在は、額縁の裏側に、植物を観た場所と期日を明記した原寸大のスケッチを添えています。


作品が完成するまでには、一緒にアトリエを運営している彫刻家の中村大介と画家の高里千世に協力を仰いでいます。アイデアと実際に植物を制作しているのは僕ですが、大ちゃんには植物を作る鉄のパーツ素材や額縁の制作を、千世さんには額縁内に植物を飾る際のアドバイスをもらっています。
鉄という錆びて朽ち果てていく素材で未来に伝えていく
――鉄という金属で、植物を表現しようと思ったのはなぜですか。
鉄というのは、会社員時代から内装を手がけてきた僕がもっとも関わってきた素材なんです。鉄を素材として使うようになったのは、そうしたことが影響していると思います。
しかし、いちばんの理由は、鉄というのが錆びて朽ち果てていく素材だからです。かつて押し花にした植物の標本というのも永遠ではなくて、いつかは干乾びて粉々になってしまうじゃないですか。鉄もそれと一緒で永遠ではありません。生の植物よりも長い期間、カタチとして存在していますが、宇宙や地球の壮大な歴史から見たら、朽ち果てていくという点において、大差がない時間だと思ったのです。
――植物標本のような形にしようと思ったことにも、何か理由があるのでしょうか。
このアイデアが浮かんだのは、じつは兄の影響があるかもしれないと思っています。兄は考古学者なのですが、昔から収集癖がありまして、部屋にはいろんなものが博物館のように飾ってあったんです。今思うと、その風景へのノスタルジーが僕の中に潜在的にあったのではないかと思います。
作品の試行錯誤をしているとき、子どものころに観た植物の標本がイメージとして現われたのです。植物の標本というのは百年以上も前から全世界で作られていた文化遺産なので、みずみずしくもないし色褪せていますよね。でも、僕はそれを観たときになぜか懐かしくて、ロマンを感じました。それと同じように、未来に伝えるものを自分の手で作ってみたいと思ったんですよね。
だから、僕は自分の作品のアートとしての評価というものを、あまり意識していないんです。インテリアの装飾品として捉えていただいてもいいと思っているんですよね。
今から百年後、僕の作品を観た人が「この人はどんな時代に、どういう所で、どんな気持ちで作ったんだろう」と思ってもらえたら本望ですね。

――今後の抱負を教えてください。
いまは、自分の見たものを“記録”として作品にしていくのが、じつに心地いいんですよね。だから、今後の作品の方向性は、あまり考えていません。
これまで自分の作品が記録であるという意識はあまりなかったのですが、山の自然はどんどん破壊されていて、このまま放っておくと本当になくなってしまう高山植物があるんじゃないかと思い始めているんです。もしかしたら、僕の作品が、貴重な記録となるかもしれません。
今後の抱負を強いて言えば、海外の山へ行ってみたいです。写真家の星野道夫さんの見たアラスカの自然の風景を観てみたいんです。コロナ禍の影響が少なくなって日常が戻りつつあるので海外旅行へのハードルは低くなっているんですが、でも、世の中が平常に近づいたぶん、今年は滞っていた内装の仕事が忙しくなりそうなんです。だから、行けないかもしれませんが(笑)。
*
モリソン小林さんは、2021年、「公益財団法人 岡本太郎記念現代芸術振興財団」および「川崎市岡本太郎美術館」の主催による『第24回岡本太郎現代芸術賞』(TARO賞)において、岡本太郎賞に次ぐ岡本敏子賞を受賞。川崎市岡本太郎美術館で開催された受賞者による展覧会で、インスタレーションで作品を披露して、アーティストとしての評価も確立しつつあります。

しかし、「作家活動と並行して、今後も内装に携わる仕事は続けていきたい。アートワークとは真逆の手仕事だが、それが自分には合っている」と穏やかに語ります。
モリソン小林さんが語るように、彼の作品が学術的な標本として貴重な資料になるような未来が訪れないことを願わずにいられません。

モリソン小林
1969年生まれ。多摩美術大学卒業後、内装会社勤務を経て、1995年にIDÉEに入社。主に店舗デザイン設計を担当し、1999年に独立。店舗デザインや建具什器の制作を手がけながら、神奈川県川崎市のアトリエで鉄を主体とした金属の彫刻作品を制作する。
* * *
素材は金属なのに、自然に存在する植物たちの生命力や美しさが現われ、どこか懐かしくて儚さも感じるモリソン小林さんの作品。以下の展覧会で出会うことができます。
【モリソン小林 special source】
・2023年3月10日(金)~3月26日(日) 「special source 3人展」 会場:「sunny cloudy rainy」(東京・蔵前)
・2023年6月24日(土)~7月15日(土) 「中村大介と2人展」 会場:「+106」(香川県高松市)
・2023年10月7日(土)~10月14日(土) 「中村大介と2人展」 会場:「hase」(名古屋市中村区)
・2023年12月 「自然礼賛」 会場:「atelier gallery」(川崎市高津区)
取材・文/山津京子 アトリエでの撮影/藤岡雅樹(小学館)